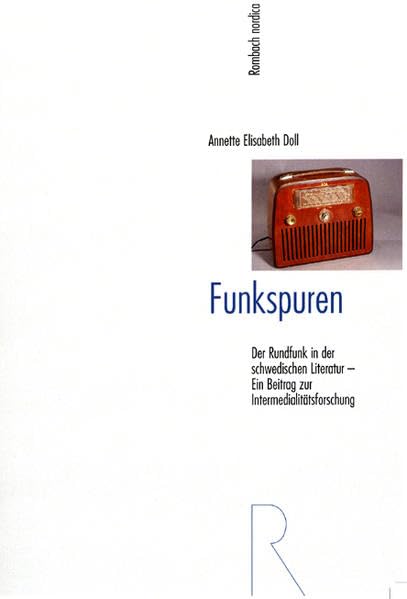1 0 0 0 「かわいい」の原因系と結果系の分類:-「かわいい」を類型化する-
- 著者
- 宇治川 正人
- 出版者
- Japan Society of Kansei Engineering
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18840833)
- 巻号頁・発行日
- 2015
- 被引用文献数
- 2
This study reports the results of a subject investigation that was conducted on the cause and effect of the phenomenon known as "kawaii." To experience that something is "kawaii" is a psychological phenomenon; however, it has not been clarified what type of causes lead to this type of effect. Due to the existence of several opinions regarding what comprises "kawaii," it is difficult to entirely clarify the topic. Three group interviews were conducted with a total of 30 subjects. The laddering method devised by D. Hinkle was used as the question form, and 15 stimuli were used for the investigation. The causes were classified into "shape," "behavior or expression," and "personality "; the effects were classified into 20 social needs and 16 emotional categories. Regarding the effects of "kawaii," "happiness" was considerably selected followed by "affiliation" and "nurturance." Moreover, the relationship between the causes and the effects was further understood.
1 0 0 0 CIOの決断(第5回)水面下の動き
- 著者
- 日本情報システムユーザー協会IT匠フォーラム
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンピュ-タ (ISSN:02854619)
- 巻号頁・発行日
- no.680, pp.132-135, 2007-06-11
前号までのあらすじ JUAS産業の創業者である社長が脳梗塞で倒れ、システム企画部長に就いたばかりの息子が取締役CIOに就任する。社長に就いた浦山は自分でシステム経費を分析、運用コストの半減を命じる。CIOになった福井は、システム子会社のトップである金山に運用の外部委託を持ちかけるが、金山は首を縦に振ろうとはしない。
1 0 0 0 愛の韓国童話集
- 著者
- 李周洪 [ほか] 著 仲村修編 オリニほんやく会翻訳
- 出版者
- 素人社
- 巻号頁・発行日
- 2001
1 0 0 0 朝鮮文学関係日本語文献目録 : 1882.4〜1945.8
- 著者
- 大村益夫/布袋敏博編
- 出版者
- [大村益夫]
- 巻号頁・発行日
- 1997
1 0 0 0 朝鮮文学関係日本語文献目録
- 著者
- 木村益夫・任展慧編著
- 出版者
- プリントピア
- 巻号頁・発行日
- 1984
1 0 0 0 『ソナギ』(黄順元作)についての一考察
- 著者
- 朴 順愛
- 出版者
- 大分大学
- 雑誌
- 国語の研究 (ISSN:09173544)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.1-14*, 2003-11
1 0 0 0 内視鏡外科治療
- 著者
- 木村 泰三
- 出版者
- 一般社団法人日本外科学会
- 雑誌
- 日本外科学会雑誌 (ISSN:03014894)
- 巻号頁・発行日
- vol.111, no.3, pp.156-159, 2010-05-01
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 Funkspuren : der Rundfunk in der schwedischen Literatur : ein Beitrag zur Intermedialitätsforschung
- 著者
- Annette Elisabeth Doll
- 出版者
- Rombach
- 巻号頁・発行日
- 2009
1 0 0 0 『夢十夜』を読む : 「第十夜」謎の女と豚
- 著者
- 越智 悦子
- 出版者
- 岡山商科大学
- 雑誌
- 岡山商大論叢 (ISSN:02868652)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.3, pp.84-67, 2006-02-10
1 0 0 0 OA 大正大学教育開発推進センター年報 第2号
- 著者
- 教育開発推進センター
- 雑誌
- 教育開発推進センター年報 第2号 = Annual Report, the Center for Educational Development (ISSN:24239720)
- 巻号頁・発行日
- pp.1-120, 2017-06-30
1 0 0 0 模型変形計測データを反映した CFD表面格子修正法の開発
- 著者
- 保江 かな子 口石 茂 橋本 敦 村上 桂一 加藤 裕之 中北.和之 渡辺 重哉 菱田 学
- 出版者
- 宇宙航空研究開発機構
- 雑誌
- 宇宙航空研究開発機構研究開発報告 (ISSN:13491113)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.1-18, 2013-03
風洞試験で計測した模型変形データを用いて, Computational Fluid Dynamics(CFD)表面格子を修正する方法を検討する.JAXAではマーカーを使ったステレオ写真法により風試模型の模型変形量を計測しており,計測したマーカー座標値を使うことで主翼の変形則を同定し,変形後の形状を定義することができる.本報告では,計測したマーカー座標値を使って変形後の形状を同定し, CFDの表面格子が通風時の風試模型形状と一致するように修正する方法を検討する.ここでは三種類の変形手法を検討する.そして,実際に模型の変形量を計測した DLR-F6FX2Bモデルに対して本手法を適用し,変形モデルの検証をおこなう.また,変形前後の形状に対して Reynolds-averaged Navier-Stokes(RANS)解析を実施することで,変形を考慮していない場合と考慮した場合とで空力特性にどの程度影響を及ぼすかを検討する.
1 0 0 0 IR 拒絶感受性が他者からの曖昧な拒絶後の選択的注意に及ぼす影響
- 著者
- 相田 直樹 礒部 智加衣 アイダ ナオキ イソベ チカエ Aida Naoki Isobe Chikae
- 出版者
- 大阪大学大学院人間科学研究科対人社会心理学研究室
- 雑誌
- 対人社会心理学研究 = Japanese journal of interpersonal and social psychology (ISSN:13462857)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.39-44, 2015-03
人は、所属欲求のため、拒絶された後に笑顔へ注意が向くことが示されている(DeWall et al.,2009)。また、拒絶感受性が高い人は平時において拒絶顔から注意をそらす傾向があることが知られている(Berenson et al.,2009)。拒絶感受性とは、不安をもって拒絶を予測し、素早く知覚し、過敏に反応する特性である。曖昧な拒絶後に、拒絶感受が高い人は笑顔に注意を向けることができるだろうか。本研究ではドットプロープ課題を用いて、次の代替仮説を検討した。拒絶感受性が高い人は、曖昧な拒絶後に笑顔に注意を向ける、もしくは、拒絶後に注意を向けるだろう。実験の結果はこれらの仮説に反し、拒絶感受性が高い人は、拒絶を経験しない統制条件において、拒絶顔に対する注意を高めることのみが示された。つまり、曖昧拒絶条件における選択的注意は、拒絶感受性による影響を受けなかった。拒絶感受性と不適切な反応の関係について考察した。It has been demonstrated that after an experience of being rejected, individuals pay increased attention to smiles, because of their fundamental need to belong (DeWall et al., 2009). Other research suggests that people with high rejection sensitivity tend to avoid attending faces showing rejection (Berenson et al., 2009). Rejection sensitivity is the disposition to anxiously expect, readily perceive, and intensely react to experiences of being rejected. Do rejection sensitive people also attend to a smile after experiencing an ambiguous rejection? In this study, we use the dot-probe task and examined the following predictions after an ambiguous rejection: highly rejection sensitive people would pay attention to (i) a smiling face, or (ii) disgust face. Contrary to these predictions, results indicated that in control condition, in which there was no rejection, highly rejection sensitive people highly attended only to the disgust faces. On the other hand, in the ambiguous rejection condition, selective attention was not affected by rejection sensitivity. We have discussed the relationship between rejection sensitivity and inappropriate reactions.
1 0 0 0 シンメトリーな咬合床の製作方法:―基準となる咬合床の製作方法
- 著者
- 大野 健夫
- 出版者
- THE ACADEMY OF CLINICAL DENTISTRY
- 雑誌
- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.316-322, 2001
総義歯を製作するとき, 咬合床を用いて咬合採得を行う工程があり, 咬合採得によって得られた情報に基づいてロー義歯が製作されることを考えれば, 咬合床の重要性が認識できる.そこで, 望ましい咬合床の備えておくべき条件と製作方法を考えてみた.<BR>咬合床は構造的には基礎床と咬合堤からなり, 次の条件を満たしていなければならない.<BR>(1) 基礎床は作業模型の模型面に対して適合精度がよい.<BR>(2) 咬合堤は提示された垂直的数値, 水平的数値が正確に記入してあること.<BR>このときには顔面正中線が示されていることはないので, 当然として正中口蓋縫線を正中線 (基準軸) として咬合堤が製作される.<BR>そして, ヒトの顔が基本的に対称的であることを前提に考えれば, 有歯顎では, 上顎正中線を中心軸として左右対称の位置に同名部位の歯牙があり, 下顎歯列がその対向関係において上顎歯列と一致するなら, 下顎正中線を中心軸として左右対称の位置に同名部位の歯があり, 上下顎の同名部位の歯は対向関係において一致する.<BR>以上のことから, 上下顎模型の各正中線を中心軸として水平的数値は左右対称であり, 上下顎の咬合堤の水平的数値は同じ大きさであることが望ましく, また, 患者によって顎骨の大きさが一人一人違うことを考えれば, 患者によってその垂直的数値や水平的数値の変化に対応できる製作方法でなければならない.<BR>「また, 同一患者においては, その患者がどの分類に属していようとも上下顎顎堤の間には, 時系列的変化にかかわらず, そこには普遍的な共通性があると考えている」<BR>以上のことを考慮したシンメトリー (左右対称) な咬合床の製作方法を述べる.<BR>咬合床製作の工程は, (1) 作業模型上にガイドラインの記入, (2) 基礎床の製作, (3) 咬合堤の製作, の順序で行う.また, 咬合床を製作するには特別な器具は必要とせず10cmの三角定規があれば十分であるが, より寸法精度を上げるために自家製の器具を開発している.また, 規格模型の制作に関しては「目で見るコンプリートデンチャー」のp.97を参考にしている.
1 0 0 0 IR J・バトラーのジェンダー・パフォーマティヴィティとそのもうひとつの系譜
- 著者
- 藤高 和輝
- 出版者
- 国際基督教大学ジェンダー研究センター
- 雑誌
- Gender and sexuality : journal of Center for Gender Studies, ICU = ジェンダー&セクシュアリティ : 国際基督教大学ジェンダー研究センタージャーナル (ISSN:18804764)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.183-204, 2017
Gender performativity is the most famous and influential theory in Judith Butler. It questioned the sex/ gender distinction which some feminists took for granted at that time when Gender Trouble (1990) was published. This distinction regarded sex as the natural category on the one hand, gender as the cultural expression of sex on the other hand. It means naturalizing the dualistic representation of gender. On the contrary, Butler's performative theory suggested that sex is not a natural category, but is a fiction which is constructed by repeating gender performances. Through denaturalizing gender, her theory criticizes the representation of gender/ sexual minorities as "unnatural" and "abnormal," and seeks to theorize the way to make their survival possible. This paper examines how gender performativity was theorized from the 1980s to Gender Trouble. Interestingly, her performative theory cannot be reduced to speech act theory, but it was also formed in relation to other theories; feminist/ queer theory and performance theory. Indeed, in her article "Performative Act and Gender Constitution" (1988) in which she referred to "performative" at first, Butler started from Simone de Beauvoir's text, The Second Sex, and then reread Beauvoir's idea of "gender as act" as "social performance" in performance theory. Moreover, she extended Beauvoir's argument of denaturalizing sex, referring to Gayle Rubin's study of kinship, Monique Wittig's theory of sex, and Esther Newton's analysis of Drag Queen. Thus, her performative theory is found not only in the context of speech act theory, but also in contexts of feminist/ queer theory and performance theory. From this genealogical perspective, this article seeks to rethink gender performativity.
1 0 0 0 DPC導入に伴う診療内容の変化について
- 著者
- 池田 俊也 小林 美亜
- 出版者
- The Health Care Science Institute
- 雑誌
- 医療と社会 (ISSN:09169202)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.167-180, 2007
- 被引用文献数
- 5
2003年度より特定機能病院等82病院に,診断群分類 (DPC; Diagnosis-procedure combination) に基づく包括支払い方式が導入され,2007年度には360病院に達している。包括支払いの対象となる医療機関では,包括範囲に含まれる薬剤・検査等のコスト適正化が経営上の重要な課題である。本研究では,DPCによる包括支払い導入前後における診療内容の変化について検討を行った。<br> 対象は,2006年4月よりDPCによる包括支払いを導入し,DPCデータ分析ソフト「ヒラソル」を採用している施設で,人工関節再置換術実施患者,ステント術実施患者とした。分析は,包括支払い導入前の2005年度と導入後の2006年度における平均在院日数,術前・術後日数,注射・検査・画像に関する出来高ベースでの請求額,典型的な診療パターンについて行った。その結果,包括支払いの導入に伴い,在院日数の短縮や包括範囲に含まれる医療行為の資源消費量の減少が認められた。<br> 但し,本研究の対象施設は,DPCデータ分析ソフトを導入していることから経営に対する意識が高いものと推察され,他の包括支払い導入施設においても同様のことが観察されるかは不明である。また,本研究では外来部門に関するデータは分析対象となっていないため,入院中に減少した医療行為の資源量が外来に移行しているかは明らかではないことから,外来を含めた1エピソード単位での医療資源消費量の分析が今後の課題である。
1 0 0 0 OA 感情的評価を条件づけられた態度対象に対する自動的評価の文脈依存性
- 著者
- 林 幹也
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.187-194, 2007-11-10 (Released:2017-02-08)
- 被引用文献数
- 1
An experiment (N=32) examined whether an affectively neutral attitude object which always accompanied an affectively positive stimulus in a specific context was automatically evaluated as positive only in that same context. In the acquisition phase, one nonsense shape with a colored background context was paired with positive personality traits. In the alternative condition, the non-sense shape was presented with no background color context and was not paired with any stimulus. In the test phase, the affective priming method used that shape as the prime stimulus. Response latencies for positive target words preceded by the shape with the colored background context as the prime stimulus were shorter than those preceded by the shape with no background context. This result shows that automatic evaluation for an attitude-conditioned object depends on the context that was presented in the acquisition phase.
- 著者
- 早岡 英介 藤川 大之
- 出版者
- 北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニット(CoSTEP)
- 雑誌
- 科学技術コミュニケーション (ISSN:18818390)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.99-112, 2010-12
1 0 0 0 OA ハンス・ホフマンの芸術教育観についての一考察 : 絵画における空間の構築性への着目
- 著者
- 下口 美帆
- 出版者
- 美術科教育学会
- 雑誌
- 美術教育学:美術科教育学会誌 (ISSN:0917771X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.241-254, 2004-03-31 (Released:2017-06-12)
The purpose of this study is to consider Hans Hofmann's view of art education. His art theories and practices had a great influence on American Abstract Expressionism in the 1930's〜1940's. I considered the interrelationship between his art theories and artworks as an artist and his educational practices as a teacher. In addition, he taught his students how to acquire their way of thinking to find their own expression. As a result, his students developed their own expressions and became principal members in the American art scene represented by Abstract Expressionism.
1 0 0 0 把持運動課題中の遅延視覚情報が重さ知覚にもたらす影響
- 著者
- 外園 洋輝 湯ノ口 万友 塗木 淳夫
- 出版者
- 電気・情報関係学会九州支部連合大会委員会
- 雑誌
- 電気関係学会九州支部連合大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, pp.521-521, 2013
本研究では,バーチャル環境による新たな知見から運動制御の解明を目指している.そこで我々は,触覚デバイスとバーチャルリアリティを用い,運動に重要な情報である視覚と触覚の計測が可能なバーチャル環境による立体視把持運動システムを構築した.視覚の遅延が把持と重さの知覚へ及ぼす影響を調査した.視覚遅延把持運動実験から,視覚遅延が物体を重く感じさせる事が分かった.しかし,把持力,把持力の変化率に変化は見られなかった.これは,重さの知覚と把持運動は別々に制御されていることを示唆している.