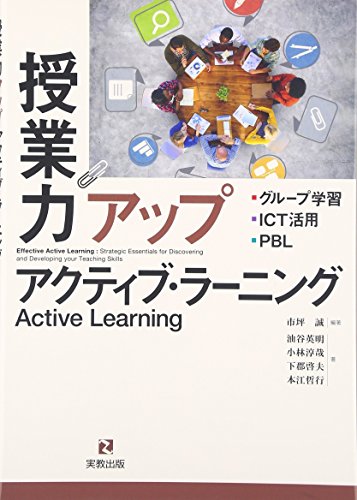1 0 0 0 OA Neural Attention Modelを用いた観点付き評判分析
- 著者
- 柳瀬 利彦 柳井 孝介 佐藤 美沙 三好 利昇 丹羽 芳樹
- 出版者
- 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, 2016
1 0 0 0 IR 相続税の再分配効果
- 著者
- 早見 弘
- 出版者
- 一橋大学
- 雑誌
- 一橋論叢 (ISSN:00182818)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.6, pp.702-715, 1969-12-01
論文タイプ||論説
1 0 0 0 初期地球のテクトニクスとマントルの進化
- 著者
- 太田 宏 丸山 茂徳
- 出版者
- 日本惑星科学会
- 雑誌
- 遊・星・人 : 日本惑星科学会誌 (ISSN:0918273X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.133-143, 1996-09-25
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 地球のダイナミックスについての新しいパラダイムの確立に向けて
- 著者
- 丸山 茂徳 熊澤 峰夫 川上 紳一
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.100, no.1, pp.1-3, 1994-01-15 (Released:2008-04-11)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 7 16
1 0 0 0 OA 中央海嶺沈み込み起源の花崗岩から得られたジルコンのHf同位体比
- 著者
- 昆 慶明 平田 岳史 小宮 剛 安間 了 丸山 茂徳
- 出版者
- 一般社団法人日本地球化学会
- 雑誌
- 日本地球化学会年会要旨集 2008年度日本地球化学会第55回年会講演要旨集
- 巻号頁・発行日
- pp.300, 2008 (Released:2008-09-06)
『生命』、『海』、『プレートテクトニクス』と並んで、『花崗岩質大陸地殻』の存在は地球を特徴付ける要素であり、その生成プロセスを明らかにすることは地球史を解明する上で非常に重要である。 本研究では、LA-MC-ICPMSを用いてタイタオ半島花崗岩から分離したジルコンの局所Hf同位体比測定を行った。その結果ジルコンの177Hf/176Hfは、現在沈み込む海洋地殻の値と誤差範囲で一致し、およそ0Maのモデル年代が得られた。このモデル年代は花崗岩マグマの原岩がマントルから分離した年代を反映することから、タイタオ半島花崗岩マグマの原岩は古いモデル年代を持つ下部地殻ではなく、沈み込む海洋地殻であることが確かめられた。
1 0 0 0 OA 総説-オフィオライトの起源とエンプレイスメント
- 著者
- 丸山 茂徳 寺林 優 藤岡 換太郎
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.3, pp.319-349, 1989-06-25 (Released:2011-02-17)
- 参考文献数
- 143
- 被引用文献数
- 2 4
A brief review of the study on ophiolite is given. 165 years have passed already since a first use of the term “ophiolite” by BRONGNIART (1813), but still have not yet obtained a broadly satisfying solution on its origin and emplacement. However, the rapidly increased data set during the last 15 years on both on-land ophiolite and oceanfloors clearly indicate the strong constraints on its origin and emplacement.The period during 1813-1927 was a time of description of ophiolite. BRONGNIART (1827) classified ophiolite into a group of igneous rocks, since then began a debate whether ophiolitic peridotite is igneous or the other in origin. SUESS (1909) had noticed that ophiolites appear characteristically in orogenic belts. It was STEINMANN (1927) who had first recognized a close association of peridotite, gabbro, diabase-spilite, and radiolarian chert suggesting a deep sea origin of ophiolite. The significance of his finding has never been looked back until the revolutional period of plate tectonics in the late' 60s.The second period of 1927-1949 was the time of debate on igeneous origin. BOWEN and his coworkers insisted igneous origin based on experimental petrology for the ultramafic rocks in general. But if so, an abnormally high temperature ca. 1, 900°C was necessary to explain the occurrence of dunite. BENSON (1926) pointed out that if BOWEN'S idea is true, the country rocks of ophiolite must be subjected a high-temperature contact metamorphism, but not in the field. HESS (1939) has given a new idea of serpentinite magma to solve the problem, but its possibility had completely been disproved by the experiment of MgO-SiO2-H2O by BOWEN and TUTTLE (1949).The third period (1949-1959) began by a break-through idea of DE ROEVER (1957), who speculated that ophiolitic peridotite is a piece of mantle material, which was brought into an orogen by a tectonic process.The fourth period (1959-1973) started by BRUNN (1959) who compared ophiolite with the rocks in the Mid-Atlantic Ridge. This period (1959-1973) was the time of plate tectonics. During the early' 60s the ocean-floor spreading theory was proposed by HESS and DIETZ, and both thought that the layer 3 is composed of serpentinite oreclogite. The year 1969 was a memorial year, when both MOORES and DAVIES distinguished cumulate peridotite from the underlying residue tectonite, the latter of which is a refractory mantle after the formation of oceanic crust by partial fusion of mantle peridotite. The best example of ophiolite was the Troodos massif in Cyprus, where the extensive-scale of parallel dike swarm develops indicating ocean-floor spreading. Thereafter an ophiolite boom has come out, and flood of papers appeared to regard ophiolite to be of mid-oceanic ridge in origin. However, several geologists have doubted mid-oceanic ridge origin by the facts of much thinner crust, more silicic volcanic composition, and frequent occurrence of phenocrystic augite in ophiolites. MIYASHIRO (1973) solved such problems, and concluded that Troodos was formed in an island-arc setting. This paper was very shocking for geologists who wanted to establish the basic framework of orogeny by plate tectonics in those days, but epoch-making on the study of ophiolite, and corresponding to the time, when the method of study has changed to be modernized and more interdisciplinary.
1 0 0 0 OA 独禁法における違反事業者に対する制裁・措置について (間宮庄平教授定年御退職記念号)
- 著者
- 楠 茂樹
- 出版者
- 京都産業大学
- 雑誌
- 産大法学 (ISSN:02863782)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.294-335, 2005-02
- 著者
- 伊藤 敏晃 高木 力 平石 智徳 鈴木 健吾 山本 勝太郎 梨本 勝昭
- 出版者
- 日本水産工学会
- 雑誌
- 水産工学 (ISSN:09167617)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.1, pp.39-43, 1995-07-31
- 被引用文献数
- 2
北海道では、エゾバフンウニやキタムラサキウニなどのウニ類を対象とし、種苗放流や、漁場造成によって資源を増加させようとする栽培漁業が積極的に推進されているが、地域によっては十分な成果が得られていない。その原因として波浪による稚ウニの打ち上げ、餌料の不足や海水交換の不良による死滅があげられる。これを防ぐために比較的静穏な海域に、稚ウニを集約的に放流し、給餌を行って育成する場を造ること、ウニが散逸しないようなフェンスを設けることなどが提案されている。また、ウニの食害による磯焼け現象が進むことも懸念されているため、ウニの行動領域を制限する安価で耐久性のあるフェンスの開発が強く要望されている。このようなウニ用フェンスを開発するためにはまずウニの行動特性を解明する必要がある。ウニの移動は管足先端部を付着基質に吸着させて管足全体を収縮させることによって行われるが、生態・行動学の分野における詳細な研究は少ない。外国産のウニについてはBullockによるアメリカムラサキウニの移動についての報告などがあるが、エゾバフンウニ、キタムラサキウニの行動学的な研究は非常に少ない。
1 0 0 0 CSRBF法による表面修復
- 著者
- カジョキンニキタ 谷口 由紀 萩原 一郎 サブチェンコウラディミール
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.1202-1211, 2004-04-15
- 被引用文献数
- 3
画像上の傷の修復問題にCSRBF 法を適用する.ここでは,著者らが開発した高速アルゴリズムに基づくCSRBF 法を用いて,画像上についた傷を修復するための手法の新たな開発を行う.本報で開発した手法を用いると,従来の画像の傷修復アルゴリズムではできなかった広範囲に及ぶ傷や大きな傷の修復を,短時間に精度良く行うことができる.また,本報では,テクスチャ模様のような色の変化が大きい画像修復に適している新たなLCSRBF 法や,多角形的な傷の修復問題に対する新しい手法の開発も行い,実際の使用例を提示してこれらの有効性について述べる.We employ the method of compactly supported radial basis functions (CSRBF)for a problem of fulfillment of damaged surface areas.In this paper we propose a new technique based on the method of CSRBF for retouching surface of damaged areas.By using our method,we can retouch disconnected large areas.It is enough speed and accuracy for practical use.We also develop a new method of LCSRBF (local compactly supported radial basis functions) for image retouching of textured images which have a sharp change in the color and a new technique for surface retouching of polygonal objects with missing or damaged areas in this paper.We show these efficacy by giving experimental results.
1 0 0 0 IR ウィットフォーゲルの水力社会論 : 中国を事例として
- 著者
- 田畑 久夫
- 出版者
- 昭和女子大学大学院生活機構研究科
- 雑誌
- 昭和女子大学大学院生活機構研究科紀要 (ISSN:09182276)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.1-20, 2016
1 0 0 0 OA 汎用静止型インバータの研究
- 著者
- 加藤 又彦 菅野 史夫
- 出版者
- 大同工業大学
- 雑誌
- 大同工業大学紀要 (ISSN:02855372)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.143-151, 1985-11
New type, large capacity thyristor cells have necessitated for new utilization of Induction motor driving and the future application is being promoted to next stage. In fact, the frequency control subjects are inportant enough to warrent the study of induction motor driving methed. The improvement of SCR cells for example gate-turn-off (G.T.O) SCR are bring about a change of static power inverter tecknology. The most desirable inverter design for various service is basically a matter of silicon controlled rectifier itself. To meet the needs for invertor equipment, voltage-frequency; current-frequency pattern of driving system and protection system is discussed at each case of induction motor. The article, also, discusses the wave form of invertor equipment in view point of Radio-noise.
1 0 0 0 キャベツ種子重量が生育に与える影響
- 著者
- 菅野 史拓 児玉 勝雄 菅原 英範
- 出版者
- 岩手県農業研究センタ-
- 雑誌
- 岩手県農業研究センター研究報告 (ISSN:13464035)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.131-136, 2001-12
キャベツの種子重量は、軽いものから重いものまでほぼ正規分布に近い分布を示していた。種子重量が軽い種子からは小さな苗が、重い種子からは大きな苗が生産され、軽い種子ほど生育がばらつく傾向にあった。種子重量の違いによる苗の生育差は、活着に影響を与えており、定植後もその生育差が縮まることはなかった。そのため、キャベツの生育斉一化のためには、種子重量を揃える必要があると考えられる。また、小さな種子は、登熟前の未熟な種子を多く含み、発芽が弱く生育がばらつく傾向にあることから、除去する事が必要である。
- 著者
- Mazur Michal
- 巻号頁・発行日
- 2016-03-24
ix, 105p
- 著者
- 坂本 史衣
- 出版者
- メディカ出版
- 雑誌
- Infection control (ISSN:09191011)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.11, pp.1131-1137, 2006-11
1 0 0 0 OA 自閉症生徒間の相互交渉における行動連鎖中断法による要求言語行動の獲得
- 著者
- 井澤 信三 霜田 浩信 氏森 英亜
- 出版者
- 日本特殊教育学会
- 雑誌
- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.33-42, 2001-11-30
本研究は、自閉症生徒間の社会的非言語行動連鎖において、「相手の行動遂行の中断状況を設定する(以下、中断操作と記す)」という行動連鎖中断法によって、仲間の行動を促す要求言語行動(「○○君、どうぞ!」)を成立させること、他の社会的行動連鎖においても中断操作が要求言語行動を生起させるかを検討すること、を目的とした。初めに自閉症3生徒間における社会的非言語行動連鎖(ボーリング)を形成し、その後、連鎖の途中での中断操作を行った。般化プローブでは他の社会的行動連鎖(黒ひげ・ダーツ)において中断操作の有無を変数とした。結果は、行動連鎖中断法により社会的非言語行動連鎖に要求言語行動を組み込むことができたこと、中断操作が標的行動の生起を制御する変数であること、を示した。中断操作は条件性確立化操作として機能したことが示唆され、行動連鎖の文脈としての意義と要求言語行動の機能化という観点から考察が加えられた。
1 0 0 0 OA 静止型電力用インバーターの研究
Rapid research and development of thyristor cells has necessitated for new utilization of Induction motor driving and the future application planning is being promoted. In fact, the frequency Control subjects are important enough to warrant the study of induction motor driving method. The advances in semiconductor cell for example G.T.O, SCR;TRIAC etc are bringing about a change of static inverter technology. The fundamental problem in choosing the most desirable invertor design is basically a matter of Silicon Controlled Rectifier itself. To meet the needs for increasingly high-performance invertor equipment, voltage - frequency pattern of driving system is discussed at each case of induction motor. The article, also, discusses in terms of the electrical system of inverter equipment, the innovative digital method applied to automated facility.
1 0 0 0 Kinect等の色距離センサを用いた点群処理と3D物体認識
- 著者
- 金崎 朝子
- 出版者
- 画像センシング技術研究会
- 雑誌
- 第22回画像センシングシンポジウム
- 巻号頁・発行日
- 2016-04-07
- 著者
- 市坪誠編著 油谷英明 [ほか] 著
- 出版者
- 実教出版
- 巻号頁・発行日
- 2016
1 0 0 0 特別展示 「日本とペルシャ・イラン」について
- 出版者
- 外務省外交史料館
- 雑誌
- 外交史料館報 = Journal of the Diplomatic Archives (ISSN:09160558)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.図版2p,89-106, 2016-03
- 著者
- 神山 晃令
- 出版者
- 外務省外交史料館
- 雑誌
- 外交史料館報 = Journal of the Diplomatic Archives (ISSN:09160558)
- 巻号頁・発行日
- no.29, pp.81-88, 2016-03