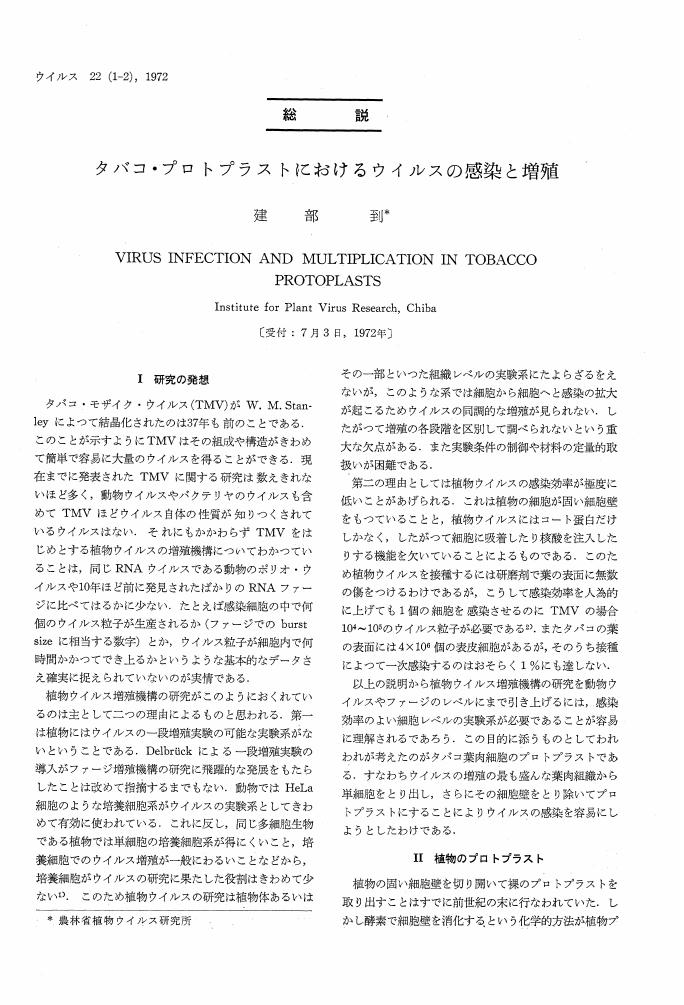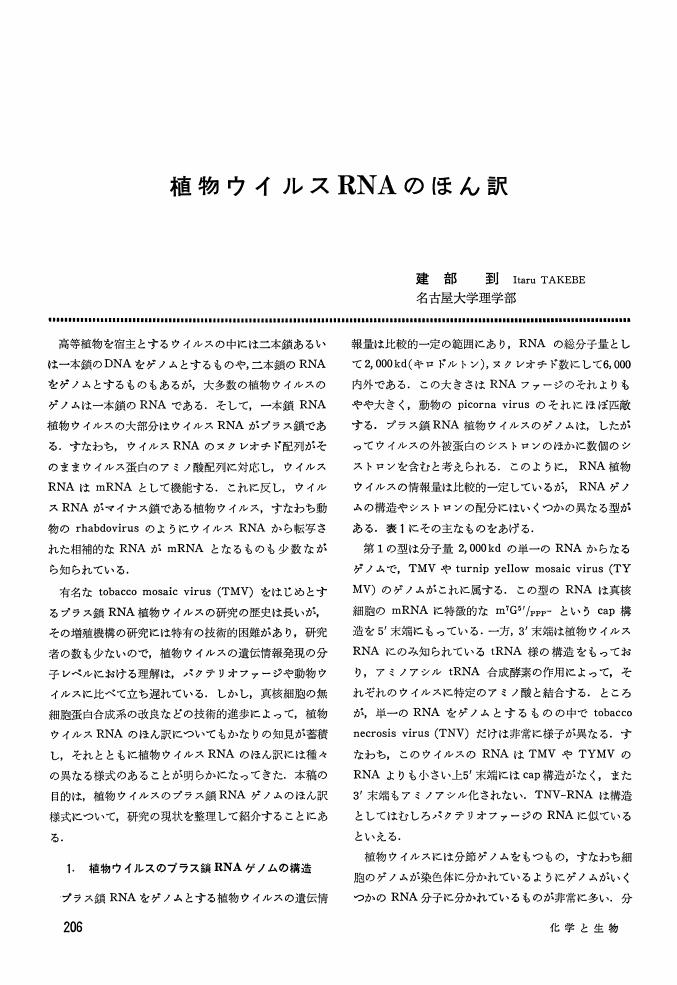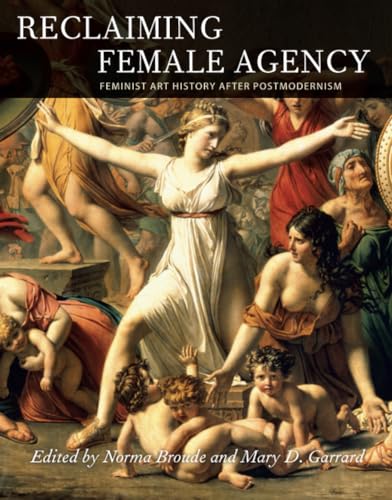1 0 0 0 IR シリア問題とレバノン--2011~2013年
- 著者
- Daher Massoud
- 出版者
- 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.62-75, 2014
2011年に発生したアラブ世界での民衆蜂起は、市民としてのアラブ人が近代的で民主的な国家を建設しようとする努力であった。その意味でアラブ民衆蜂起が発生した主な原因はもっぱら国内要因であり、そこに地域的、国際的な介入が加わったのである。アラブ民衆蜂起はシリアでは内戦に発展し、その影響は現在周辺国にも及んでいる。シリアが内戦に至った要因を理解するためには、シリアとそれを取り巻く現状を理解するだけでなく,シリアという国家が持つ歴史、なかでもフランス委任統治期の分断統治政策の失敗、ハーフィズ・アサドによる独裁体制の構築と継続、イスラエルによる干渉といったシリア現代史の影響を検討することが重要である。シリア内戦はレバノン、ヨルダン、トルコなどの周辺国にも少なからぬ影響を与えている。シリア難民の流出は、レバノンとヨルダンにとって社会と経済の負荷となっている。またシリア国内の分断と混乱は、レバノンの国内宗派対立をも先鋭化させた。他方でシリア内戦が長期化するにともない、イスラエルによるシリアとレバノンへの干渉が懸念されるようになっている。シリア内戦およびそれに対するイスラエルの対応は、結果的にレバノンへの大きな圧力となった。今後レバノンが主権国家としての安定的な地位を維持するためには、シリア内戦への政治的な関与を避け,国内各勢力の融和および各勢力の協調による国家運営を進めることがこれまで以上に必要である。
1 0 0 0 IR シリア問題とレバノン――2011~2013年
- 著者
- Daher Massoud
- 出版者
- 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- 中東レビュー (ISSN:21884595)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.62-75, 2014
<p>2011年に発生したアラブ世界での民衆蜂起は、市民としてのアラブ人が近代的で民主的な国家を建設しようとする努力であった。その意味でアラブ民衆蜂起が発生した主な原因はもっぱら国内要因であり、そこに地域的、国際的な介入が加わったのである。</p><p>アラブ民衆蜂起はシリアでは内戦に発展し、その影響は現在周辺国にも及んでいる。シリアが内戦に至った要因を理解するためには、シリアとそれを取り巻く現状を理解するだけでなく,シリアという国家が持つ歴史、なかでもフランス委任統治期の分断統治政策の失敗、ハーフィズ・アサドによる独裁体制の構築と継続、イスラエルによる干渉といったシリア現代史の影響を検討することが重要である。</p><p>シリア内戦はレバノン、ヨルダン、トルコなどの周辺国にも少なからぬ影響を与えている。シリア難民の流出は、レバノンとヨルダンにとって社会と経済の負荷となっている。またシリア国内の分断と混乱は、レバノンの国内宗派対立をも先鋭化させた。他方でシリア内戦が長期化するにともない、イスラエルによるシリアとレバノンへの干渉が懸念されるようになっている。</p><p>シリア内戦およびそれに対するイスラエルの対応は、結果的にレバノンへの大きな圧力となった。今後レバノンが主権国家としての安定的な地位を維持するためには、シリア内戦への政治的な関与を避け,国内各勢力の融和および各勢力の協調による国家運営を進めることがこれまで以上に必要である。</p>
- 著者
- 山本 香
- 出版者
- 国際ボランティア学会
- 雑誌
- ボランティア学研究 (ISSN:13459511)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.127-139, 2015-02-24
コミュニティ間の往来の増加や、オンライン・コミュニティの活発化により、近代コミュニティは地理的近接性に関わらず人々の連帯を拡大している。そうしたコミュニティは、とくに難民による学校経営において大きな影響力を持つ。難民には身分を保証する行政や地域社会がないため、彼らによる学校経営に公共性という保障を与えるのは、独自に形成されたコミュニティに他ならない。それはシリア難民が経営する学校の事例でも確認できる。彼らのコミュニティは構成員の営みに伴って国境を越えて広がり、インターネットを通して繋がっている。また、学校内にも独特のコミュニティが形成されている。そこでは、とくに教師と生徒がモラルを通じて連携している。子どもはそこで紛争で負った傷や憎しみを表出させ、帰属意識を獲得するとともに心理的な安定を得ている。コミュニティへの帰属は、社会関係資本を得るだけでなく、構成員としての責任を負い、他者との相互依存関係を構築することを意味している。そのなかで難民は受動的な立場に留まらず、そこに活動の主体として固有の意義を見出している。コミュニティはそのような難民の営みを支え、強化する役割を果たしている。
- 著者
- トゥーノ エリック 秋山 聰
- 出版者
- 東京大学グローバルCOEプログラム「死生学の展開と組織化」
- 雑誌
- 死生学研究 (ISSN:18826024)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, 2009-03-15
公開・国際シンポジウム「聖遺物とイメージの相関性 東西比較の試み」
- 著者
- 川端 悠一郎 古賀 雅伸 津村 祐司 矢野 健太郎
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 研究報告コンピュータと教育(CE)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.12, pp.1-8, 2015-02-07
本研究では,制御工学において多用される行列などの数式を効率的に扱える数値計算言語 MATX を Android 搭載のタブレットや Android Wear 搭載のスマートウォッチで利用できる数値計算ツール MATX mobile を開発した.本ツールを使用することにより制御工学教育の演習や実験における制約が緩和されるだけでなく,教育効率の向上が期待できる.
1 0 0 0 OA タバコ・プロトプラストにおけるウイルスの感染と増殖
- 著者
- 建部 到
- 出版者
- 日本ウイルス学会
- 雑誌
- ウイルス (ISSN:00426857)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1-2, pp.1-13, 1972-07-01 (Released:2010-03-16)
- 参考文献数
- 37
1 0 0 0 OA 葉肉細胞プロトプラスト系の開発
- 著者
- 建部 到
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.9, pp.619-621, 1984-09-25 (Released:2009-05-25)
1 0 0 0 OA 植物ウイルスRNAのほん訳
- 著者
- 建部 到
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.4, pp.206-212, 1979-04-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 28
- 著者
- 福武 敏夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.182-188, 2013
人格は背景に社会があって初めて問題になり, 人格障害は社会の中で扱われる。統合失調症や重度のうつ病が代表格であり, "idiopathic/developmental sociopathy"といえる。一方, 人格変化は, 何らかの脳損傷により生じ, 非言語的コミュニケーションを通して行動学的に判断される。人格変化も高度であれば, "acquired sociopathy"と捉えられる。本稿では, 左視床傍正中動脈(背内側核・正中核群)梗塞による意識障害から回復後に著明な人格・情動変化と前頭葉様症候を呈した48 歳男性例を紹介するが, 明らかな記憶障害を伴っていなかったことが大きな特徴であり, 脳における記憶回路(Papez)と情動回路(Yakovlev)の独立性を考える上で重要な症例と思われる。背内側核は, 前頭葉に想定されている3 つのサーキット(背外側部, 前頭眼窩野, 前部帯状回)のすべての要にあり, 統合失調症においても重要とされている。その病態分析のために, 同様症例の蓄積が望まれる。
1 0 0 0 剛性工作機械は重くなけらばならぬか(工作機械)
- 著者
- 田中 勇次
- 出版者
- 公益社団法人精密工学会
- 雑誌
- 精密機械 (ISSN:03743543)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.87, pp.717-721, 1940-12-25
本研究では, 数学的表現に近い形でプログラムを記述できる数値計算言語MaTXをAndroid搭載のスマートデバイスで利用可能な数値計算ツールを開発した.このツールを利用することで,座る場所がない様なPCを用いた作業が困難な現場での制御系設計などの計算結果の確認や調整が可能である.さらに,スマートデバイスのタッチ機能等を利用したUIの開発やAndroid Wear搭載のウェアラブルデバイスとの連携を図ることで利便性を向上させた.
1 0 0 0 WWW検索結果絞込みの一手法
- 著者
- 石井 壮介 力宗 幸男
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. CQ, コミュニケーションクオリティ (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.310, pp.13-18, 2004-09-10
- 被引用文献数
- 1
本稿では、ユーザに単語の「意味」や「定義」を提供するために、検索エンジンでのWWW検索結果を係り受け解析を用いて絞り込む手法を実装したシステムの開発を行った。具体的には、調べたい単語を含む文をGoogleの検索結果を用いてWeb上から引っ張り、その文を係り受け解析し、どの程度の確率でその文が単語の意味を表しているのかを表示するようにした。その評価の結果から、一般的な国語辞典に比べて、俗語や専門用語の意味を検索するのが得意である、新語辞典よりも索早く新語に対応することが出来るといったことなどが明らかになった。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コンピュ-タ (ISSN:02854619)
- 巻号頁・発行日
- no.752, pp.82-84, 2010-03-17
競合ベンダーに決まりかけていた商談を、ドリーム・アーツが土壇場で逆転した。本番さながらのデモシステムを開発し、製品選択を左右する利用部門の心をつかんだ。「Notes/Domino」をリプレースした社内ポータルシステムは、2009年11月に稼働した。(文中敬称略) 「まだ契約していないんだ。A社の製品を導入する方向で動いていたのだが、利用部門が納得してくれない」。
1 0 0 0 OA 安息香酸塗膜による模型船Wave Profileの測定
- 著者
- 乾 崇夫 菊池 義男 岩田 達三
- 出版者
- The Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers
- 雑誌
- 造船協會論文集 (ISSN:18842062)
- 巻号頁・発行日
- vol.1956, no.100, pp.47-67, 1956 (Released:2010-01-25)
- 参考文献数
- 12
The wave profile measurements are made with two wall-sided, deep-drafted mathematical models (S-103, S-203) by applying the chemical film method, where the Benzoic Acid is effectively used for the first time, and found as pre-eminently suited to contrasting the flow phenomena on ship models such as wave profiles, initial still water lines, stream lines, and laminar flow area.Comparisons are also made between the calculated and the observed wave profiles.Coincidence is good along the models, but is unsatisfactory in the rear.The principal cause might be safely ascribed to the fact that the wake intesity is always extinguishedly strong just on the narrow band in the vertical symmetrical plane (y=0).Conclusions are then drawn that the present field of the mentioned comparisons between the theory and the observation must be extended from one dimension (on the line y=0, exclusively) to two dimensions, to which the photographic measurements by stereograph might be expected as essential.
1 0 0 0 OA 浅水における造波抵抗
- 著者
- 乾 崇夫 菊池 義男 岩田 達三
- 出版者
- The Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers
- 雑誌
- 造船協會論文集 (ISSN:18842062)
- 巻号頁・発行日
- vol.1956, no.100, pp.35-45, 1956 (Released:2009-09-16)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 2
Since 1944, when one of the present Authors (INUI) and his collaborator calculated mathematically the wave-making resistance of ships in a shallow sea, necessity has long been recognized for making further quantitative investigations regarding to the practical adaptability of the theory. The following notes are aimed for clarifying the still remained question to what extent such a linearized wave-making theory can be safely applied in cases of a restricted water (b=h=finite) as well as a shallow water (h=finite, b=infinitive), where h denotes the depth of a water, b the width.A 1.750 m mathematical model S-201, whose equivalent source distribution is known, is towed in the Tokyo University Tank at the depth of water h/L=1.371, 0.400, 0.300 and 0.200.Comparatively good coincidence has been obtained between the calculated and measured wavemaking resistance, excluding the narrow critical range of Fh=0.820.95 where the KREITNER'S non-linear restricted water effect is clearly observed especially at the shoalest depth h/L=0.200.
1 0 0 0 OA 船体表面条件を厳密化した低速造波抵抗理論
- 著者
- 下村 芳弘 北沢 孝宗 乾 崇夫 梶谷 尚
- 出版者
- The Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers
- 雑誌
- 日本造船学会論文集 (ISSN:05148499)
- 巻号頁・発行日
- vol.1979, no.146, pp.27-34, 1979 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 12
The low speed wave resistance theory developed by Baba4) and Maruo5) seems to be a promising theory to predict the wave resistance of conventional ships, because it includes the nonlinear effect of the free surface condition. The wave resistance curves calculated by the low speed theory, however, have large humps and hollows, and they do not agree with the measured7) 10) .In this paper, a refinement of the low speed theory is discussed by imposing the more accurate hull surface condition. The wavy source distribution added to satisfy the hull sruface condition is obtained numerically, and the wave resistance, the hull side wave profiles and the velocities around the hull surface are evaluated. The results coincide fairly well with the measured values, especially the humps and the hollows of the calculated wave resistance curves are remarkably reduced.It is ascertained that the added source distribution plays an important role to improve the low speed wave resistance theory, in spite that its strength is one-order smaller than that of the double model source.
1 0 0 0 OA 球状船首の造波効果に関する水槽試験
- 著者
- 乾 崇夫 高幣 哲夫 熊野 道雄
- 出版者
- The Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers
- 雑誌
- 造船協會論文集 (ISSN:18842062)
- 巻号頁・発行日
- vol.1960, no.108, pp.39-51, 1960 (Released:2009-09-16)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 3
As to the wave-interference phenomena connected with the bulb there have been presented two kinds of explanations : one being theoretical, and the other practical.Following the theoretical explanation, which is largely indebted to Havelock and Wigley, we may assume that the wave-making characterististics of the bulbous bow can be safely represented by an isolated point doublet. If admitted, this goes at once to the conclusion that the free wave patterns due to the fitted bulb can be intentionally put just in inverse phase or with strictly half wave-length difference against the main hull waves. This is nothing but the most desirable situation for us in view of promoting the maximum interfering merits of the bulb.On the contrary, the other explanation enforces, rather practically, too much importance of the virtual increment in the wave-making length of the hull which is caused by the bulb waves. In this way, it has long been believed that the reduced wave-making resistance accompanying the bulbous bow has much to do with its increased “effective wave-making length”. From this standpoint of view, it is suggested that, when any amount of bulb merit observed, the bulb waves must proceed by some intermediate fraction between 1/41/2 of ship wave length against the main hull waves. This means that from the bulbous bow we can expect only an incomplete interfering merit at the best.This report is aimed for the experimental determination of the existing conflict, mentioned above, with regard to the 'actual' phase-difference between the bulb waves and the hull waves. The wave analysis procedure is applied for the first time. The conclusion is that the theoretical treatment of the bulb which is introduced by Havelock and Wigley can be practically approved. A few remarks are also made on the two different phases of the hydrodynamical characteristics of the bulbous bow. Its corresponding system of singularities is represented by the combination of an isolated doublet with a continuous source distribution.The former has a positive and therefore the same sense with the latter in hull form characteristics, but has a negative and therefore the reverse sense in wave-making characteristics. This is the true reason why the wavemaking resistance is sometimes reduced remarkably with the bulbous form whose displacement is larger by its bulb than the original form.
- 著者
- edited by Norma Broude and Mary D. Garrard
- 出版者
- University of California Press
- 巻号頁・発行日
- 2005
- 著者
- 鈴木 誠 栗田 和弥 麻生 恵
- 出版者
- 社団法人日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 : 日本造園学会誌 : journal of the Japanese Institute of Landscape Architecture (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.5, pp.5-8, 1995-03-31
- 被引用文献数
- 3 3
日本人と結婚し在日する知日家欧米人とその伴侶の日本庭園に対する認識・イメージをアンケート調査し比較考察した。その結果、彼等の日本庭園の体験度、理解度は日本人と大差はな<、日本庭園に対する感覚的イメージもほば同様であった。日本庭園関連用語などはむしろよく理解していると自認し、外国人にも日本庭園は理解できると彼我共に認めていた。彼我で異なるのは、借景の意味内容や枯山水の認識、わび・さびについての理解がやや低くなることであった。また、「日本庭園」から日本人が具体的庭園要素を連想イメージするのに対し、欧米人は静寂、緑、平和などの印象を多くあげ感性的に庭の雰囲気を享受する姿勢をもつことが認められた。
1 0 0 0 データ並列計算のための拡張C言語NCX
- 著者
- 湯淺 太一 貴島 寿郎 小西 浩
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌. D-I, 情報・システム, I-コンピュータ (ISSN:09151915)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.2, pp.200-209, 1995-02-25
- 被引用文献数
- 10
NCXは,超並列計算実用化のための重要な計算モデルの一つであるデータ並列に基づくプログラミングのために設計された拡張C言語である.C言語からの移行が容易であること,効率の良い処理系が低コストで実現できこと,統一のとれた言語であること,などを目指して設計された.フルセットのC言語を実行する能力をもつ仮想プロセッサ群を基本とし,プロセッサ間通信などのデータ並列計算機能を,ベースとなるC言語の設計方針にできるだけ従って設計されている.さまざまなアーキテクチャ上で使用されることを前提としており,実際にいくつかの異なるアーキテクチャをターゲットとした処理系の開発が現在進められている.本論文では,NCXの主要な拡張機能を,プログラム例と共に概説し,仮想プロセッサという単純明解な概念を基本としながら,データ並列計算に十分な機能をNCXが提供できることを示した.