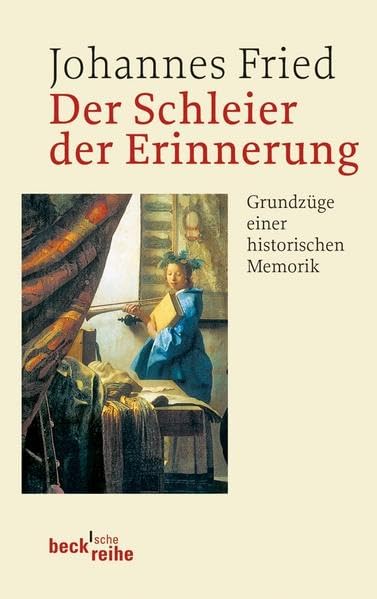1 0 0 0 OA 見ぬ世の友人名目録
- 著者
- [山口豊山] [編]
- 出版者
- [ ]
- 巻号頁・発行日
- vol.東京の部, 1800
1 0 0 0 OA 墓所一覧表
- 著者
- [山口豊山] [編]
- 出版者
- [ ]
- 巻号頁・発行日
- 1800
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経レストラン (ISSN:09147845)
- 巻号頁・発行日
- no.328, pp.52-58, 2003-05
一昔前と比べて、最近は飲食店のサービスレベルが格段にアップした。非常に喜ばしいことだが、時には、サービスの押し売り状態になっていることもあるようで、「そこまでされては、かえってありがた迷惑と感じてしまう」と漏らすお客の声もちらほら聞こえ始めている。店側としてはよかれと思って工夫したサービスも、お客に不快な思いをさせては逆効果だ。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経レストラン (ISSN:09147845)
- 巻号頁・発行日
- no.377, pp.6-8, 2006-11
「第11回 日経レストラン メニューグランプリ」で準グランプリを、第12回にはグランプリを受賞した小倉龍介氏が、今年10月1日に地元の三重県明和町で「Ryu」を開業した。フランス料理がベースの創作料理店。銀行の融資担当者やデザイン会社を驚かせるほどの緻密な経営計画書を作り、グランプリ賞金100万円も充てて建てた念願の自分の店だ。「30歳までに独立するのが夢だった。
- 著者
- 千代 孝夫
- 出版者
- メディカ出版
- 雑誌
- エマージェンシー・ナーシング (ISSN:09154213)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.9, pp.864-866, 2004-09
1 0 0 0 手話ワープロ構築に関する基礎研究
- 著者
- 松本 崇 鎌田 一雄
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)
- 巻号頁・発行日
- vol.1993, no.80, pp.41-48, 1993-09-17
聴覚障害者の多くがコミュニケーション手段として用いている手話と,健聴者が用いている音声言語の相互変換をコンピュータを用いて実現することができれば,両者間のコミュニケーションは円滑なものとなり,その社会的意義も大きいと考える.本稿では,そのようなシステムの1つである「日本語かなべた書き文」から「同時法的手話単語列」」を生成する「手話ワープロ」構築の基礎検討について述べる.今回,日本語解析処理部分には,既成のかな漢字変換システムWnnを利用することで,入力日本語文の制限を緩和している.しかし,Wnnを利用する場合も課題がいくつかあり,その解決方法を示すとともに,今後の課題である手話の使い分け,未登録語に対する対処方法についても述べる.Many of hearing impaired people use signed language as the primary means of communication in daily life, while hearing people use spoken language. The realization of system, that translates sign language into spoken language and vice versa, makes communication between hearing impaired people and hearing ones smooth. In this paper, basic investigation of constructing "Sign Word Processor" that transforms a Japanese Kana sentence into a sequence of Japanese sign words is described. We use a Kana-Kanji translation system called "Wnn" in a part of Japanese analysis and certain processing. We bring up issues to be solved which occur in using "Wnn" and give some approaches to finding their solutions. We furthermore, describe processing techniques for selecting an appropriate sign word among candidates and for non-entry words in Japanese-Sign translation dictionary.
1 0 0 0 OA 19. 雲仙岳の地震活動と阿蘇山の火山活動(日本火山学会1976年度秋季大会)
- 著者
- 澤田 可洋
- 出版者
- 特定非営利活動法人日本火山学会
- 雑誌
- 火山. 第2集 (ISSN:04534360)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, 1976-12-15
「京都」は1994年に世界文化遺産に登録された。本稿は,1990年代後半以降の京都市の景観問題,歴史的環境保全の軌跡を,「伝統の消費」という観点から論じる試みである。具体的には,「町家保全」と「まちなか観光」の動きを追跡することとなる。前稿(野田,2000)では,主に1990年代半ばまでを扱い,<京都らしさ>を求める「外からのまなざし/内からのまなざしの交錯」が,都市計画と景観保全に制度化されたことを指摘した。本稿では,歴史都市・京都をとりあげることによって,世界遺産という「外からのまなざし」によって,「古都という名称のテーマパーク化」が進行しつつあるという,悲観的な診断をもとに,グローバル化の進む現代社会において「外からのまなざし」「グローバルなまなざし」に抗した「都市再生」のあり方について考えてみたい。
1 0 0 0 OA 創薬システムの現状
- 著者
- 丹羽 朋子
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.3, pp.196-200, 1993-07-31 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 21
1 0 0 0 OA 認知面接と修正版認知面接における出来事の再生と反復提示された誘導情報の情報源再認
- 著者
- 白石 紘章 仲 真紀子 海老原 直邦
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 認知心理学研究 (ISSN:13487264)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.33-42, 2006-08-31 (Released:2010-10-13)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1 2
本研究は映画で提示された情報の再生,および情報源再認について,2種類の認知面接の効果を検討したものである.特に,繰り返し誘導情報を与えた場合の情報源再認について,面接の効果を評価した.72名の大学生は映画を見た後,誘導情報を含む事後質問紙に回答した.誘導情報の反復回数は,0回,1回,3回と操作された.24時間後,参加者は,認知面接,“文脈の心的再現”と“悉皆報告”教示で構成された修正版認知面接,または構造面接のいずれかを受けた.面接後,参加者は誘導情報についての情報源再認課題を行った.その結果,修正版認知面接は,認知面接よりも所要時間が短いにもかかわらず,構造面接よりも多くの,認知面接に匹敵する情報量を引き出した.しかし一方で,修正版認知面接,構造面接よりも認知面接で,情報源判断が優れていた.結果について理論的,実務的な観点から考察を行った.
- 著者
- 松下 真也 Shinya Matsushita Matsuyama University Faculty of Business Administration
- 出版者
- 松山大学総合研究所
- 雑誌
- 松山大学論集 (ISSN:09163298)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.31-44, 2013-12
1 0 0 0 可能表現の対象格標示「ガ」と「ヲ」の交替
- 著者
- 青木 ひろみ
- 出版者
- 独立行政法人国際交流基金
- 雑誌
- 世界の日本語教育. 日本語教育論集 (ISSN:09172920)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.133-146, 2008-06-30
1 0 0 0 高専50年問題から何を学ぶか
- 著者
- 大成 博文
- 出版者
- 日本高専学会
- 雑誌
- 日本高専学会誌 : journal of the Japan Association for College of Technology (ISSN:18845444)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.63-68, 2013-07-31
高専創立から今日までの50年間を振り返り,そこに形成された根強い構造的問題を究明するとともに,そこから学ぶべき教訓を明らかにした.まず,専科大学への名称変更を特徴とする「高専危機論」の解明を通じて,高専の将来を自分たちで考え,自分たちで決めるという「自立」の大切さを学んだ.また,高専当初における超過密の詰め込み教育の反省を踏まえ,高専生の発達に則した教育内容を自主的研究に基づく内発的実践の重要性を指摘した.さらに,高専固有の「教育と研究の対立問題」が高専教員の自立を阻害したことを示し,この対立を「教育と研究の両立」によって実践的に解決することの重要性を明らかにした.最後に,テクノセンターを核にして地元の中小企業と親密な連携を特徴とする「地域に根ざした高専づくり」が考察され,とくに企業との共同研究の成功と実績づくりにおいて,高専における総合的な研究力の向上に重要な役割を果たすことを示した.
1 0 0 0 IR 「の」の代用による連用関係の連体関係への転換--ガ格、ヲ格、ニ格、デ格を中心に
- 著者
- 黄 成湘 HUANG Chengxiang
- 出版者
- 千葉大学大学院人文社会科学研究科
- 雑誌
- 千葉大学人文社会科学研究 (ISSN:18834744)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.249-264, 2009-09
「名詞+格助詞+用言」の用言を名詞化して、ガ、ヲ、ニなどの格助詞を「の」に転じ、全体で名詞句を作ることを《「の」の代用による連用から連体への転換》という。本稿は日本語の深層格を再度まとめなおした上で、その深層格の角度から、どんな連用格が「の」の代用によって、連体関係に転換できるかを考察した。その結果、二種のガ格、四種のヲ格、二種のニ格、二種のデ格が「の」の代用で連体関係に転換できることがわかった。
- 著者
- Christoph Wagner Oliver Jehle (Hrsg.)
- 出版者
- Schnell + Steiner
- 巻号頁・発行日
- 2012
1 0 0 0 避難所での指圧救護と主訴
- 著者
- 月足 弘法 中盛 祐貴子 菅原 伸人
- 出版者
- 日本指圧学会
- 雑誌
- 日本指圧学会誌 = Journal of Shiatsu Society of Japan (ISSN:21874883)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.21-23, 2012
- 著者
- Johannes Fried
- 出版者
- C.H. Beck
- 巻号頁・発行日
- 2012