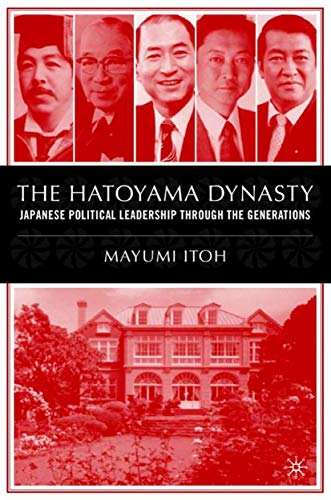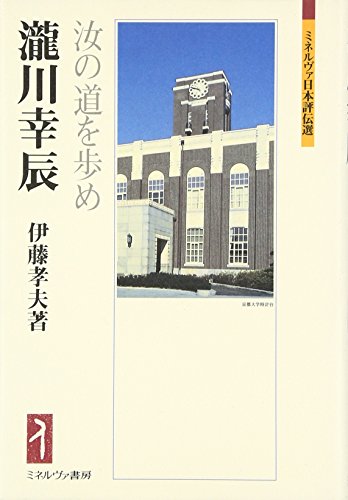- 著者
- 池田 研二
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- Brain and nerve : 神経研究の進歩 (ISSN:18816096)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.5, pp.651-655, 2015-05
- 著者
- 森山 哲美
- 出版者
- The Japanese Society for Animal Psychology
- 雑誌
- 動物心理学年報 (ISSN:00035130)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.101-113, 1981
従来, 刻印づけにおける追従反応は, 離巣性の種 (non-altricial species) の新生児が, その親に対して示す愛着行動の1つとして解釈されてきた。さらに, LORENZzは, その初期の見解 (7) の中で, この刻印づけによる新生児の行動と一般の学習行動とを, 次の2点を基にして区別した。1), 刻印づけは, 不可逆性 (irreversibility) を有する, 2), 刻印づけには, 臨界期 (critical period) が存在する。<BR>LORENZ以降, この2点に関して様々な議論が展開され (1, 5, 6, 9, 10, 12, 13), 現在のところ, この過程については, 「個体のごく限られた時期に獲得形成され, 比較的永続性のある学習の一部である」と解釈されている (8) 。しかし, 追従反応が子の親に対する愛着行動の一種であるとするならば, 個体の, 後の成長過程で受ける様々な社会的刺激 (例えば, 仲間の個体) によって, 何らかの変容をこの反応は受けるものと思われるし, さらに愛着行動に影響する要因として, 親にあたいする刺激対象との接触回数を考えるのであれば, その回数の多少が, 愛着の強さの程度に影響し, 追従反応にも何らかの変化が生ずるものと思われる。もし, このような反応の変容が, 後の個体の成長過程で生ずるのであれぼ, LORENZの主張した不可逆性は, 成立しにくいものと思われる。さらに, 臨界期に関しては, それが過ぎてからも刻印づけの形成が可能であるという報告があり (3), その存在について明確な結論が出されていない。<BR>そこで, 本研究は, ニワトリのヒナの刻印づけの指標として, 刻印刺激への追従時間量ならびに追従出現頻度を用い, 約1ケ月間, 飼育条件 (単独・集団), 刺激呈示条件 (呈示回数) を変化させることによって追従反応に如何なる変化が生ずるかを調べ, さらに臨界期を過ぎた個体でも刻印づけ形成が可能であるか否か検討することを目的とした。
1 0 0 0 OA 明夷待訪録 : 近世支那政治論策
1 0 0 0 公開講座の受講動機と心理的充足に関する考察
- 著者
- 藤岡 英雄
- 出版者
- 徳島大学
- 雑誌
- 徳島大学大学開放実践センター紀要 (ISSN:09158685)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.21-48, 1994-06
- 著者
- 深見 友紀子
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.333-341, 2013
子どもにとって主な音楽学習の場は,学校の音楽室と,一般的に"習い事"と称されている企業の音楽教室や街の音楽教室である.本資料では,筆者の音楽教室で取り入れている情報通信技術,情報通信技術を活用したインフォーマルラーニングの事例を紹介した.具体的には,(1)ピアノ教育雑誌に掲載された情報通信技術に関連する記事,筆者の音楽教室,学校音楽教育における情報通信技術の活用状況を提示した.(2)情報通信技術による音楽聴取機会の増加,情報通信機器の操作スキルの向上等により,子どもたちが音楽演奏へのアプローチの仕方を変化させていること,とりわけ保守的なピアノ教育の現場で,このような動きが子どもたちから自然に生まれてきていることを示した.(3)子どもの音楽学習でインフォーマルラーニングが発展する背景や要件,身につけたスキルを認定することの難しさ等,今後の課題について言及した.
1 0 0 0 OA 日本産Hydnotrya(クルミタケ属)の分子系統解析について
- 著者
- 大前 宗之 折原 貴道 白水 貴 前川 二太郎
- 出版者
- 日本菌学会
- 雑誌
- 日本菌学会大会講演要旨集 日本菌学会第55回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.7, 2011 (Released:2012-02-23)
地中に子実体を形成する菌類,いわゆる地下生菌の大部分は外生菌根菌であり,これらは外生菌根性の樹木が分布する地域を潜在的な分布域とする.日本には,様々な外生菌根性の樹木が広く優占しているため,これら地下生菌の多様性も高いことが推察される.しかし,日本における地下生菌の分類学的な研究は著しく遅れており,その多様性の全貌把握には至っていない.HydnotryaはPezizales,Discinaceaeに含まれる地下生菌であり,日本ではこれまでH. tulasnei(クルミタケ)の一種しか報告されていない.しかし,菌根由来のDNAを用いた系統解析により,日本にはより多くの系統群が分布している可能性が示されている.そこで,演者らは,日本におけるHydnotrya属菌の多様性を明らかにすることを目的とし,採集した子嚢果及びGenBankのデータを用い,核rDNAのITS領域,及び28S領域の分子系統解析を行った.その結果,日本におけるHydnotrya属菌は大きく3つのクレード(クレードA, B, C)に分かれた.クレードAはアジア,北アメリカ,ヨーロッパの種から構成され,その中で,日本産標本は,韓国の外生菌根から検出されたHydnotrya属菌と単系統群を形成した.クレードBは日本産標本のみから構成され,クレードAの姉妹群となった.クレードCは日本産の標本とヨーロッパ産H. cubisporaから構成された.
- 著者
- Mayumi Itoh
- 出版者
- Palgrave Macmillan
- 巻号頁・発行日
- 2003
1 0 0 0 瀧川幸辰 : 汝の道を歩め
1 0 0 0 瀧川事件 : 記録と資料
- 著者
- Yuki Yanagisawa Kosuke Hasegawa Naohisa Wada Masatoshi Tanaka Takao Sekiya
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- Biophysics and Physicobiology (ISSN:21894779)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.69-78, 2015 (Released:2015-11-12)
- 参考文献数
- 19
Chemiluminescence (CL) of firefly luciferin (Ln) consisting of red and green emission peaks can be generated by dissolving oxygen (O2) gas in deoxygenated dimethyl sulfoxide containing potassium tert-butoxide (t-BuOK) even without the enzyme luciferase. In this study, the characteristics of CL of Ln are examined by varying the concentrations of both Ln ([Ln]) and t-BuOK ([t-BuOK]). The time courses of the green and the red luminescence signals are also measured using a 32-channel photo sensor module. Interestingly, addition of 18-crown-6 ether (18-crown-6), a good clathrate for K+, to the reaction solution before exposure to O2 changes the luminescence from green to red when [t-BuOK] = 20 mM and [18-crown-6] = 80 mM. Based on our experimental results, we propose a two-pathway model where K+ plays an important role in the regulation of Ln CL to explain the two-color luminescence observed from electronically excited oxyluciferin via dioxetanone.
1 0 0 0 OA 放送コンテンツアーカイブのためのメタデータモデル構築
- 著者
- 萩原 和樹 三原 鉄也 永森 光晴 杉本 重雄
- 出版者
- 「ディジタル図書館」編集委員会
- 雑誌
- ディジタル図書館 (ISSN:13407287)
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.10-18, 2014-11-11
- 著者
- 両角 彩子 永森 光晴 杉本 重雄
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告情報学基礎(FI)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, no.105(2008-FI-092), pp.1-14, 2008-10-30
近年の情報技術の発展に伴い、マンガ作品の情報の共有・交換が盛んに行われるようになった。筆者らの研究室では、マンガに関する情報を統合的に扱うためのマンガメタデータスキーマを開発している。その一部に、読者が作品の内容を書き表すためのメタデータスキーマがある。本稿はマンガの知的内容を表すことを目的としているため、同心ストーリーの表現手法である小説や映画も参考にする。そこで、 Wikipedia 内に表れるマンガ麹小説の作品記事から 100 件をそれぞれ無作為に抽出し、記述項目について調査した。これらの調査結果および目次テンプレートを参考に、読者が作品の知的内容を書き表すためのメタデータ基本セットを提案する。
- 著者
- 谷口 祥一 鴇田 拓哉
- 出版者
- 日本図書館研究会
- 雑誌
- 図書館界 (ISSN:00409669)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.5, pp.572-580, 2010-01-01
1 0 0 0 OA 利用者の特性と環境に応じたリソース選択のためのメタデータスキーマモデル
- 著者
- 両角 彩子 杉本 重雄
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告情報学基礎(FI)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.108(2005-FI-081), pp.7-18, 2005-11-02
利用者の特性に関わらずリソースを簡単に探し出し、利用できること、すなわちリソースへのアクセシビリティを高めることへの要求が、リソースやリソースの利用方法・利用目的の多様化によって高まっている。たとえ内容が同一であるとみなすことのできるリソースであっても、利用者の特性に応じた方法で表現され、また、利用環境に応じた形式で実現されたリソースを、利用者が簡単に選択し、提供することが求められる。この要求を満たすためには、「どのような特性を持つ利用者」が「どのような環境」で「どのようなリソース」を利用したいのかという利用者の要求を表現した上で、利用者の要求とそれにマッチするリソースを選択し、適切なリンクを提供する仕組みが必要である。そこで、利用者が簡単に自らの特性や利用環境に適したリソースへアクセスできるようにすることを目的として、本稿では、アクセシビリティのためのメタデータ、IFLAによるFunctional Requirements for Bibliographic Records (FRBR)、OpenURLの動的なリンキング機能等に基づいて、利用者の特性や環境と、リソースという双方の視点からアクセシビリティに関する情報を表現し、適切に利用者とリソースを結びつけるメタデータスキーマのモデルを提案する。
1 0 0 0 OA バディキッズ・アドベンチャー・チャレンジ・プログラムの開発と実践
- 著者
- 遠藤 大哉 青柳 健隆 岡 浩一朗
- 出版者
- 日本スポーツ産業学会
- 雑誌
- スポーツ産業学研究 (ISSN:13430688)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2, pp.2_185-2_199, 2015 (Released:2015-11-12)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1
Outdoor education contributes to positive youth development. Existing outdoor education in Japan has been conducted only in an “episodic” manner with a “single activity” basis in “imitation nature”, although regular and various activities in “grand nature” have been considered more valuable for the growth of children. Therefore, the purposes of the present study were to develop and practice an outdoor education program that performed a “plural number” of experiences with “multiple activities” in “genuine nature”, and to clarify the availability of the program. For this purpose, the “Buddy Kids Adventure Challenge Program” was developed on the basis of 12 years of practice with the “Buddy Adventure Team (Non-Profit Organization)”. An inventory survey was conducted for 49 participants in the Buddy Kids Adventure Challenge Program and 26 participants′ parents to evaluate the program in 2013. Free descriptive answers for the questions with respect to experiences in the program were descriptively analyzed and a model of the growth of the participants in the Buddy Kids Adventure Challenge Program was generated. As results, self-esteem was increased by developing competence. Additionally, outdoor activities in the program and flow experience were associated. Strong relationship between adverse circumstances and flow experience were also demonstrated. The growth model of the present study showed that desiring pleasure in “grand nature” could allow participants to confront adverse circumstances. These adverse circumstances give participants flow experience and confidence by helping them to overcome adverse circumstances. Finally, self-esteem was increased and growth of participants was enhanced.
- 著者
- 小川 芳樹 西川 清史
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会総合大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2011, 2011-02-28
1 0 0 0 OA スポーツのルールと身体文化 : キックボクシングを事例に
- 著者
- 木本 玲一
- 出版者
- 相模女子大学
- 雑誌
- 人間社会研究 (ISSN:13494953)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.69-88, 2015-03