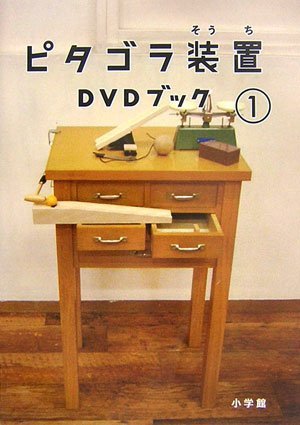1 0 0 0 OA 小学校算数における乗法の導入問題に関する研究
- 著者
- 上岡学
- 出版者
- 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会第56回総会
- 巻号頁・発行日
- 2014-10-09
はじめに日本の小学校の算数教育において、乗法指導の導入は1当たり量を先(被乗数)に記述する指導方法が定着している。そこで本研究では、乗法の導入問題を作成するときに1当たり量が先にくる問題がどのぐらいの割合で出現するのかを調査研究した(調査1)。さらに乗法の導入問題において1当たり量が問題文中において後半にある場合(逆向問題)、立式はどのように考えたらよいのかについても調査研究した(調査2)。(調査1)(方法)大学生に対して、「かけ算の導入問題としてふさわしいと思う問題を作成してください」という課題を与える。(対象)大学生84名(結果)(1)「かけ算導入問題」について①1当たり量が前半(先)にくる問題(順行問題)の出現率は、63.1%であった。たとえば、「2つのおかしが入った袋が3つあります。おかしは全部でいくつですか。」という問題である。「前半の数字×後半の数字」とすれば、自動的に「1当たり量×かける数」となる問題である。②1当たり量が後半(後)にくる問題(逆行問題)の出現率は、29.8%であった。たとえば、「4人の友だちに、チョコレートを5つずつ配ります。チョコレートはいくついりますか。」という問題である。1当たり量を先という指導であれば、「後半の数字×前半の数字」となり、意識して「1当たり量×かける数」と逆にしなければならない問題である。③1当たり量が交換可能な問題(中立問題)の出現率は、1.2%であった。たとえば、「学校の靴箱は、縦に5つ、横に6つ並んでいます。全部でいくつの靴箱がありますか。」という問題である。どちらの数も同等の関係である問題である。(長方形の面積の公式は「縦×横」であるので、「縦」が「1当たり量」であると考えれば①に含まれるが本研究では③とする。)④その他課題意図の取違えは、6.0%であった。(調査2)(方法)逆向問題「5人の友達にチョコレートを3つずつ配ります。全部でいくつでしょうか。」という問題を提示して、それに対する立式の考えを5択(A:式は5×3であり、3×5は間違いである/B:式は5×3であるが、3×5でもよい/C:式は3×5であり、5×3は間違いである/D:式は3×5であるが、5×3でもよい/E:式は5×3でも、3×5でもよい)から選択する。(対象)大学生80名(結果)①A「式は5×3であり、3×5は間違いである」は現行の指導方法から最も遠い考え方であるが16.3%であった。また議論になることがあるC「式は3×5であり、5×3は間違いである」については15.0%であった。意味を理解していれば認められるべきE「式は5×3でも、3×5でもよい」は10.0%であった。②BとCは、一方の指導を強調するが、他方も許容であるとする考え方であるが、いずれも約30%であり、合わせると約60%であった。
1 0 0 0 最も新しい結核征服の科学 : 忘れられた精神療法
1 0 0 0 OA 25億までの素数の分布について
- 著者
- 松浦 孝行
- 出版者
- 産業医科大学学会
- 雑誌
- 産業医科大学雑誌 (ISSN:0387821X)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.3, pp.381-390, 1982-09-01
素数および整数に関する研究の一資料として, 25億までの素数の分布について調べ, その結果を一部まとめて若干のTableを作成した. Tableは全部で5つあり, それぞれ1千万までの10万区間ごと, 1億までの100万区間ごと, 10億までの1千万区間ごと, 25億までの1億区間ごと, 特定のいくつかの10万区間に関するものである. 表の内容には, 素数の個数, 双子素数の組の個数, 最大の双子素数の組, 120m+1型素数の個数, 最大の120m+1型素数およびTablel・Table2ではその原始根, 連続する2つの素数が切取る最大区間, 10万区間における素数の個数の最大・最小値,10万区間における双子素数の組の個数の最大・最小値, Table5では三つ子素数の組の個数などが含まれている.
1 0 0 0 『中右記』 卒伝について
- 著者
- 杉本 理
- 出版者
- 学術雑誌目次速報データベース由来
- 雑誌
- 古代文化 (ISSN:00459232)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.31-38,55, 1993
1 0 0 0 OA 学校法人城西大学創立50周年記念事業『寒椿』水田三喜男伝[ポスター]
- 著者
- 学校法人城西大学出版会
- 出版者
- 学校法人城西大学出版会
- 巻号頁・発行日
- 2015-06 (Released:2015-06-01)
学校法人城西大学創立50周年記念事業
- 著者
- Hiroaki OHFUJI Masashi YAMAMOTO
- 出版者
- 一般社団法人日本鉱物科学会
- 雑誌
- Journal of Mineralogical and Petrological Sciences (ISSN:13456296)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, no.4, pp.189-195, 2015 (Released:2015-08-29)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 15
This study demonstrates the validity of a thin osmium coating for quantitative energy–dispersive spectroscopic (EDS) analysis, particularly for light elements such as O (and potentially C and N) in natural/synthetic minerals. An osmium coating prepared by chemical vapor deposition provides an extremely thin and uniform layer whose thickness can be controlled simply by coating time. Because of the high reproducibility and reliability of the osmium coating process, users have no difficulty in evaluating the actual coating thickness, which enables strict and precise absorption corrections (for the coating layer), even for low–energy characteristic X–rays, which are susceptible to attenuation by the coating layer itself. Our results show that oxygen concentrations in silicate and oxide minerals can be quantified correctly when using the osmium coating, whereas quantification using a carbon coating afforded values that were a few wt% lower than stoichiometry, probably due to the uncertainty of the actual coating thickness (i.e., the absorption correction was incorrect). The ability to accurately quantify oxygen may stimulate new analytical applications, such as the estimation of Fe2+/Fe3+ concentrations and water content in minerals. Furthermore, the Os–coated samples prepared for EDS analysis are also suitable for electron back–scattered diffraction (EBSD) analysis without re–polishing and re–coating, which are usually routine but time–consuming tasks in the case of carbon–coated samples.
1 0 0 0 タマガイ類の捕食活動の進化学的研究
1.“生きている化石"モクレンタマガイの解剖学的研究を行った結果、この巻貝は原始的な神経系をもち、多くの点で淡水性のリンゴガイ科の巻貝に近縁であることが明らかとなった。また、モクレンタマガイは肉食性ではなく、植物食であったことが明らかとなった。この発見により、タマガイ類は白亜紀中頃に出現し、従来三畳紀から知られているモクレンタマガイ類とは類縁が薄く、しかもそれらは他の貝類に穿孔して捕食しなかったと考えられる。その結果、タマガイ類とその捕食痕の化石記録は調和的となり、従来のタマガイ類の捕食の起源についての2説のうち、白亜紀中期起源説が正しいことがわかった。2.タマガイ類の捕食痕を調査した結果、それらの中には他の原因で似たような穴ができることがわかった。1つはカサガイ類による棲い痕で、白亜紀のアンモナイトの殼表面に多く見つかった。これらは小型のカサガイ類が殼表面の1ヶ所に定住する為、その部分が殼形と同じ形に凹むためにできたと思われる。穴はタマガイ類の不完全な捕食痕のようにパラボラ形で中央がやや凸となるが、形は大きくやや不規則な点などで区別ができる。従来、モササウルスの噛み痕といわれているプラセンチセラス属アンモナイトの穴も同じ起源と考えられる。その他、無生物的にタマガイ類の捕食痕に似た穴ができることもわかった。3.巻貝各種のタマガイ類の捕食痕を調査した結果、殼形により捕食の様式が異なる1例を見出した。これは巻貝の殼形態が長く伸長することが捕食から身を守る適応形態となっていることである。つまり、殼の伸長度と捕食痕の数の頻度を調べた結果、殼形が長くなると捕食痕数も増加することがわかった。従来捕食痕をもつ個体の頻度で捕食圧を推定した研究例は再評価する必要がでてきた。
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1933年03月13日, 1933-03-13
- 著者
- 戸部 順一
- 出版者
- 成城大学
- 雑誌
- 成城文藝 (ISSN:02865718)
- 巻号頁・発行日
- vol.185, pp.40-20, 2004-02-25
- 著者
- N. Ota N. Gorjizadeh Y. Kawazoe
- 出版者
- (公社)日本磁気学会
- 雑誌
- Journal of the Magnetics Society of Japan (ISSN:18822924)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.5, pp.573-578, 2010-09-01 (Released:2010-09-14)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 6 34
Several experiments have recently found room-temperature ferromagnetism in graphite-like carbon based materials. This paper offers a model explaining such ferromagnetism by using an asymmetric nano-graphene. Our first typical model is C48H24 graphene molecule, which has three dihydrogenated (-CH2) zigzag edges. There are several multiple spin states competing for stable minimum energy in the same atomic topology. Both molecular orbital and density function theory methods indicate that the quartet state (S=3/2) is more stable than that of doublet (S=1/2), which means that larger saturation magnetization will be achieved. We also enhanced this molecule to an infinite length ribbon having many (-CH2) edges. Similar results were obtained where the highest spin state was more stable than lower spin state. In contrast, a nitrogen substituted (-NH) molecule C45N3H21 demonstrated opposite results. that is, the lowest spin state (S=1/2) is more stable than that of highest one (S=3/2), which arises from the slight change in atom position.
1 0 0 0 OA 海洋温暖化がエイ類の生物量、分布および行動生態に及ぼした影響の解明
本研究では近年の温暖化傾向がエイ類に与えている具体的な影響について検証することを目的として調査を行った。その結果,モデル海域である有明海でのエイ類の分布特性と種組成,東アジア河口域生態系におけるエイ類の分布状況について新たな知見を得ることができ,有明海および東アジア河口域との共通種についてリストアップすることができた。それらの生物情報に基づき,温暖化により西日本に卓越したと考えられたナルトビエイの分布,日周行動,行動と水温との関係について解析した。ナルトビエイは従来から少なくとも九州沿岸域には分布していたが,冬季の平均的な水温が上昇傾向にあることから繁殖・摂餌場に近い深場で越冬可能となり,徐々にその分布を本州西部にまで拡大した可能性があること等を明らかにした。
1 0 0 0 ピタゴラ装置DVDブック
- 出版者
- 小学館
- 巻号頁・発行日
- 2006
- 著者
- 井手 弘人
- 出版者
- 長崎大学
- 雑誌
- 長崎大学教育学部紀要 (ISSN:21885389)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.29-41, 2015-03-01
- 著者
- Mogi Kiyoo
- 出版者
- 東京大学地震研究所
- 雑誌
- 東京大學地震研究所彙報 (ISSN:00408972)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.99-134, 1958-07-23
噴火の際に火山周辺の地殻が著しく変動することは,古く1910年の有珠山の噴火の場合に大森博士によつて精密水準測泣が行われて以来,主な噴火について同様の測量が実施されて,次第に明らかになつて来た.これらの火山周辺の地殻変動に関する研究は必ずしも少なくないけれども,火山の噴火の機構との関係としてその火山学的意味を吟味したものはほとんど見られない.本論文ではこれまでに得られた測量の結果を調べて地殻変動の特性及び,噴火現象との関係を明らかにすることを試みた.
1 0 0 0 歌舞伎を救ったのは誰か?--アメリカ占領軍による歌舞伎検閲の実態
- 著者
- Brandon James 鈴木 雅恵
- 出版者
- 日本演劇学会
- 雑誌
- 演劇学論集 (ISSN:13482815)
- 巻号頁・発行日
- no.42, pp.145-197, 2004
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 橋本 碩
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- 動物分類学会誌 (ISSN:02870223)
- 巻号頁・発行日
- no.37, 1988-06-25
1 0 0 0 OA 20~30歳代校友の多様なネットワーク開発 -首都圏をモデルケースとして
1 0 0 0 日本語の主語小考
- 著者
- 谷守 正寛
- 出版者
- 甲南大学国際言語文化センター
- 雑誌
- 言語と文化 (ISSN:13476610)
- 巻号頁・発行日
- no.19, pp.137-150, 2015
1 0 0 0 OA 在香港フィリピン人家事労働者の現況 : 香港が就労先として選択される理由
- 著者
- 合田 美穂
- 出版者
- 甲南女子大学
- 雑誌
- 甲南女子大学研究紀要. 人間科学編 = Studies in human sciences (ISSN:13471228)
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.75-81, 2008-03-20
1980年代以降,香港からの「プル要因」,フィリピンにおける「プッシュ要因」の相乗効果で,多くのフィリピン人女性が,家事労働者として,香港に渡ってきた。彼女たちは,香港にて家事労働を担うことによって,香港人社会の家庭における問題を解決し,また,それと同時に,フィリピンに外貨収入をもたらすことによって,フィリピン経済の活性化にも貢献し続けている。本研究では,外国人家事労働者に関する労働法例,就労における諸問題,フィリピン人家事労働者の香港流入の背景,余暇活動についての考察を行ない,それらの考察を通して,在香港フィリピン人家事労働者の現況を理解するとともに,なぜ,彼女たちが,香港を選択したのかという理由を導くことにつとめたものである。