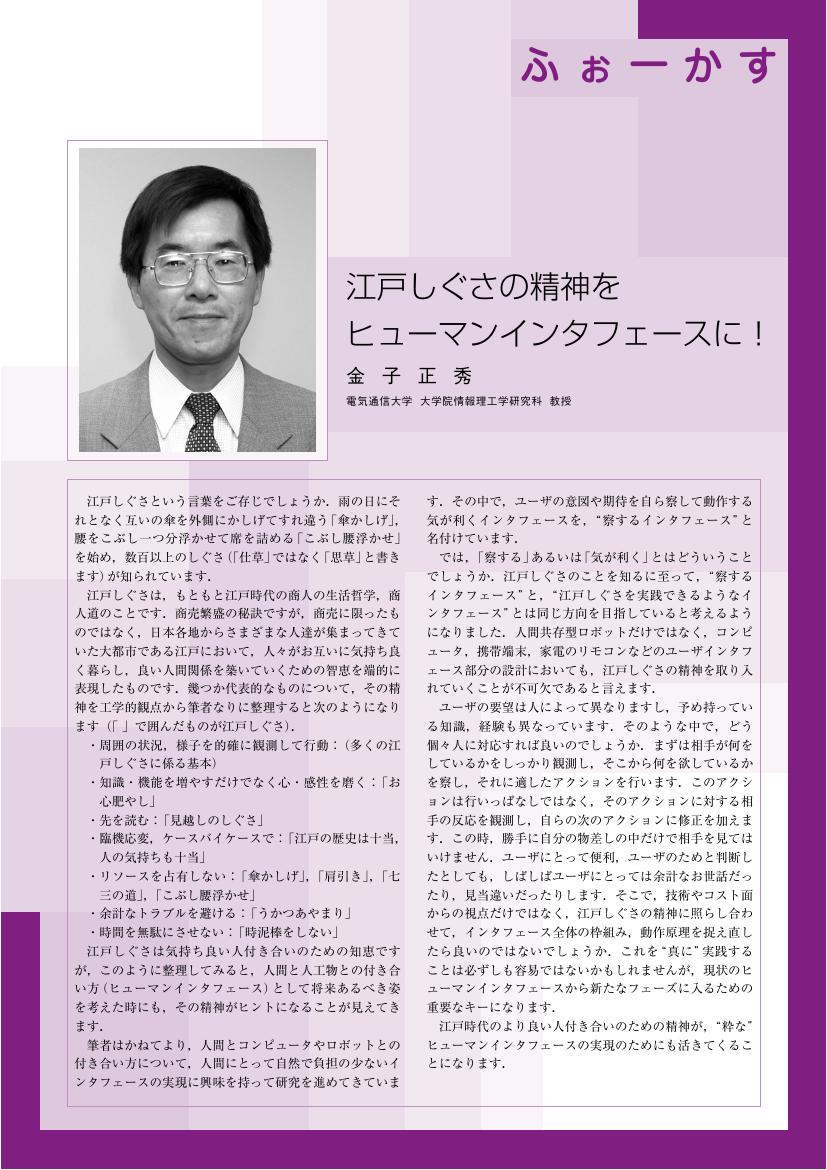1 0 0 0 OA 複数人による知識創造活動を行う会議に及ぼす室内音環境の影響
- 著者
- 辻村 壮平 秋田 剛 小島 隆矢 佐野 奈緒子
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.711, pp.397-405, 2015 (Released:2015-06-24)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 9
In order to investigate an influence of indoor sound environment in office on knowledge creative activity, subjective experiments were conducted in our study. In this experiments, subjective evaluations on “ease of meeting”, “quietness of sound environment” and “listening difficulty of speech” in two different types of group meetings (decision-making meeting and discussion to think of creative ideas) were measured under five types of sound environmental conditions (no-noise LAeq, 5min 38 dB, ambient noise (conversation noise) LAeq, 5min 40 dB, 45 dB, 50 dB, 60 dB) in a meeting room of the university. From the results, in regard to “quietness of sound environment”, we found that subjects start feeling noisy (not quiet) in sound environmental condition of ambient noise 50 dB, and that of 60 dB have an increased “listening difficulty of speech”. In the ambient noise 50 dB, “ease of meeting” was the highest evaluation for discussion to think of creative ideas among these experimental conditions. Furthermore, to investigate psychological factors related to ease of meeting, multiple regression analysis was performed using the data obtained from subjective experiments. These results of multiple regression analysis show that a quiet sound environment is not necessarily desirable in discussion to think of creative ideas. It was found that very quiet sound environment decrease the evaluation of “ease of meeting” in discussion to think of creative ideas. Thus, it was suggested that recommended indoor sound environmental condition to conduct discussion to think of creative ideas was ambient noise 50 dB.
1 0 0 0 OA 合併は地域に何をもたらしたのか - 京都・滋賀の事例検証 -
- 著者
- 岡田 知弘 京都大学経済学部岡田ゼミナール
- 出版者
- 京都大学経済学部岡田ゼミナール
- 巻号頁・発行日
- pp.1-176, 2015-02
序 本書は、京都大学経済学部岡田ゼミナールの2013年度調査報告書である。今回、2・3回生ゼミナールの学生諸君が共同テーマにしたのは、「平成の大合併」の検証である。「平成の大合併」とは、周知のように1999年の合併特例法と、それを引き継いだ「合併新法」によって2010年度まで続けられた、政府主導の市町村合併政策である。ほぼ10年の聞に、日本の市町村数は3232から1730まで減少した。政府は、当初、「地方分権の受け皿としての基礎自治体の行財政基盤の確立」を掲げ、1000市町村に集約することを目標としていたが、全国各地で合併反対の動きがあり、その目標は達成できなかった。1999年の合併特例法では、合併特例債の発行や地方交付税の算定替え特例(合併前の自治体ごとに交付税を計算し、合算額を10年間にわたり交付。その後5年かけて、新市のみの一本算定とし本来の交付税水準に削減する)という「アメ」とともに、小規模自治体ほど地方交付税の削減率を高める「ムチ」の政策手段が準備され、合併を推進した。しかも、その際に、「合併すれば地域は活性化する」という言説が意図的に流布された。例えば、小泉内閣の「骨太の方針2001」では、「『個性ある地方』の自立した発展と活性化を促進することが重要な課題である。このためすみやかな市町村の再編を促進する」と明記された。市町村合併によって地域が活性化するという理由について、当時の総務省のホームページでは、「より大きな市町村の誕生が、地域の存在感や『格』の向上と地域のイメージアップにつながり、企業の進出や若者の定着、重要プロジェクトの誘致が期待できます」と掲げられたのである。「感」「格」「イメージ」「期待できます」という、客観的な根拠に基づかない、主観的な言葉と期待感で活性化が語られていたといえる。ところが、時間経過とともに、合併による効果が、地方行財政面だけでなく、地域経済・地域社会への影響として、芳しくないことが全国各地から指摘されるようになった。その結果、2009年6月の第29次地方制度調査会の答申では、政府主導による市町村合併については「一区切り」をつけるとされたのである。同調査会発足当時は、自公政権の下で、さらなる市町村合併に加えて、現行の都道府県を廃止し、国の地方出先機関と再編統合をはかる道州制の導入も本格的に検討されようとしていた。だが、同調査会においては、合併検証なくしてさらなる市町村合併をすすめるべきではないという意見が多く出されたのである。「平成の大合併」においては、2004年から05年にかけて合併した自治体が多い。それらの自治体は、合併から10年を迎え、種々の特例措置が終了しつつある。現時点において、市町村合併が地域に対してしいかなる影響をもたらしているのか、この点を調べてみたいというのが多くの学生の共通の問題関心となった。事前学習や松本市での合宿調査を経て、今回のゼミナールでは3つのグループをつくることにした。そのグループ分けの基準のひとつは、合併方式の違いによる。合併方式には、大きな都市自治体に周辺の小さな自治体が編入される「編入合併」と、自治体同士が対等合併し新しい自治体を形成する「新設合併」の2つがあり、両者を対象にするということである。本報告書では、II章の京都市と京北町との合併が「編入合併」にあたる。第二に、「新設合併」についても農村部の町村が合併するタイプと、比較的都市化した市町が合併するタイプがある。本報告書では、I章の南丹市の合併が前者にあたり、III章の滋賀県近江八幡市の合併が後者にあたる。近江八幡市と安土町との合併を採り上げたのは、京都府以外の府県における市町村合併をみてみたいということと、激しい合併反対運動が展開された旧安土町の合併後の状況を調査してみたいという問題意識からであった。調査は、グループごとに、合併の経緯や行財政分析等の共通事項を設定することに加え、それぞれの地域固有の特性(地域産業、高齢化と福祉、合併反対運動、地域自治組織等)に着目し、深く掘り下げる方法をとった。どのグループも、行政機関にとどまらず、経済団体、住民自治組織、住民団体、議員等へのヒアリングを中心に調査を実施したが、II章の京北町地域では、自治振興会のご協力をえて住民アンケートも試みた。これらの調査結果をグループごとにまとめる作業を行ったが、できるだけ客観的なデータに基づく検証を行うこととしたために、膨大なページ数の報告書となった。いま、行政を中心とした合併検証報告書が各自治体で公表されつつあるが、それらと比較するならば、本報告書の特徴は、学生の視点から、行財政分野に限定せず、住民の地域生活や経済活動、さらに自治行為にいたる多面的な分野にわたる地域への影響を丁寧かつ率直に明らかにしていったところにある。もとより、そこには認識不足による不十分な記述や、誤解による記述も残されている可能性もある。それらを含めて、ひとつの合併検証の記録として、参照いただければありがたいと思う。併せて、忌憚のないご批判をいただければ幸いである。
1 0 0 0 OA Acute Hypertensionの内耳におけるExtravasationへの影響
- 著者
- 橘 正芳
- 出版者
- THE JAPAN OTOLOGICAL SOCIETY
- 雑誌
- Ear Research Japan (ISSN:02889781)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.13-16, 1981 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 11
1 0 0 0 OA 階層的独立固有時間刻み法によるグラフ可視化計算の高速化
- 著者
- 松林 達史 山田 武士
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌数理モデル化と応用(TOM) (ISSN:18827780)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.SIG15(TOM18), pp.126-136, 2007-10-15
本研究では,大規模なネットワークデータのための高速かつ効率的な可視化座標計算の手法を提案する.従来のネットワーク可視化手法の1つとして Fruchterman らによる力学モデルを用いる手法がよく知られている.彼らの手法はノード間やエッジに対し力学関数を与えることにより,系全体のエネルギーを定義し,加速度方向に各ノードの座標を更新することによって,系のエネルギーの極小状態を求める.この手法では座標の更新頻度は一様で,すべてのノードを毎回更新していたが,提案手法では階層的独立固有時間刻み法を用いて個々のノードに独立な更新時間を設定し,局所的に更新頻度を変えることにより計算の高速化を可能にした.この手法は,天体力学において用いられている局所的に密集した領域を精度良く計算する手法を,グラフ可視化手法に拡張したものである.また,提案手法は並列処理に適しており,粒子間相互作用専用並列計算機 MDGRAPE-3 PCI-X に実装することによって,計算速度の数百倍高速化が可能であることを示した.さらに,LGL(Large Graph Layout)法を用いた Opte Project の可視化結果との比較を行い,提案手法により高精度な可視化が可能であることを示した.
1 0 0 0 歯科治療に関連した重篤なショック, 心肺停止報告200例の検討
- 著者
- 伊藤 寛 小川 幸恵 清野 浩昭 川合 宏仁 山崎 信也 奥秋 晟
- 出版者
- The Japanese Society of Reanimatology
- 雑誌
- 蘇生 (ISSN:02884348)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.82-87, 2005-07-20
- 被引用文献数
- 17
歯科治療における死亡事故報告は後をたたない。我々は, 各種メディアから知り得た歯科治療に関連した重篤なショック, 心肺停止報告200例について分析した。その結果, ショック45例, 心肺停止155例, 死亡126例であった。これらの多くは局所麻酔や観血処置に起因し, 何らかの全身的合併症を有していたものが全200例中75例 (38%) であった。また小児, 障害児者に多く行われる抑制治療が起因と思われる死亡は19例で, 全死亡例の15%であった。このような事故を回避するために, 歯科医師の医学知識全身管理能力の向上が必要であり, 特に, 最低限のリスクマネージメントとしてBLS, ACLSの習得は必須であると思われた。
1 0 0 0 OA エンドウの病害抵抗性に果すピサチンの役割とその制御機構
- 著者
- 白石 友紀
- 出版者
- 日本植物病理学会
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.295-295, 1980-07-25 (Released:2009-02-19)
1 0 0 0 OA ラジオ放送番組一覧表初期ラジオ放送研究のために
1 0 0 0 診断力てすと 下顎骨の硬い無痛性の腫脹
- 著者
- 平賀三嗣
- 雑誌
- デンタルダイヤモンド
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.19-20, 2004
- 被引用文献数
- 1 1
- 著者
- 藤野 ヤヨイ 藤野 邦夫
- 出版者
- 精神看護出版
- 雑誌
- 精神科看護 (ISSN:09105794)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.8, pp.72-75, 2003-08
1 0 0 0 OA チュニジア革命と非暴力行動論
- 著者
- 三石 善吉
- 出版者
- 筑波学院大学
- 雑誌
- 筑波学院大学紀要 (ISSN:18808859)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.1-13, 2012
1 0 0 0 OA 248 母子・父子家庭と保育所
- 著者
- 上村 康子
- 出版者
- 日本保育学会
- 雑誌
- 日本保育学会大会研究論文集
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.496-497, 1991-05-01
1 0 0 0 學童唱歌 : 小學校教科用
1 0 0 0 IR 小学校における中休み牛乳提供の実践とその効果
- 著者
- 石井 雅幸 矢野 博之 鈴木 映子
- 出版者
- 大妻女子大学
- 雑誌
- 大妻女子大学家政系研究紀要 (ISSN:1346860X)
- 巻号頁・発行日
- no.47, pp.27-37, 2011-03-03
1 0 0 0 OA 産業廃棄物不法投棄現場の考古学的復元
- 著者
- 遠部 慎
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物学会研究発表会講演論文集 第19回廃棄物学会研究発表会
- 巻号頁・発行日
- pp.273, 2008 (Released:2008-11-25)
本発表では、これまでほとんど注目されていない考古学的な記録を基に、旧石器時代以降の水ヶ浦一帯の過去をまとめてみた。この半世紀の中で、水ヶ浦一帯にもっとも大きな爪跡を残した豊島事件であるが、事件に先立ち、真っ先に破壊されたのは、景観とともに遺跡である。今後、不法投棄を引き起こさないためにも、各地域でこのような事件を語り継ぐという観点は必要であるが、本研究のように、長いタイムスパンの中で、産業廃棄物不法投棄現場に歴史的な意味を見出す事例は少ない。さらに遺跡破壊と産業廃棄物不法投棄が同時に行われた事例についての検討という意味では、まさにモデルケースとなろう。
- 著者
- Hang Chuon Naron
- 出版者
- Ministry of Economy and Finance : Supreme National Economic Council
- 巻号頁・発行日
- 2008
1 0 0 0 OA 江戸しぐさの精神をヒューマンインタフェースに!
- 著者
- 金子 正秀
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.k11-k11, 2011 (Released:2013-03-01)
1 0 0 0 肝がんなんかに負けないぞ―最新の肝がんの診断と治療―
- 著者
- 舛井 秀宣
- 出版者
- Study Group of Microwave Surgery
- 雑誌
- Journal of Microwave Surgery (ISSN:09177728)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.33-38, 2009
Treatment results for HCC were the barrel severely one, 30 years ago. At that time, the liver resection was not safe maneuver yet, though there was no effective treatment method except the liver resection. Afterwards, the liver resection has rapidly evolved to the safe cure by the establishment of hemostasis such as microwave coagulation during resection and the development of the operation equipment. <br>Hepatic resection and other treatment for HCC have showed remarkable progress in these 2 decades. This progress brought dramatic improvement of curability for HCC. <br>In addition, advancement of diagnostic imaging, development of tumor maker of HCC resulting in definition of high risk group of HCC, led to the further improvement of treatment result of HCC.