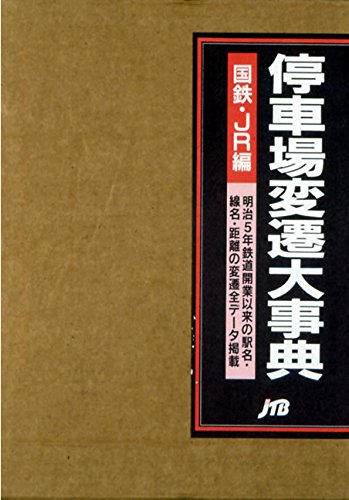- 著者
- 神事 努 森下 義隆 平山 大作
- 出版者
- 日本バイオメカニクス学会
- 雑誌
- バイオメカニクス研究 : 日本バイオメカニクス学会機関誌 (ISSN:13431706)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.41-46, 2012
5 0 0 0 OA 社会的スキルおよび共感反応の指向性からみた大学生のウェルビーイング
- 著者
- 鈴木 有美 木野 和代
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.125-133, 2015 (Released:2015-03-26)
- 参考文献数
- 39
- 被引用文献数
- 1 3
本研究は,ウェルビーイングの検討において共感性を考慮する重要性に着目し,特に共感性の感情的側面である共感反応の他者指向性―自己指向性の違いに焦点を当ててウェルビーイングにおける差異を検討した。大学生210名を対象とした相関分析の結果から,他者指向的な共感反応傾向および社会的スキルの高い者ほど日常生活や対人関係で満足している一方,自己指向的な共感反応傾向が高く社会的スキルの低い者ほどディストレスの多い傾向が明らかとなった。また,他者/自己指向的な共感反応および社会的スキルにより分析対象者を4クラスタに分類し,ウェルビーイングの差異を検討した分散分析では,他者指向的な共感反応傾向が高く,自己指向的な共感反応傾向が低く,社会的スキルの高いクラスタのウェルビーイングが良好であった。これらにより,自身のウェルビーイングを維持するためには,社会的スキルが高いというだけでなく,他者指向的に共感すると共に自己指向的に共感しない重要性が示された。
5 0 0 0 OA 鼻副鼻腔炎検出菌に対する局所療法の効果 ベストロン®, イソジン®を用いて
- 著者
- 藤原 啓次 酒井 章博 保富 宗城 山中 昇
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.7, pp.599-604, 2004-07-01 (Released:2011-10-07)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2 3
We clinically studied the effectiveness of nasal nebulizer therapy with cefmenoxime hydrochloride (CMX) and nasal drops of povidone iodine for acute rhinosinusitis in children. We evaluated the results using the standard for new antibiotics of the Japanese Society of Chemotherapy. The subjects were 50 children with acute rhinosinusitis. By the standard for total evaluation, consisting of clinical and bacteriological study, the cure rate of the CMX nebulizer group was 68%, that of the group using nasal drops of povidone iodine was 23.1%, and that of the controls was 38.5%. The cure rate with nasal drops of povidone iodine was not higher than that with CMX nebulizer therapy. However, with the nasal drops of povidone iodine, in 2 of 3 cases, PISP (penicillin intermediately resistant S. pneumoniae) disappeared and in 2 of 2 cases, MRSA (methicillin-resistant S. aureus) disappeared. The nasal drops of povidone iodine were found to be effective for drug-resistant organisms such as PISP and MRSA.
5 0 0 0 OA 歯周病治療による菌血症と人工関節感染
- 著者
- 小林 哲夫
- 出版者
- 日本関節病学会
- 雑誌
- 日本関節病学会誌 (ISSN:18832873)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.97-101, 2017 (Released:2018-07-31)
- 参考文献数
- 29
Bacteremia occurs through the translocation of oral bacteria from subgingival biofilms into the systemic circulation following daily oral hygiene activities and dental procedures. Bacteremia is caused more frequently in the treatment of periodontal disease than in other dental procedures. Periodontal treatment involves mechanical debridement, which consists of plaque control, scaling and root planing, and periodontal surgery. The debridement of bacterial biofilms in close proximity to the ulcerated epithelium of the gingival sulcus or periodontal pocket may lead to bacteremia. Therefore, it is essential to maintain oral hygiene and periodontal health in order to decrease the risk of bacteremia. It has long been debated by the American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) and the American Dental Association (ADA) whether or not the risk of prosthetic joint infection (PJI) is related to bacteremia after professional dental treatments. Currently, there is strong evidence of such an association. In addition, the indirect evidence obtained from multiple moderate-strength studies suggests that the use of prophylactic antibiotics reduces the incidence of post-dental procedure bacteremia. However, there have been no studies regarding the relationship between bacteremia and PJI. In summary, it is necessary to consider the risk of dental procedure-induced bacteremia and patient characteristics when prescribing prophylactic antibiotics for patients with prosthetic joints who are undergoing dental procedures. It may be particularly beneficial for these patients to maintain good oral hygiene.
- 著者
- 大塚 攻 田中 隼人
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.42-44, 2021-08-31 (Released:2021-08-31)
- 参考文献数
- 13
5 0 0 0 OA 個人差から集団差への一般化における心理的本質主義の役割
- 著者
- 塚本 早織 唐沢 穣
- 出版者
- 人間環境学研究会
- 雑誌
- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.13-20, 2015 (Released:2015-06-30)
- 被引用文献数
- 1 1
自分とは反対の性格特性を持つ他者が,異なる民族の一員であった場合,人はその性格の違いを民族性が原因であるかのように解釈する場合がある。日常生活においてみられるこのような過度な一般化は、民族に関する偏ったステレオタイプを形成する一因となる。本研究は、個人の特徴に関する知識が、カテゴリーに関する知識へと一般化される状況と、それに影響を与える個人差要因に着目した実証的研究を行った。個人差要因として、心理的本質主義信念を測定し、民族カテゴリーに行動や認知の原因となる本質的因子の存在を錯覚しやすい人ほど、他民族他者と自身の違いを民族性の違いとして一般化する傾向が強いと予測した。実験参加者は全て日本人学生であったが、実験参加のパートナーという名目で「留学生」(実験1ではインドネシア国籍、実験2では中国国籍)あるいは「日本人」の実験協力者と同時に実験に参加した。実験では、参加者および実験協力者に対して認知傾向を調べるテストを行い、テスト後に偽のフィードバックを与えた。フィードバックとして、パートナー間にみられる認知傾向の類似性(同じ・異なる)を操作した。その結果、パートナー間の類似性に関する情報を日本人および留学生全般に一般化する程度は、パートナーの国籍とフィードバックの類似性の組み合わせによって異なることが明らかとなった。具体的には、留学生パートナーとの間に認知傾向の違いが告げられた参加者において、その違いを日本人および留学生カテゴリーに一般化し、民族間の差異を過度に推測する傾向がみられた。同様の一般化傾向は、日本人パートナーと同じ認知傾向があると告げられた参加者にもみられた。しかし、留学生との違いを民族間の差異に一般化した前者の場合のみ、その程度が心理的本質主義信念の強さと関連していることが明らかになった。本研究により、異なる民族他者との交流で得られる些細な情報からも、民族に関するステレオタイプが形成される可能性が示唆され、それには民族カテゴリーに関する信念の個人差が影響を与えることが明らかとなった。
5 0 0 0 OA 宇宙とコンクリート~月面基地建設~
- 著者
- 齊藤 亮介 鵜山 尚大
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.9, pp.971-975, 2016 (Released:2017-09-01)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 栗林 佳代
- 出版者
- 佐賀大学経済学会
- 雑誌
- 佐賀大学経済論集 / 佐賀大学経済学会 (ISSN:02867230)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.4, pp.39-63, 2010-11
5 0 0 0 OA 宗教の教育と伝承 : ベイトソンのメタローグを手がかりにして(<特集>宗教の教育と伝承)
- 著者
- 飯嶋 秀治
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.2, pp.265-292, 2011-09-30 (Released:2017-07-14)
本稿では、「宗教の教育と伝承」を考える糧として、グレゴリー・ベイトソンのメタローグを取り上げる。そこで、メタローグを、まずは(一)ベイトソンの諸テクスト内部から、その重要性を確認する。その上で、(二)次にそれを当時、彼がおかれていた歴史的コンテクストに照らして、その効果と行方を検討してゆく。ここでは特に、パールズのゲシュタルト療法との交流と、エリクソンとの催眠療法との影響関係を重視する。結論として、ベイトソンのメタローグは、「聖なるもの」それ自体を語らずに提示する表現形式であった可能性を論じる。それは「宗教の教育と伝承」をテクスト上でどのように行うのかという可能性の一端に光を投げかけてくれるであろう。
5 0 0 0 OA 大都市圏郊外における買い物行動の縦断データ分析―平城ニュータウン居住者を事例に―
- 著者
- 稲垣 稜
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.151-166, 2019 (Released:2019-07-13)
- 参考文献数
- 48
- 被引用文献数
- 2
横断データにもとづいて大都市圏郊外の買い物行動を明らかにした研究は数多く存在するが,縦断データに焦点を当てた研究は少ない。本研究では,大阪大都市圏の郊外に居住する人々の買い物行動に関する長期的な縦断データを収集する。対象地域は大阪大都市圏の東部郊外に位置する奈良市の平城ニュータウンであり,アンケート調査にもとづいて分析を行った。バブル経済期までは,大阪大都市圏の上位中心地である難波・心斎橋,下位中心地である大和西大寺駅周辺で高級服を購入するスタイルが維持されていたが,バブル経済崩壊以降難波・心斎橋の利用割合が大幅に低下した。最寄品である普段着の購入においても,1980年時点では百貨店の利用が一定程度あった。しかし1980年代以降,平城ニュータウンに総合スーパーが立地したことにより,普段着を平城ニュータウン内で購入する割合が上昇した。本研究では,大都市圏における買い物環境の変化に伴い郊外居住者の買い物行動が絶えず変化してきたこと,さらには現住地への入居時期により買い物行動の変化の仕方が異なることを明らかにした。
5 0 0 0 OA 北海道庁の地形図に関する資料
- 著者
- 羽田野 正隆
- 出版者
- 北海道地理学会
- 雑誌
- 北海道地理 (ISSN:02852071)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, no.52, pp.54-56, 1978-01-30 (Released:2012-08-27)
- 参考文献数
- 4
5 0 0 0 OA 「発言」の価値:ハーシュマン再訪
- 著者
- 八田 真行
- 出版者
- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター
- 雑誌
- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.10, pp.607-614, 2009-10-25 (Released:2018-02-26)
- 参考文献数
- 7
5 0 0 0 近代における雅楽概念の形成過程
- 著者
- 鈴木 聖子
- 出版者
- 文化資源学会
- 雑誌
- 文化資源学 (ISSN:18807232)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.41-49, 2005
5 0 0 0 OA 過去の出来事を“語り継ぐ”ということ
- 著者
- 菅野 幸恵 北上田 源 実川 悠太 伊藤 哲司 やまだ ようこ
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学研究 (ISSN:24357065)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.6-24, 2009 (Released:2020-07-07)
本論文は,奈良女子大学で行われた日本質的心理学会第 4 回大会におけるシンポジウムの内容を収録したものである。北上田氏は,沖縄での平和ガイドの実践経験から,非体験者が過去の出来事とどのように出会うのかという体験の創出を重視した,伝えながら共に学ぶガイドのあり方について述べた。実川氏は,水俣展を開催した経験から,自由に足を運びやすい展覧会という場の可能性,聞く側の準備の必要性について述べた。ふたりの話題提供に対して,質的心理学の立場から,伊藤哲司氏,やまだようこ氏がコメントを行った。伊藤氏はベトナムやタイでのフィールドワークの経験から,あえて語らないことの意味についてコメントした。やまだ氏はナラティヴの立場から,2 氏の実践のあり方と語り手と聞き手の関係をむすぶメディエーターの役割を重視した協働の学びのトライアングルモデルとの関連について述べた。最後に,“語り継ぐ”ことについて,双方向性,メディエーターを通した個別の体験のむすび,語らないことの意味から考察した。
5 0 0 0 IR 持続可能な地域福祉社会の構築のために : 「地域包括ケアシステム」の検討を通じて
- 著者
- 小幡 あゆみ
- 出版者
- 九州大学持続可能な社会のための決断科学センター
- 雑誌
- 決断科学 (ISSN:24238759)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.71-81, 2017-03-23
- 著者
- 若尾 良徳 Yoshinori WAKAO 浜松学院大学 Hamamatsu Gakuin University
- 出版者
- 浜松学院大学
- 雑誌
- 浜松学院大学研究論集 (ISSN:18807178)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.37-48, 2013-03