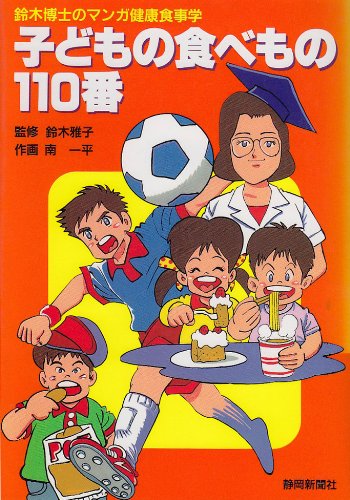- 著者
- 福原 朗子 小川 直久 金子 文俊
- 出版者
- 公益社団法人日本工学教育協会
- 雑誌
- 工学教育研究講演会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.61, pp.336-337, 2013-08-29
1 0 0 0 マンガで見る鴨方の歴史 : 鴨方町合併40周年記念事業
1 0 0 0 子どもの食べもの110番 : 鈴木博士のマンガ健康食事学
1 0 0 0 マンガ岡山物語
- 著者
- 山陽新聞社出版局編
- 出版者
- 岡山城築城四百年関連事業推進協議会
- 巻号頁・発行日
- 1996
1 0 0 0 まんが西蔵探検家能海寛
- 著者
- 江本嘉伸原作・シナリオ 南一平画 波佐文化協会編
- 出版者
- 波佐文化協会
- 巻号頁・発行日
- 2002
- 著者
- 安田 昌弘
- 出版者
- 京都精華大学
- 雑誌
- 京都精華大学紀要 (ISSN:09173986)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.3-26, 2012
1 0 0 0 OA 市場情報を用いたニュース記事評価と価格分析
- 著者
- 五島 圭一 高橋 大志 寺野 隆雄
- 雑誌
- 経営課題にAIを! ビジネス・インフォマティクス研究会資料 = SIG-BI
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, 2014-11-20
Many stuides have been attempting to uncover the relationship between asset price fluctuations and textual information. However, in many cases, subjective evaluations of researchers have significant impacts on results. In this paper, we propose an objective evaluation method of news article using stock prices. Firstly, we give class labels (negative-positive) to every news articles by using event study analysis. Secondly, we compute vector representations of news aritcles by morphological analysis and tf-idf. Finally, we make Support Vector Machine classifier and give class labels (negative-positive) to other news articles. This method enable objective analyses of textual data in financial contexts.
1 0 0 0 OA 跳躍能力の評価方法におけるバウンディングの提案
1 0 0 0 IR 西洋中世美術におけるイメージ言語とタイポロジー : 図像テクストの生成・解釈・機能
- 著者
- 木俣 元一
- 巻号頁・発行日
- 2005-05
科学研究費補助金 研究種目:基盤研究(C)(2) 課題番号:15520084 研究代表者:木俣元一 研究期間:2003-2004年度
- 著者
- 三浦 篤
- 出版者
- 学術雑誌目次速報データベース由来
- 雑誌
- 比較文学研究 (ISSN:0437455X)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, pp.83-93, 2001
1 0 0 0 IR 言語の構造としての視覚藝術
- 著者
- 奥津 聖
- 出版者
- 山口大学
- 雑誌
- 山口大学哲学研究 (ISSN:0919357X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.19-45, 2001
初期ルネッサンスのある時期から、絵画の中に文字を描くことはタブーとなった。遠近法的絵画は自然らしさを追及するものであったからである。二十世紀の欧米の前衛藝術はこのタブーに兆戦した。コンセプチュアル・アーティストたちはついには言語のみを用いた視覚藝術を生みだすに至る。藝術は一行の文章に集約されるというわけである。1989年『中国現代藝術展』でデヴューした中国人アーティストの多くも言語をテーマにする作品を発表し始めた。しかしかれらの作品のコンセプトは欧米のそれとは別のコンテクストから生み出されたものである。この論文では、主として徐冰の作品を取り上げて、かれの問題の所在を内在的に考察することを通じて、かれの作品が言語の構造、言語の本質を問うものであり、言語の構造としての視覚藝術を成立させようとするものであることを明らかにする。 これは「イメージの解釈学の成立」における言語とイメージの問題を考察するための新たな素材を発掘する試みでもある。
- 著者
- 三浦 篤
- 出版者
- 恒文社
- 雑誌
- 比較文學研究 (ISSN:0437455X)
- 巻号頁・発行日
- no.77, pp.4-26, 2001-02
1 0 0 0 イメージとテクスト:パラゴーネ (特集 美術とパラゴーネ)
- 著者
- Lewis Francis Ames 秋山 聰
- 出版者
- 三元社
- 雑誌
- 西洋美術研究
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.8-23, 2002
1 0 0 0 6次元ラベルに基づく個人フォトコレクションの分析と可視化
「個人フォトコレクションの分析と可視化」という課題を研究しているが、昨年に画像分析に焦点を置き、「6次元ラベル」に基づく新しい画像アノテーション方法を提出した。その方法は現在流行するソーシャルネットワークを利用し、インターネットにおける画像の視覚的な特徴及びそれに付属するソーシャルインフォメーションへの分析を通じて画像を精確に注釈する。今年度、画像の可視化に注目した研究を行った。具体的には以下の2点に分けられる。1. インターネットにおける大量の画像向けの可視化 : 制約付きコラージュの即時生成本研究では、新しい自動的・高速なコラージュ生成を提案した。複雑な画像顕著性分析をしないで済み、ユーザの定義したキャンパスサイズにぴったりおさまるように入力画像のコラージュを生成する。その方法は大量データのリアルタイム動的画像コラージュの生成に適している。極めて高速であり、100枚の画像を処理するには0.5ミリ秒以内で済み、従来の計算法より速度は何オーダーも桁違いに早くなった。その成果は国際会議APASIPA 2013に発表され、フルペーパー論文をすでにIEEE Transaction on Multimediaに投稿した(査読中である)。2. ユーザー個人向けの画像可視化 : 漫画化等の視覚効果の生成我々の研究は自然的画像の1. 漫画2. 鉛筆手描き3. アニメーション4. 油絵への高速な変換処理を実現した。漫画を例にしてみれば、1000^*800の入力画像である場合、既存研究では数十秒から数分間までの時間が必要であるのに対して、我々の方法では0.8秒だけで十分であり、百倍にも早くなっていると言える。出力画像の品質から見ても、既存の5つの漫画風画像転換Appと比較しても提案手法の品質が遥かに優れていることを確認した。本研究は国際会議PCM2013とICASSP2014にて発表した。また、関連のdemoを超臨場感コミュニケーション産学官フォーラム(URCF2013)で展示した。
1 0 0 0 OA DLRO,ODLROと超流動
- 著者
- 長岡 洋介
- 出版者
- 物性研究刊行会
- 雑誌
- 物性研究 (ISSN:05252997)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.6, pp.257-263, 1975-03-20
この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。
目的:本研究の目的は,アバタ自体が休息,もくしはリラックスすることにより,作業者がそれをみただけで癒されるたり,あるいは休息行為を促されるためのインタフェース作りである.これに必要なアバタの見かけや動作を開発・実装し,効果についてアンケート調査を行う.方法:MSオフィスアシスタント(以下MSアシスタント)と同等のサイズのキャラクター(癒しキャラ)を1個作成した.癒しキャラには背伸びなど全8動作を行わせた.これに対して,10個のMSアシスタント(犬,イルカなど)から各8動作,計88動作を抽出した.これらの癒し効果について,Web上でアンケート調査を行った.アンケートは7段階評価であり,分析的項目(5つ)と包括的項目(3つ)から構成された.手順:Web上のアンケートサイトにて,被験者1人あたりMSアシスタント2個と癒しキャラの計3個を評価させた.なお,MSアシスタントはランダムに割りふった.各キャラクターの被評価人数は約30名であった.結果:癒しを促進するキャラクターと行動を明らかにするために,評価項目ごとに,癒しキャラとMSアシスタントの88種類の行動について一元配置分散分析を行った.その結果,全体的な傾向として,犬とイルカの行動が,他のキャラクターに比べ,より癒しを促進していることが明らかになった.考察:花や貝殻など癒しイメージが感じられるものや,火炎放射器を使うなど意外性・非日常性が感じられる行為に癒し効果が認められた.また,キャラクターの「かわいさ」も重要な要因であることがわかった.今後の癒しキャラ開発では,作業者が日常とっている行動との関連や,キャラクターの影響を考慮する必要がある.また,作業者自身が休息行為を行うことによる癒し効果や,脳科学の知見の検証にも展開させていきたい.<スケジュール>平成19年3月日本教育工学会研究会における成果発表
- 著者
- 志茂 浩和 Hiroyasu SHIMO
- 出版者
- 神戸芸術工科大学図書館
- 雑誌
- 芸術工学2012
- 巻号頁・発行日
- 2012-11-30
オリジナルキャラクターをデザインし、アニメーション可能な3 次元コンピュータグラフィックスオブジェクトを制作するためには、多くのプロセスを経なくてはならない。特に、アイディアスケッチの段階から、コンセプトモデルに至るプロセス、すなわち2 次元から3 次元への変換において、形態を完全に把握することは困難だ。このプロセスを従来のポリゴンモデリングだけで乗り切ろうとすると、多くの時間と妥協を余儀なくされる。結果的に試行錯誤の余地は極めて少なくなり、品質に影響する。これを解消するには、モデリングプロセスの中にスカルプトモデリングを導入することが効果的であることが予想できる。ただし、すべての対象に同じように効果があるとはいえないし、アニメーションで用いるには不都合な要素を含む。複数のソフトを場面やスキルに応じて使い分ける必要もある。これらを踏まえ、新しいキャラクターを設計し、アニメーションを前提としたオブジェクトとして成立するまでのプロセスを実践した。学生の制作に効果的であることを念頭にワークフローを構築することも目的としている。本稿は、これらのプロセスを報告するものである。To make an original character which can be animated in the 3D Computer Graphics,one should pass through a great deal of processes.Especially,process from the idea sketch to the conceptual model and then converting the 2D model completely to the 3D model is a tough process.Using only the polygon modeling to overcome the process mentioned above consumes great time and efforts. In spite of such hard efforts it is not sure that the quality will be better and error will be less in the models. So, to overcome these the sculpting modeling process is used along with the polygon modeling process which will give the better result comparing to the polygon modeling process only. However,it cannot be said that the process will influence equally to every type of subject because the animation process follows after the modeling process. But,with the skills of different 3D software and utilizing it correctly will allow one to get best final result .In this manuscript, there is the explanation from setting up a new character considering the workflow of animation process in prerequisite which will help the students in systematic work flow of the modeling process.
1 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1920年10月07日, 1920-10-07
1 0 0 0 実写の動画像からの非実写変換による映像の好ましさ向上
- 著者
- 瀧上順也 加藤禎篤 ブン・チュンセン
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告オーディオビジュアル複合情報処理(AVM) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, no.69, pp.39-44, 2008-07-16
- 参考文献数
- 10
本稿では,実写の動画像を非実写化することにより,動画像の好ましさを向上する効果があるかについて検証を行った.まず,イラストレータによる理想的な手描きの非実写映像によって実写映像と異なる表現方法 (画風)に変更することで,映像に対する総合的な好ましさを損なうことなく,個別の要素に対する印象の好ましさを向上させる効果があることを確認した.次に,動画像の動きの滑らかさに関して,非実写変換によって,低いフレームレートにおいても実写映像に比べて働きのギクシャクさを感じにくくなることを確認した.これらの結果を,それぞれの主観評価に用いた方法と合わせて報告する.In this paper, we report the effects of improving viewer's impression for videos by non-photorealistic rendering. Our subjective test, first, reveals that non-photorealistic videos improve viewer's impression on several sub-elements in the original photorealistic videos without detracting overall visual preference. We, then, confirm that non-photorealistic videos reduce perceived jerkiness even in the low frame rate compared to the original photorealistic videos. We also report the subjective test methods designed for the evaluations.