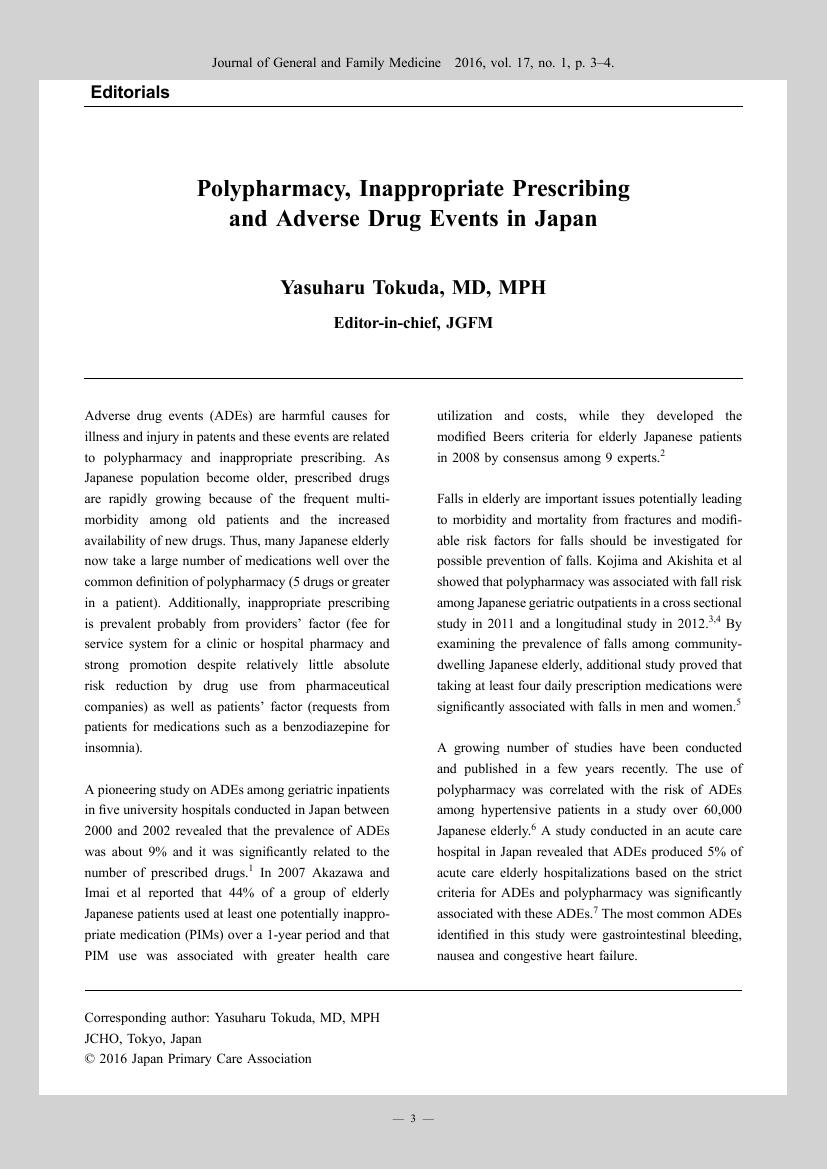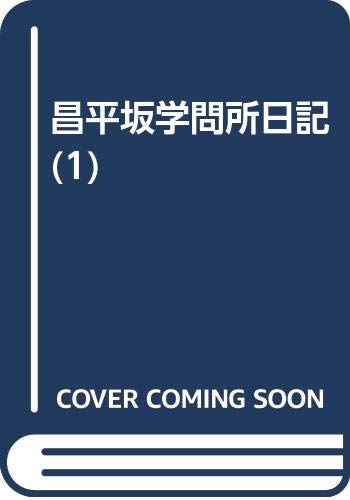5 0 0 0 OA 中世の大阪 : 水走氏・渡辺党を中心に
- 著者
- 小西 瑞恵 コニシ ミズエ Mizue KONISHI
- 雑誌
- 大阪樟蔭女子大学研究紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.3-14, 2011-01-31
中世の大阪地域で活躍した武士団の実像を、河内水走氏と摂津渡辺党・渡辺氏について実証した。中世後期の武士団を検討するという第一の課題については、畿内型武士団としての水走氏や渡辺氏が、南北朝時代には南朝方や北朝方に帰属しながら、室町時代には幕府の守護領国体制に組み込まれていく過程を、あきらかにできた。水走氏と渡辺党を比較するという第二の課題については、畿内型武士団としての特徴に基本的な相違はないが、水走氏は枚岡神社の祀官として江戸時代も中河内の名族としての地位を保ち、渡辺氏は豊臣秀吉の大坂城が築かれた頃、渡辺の地を離れて奈良に去るという違いについて、地域の歴史の違いとして検討を加えた。中世の国家機構を構成する朝廷・官衙や権門寺社と幕府に奉仕したのが、畿内型武士団としての水走氏や渡辺党であった。水走氏や渡辺氏が水軍・武士団として交通や流通機能を担ったことが、中世を通じて活躍した独自の強さの理由であり、また、近世に武士身分として生き残れなかった理由でもある。
5 0 0 0 自ら進んで自己開示する場合と尋ねられて自己開示する場合との相違
- 著者
- 熊野 道子
- 出版者
- 日本教育心理学協会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.4, pp.456-464, 2002
- 被引用文献数
- 1
この研究の目的は,自己開示の状況的要因の1つで,自己開示のきっかけとなる要因である尋ねることに着目し,自ら進んでの自己開示と尋ねられての自己開示の相違を検討することである。315名の大学生を開示内容が社会的に望ましい場合(159名)と社会的に望ましくない場合(156名)に分け,自ら進んで開示する場合と尋ねられて開示する場合のそれぞれに,自己開示の程度,動機,開示後の気持ちについて回答を求めた。その結果,以下のことが明らかになった。(1)開示程度については,開示内容が社会的に望ましくない場合は,自ら進んでより尋ねられて開示する程度が高かった。(2)開示動機については,自ら進んで開示する場合は感情性を動機として開示が行われやすく,尋ねられて開示する場合は規範性を動機として開示が行われやすかった。(3)開示後の気持ちについては,不安といった否定的な感情では,自ら進んで開示する場合も尋ねられて開示する場合も,統計的有意差が認められなかった。一方,肯定的な感情では,自ら進んで開示する場合は安堵感が高く,尋ねられて開示する場合は自尊心が高かった。
- 著者
- 森 伸晃 柏倉 佐江子 高橋 正彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本環境感染学会
- 雑誌
- 日本環境感染学会誌 (ISSN:1882532X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.48-54, 2016 (Released:2016-04-05)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
医療関連感染は入院期間の延長や予後の悪化,医療費の増加をもたらすため,各施設の感染対策に関わる専従もしくは専任者に期待される役割は大きい.今回,専従もしくは専任者の存在によるClostridium difficile感染症(CDI)対策を含めた院内感染対策の違いを明らかにするためにアンケート調査を行った.アンケート調査は,「国立病院機構におけるC. difficile関連下痢症の発生状況と発生予防に関する研究」のデータを利用し,2010年8月に全国144の国立病院機構施設のうち感染制御チーム(ICT)がある47施設を対象に行った.調査項目は計22項目で,1)院内感染対策の体制,2)ICTの業務と権限,3)標準予防策,4)環境・設備,5)CDI対策に大別した.専従もしくは専任者がいるのは26施設(55.3%)であった.専従もしくは専任者がいる施設では,ICTのコンサルテーション対応,抗菌薬の届出制,一般病室の清掃頻度が週5日以上,CDIに関する患者および患者家族に対する指導の項目が,いない施設に比べて統計学的に有意に実施されていた.専従もしくは専任者のいる施設では院内感染対策に関して優れた点がみられ,その役割が示された.しかし,専従もしくは専任者がいたとしてもまだ十分にできていない項目があり,これらについては今後の課題である.
5 0 0 0 OA Twenty Theses on Politics and Subjectivity
- 著者
- Bosteels Bruno
- 出版者
- Institute for Research in Humanities Kyoto University
- 雑誌
- ZINBUN (ISSN:00845515)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.21-39, 2016-03
International Symposium "Provided that this lasts…": Politics, Subject, and Contemporary Philosophy (January 12th, 2015)
5 0 0 0 会話者のコミュニケーション参与スタイルを指し示すCOMPASS
- 著者
- 藤本 学
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.290-297, 2008
- 被引用文献数
- 1
This article examined the communication participation styles of how one commits to communication, and postulated the COMPASS which measures these styles. The tendency of participants' acts in small group communications in daily life was investigated, and the communication participation style, consisting of four factors - conversation management, active participation, passive participation, and negative participation - was extracted. Active and passive participation are basic styles in communication in relation to assertiveness and responsiveness. Conversation management is related to meta-conversation which manipulates conversation development. Negative participation is a useful factor distinguishing the listeners and spectators. These participation styles showed a significant relation to individual attributes.
- 著者
- Bao-Juan Cui Dao-Qing Wang Jian-Qing Qiu Lai-Gang Huang Fan-Shuo Zeng Qi Zhang Min Sun Ben-Ling Liu Qiang-San Sun
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- Journal of Physical Therapy Science (ISSN:09155287)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.7, pp.2327-2331, 2015 (Released:2015-07-22)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1 6
[Purpose] This study investigated the effects of a 12-hour neuromuscular electrical stimulation program in the evening hours on upper extremity function in sub-acute stroke patients. [Subjects and Methods] Forty-five subjects were randomized to one of three groups: 12-hour neuromuscular electrical stimulation group (n=15), which received 12 hours of neuromuscular electrical stimulation and conventional rehabilitation for the affected upper extremity; neuromuscular electrical stimulation group (n=15), which received 30 min of neuromuscular electrical stimulation and conventional rehabilitation; and control group (n=15), which received conventional rehabilitation only. The Fugl-Meyer assessment, Action Research Arm Test, and modified Ashworth scale were used to evaluate the effects before and after intervention, and 4 weeks later. [Results] The improvement in the distal (wrist-hand) components of the Fugl-Meyer assessment and Action Research Arm Test in the 12-hour neuromuscular electrical stimulation group was more significant than that in the neuromuscular electrical stimulation group. No significant difference was found between the two groups in the proximal component (shoulder-elbow) of the Fugl-Meyer assessment. [Conclusion] The 12-hour neuromuscular electrical stimulation group achieved better improvement in upper extremity motor function, especially in the wrist-hand function. This alternative therapeutic approach is easily applicable and can be used in stroke patients during rest or sleep.
5 0 0 0 OA 太平洋炭鉱主婦会の記録:北海道炭鉱主婦協議会の会長の聞き取りと資料を中心に 【改訂版】
- 著者
- 西城戸 誠 大國 充彦 久保 ともえ 井上 博登
- 出版者
- 産炭地研究会(JAFCOF)
- 雑誌
- JAFCOF釧路研究会リサーチ・ペーパー
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.1-107, 2015-06-28
本報告書は,2009〜2013 年度日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究A)『旧産炭地のネットワーキング型再生のための資料救出とアーカイブ構築』(課題番号・21243032 研究代表者・中澤秀雄),2014 年度~2018 年度日本学術振興会科学研究費補助金(基盤研究A)『東アジア産炭地の再定義: 産業収束過程の比較社会学による資源創造』(課題番号・26245059 研究代表者・中澤秀雄)の研究成果の一部
5 0 0 0 IR 『世界の中心で、愛をさけぶ』論 : アキがいる世界、いない世界
- 著者
- 柄澤 尚美 KARASAWA Naomi
- 出版者
- 都留文科大学大学院
- 雑誌
- 都留文科大学大学院紀要 (ISSN:18801439)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.1-17, 2014
5 0 0 0 OA 仏教学新知識基盤の構築―次世代人文学の先進的モデルの提示
- 著者
- 下田 正弘 小野 基 石井 清純 蓑輪 顕量 永崎 研宣 宮崎 泉 Muller Albert 苫米地 等流 船山 徹 高橋 晃一
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 基盤研究(S)
- 巻号頁・発行日
- 2015-05-29
本研究事業は、永続的に利用可能な仏教学の総合的知識基盤を日本に構築し、世界の仏教研究におけるウェブ知識拠点(ハブ)を構築することで次世代人文学のモデルを提供することを目的とする。これを達成するため、(1)大蔵経テキストデータベース(SAT-DB)を継続的に充実発展させ、(2)有望な新規国際プロジェクトを支援し、連携してSAT-DBネットワークを拡充し、(3)人文学の暗黙的方法の可視化を図って人文学テクストの適切なデジタル化を実現するためTEIと連携してTEI-Guidelinesを中心とするテクスト構造化の方法を精緻化し、(4)ISO/Unicodeとの連携し、国内のデジタル・ヒューマニティーズ(人文情報学)に関する研究教育の環境向上を図り、人文学国際化を支援する研究環境を整備する。これらの成果はSAT大蔵経テキストデータベースにオープンアクセスのかたちで反映させることをめざす。本年度は、James Cummings(Newcastle University, UK)、Paul Vierthaler(Leiden University, NLD)を迎えた国際会議「デジタルアーカイブ時代の人文学の構築に向けて」をはじめ、国際会議とワークショップを3回主催し、国内外で招待講演を行うとともに、東大から2度のプレスリリースを行って、当初の研究計画を大きく進展させた。その成果は、次世代人文学のモデルとなる新たなデジタルアーカイブSAT2018の公開となって結実した。SAT2018は、直接の専門となる仏教研究者にとって実用性の高い統合的研究環境を提供するばかりでなく、人文学研究のための専門知識デジタルアーカイブのモデルになるとともに、人文学の成果を一般社会に利用可能なかたちで提供する先進的事例となった。
5 0 0 0 OA 脳循環障害によるめまい
- 著者
- 澤田 徹
- 出版者
- 一般社団法人 国立医療学会
- 雑誌
- 医療 (ISSN:00211699)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.2, pp.143-148, 1983-02-20 (Released:2011-10-19)
- 参考文献数
- 8
脳循環障害における「めまい」について, その種類と発現頻度を検討し, 脳循環の立場からその発現機序に考察を加えた.国立循環器病センターSCUへ収容された, 脳卒中新鮮例547例中, めまいを訴えたものはvertigo 18例, dizziness 21例の計39例(7.1%)であつた. その内訳をみると, vertigoは脳幹および小脳の血管障害における出現頻度が高く, とくに小脳出血では6例中5例(83.3%)がvertigoを主訴としており, 診断的意義が大きい. 一方, 大脳半球の血管障害では発作時めまいを訴えるものは少なく, 脳出血1.5%, 脳梗塞3.3%であつた.N2O法による脳血流測定法では, 椎骨脳底動脈系の血管障害では, めまいの有無により脳血流量に差はなかつたが, 大脳半球の血管障害ではめまい出現例で有意の脳血流低下が認められた. このことは, vertigoは局所的な循環障害に起因し, dizzinessは全脳血流低下と関係が深いことを示唆する.
5 0 0 0 OA 貧困地域と非識字者への視点
- 著者
- 武田 尚子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.486-503, 2015 (Released:2016-03-31)
- 参考文献数
- 15
本稿は, テレビ草創期のNHKドキュメンタリー・シリーズの2本の番組を取り上げ, 地域研究資料としての意義を考察した. これらの番組は, 1960年代に広島県因島の家船集落を取材したもので, 漁村の貧困と不就学児童の問題に焦点をあてている. このシリーズは, 民俗学の視点を参照して, 底辺層の生活に迫り, その人々が直面している社会的ジレンマを視聴者に問うという方針で制作された. これとほぼ同時期に, 同じ集落で, 宮本常一が参加した民俗学調査が実施された. これら2つの調査・取材は, いずれも民俗学的関心に基づいて実施されたものであるが, 見出した知見には相違がみられる.テレビ・ドキュメンタリーは, 階層的視点が明確で, 貧困地域という集落特性を映像で実証的に示している点に意義がある. これによって, ミクロな地域社会の事象をマクロな社会構造に位置づけてとらえることが可能になった. しかし, その一方で, 民俗学調査報告書と比較すると, テレビ・ドキュメンタリーは, 該当地域に居住していた非識字者を貧困の視点でとらえる傾向がつよく, 非識字者の集団が保持していた口承文化の豊かさについて, 理解が浅い面があったことがわかる.以上のように本稿は, 民俗学調査と比較することによって, テレビ・ドキュメンタリー番組を地域資料として利用する場合の長所および留意点を明らかにしたものである.
5 0 0 0 OA Kreiselの予想について
- 著者
- 遊上 毅
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.30-38, 1986-02-07 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 13
5 0 0 0 OA 弁慶説話の成立と展開 : 御伽草子『弁慶物語』まで(昭和60年度卒業研究佳作)
- 著者
- 北澤 良子
- 出版者
- 上田女子短期大学
- 雑誌
- 学海 (ISSN:09114254)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.48-55, 1986-03
5 0 0 0 OA 火星におけるコーン地形
- 著者
- 野口 里奈 栗田 敬
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.125, no.1, pp.35-48, 2016-02-25 (Released:2016-03-22)
- 参考文献数
- 71
- 被引用文献数
- 3 6
Cone morphologies with a variety of origins and sizes have been widely identified on Mars using remote sensing data such as ultra-high resolution visible images. Currently, small cones of less than 100 m in bottom diameter can be identified. These Martian cones are located in young surface regions, suggesting they were produced in an environment that existed in recent geological history. They had volcanic, periglacial, and other origins. This paper first introduces a classification of terrestrial cone morphology: volcanic (spatter cones, scoria/pumice cones, maars, tuff rings, tuff cones, and rootless cones), periglacial (pingos), and others (mud volcanoes). Then, it reviews the characteristics of cone morphology on Mars focusing on morphology, morphometry, and distribution. Previous cone studies show the existence of explosive basaltic eruptions on recent Mars, while young lava flows were pervasive. The prevalence of rootless cones suggests the presence of water/ice during their formation at many places on Mars. These discoveries contribute to clarifying the recent surface environment and thermal state of Mars. To further apply terrestrial knowledge to Martian cones, it is necessary to understand the relationship between the morphology and the formation process of cone morphologies on Earth from a wide perspective.
- 著者
- 王 杲 高橋 光輝
- 雑誌
- 研究報告グループウェアとネットワークサービス(GN)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015-GN-93, no.50, pp.1-8, 2015-01-19
近年,中国の急激な経済発展に伴い,コンテンツ市場も大きく活性化されている.しかし,日本で行われているキャラクタービジネスが成功している事例は中国では極めて少ない.さまざまな制約などの厳しい環境がある中国で,日本型キャラクタービジネスの展開は今後も厳しい状況ではないかと推測される.今回は,著者がプロデューサーとして参加し,中国で展開した “VOCALOID CHINA PROJECT” の事例を基に,海賊版問題や放送規制が厳しく文化も違う中国で,実際に行ったどんな問題に直面したのか.また,ユーザーとなる中国の若者がどんな影響を受けたのかを記録し,分析する.
- 著者
- Yasuharu Tokuda
- 出版者
- 日本プライマリ・ケア連合学会
- 雑誌
- Journal of General and Family Medicine (ISSN:21896577)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.3-4, 2016-03-18 (Released:2016-03-25)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 4
- 著者
- 尾上 典子
- 出版者
- 亜細亜大学
- 雑誌
- 経営学紀要 (ISSN:13403230)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.1-30, 2005-07
5 0 0 0 OA 牛由来匂い物質結合タンパク質の結合モデルとその実証
- 著者
- 池松 峰男 イケマツ ミネオ Mineo Ikematsu
- 雑誌
- 雲雀野 = The lark hill
- 巻号頁・発行日
- no.38, pp.1-10, 2016-03-31
5 0 0 0 OA プログラミング入門をどうするか:6. 東京大学における全学プログラミング教育
東京大学の1年生は全員,まず夏学期に必修講義である「情報」で情報に関する基本的な知識を学ぶ.理系の学生は,続く冬学期の「アルゴリズム入門」で,プログラミングをさらに学び,アルゴリズムや計算量,数値計算等についての理解を深める.東京大学は総合大学であるため,これらの全学教育では,情報系に興味のない学生にも,プログラミングを学び,面白さを感じてもらわなければならない.しかも,「情報」では履修者が数千人(数十クラス)にも達するため,プログラミングが専門ではない教員も授業を担当せざるを得ない.本稿では,これらの困難を解決するための工夫を中心に,東京大学での全学プログラミング教育の理念と現状について報告する.