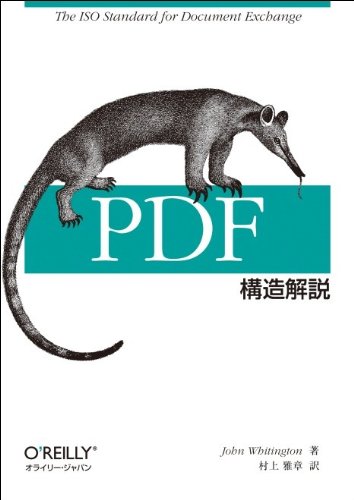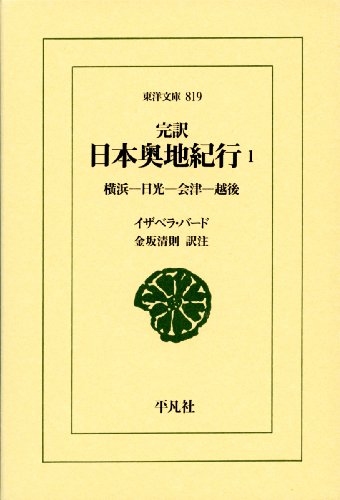1 0 0 0 IR 昔話の叙述の展開とその構造 : 異類女房譚を例として
- 著者
- 川添 裕希
- 出版者
- 慶應義塾大学国文学研究室
- 雑誌
- 三田國文 (ISSN:02879204)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.18-26, 1986-12
1 0 0 0 節用文字と字類抄諸本の系譜
- 著者
- 小川 知子
- 出版者
- 北海道大学国語国文学会
- 雑誌
- 国語国文研究 (ISSN:02890488)
- 巻号頁・発行日
- no.112, pp.23-35, 1999-07
1 0 0 0 OA 訓註日本外史
- 著者
- 奥村梅皐 (恒次郎) 編
- 出版者
- 山本文友堂
- 巻号頁・発行日
- vol.巻15−22,附録 人名地名索引, 1911
1 0 0 0 OA 訓註日本外史
- 著者
- 奥村梅皐 (恒次郎) 編
- 出版者
- 山本文友堂
- 巻号頁・発行日
- vol.巻1−14, 1911
1 0 0 0 群馬県の木造3階建て温泉旅館建築
- 著者
- 村田 敬一 初田 亨
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.538, pp.243-249, 2000
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 3 2
This research studies the wooden 3-storied hot spring inn architecture in Gunma Pref. As a result, the following became with obvious. 1. The description of the most ancient times that is related to 3-storied is 1818 years in Kusatsu hot spring. 2. 3-storied was occupying 50% of hot spring inn architecture in Minakami in Showa early period. 3. There was not the law that 3-storied prohibits in the Kusatsu hot spring in the Edo period. 3-storied was able to build even if it becomes around 1960. 4. 3-storied is built the 39 ridges in 1999 year present Gunma Pref. 5. Beside the era falls the 3-storied appearance becomes the designs that were taken up and the independence of the guest room rises.
1 0 0 0 IR 押領使・追捕使関係史料の一考察
- 著者
- 寺内 浩
- 出版者
- 愛媛大学法文学部
- 雑誌
- 愛媛大学法文学部論集 人文学科編 (ISSN:13419617)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.87-101, 2011
1 0 0 0 IR 諸国押領使・追捕使史料集成(付 諸国押領使・追捕使について)
- 著者
- 下向井 竜彦
- 出版者
- 広島大学文学部
- 雑誌
- 広島大学文学部紀要 (ISSN:04375564)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.p1-41, 1986-01
This paper is the collection of historical materials on Shokoku-Oryoshi and Tsuibushi from 10 century to 12 century in Japan. The materials are gathered chronologically under each Kuni (国), whose order is according to the accepted order of Do (道). In the latter half of this paper, I examined fundamental facts in the present materials.
1 0 0 0 OA 明治末期「教育的図画」創出をめぐる「技術」の問題 : 柿山蕃雄とその周辺
- 著者
- 塚田 美紀
- 出版者
- 東京大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 東京大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13421050)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.347-355, 1998-03-26
This paper examines art education of Kakiyama Ban-yu, who studied in the Art School of Tokyo founded by Ernest Fenollosa and Okakura Tenshin, and contributed to the birth of "art pedagogy" in primary education. Revealing the composition of drawing and painting technics in his "art pedagogy", this paper illuminates the structure of his systematization of art skills. The conception of "art pedagogy" was raised by professors of Art School of Tokyo and Teachers School of Tokyo, to construct a systematic teaching method in general education by integrating the technics of Western art and Japanese traditional art. Kakiyama actually tried to explore his own method by organizing the technics not from the teacher's viewpoint but from student's one as art creator. This Kakiyama-method succeeded to those of his antecedents and resembled to those of his contemporaries much in contents of the technics. Nevertheless the way of organizing drawing and painting technics as art creator was unique, and at this point he should be regarded as a pioneer of art education in general education, and as an educator quite different from the mainstream of "art pedagogy".
1 0 0 0 OA 全固体電池の実用化に向けた高イオン伝導性ガラスセラミックスの創製
Li_2S-P_2S_5 系をベースとするガラスの作製方法、結晶化条件、組成を詳細に調べることによって、室温で 5×10^<-3>S cm^<-1>以上の高い導電率を示す硫化物ガラスセラミックスを作製した。またこれまでほとんど検討されていない硫化物電解質の大気安定性の評価方法を確立した。Li_2S 含量 75mol%組成の電解質が比較的大気安定性の高いことを見出し、さらに金属酸化物との複合化によって、大気安定性を向上させることができた。得られた電解質を用いた全固体リチウム電池が、サイクル性に優れた二次電池として作動することがわかった。
1 0 0 0 特別支援学校における介護等体験プログラムの類型化に関する研究
- 著者
- 平岡 昌樹
- 出版者
- 大阪市立生野特別支援学校
- 雑誌
- 奨励研究
- 巻号頁・発行日
- 2012
学生が指導を受けた2,3校の特別支援学校の体験内容を時系列でまとめたもの事例研究はあるが,特別支援学校で介護等体験の体験内容を類型化した研究は管見の限りほとんどない。本研究では,特別支援学校でどのような体験内容・学習内容が設定されているかを全国的にまとめ,その傾向等を分析する。また,受け入れ担当者が,体験内容や指導する学生,送り手である大学に対して抱く意識や特徴を明らかにする。全国の特別支援学校1049校(平成23年5月1日現在)から,「平成23年度全国特別支援学校実態調査(全国特別支援学校長会)」を使用し367校を無作為抽出し,サンプリング調査を実施した。調査は郵送による質問紙法によって実施した。質問紙並びに依頼文を抽出校に郵送し、「介護等体験を主として担当する方」に記入を依頼した。アンケートを送付した367校の内,計283校から回答を得た(回収率77.1%)。回答を得た特別支援学校の障害種別は,知的障害115校(44.1%),肢体不自由障害33校(12.6%),視覚障害16校(6.1%),聴覚障害20校(7,7%),病弱障害11校(4.2%),知肢併置校43校(16.5%),その他併置校23校(8.8%)であった。受け入れ学生が最も多かった学校は466人(東京都)であった。全国平均は72.0人であった。都道府県別に調査すると,最も多いのは東京都で平均252.9人,次いで京都153.0人,愛知150.8人,奈良148.0人,広島130.7人,大阪1252人となっており,首都圏や中京圏,近畿圏といった大学数の多い都府県であることが推測できる。体験の内容の結果から,ほとんどの学校で「児童生徒との交流」「授業の補助」など学生が子どもたちとできるだけ多くの時間過ごせるように工夫していた。また,「障害についての説明」など学生の障害理解,障害児教育の意識向上に資する目的の学習内容が設定されていた。介護等体験実施からすでに15年近い時が立ち,特別支援学校の学生の受け入れ体制が確立してきているようである。「体験内容の改善の必要性」を感じているという学校は,調査対象校の2割弱に過ぎなかった。「介護等体験は教員になった時に役立つか」といった体験の効果についての項目においても,「そう思う」という回答が8割以上であり,介護等体験が学生に効果があるという回答を得た。一方で,「学生の姿勢・マナー」や「大学側の事前指導」に対する要望がおよそ半数の学校からあげられた。
- 著者
- Michael Cook
- 出版者
- Library Association Pub.
- 巻号頁・発行日
- 1993
1 0 0 0 勝海舟の対外思想とその背景(日本史修士論文要旨,彙報)
- 著者
- 金澤 裕之
- 出版者
- 慶應義塾大学
- 雑誌
- 史学 (ISSN:03869334)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.4, 2002
- 著者
- 丸山 直樹
- 出版者
- 「野生生物と社会」学会
- 雑誌
- ワイルドライフ・フォーラム (ISSN:13418785)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.73-84, 2000-06-19
- 被引用文献数
- 1
尾瀬地区に侵入して, 成長中のニホンジカ個体群を放置することは, 環境収容力を低下させ, その過程で尾瀬の生物群集に種の絶滅, 減少, 地域外種の侵入促進などが起こり, 自然生態系を退行に導くことが予想される。それゆえに何らかの人為的干渉が必要とされる。しかし, シカの完全駆除は容認されない。最近の本種の非生息はシカ排除の根拠にならない。少なくとも縄文海進期以降の気温などの環境変化からかつての尾瀬地区でのシカの生息の有無を検討しなければならない。駆除は緊急策として容認されるだろう。植生保護を目的とする人工構築物の設置も一時的には容認されるだろうが, 群集への影響評価が緊急に必要である。尾瀬地区が自然生態系保護地区であるという性格を第一に重視するならばこれらの人為的干渉の恒常化は認められない。生態系生態学的にみた系の復元を前提にした自然放置, すなわち自然過程を尊重した生態系管理への移行を目標にするべきである。尾瀬は国民の関心を集める日本の代表的な湿原地帯であることから, 社会的な合意形成に向けて, 研究調査, 行政的審議過程および結果などの情報公開, 自然生態系保護の普及, 直接的利害関係者だけではない, より広範囲の国民の意思決定への参加システムの完成が必要である。
1 0 0 0 倉庫建築
- 著者
- 佐々木 哲二
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 建築雑誌 (ISSN:00038555)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.523, pp.713-717, 1929-07-25
1 0 0 0 PDF構造解説
- 著者
- John Whitington著 村上雅章訳
- 出版者
- オーム社 (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2012
1 0 0 0 完訳日本奥地紀行
- 著者
- イザベラ・バード [著] 金坂清則訳注
- 出版者
- 平凡社
- 巻号頁・発行日
- 2012
1 0 0 0 語学学習を目的とした小学生向けデジタル絵本教材システムの評価
- 著者
- 小宮山 美緒 古井 陽之助 速水 治夫
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告グループウェアとネットワークサービス(GN) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.9, pp.191-196, 2006-01-27
近年,学校教育とe-Learningの関わりが注目されつつある.著者らは,今後需要が高まると予測される小学校の児童を対象にしたe-Learningシステムの開発を試みてきた.本論文では,新しく開発した小学生向けデジタル絵本教材システムとその評価実験について述べる.評価実験は,閲覧システムを中心に使用すると想定した4~9歳の児童と,閲覧システム・作成システムの両方を使用すると想定した10~12歳の児童に着目して行った.その結果,英語経験の有無を問わず楽しく英語の絵本を読むことができることが確認できた.また,英語経験が無い児童が楽しく英語の絵本を作成できることが確認できた.Recently, the relation between school education and e-Learning is attracting attention. We have been developing e-Learning systems for elementary school students, because there is a prediction that the demand for such systems will increase in the near future. This paper introduces a digital picture-book system for elementary school student's linguistic study, and describes the experimental evaluation of the system. In this evaluation, we paid attention to two categories of children: the age of four or nine, and the age of ten or twelve. In our assumption, the former would use the browsing function mainly, while the latter would use both the browsing function and the authoring function. The result indicates that the children enjoyed reading English picture-books whether they had experienced English or not, and that even the children without such experiences enjoyed creating English picture-books.