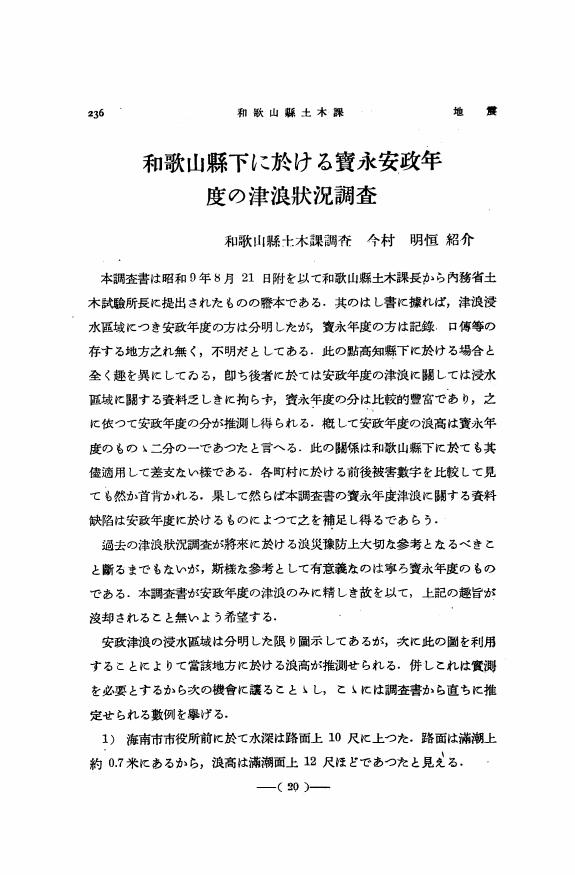1 0 0 0 圏論的結合子の操作的意味について
Curienは,カルテシアン閉圏(cartesian closed category,以下,CCCと略す)の定義における普遍写像性を,圏論的結合子と呼ばれる特別な射に関する等式に翻訳し,この等式を書き換え規則とみなすことで,関数型言語の操作的意味が圏論を通じて与えられることを示唆した.特にCCCの圏論的結合子から型,すなわち定義域と値域に関する情報と,終対象に関する結合子を取り除いた代数系(C-モノイドと呼ばれる)を用いれば,型なしのラムダ計算を従来の項書換え系として扱うことができる.横内も独立して,型なしの場合に圏論的結合子の等式を書き換え規則として扱うことを提唱した.しかし圏の射はf:A→Bのように定義域Aと値域Bによって型付けられた存在であり,射の結合は一方の値域と他方の定義域が一致するような射の対に対してのみ部分的に定義される.個々の結合子についても,異なる対象の上で同様に作用し得るという多相的な性質を持っている.たとえ型なしのC-モノイドを扱うとしても,結合子に関する個々の等式がどのような計算的・意味論的性質に連係しているのかが明らかでないので,合流性や停止性といった項書換え系の性質を考察することが困難である.本稿では,まずCCCのための圏論的結合子とその等式を随伴関手から直接導き出し,自由圏を生成する逐次式計算系を定義する.そしてこの体系におけるカット除去を圏論的結合子の操作的意味として用いることを提案する.
1 0 0 0 随伴関手を用いた圏論的結合子の導出
- 著者
- 森 彰 松本 吉弘
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌 (ISSN:18827764)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.10, pp.2422-2432, 1995-10-15
圏論的結合子(categorical vombinator)はラムダ計算の変数を含まない翻訳であることから、圏論的解釈を利用した関数型言語の実装に用いられている。本稿では圏の構造を随伴関手(adjointfunctor)で定義することで、圏論的結合子とその等式が圏論の基本概念から天下り的に導かれることを示す。圏論的結合子は随伴関手に付随する自然変換である単因子(unit)と余単因子(counit)として得られ、その等式は圏、関手、自然変換の定義、および随伴関手の三角可換図(triangular identity)から直接導かれる。まず最初にカルテシアン閉圏(cartesian closed category)のための圏論的結合子の導出について述べ、これを用いた自由圏の構成を示す。そして次に圏論的結合子の非外延的(non-extensional)な等武が半随伴関手(semi-adojoint functor)から導かれることを示す。最後に一般の極限対象(1imit object)や再帰的対象(recursive object)について考察し、その際に右随伴関手と左随伴関手の双対性(dua1ity)がどのように作用するかをみる。
過栄養に基づく肥満即ち脂肪組織の過剰蓄積は、最もcommonな成人病(生活習慣病)の糖尿病、高脂血症、高血圧、動脈硬化症等やさらに大腸癌や炎症性腸疾患の大きな発症基盤となっている。本研究では脂肪組織、特に病態と密接に関連する内臓脂肪の分子生物学的特性を明らかにすることによって、多彩な病態を発症せしむる分子機構を、国際的な研究協力によって解明しようとするものである。私達は脂肪組織発現遺伝子の蓄積部位別大規模シークエンス解析により、内臓脂肪が従来考えられていたような単なる受動的なエネルギー備蓄細胞ではなく、多彩な生理活性物質を合成・放出する分泌細胞であることを示した。フランス、パスツール研究所のDr.Auwerxはdifferential displayによる脂肪蓄積部位別発現遺伝子解析を行い、それぞれの脂肪組織に高発現する遺伝子を示した。私達は大規模シークエンス解析の過程で、脂肪細胞特異的に発現する新規分子、adiponectinを発見し、病態発症との関連について解析した。Adiponectinは血漿中に5-10μg/mlの高濃度で存在する脂肪細胞分泌蛋白であるが、肥満、特に内臓脂肪蓄積時には著しい血中濃度の低下が認められた。本分子は内皮細胞の単球接着抑制や平滑筋増殖抑制作用を有する抗動脈硬化防御因子であり、内臓脂肪蓄積における減少は重要な血管病発症の分子メカニズムの一つと考えられた。一方Dr.Auwerxは脂肪細胞分化のmaster regulatorであるPPARγに着目し、肥満発症における意義を示した。さらに本分子が腸管上皮細胞に発現しており、この細胞の分化増殖を調節していることを明らかにした。また過栄養における大腸癌の発症や、内臓脂肪蓄積とクローン病発症の関連を、PPARγを中心に明らかにした。平成11年度動脈硬化学会にDr.Auwerxを招き、互いの成果を公表した。本研究により脂肪蓄積、特に内臓脂肪蓄積と病態発症との関連を、国際間で情報交換することにより、分子レベルで明らかにされた。
【研究目的】サリドマイド(Tha)は多発性骨髄腫の適応で国内承認されたほか,種々の悪性腫瘍で有効性が報告されている.内分泌療法抵抗性前立腺癌においてもドセタキセル(DTX)との併用により臨床的有用性を示したとの報告があるが,その基礎的検討は十分に行われていない.そこで,ヒト前立腺癌細胞を用い,Tha単独あるいはDTXとの併用時における抗腫瘍効果について検討した.【研究方法】ヒト前立腺癌細胞は,アンドロゲン非依存性細胞株(PC-3)を用いた.PC-3は常法に従い継代培養し実験に用いた.PC-3を96穴プレートに播種後24hr培養し,Tha,DTXを単独あるいは併用にて一定時間曝露した.細胞生存率を蛍光ホモジニアス法を用いて測定し,種々の条件における抗腫瘍効果を比較した.【研究成果】1.Tha単独曝露:Thaの抗腫瘍効果は濃度・時間に非依存的であり,Tha 10μMにおける72hr曝露後の細胞生存率は約80%であった.2.DTX単独曝露:濃度・時間依存的に細胞生存率の低下を認め,DTX 10nMにおける24hrおよび72hr曝露後の細胞生存率は約60%および約40%であった.3.Tha前曝露後のTha/DTX併用曝露:DTX 10nM単独曝露群と比較して,DTX曝露期間中のみTha 10μMを併用した群では約10%,DTX曝露72hr前からThaを曝露した群では約30%,さらにDTX曝露期間中にもThaを併用した群では約50%の細胞生存率の低下を認め,Thaの前曝露およびDTXとの併用により抗腫瘍効果の増強が示された.これはThaのDTXとの併用における臨床的有用性を支持するものであった.また,DTX耐性PC-3を作製し,耐性化細胞におけるTha併用の有用性およびTha併用による抗腫瘍効果の増強メカニズムについて検討を行っている.
1 0 0 0 アディポネクチン受容体の生理機能・情報伝達機構と病態生理学的意義
これまで、肥満によってアディポネクチン(Ad)が低下することが、メタボリックシンドロームの少なくとも大きな原因の1つになっていると考えられてきた。我々は、さらに、肥満・インスリン抵抗性によって、総量のAdだけのみならず、高活性型である高分子量型(HMW)Adがとりわけ低下してくることを見出した。そして、PPARγアゴニストであるチアゾリジン誘導体(TZD)がこのHMWAdを顕著に増加させることを見出した(Diabetes 54:3358,2005)。我々は更に、Ad欠損マウスを用いて、このTZDによる総量、あるいはHMWAdの増加が、TZDによる抗糖尿病作用に有意に貢献していることを示した(J.Biol.Chem.,281:8748,2006)。我々は先に、Ad受容体(AdipoR)1とAdipoRを同定し,AMPキナーゼ、及びPPARαの活性化などを介し、脂肪酸燃焼や糖取込み促進作用を伝達していることを示し(Nature 423:762,2003)、さらに肥満・2型糖尿病のモデルマウスにおいては、AdipoRの発現量が低下し、Ad感受性の低下が存在することを報告してきた(J.Biol.Chem.279:30817,2004)。今年度は先ず、肥満症におけるAdipoRの発現低下を、PPARαアゴニストが脂肪組織において回復させ、MCP-1の発現を抑制し、マクロファージの浸潤を抑制し、炎症が惹起されるのを低減させているのを見出した(Diabetes 54:3358,2005)。Adの血中レベルを増加させるPPARγアゴニストとの併用、あるいはPPARαγのデュアルアゴニストは実際にモデルマウスで相加効果を発揮しており、現在臨床治験が進んでいるPPARαγのデュアルアゴニストの作用機構を少なくとも一部説明するものと考えられた。アデノウイルスと遺伝子欠損マウスを用いてAdipoR1とR2が生体内において、アディポネクチンの受容体として機能し、AMPKとPPARαの活性化に重要な役割を果たすことを示した(投稿準備中で平成18度中に公刊予定)。AdipoR1に特異的に結合する分子を同定し、その中の2つの分子がAMPKの活性化に重要な役割を果たすことを明らかにした(投稿準備中で平成18度中に公刊予定)。
- 著者
- 綿貫 克彦 片岡 信弘
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SWIM, ソフトウェアインタプライズモデリング (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.108, no.185, pp.15-19, 2008-08-15
近年SOAによるシステム開発が注目を浴び始めた.SOAではサービスを接続することによりシステムを構築する.本提案ではBPMNを使用することによりビジネスプロセスモデルからESBによるサービス接続定義を自動生成させる.
1 0 0 0 OA 大規模高速特定物体認識とその実世界指向Webへの応用
実世界指向Web とは,我々の周囲にある物体が情報の出入り口になるWeb である.物体にカメラをかざすと関連情報を瞬時に取り出せる.また,物体の撮影を通してユーザ自らが情報を関連付けることもできる.扱う物体は,文字,文書から3次元物体,顔など様々である.本研究では,このような新しいWeb を実現する上で必須となる物体認識技術の大規模化(文書の場合,1 億ページの識別),高速化(文書の場合,27ms/query),高精度化(文書の場合,認識率99%),およびその理論的基盤の構築,さらには,実世界指向Web のプロトタイプの作成を行った.
1 0 0 0 付加情報の一般的な割当(パターン認識)
- 著者
- 岩村 雅一 古谷 嘉男 黄瀬 浩一 大町 真一郎 内田 誠一
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌. D, 情報・システム (ISSN:18804535)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.5, pp.579-587, 2010-05-01
- 被引用文献数
- 1
特徴量のみでは本質的に避けることができない誤認識を回避するために,付加情報を用いるパターン認識という枠組みが提案されている.この方式では,パターン認識を行う際に,付加情報と呼ばれるクラスの決定を補助する少量の情報を特徴量と同時に用いて認議性能の改善を目指す.付加情報は自由に設定でき,通常は誤認識率が最小になるように設定する.ここで問題となるのは,誤認識率が最小になる付加情報の設定方法である.常に正しい付加情報が得られるいう理想的な条件においては既に問題が定式化され,付加情報の割当方法が導かれている.しかし,実環境での使用を考えると,付加情報に生じる観測誤差を考慮した割当方法が求められる.そこで本論文では付加情報の観測誤差を考慮に入れて,問題を新たに定式化する.これは付加情報が誤らない場合にも有効な一般的なものである.本論文で導いた割当方法が有効に機能することをマハラノビス距離を用いた実験で例示する.
1 0 0 0 競争構造の差異とストアブランドの意味解釈に関する研究
本研究は、ストア・ブランドに焦点を当てて、ブランドの意味形成と競争関係に関する内容を取り扱った。ストア・ブランドとは、「顧客の知覚空間上に形成された店舗あるいは複数店舗の総体であるストア・ブランド・レベルにおける意味の集合体」であり、顧客の店舗に対する意味形成は、店舗で提供される製品やその価格、店舗のサービスや雰囲気、それに関わる広告等のマーケティング活動を通して行われる。しかし、その店舗の製品やサービスに対する評価は、他の競争する店舗との相対的な関係のなかで決定されることも否めない。そこで、ブランドの意味をブランドの意味構造として、競争相手との関係性を競争構造としてそれぞれ捉え、ブランドの意味構造と競争構造との関係を見ることによって、競争構造の差異がストア・ブランドの意味形成にいかなる影響を与えているかを考察した。意味構造をコアの意味内容とフリンジの意味内容から構成されたネットワークとして捉え、競争構造として店舗立地を取り上げ、消費者の生活空間における店舗数の問題である量的側面と、どの競合店舗が同一の生活空間に存在しているかという質的側面に分類した。ケースとして、ストア・ブランドに対するイメージが比較的安定しており、他店との比較が容易なファストフード店(マクドナルド、モスバーガー、ミスタードーナツ等の7社)を分析対象にし、質問紙によるアンケート調査を行った(被験者は関西および関東在住の女子大学生100名)。その結果として、消費者の生活空間に多く存在しているファストフード店ほど、そのブランド評価が高いことがわかった。また、「消費者の生活空間にある競合店舗の組み合わせが異なれば、それぞれのストアブランドの意味内容も変化する」という仮説に対して、統計的に有意な結果は得られなかったが、消費者のファストフード想起集合との関係がある程度認められた。
1 0 0 0 OA 東アジアの民族移動 : 前期(五胡時代)の政治と社會を中心として
- 著者
- 田村 實造
- 出版者
- 京都大學文學部
- 雑誌
- 京都大學文學部研究紀要 (ISSN:04529774)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.1-90, 1968-10-20
この論文は国立情報学研究所の学術雑誌公開支援事業により電子化されました。
1 0 0 0 農地の所有構造の変化に関する研究--土地持ち非農家に関して
- 著者
- 中野 哲二
- 出版者
- 鹿児島国際大学経済学部学会
- 雑誌
- 鹿児島経済論集 (ISSN:13460226)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.315-330, 2009-03
1 0 0 0 OA スギの花芽分化期および花芽の発育経過について
- 著者
- 橋詰 隼人
- 出版者
- 一般社団法人日本森林学会
- 雑誌
- 日本林學會誌 (ISSN:0021485X)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.11, pp.312-319, 1962-11-25
- 被引用文献数
- 9
1) 雄花芽は新条の先端部の葉腋に形成されたが, 雌花芽は新条の頂芽に分化した。2) 自然状態における雄花芽の分化期は6月下旬〜9月下旬であった。花芽分化後, 雄花芽は急速に生長して, 短期間で雄しべおよび造胞組織の分化が認められた。そして, 9月中旬〜11月上旬の期間に花粉が形成された。3) 自然状態における雌花芽の分化期は7月中旬〜9月中旬であった。雌花芽では, 花芽分化後短期間で苞鱗の分化が認められ、8月上旬〜10月中旬の期間に胚珠が形成された。胚珠はその後珠皮と珠心に分化した。10月下旬にはすべての雌花で珠皮と珠心の完全に分化した胚珠が認められた。開花期は2月下旬〜3月下旬であった。4) 雌花芽の分化開始期は雄花芽よりも2〜3週間おそかった。また分化期間は雄花芽よりもみじかい傾向がみられた。5) 同一新条における花芽分化あるいは同一花芽における花部器官の分化は求頂的に進行した。6) 花芽分化期および花芽の発育経過には, 年により10〜20日の早晩がみられるようである。7) ジベレリン処理の場合は処理後約30日で花芽分化が開始された。ジベレリン処理によっておこる花芽分化の期間は自然分化に比して約2ヵ月ながいようであった。9月までの処理区では胚珠および花粉は年内に形成され, 開花期は自然分化に比して著しく相違しなかった。しかし, 10月処理区では花芽の発育が抑制され, 花粉は翌春形成された。したがって, 開花期は15〜20日おくれるようである。
1 0 0 0 OA 和歌山縣下に於ける寶永安政年度の津浪状況調査
- 著者
- 今村 明恒
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震学会
- 雑誌
- 地震 第1輯 (ISSN:00371114)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.6, pp.236-249, 1938-06-15 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 D-12-15 弛緩法に基づく文書画像のレイアウト解析
- 著者
- 岩田 基 黄瀬 浩一 松本 啓之亮
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会総合大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.1999, no.2, 1999-03-08
1 0 0 0 OA カメルーン東南部の狩猟採集民バカにおける社会文化変容
- 著者
- 大石 高典
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第46回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.158, 2012 (Released:2012-03-28)
アフリカ熱帯林の狩猟採集民の社会は、徹底した分配により、平等主義を規範とする社会として描かれてきた。本発表では、換金作物栽培を開始したカメルーン東南部の狩猟採集民バカが、集団内部の経済的不平等や貨幣経済の流入にともなう社会変化をどのように認識し、対応しているのかについて、最近変化が見られるようになった呪術・邪術に関わる言説や行動に着目して検討する。
1 0 0 0 ファジィ測度論入門〔1〕
- 著者
- 菅野 道夫 室伏 俊明
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 日本ファジィ学会誌 (ISSN:0915647X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.174-181, 1990-05-15
- 被引用文献数
- 2
- 著者
- 村田 厚生 三宅 貴士 森若 誠
- 出版者
- Japan Ergonomics Society
- 雑誌
- 人間工学 = The Japanese journal of ergonomics (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.20-30, 2011-02-15
- 被引用文献数
- 2 4
本研究では,使いやすい視線入力ブラウザを開発するための基礎として,視線入力を用いたメニュー選択方法(I-QGSM法)を提案し,従来法(垂直表示,水平表示,サークル表示,QGSM法)との比較実験を実施し,若年者と高齢者に対してユーザビリティの優れたメニュー選択方法を明らかにした.高齢者に関しては,いずれの方法もマウスと同程度の作業時間でメニュー選択が可能であることが明らかになった.若年者については、視線入力を用いたサークル表示は避けなければならないことが示唆された.また,I-QGSMを用いると,エラー率が減少することが分かった.主観評価については,高齢者では,I-QGSMの評価値が高かった.以上より,I-QGSMを用いてメニュー選択を実施する場合には,マウスと比較して,高齢者は同等以上,若年者についてはほぼ同等の作業スピードでメニュー選択ができることが分かり,I-QGSMの有効性が示された.
1 0 0 0 IR 医療ソーシャルワークにおける「退院援助」の変遷と課題
- 著者
- 中野 加奈子
- 出版者
- 佛教大学
- 雑誌
- 佛教大學大學院紀要 (ISSN:13442422)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.221-235, 2007-03-01
退院援助は、日本に医療ソーシャルワークが導入されて以来取り組まれてきた医療ソーシャルワーカー(以下、MSW)の主要な業務の一つである。これまでの歴史の中で、MSWは、社会問題としての生活問題の解決に取り組む実践を積み重ね、実践の中から退院援助の理論を構築してきた。しかし一方で、これまで「退院問題」「退院計画」「退院援助」という用語は曖昧な使われ方をしており、さらに、医療制度の様々な「改正」によって、医療ソーシャルワークが機能し得ない状況が起こりつつある。本論では、上記の用語の概念整理を行い、「退院援助」において、MSWが患者・家族の様々な生活問題を捉え、それらの解決・調整をしながら、患者・家族の主体形成にも関わる援助を行っていることを明らかにした。さらに、今後は、生活全体を捉える視点からの生活問題のアセスメントや、退院援助対象者のスクリーニングの「標準化」が必要であり、さらに退院後のフォローアップが必要となることを考察していくものである。
1 0 0 0 21. 宮城県沖地震による名取市手倉田の震害調査報告(構造系)
- 著者
- 山田 哲男
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会東北支部研究報告集 (ISSN:13434713)
- 巻号頁・発行日
- no.33, pp.81-84, 1979-03-17