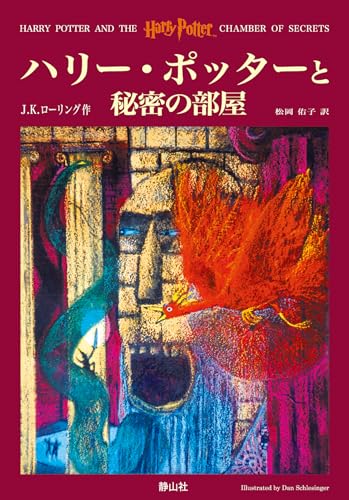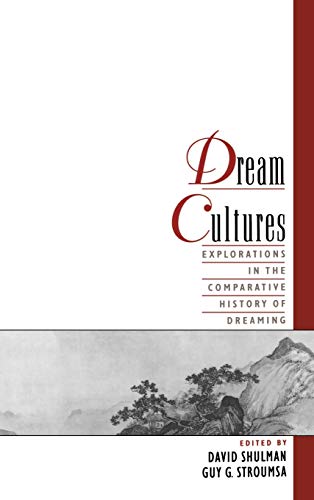1 0 0 0 OA 動物保護のドイツ憲法前史(1) : 「個人」「人間」「ヒト」の尊厳への問題提起1
- 著者
- 藤井 康博
- 出版者
- 早稲田大学法学会
- 雑誌
- 早稻田法学会誌 (ISSN:05111951)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.397-453, 2008-10-25
1 0 0 0 OA サンゴ礁学-人と生態系の共生・共存のための未来戦略-
- 著者
- 茅根 創 山野 博哉 酒井 一彦 山口 徹 日高 道雄 鈴木 款 灘岡 和夫 西平 守孝 小池 勲夫
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 新学術領域研究(研究領域提案型)
- 巻号頁・発行日
- 2008-11-13
サンゴ礁学の目的は,生物,化学,地学,工学,人文の諸分野を,複合ストレスに対するサンゴ礁の応答という問題設定のもとに融合し,サンゴ礁と人との新たな共存・共生を構築するための科学的基礎を築くことである.本領域では,ストレス要因の時空変化を評価して,遺伝子スケールから生態系スケールまで整合的なストレス応答モデルを構築し,サンゴ礁と共生する地域のあり方を提案した.本課題は,こうして産まれた新しい学問領域を確立し,他分野へ展開するとともに,地域社会への適用と人材育成を継続的に行うために,以下の活動を行った.新しい学問領域の確立:平成25年9月29日―10月2日に,海外から研究者を招へいして,「サンゴ礁と酸性化」に関する国際ワークショップ(東京大学伊藤国際学術センター)を開催し,今後の展開について議論した.12月14日日本サンゴ礁学会第16回大会(沖縄科学技術大学院大学)では,「サンゴ礁学の成果と展望」というタイトルで,総括と次のフェイズへ向けての戦略を示した.また,”Coral Reef Science” の原稿を,各班ごとに作成して,現在編集作業を進めている.他分野への展開:12月15日,日本サンゴ礁学会第16回大会において,公開シンポジウム「熱帯・亜熱帯沿岸域生物の多様性へのアプローチと課題」を,日本サンゴ礁学会主催,日本ベントス学会,日本熱帯生態学会共催によって開催して,サンゴ礁学の成果を,関係する生態系へ展開する道を議論した.地域社会への適用:これまでに19回石垣市で開催した地元説明会・成果報告会のまとめの会を,2013年8月に実施して,プロジェクト終了後の地元と研究者の連携のあり方,研究成果の還元の継続を話し合った.人材育成:サンゴ礁学の取り組みのひとつとして,これまで4回実施したサンゴ礁学サマースクールを,東京大学と琉球大学共同の,正規の実習科目として定着させることに成功した.
1 0 0 0 ハリー・ポッターと秘密の部屋
- 著者
- J. K. ローリング作 松岡佑子訳
- 出版者
- 静山社
- 巻号頁・発行日
- 2000
1 0 0 0 OA 環状ジアデニル酸の生理活性探索
1 0 0 0 OA 1.内視鏡診断
- 著者
- 門馬 久美子 吉田 操 榊 信廣
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.1, pp.28-35, 2000-01-10 (Released:2008-06-12)
- 参考文献数
- 10
胃・食道逆流症(gastroesophageal reflux diseases: GERD)とは,食道内酸逆流により引き起こされる病態すべての総称であり,自覚症状あるいは,他覚所見を有するものである.食道粘膜への過剰な刺激は,食道粘膜の炎症性変化を起こすが,有症状者でも内視鏡有所見者は半数程度であり,自覚症状と粘膜所見の間には乖離がある.内視鏡にて観察される食道炎の大半は,上皮の欠損によるびらん・潰瘍性の変化であり,食道・胃接合部から口側へ,連続的あるいは非連続的に広がり,食道・胃接合部に近い下部食道に最も変化が強い.内視鏡所見を分類するには,ロサンゼルス分類,あるいは,食道疾患研究会の新分類案が使用されている.
1 0 0 0 PKCS#1V15署名の実装における脆弱性の攻撃可能性
- 著者
- 金岡晃 杉本 浩一
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告コンピュータセキュリティ(CSEC) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, no.129, pp.1-5, 2006-12-08
- 参考文献数
- 2
YPTO2006のRumpSessionにおいてB1eichenbacherにより、一部のPKCS#lvL5署名を実装するソフトウェアに脆弱性が存在することが発表された。その脆弱性は広く利用されているオープンソースソフトウェアopensslにも存在することがわかり、社会に広く影響を与えた。B1eichenbacherにより示された攻撃法はいくつかの条件が必要となることが示されているが、本論文ではさらなる解析を行うことで、より詳細な攻撃条件を示した。さらに現実的に利用されている環境を考慮し、その脆弱性の脅威を正確に把握した。Bleichenbacher showed that some PKCS#lvl.5 signature implemantation has vulnerability at CRYPTO 2006 Rump Session. That vulnerability enable PKCS#15vl.5 signature forgery without private key under some conditions. Though Bleichenbacher also showed some conditions to attack, there are more detailed one. In this paper, I will show more detailed conditions and consider real threat on that vulnerability.
1 0 0 0 第2次若槻内閣の瓦解(国際教養学科専任教員)
- 著者
- 渡辺 孝
- 出版者
- 武蔵野短期大学
- 雑誌
- 武蔵野短期大学研究紀要 (ISSN:02888025)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.167-177, 1999-06-25
1 0 0 0 太陽黒点の生成・発展機構
- 著者
- 増田 皓子 (2009 2011) 渡邉 皓子 (2010)
- 出版者
- 京都大学
- 雑誌
- 特別研究員奨励費
- 巻号頁・発行日
- 2009
本年度は太陽黒点微細構造の分光的性質の時間変化を知るということを目的に解析を行なった。アンブラルドットはサイズが小さく寿命も短いため、その分光性質の時間発展を求めるには現在の観測技術では限界に近い程の高い時間・空間分解能が必要となる。スペインのLuis Bellot Rubio教授から提供を受けたデータは、黒点を撮影した世界最高級のデータであり、このデータを得た事で、アンブラルドットの時間発展の統計的調査に世界で初めて取り組むことができた。その結果、「背景磁場の弱い所では、アンブラルドットに伴ったローカルな磁場強度の減少と磁力線の傾斜が観測されたが、背景磁場の強い所では、逆にローカルな磁場強度の増加と磁力線が垂直に近づく様子が観測された」といった、これまでに報告されていなかった結果を得た。申請者は理論モデルとして、黒点の太陽表面上での位置とスペクトル線の形成領域の変化を取り入れた新しいモデルを提案した。これらの結果をまとめた論文は、The Astrophysical Journalに2011年12月に提出され、2012年1月にレフェリーレポートを受け取った。レフェリーのコメントは非常に好意的であり、現在改訂論文を準備中である。また、博士課程で行なった研究の集大成として博士論文を執筆、提出した。内容は、太陽黒点に関するイントロダクションの他に三章立てで[1]移動速度の速いアンブラルドットの時間変化[2]アンブラルドットの背景磁場への特徴依存性[3]アンブラルドットの速度場・磁場の時間変化という構成にした。[1]と[2]の内容は、それぞれ2010年、2009年に申請者が主著で査読論文として出版された内容に基づいている。黒点暗部微細構造についての観測的性質をほぼ全て網羅した包括的な論文に仕上がったと思う。博士論文は無事に受理され、2012年3月に博士号を取得した。
1 0 0 0 同志社商學
- 著者
- 同志社大學商學會 [編輯]
- 出版者
- 同志社大學商學會
- 巻号頁・発行日
- 1949
1 0 0 0 OA 国際規範の競合と複合化についての比較研究
本研究では、国際規範の発展における規範間の競合または複合のプロセスを明らかにすることを目的とした。グローバル、リージョナル、ナショナルの各レベルにおいて、①規範的アイディアの競合や複合が、どのような制度変化をもたらすか、②多様な行為主体(国家、国際機構、市民社会、企業等)が競合または複合の過程にどのように関っているか、または、競合や複合から生じる問題をどのように調整しているか、の二点を中心的な問いとして、事例分析を行った。成果は、国際・国内学会発表や論文発表を通じて逐次公開した。最終的には、編著『国際規範の複合的発展ダイナミクス(仮題)』(ミネルヴァ書房)として近刊予定である。
1 0 0 0 インドの選挙 (特集 インド ここがおもしろい)
- 著者
- 南埜 猛
- 出版者
- 古今書院
- 雑誌
- 地理 (ISSN:05779308)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.6, pp.52-57, 2004-06
1 0 0 0 インド系移民統計に関する一考察
- 著者
- 南埜 猛
- 出版者
- 兵庫教育大学
- 雑誌
- 兵庫教育大学研究紀要. 第2分冊, 言語系教育・社会系教育・芸術系教育 (ISSN:09116222)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, pp.69-80, 2002
1 0 0 0 OA シナプス構造の分子解剖
1 0 0 0 社會經濟史學
- 著者
- 社會經濟史學會 [編]
- 出版者
- 日本評論社 (發賣)
- 巻号頁・発行日
- 1931
- 著者
- edited by David Shulman and Guy G. Stroumsa
- 出版者
- Oxford University Press
- 巻号頁・発行日
- 1999
1 0 0 0 時間依存周期写像を用いたカオス想起モデル
- 著者
- 田中 剛 中川 匡弘
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界 (ISSN:09135707)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.11, pp.1826-1843, 1996-11-25
- 被引用文献数
- 9
本論文において,パラメータ制御を伴う区分線形周期写像を用いた,自己想起モデルが提案される.実際,本モデルの活性化関数は,ネットワークの準安定状態である偽記憶に陥ることなく,高い記憶容量を実現するため,単調周期写像の間を非単調周期写像を経て制御される.また,本モデルは,周期写像に基づくカオスカ学により,カオスを用いた記憶探索モデルを構成でき,更に入力に関する情報を外部刺激として与えることにより自己想起が実現される.計算機シミュレーションの結果から,本モデルは,探索モードにおいてでさえ,記憶率L/N〜0.5までは完全想起が実現されることが見出された.更に,ネットワークを非同期的動作させることにより,想起特性の改善,および,記憶容量が向上(探索モードにおいて記憶率L/N〜0.56)が確認され,ネットワークの非同期動作におけるカオスの有用性が見出された.
1 0 0 0 OA 看護学士課程における島嶼看護学教育の効果と課題に関する研究
1 0 0 0 OA セクシャル・ハラスメントの不法行為評価(1)
- 著者
- 和田 美江
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.5, pp.219-272, 2003-01-24
1 0 0 0 OA セクシャル・ハラスメントの不法行為評価(2・完)
- 著者
- 和田 美江
- 出版者
- 北海道大学大学院法学研究科
- 雑誌
- 北大法学論集 (ISSN:03855953)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.6, pp.251-305, 2003-03-20
- 著者
- 三宅 裕子 山崎 不二子 田原 孝
- 雑誌
- 診療録管理 : 日本診療録管理学会会誌 = Medical record administration (ISSN:0916345X)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.57-62, 1996-02-20
- 被引用文献数
- 3