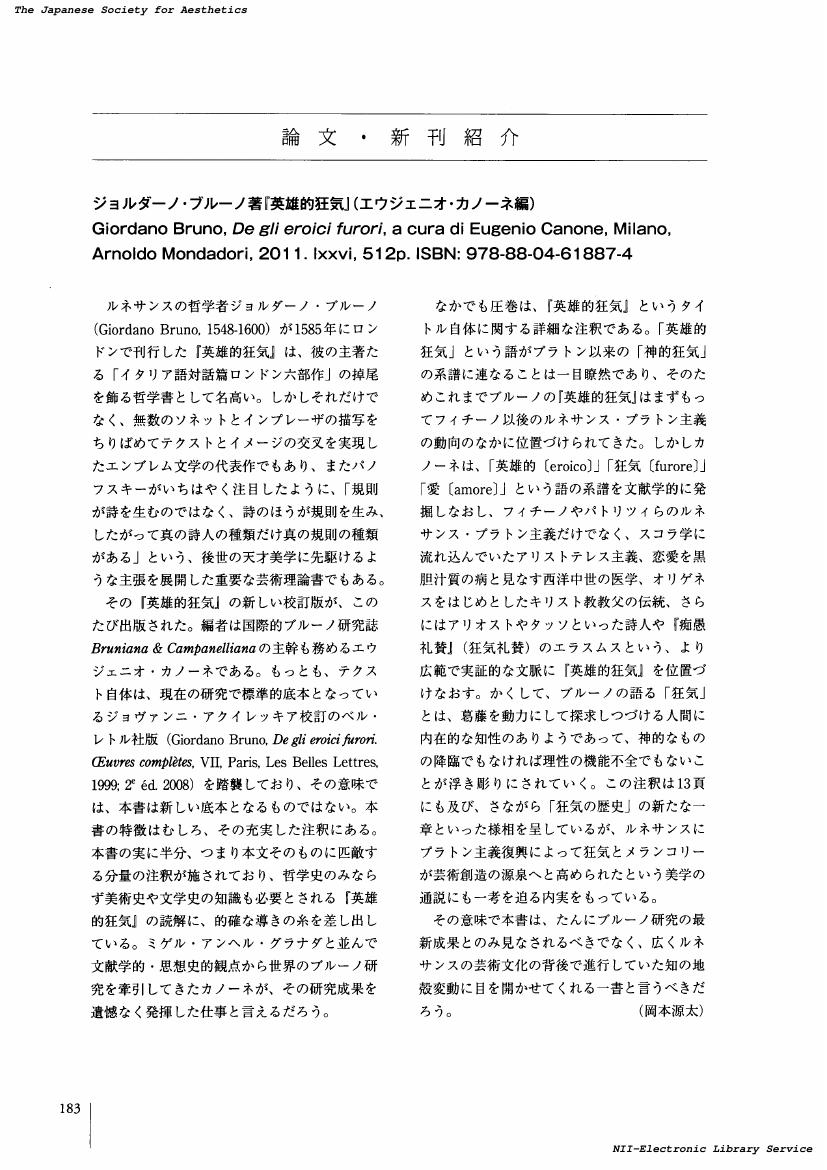4 0 0 0 OA 掲載原稿の撤回について
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会誌 (ISSN:13498509)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.3, pp.e1, 2022-06-01 (Released:2022-07-20)
短報「生分解性不織布ポットを用いたスギ・ヒノキ苗の植栽後2年間の成長」 著者:北原文章,酒井敦,米田令仁 巻号:102巻4号263-269ページ,2020年 上記短報について,著者及び著者の所属機関から日本森林学会誌編集委員会に対し,撤回の申し出があった。 編集委員会でその内容を検討した結果,著者らによる申し出を受理し,日本森林学会誌編集委員会は当該論文を撤回する。 詳細はPDFを参照のこと。
4 0 0 0 OA 教員養成におけるSTEM/STEAM 教育の展望
- 著者
- 北澤 武 赤堀 侃司
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.297-304, 2021-03-10 (Released:2021-03-15)
- 参考文献数
- 50
- 被引用文献数
- 2
米国を中心に海外で普及しているSTEM/STEAM 教育について,我が国でも文部科学省や経済産業省を中心に議論がなされてきた.そして,2020年度から小学校から段階的に施行する新学習指導要領を踏まえつつ,教科横断的な側面と既存の教科内で扱われる問題の文脈を他の領域と関わらせる側面がある統合型STEM 教育に,リベラルアーツの考え方に基づきながら美術,音楽,文学,歴史に関わる学習を「A」として取り入れた日本型STEAM 教育の議論が行われているが,これを実践できる教員を養成することが課題となっている.本稿では,我が国で議論されているSTEM/STEAM 教育に着目しながら,教員養成に求められるSTEM/STEAM 教育の展望を述べる.
4 0 0 0 IR 明治の名所 : 『国学和歌改良論』から鉄幹まで
- 著者
- 堀下 翔
- 出版者
- 筑波大学日本文学会近代部会
- 雑誌
- 稿本近代文学
- 巻号頁・発行日
- no.44, pp.1-18, 2021-03-31
4 0 0 0 OA 「 絶 版 」状 態 の 放 送 ア ー カ イ ブ教育目的での著作権法改正の私案
- 著者
- 大髙 崇
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.6, pp.34-51, 2022-06-01 (Released:2022-07-27)
教育のICT活用が本格化する中、放送局に保存される膨大な数の放送アーカイブを、授業等で利用するニーズが高まりつつある。本稿の主眼は、放送局等から教育機関に放送アーカイブを提供するうえで課題となる権利処理の問題に注目し、著作権法の新たな権利制限規定の私案を提示ながら、その妥当性を検討することにある。私案は、放送アーカイブのうち権利処理が難しく、一般の市場で入手困難なものを、「絶版」として再定義し、それらを授業等の目的と限定的な範囲での配信であれば権利制限とするものだ。国際的な手法「スリー・ステップ・テスト」にもあてはめ検討し、私案の妥当性を確認した。併せて検討した拡大集中許諾制度の効果と課題も示す。また、仮に私案が実現しても、学校のネットワーク環境や認証システムなど、ほかにも課題はある。しかし、それらの課題を克服すれば、放送アーカイブが多くの社会的ニーズに貢献する可能性を指摘する。
- 著者
- 竹内 一真 海老田 大五朗 田中 大介
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学フォーラム (ISSN:18842348)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.5-15, 2020 (Released:2021-10-28)
4 0 0 0 OA 建物設備の進化に伴う既存住宅の経済的陳腐化 首都圏中古戸建て住宅市場の分析
- 著者
- 鈴木 雅智 新井 優太
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.779, pp.219-229, 2021 (Released:2021-01-30)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1 1
Compared to western countries, Japan still has a large number of new housing starts while vacant stocks have been increased over time. A possible explanation is that effective age of houses is short in housing market: existing housing stock becomes economically obsolete once new housing equipment emerge among newly built houses. Although reform and renovation take place to update part of the equipment, some may be difficult to be inserted through renewal, and thus, newly built houses play a crucial role to update housing quality to the contemporary needs. The purpose of this paper is to measure (i) the degree of economic obsolescence of properties from lacking emerging housing equipment and (ii) effect of renewal activities on improving housing quality, price, and depreciation. To capture such a market mechanism, which has been ignored in architectural literature, we employ a novel dataset on resale transactions of detached houses in the Tokyo metropolitan area with details on their housing equipment and renewal activities. First, we investigate relations between diffusion rate of housing equipment and renewal activity. For sanitary equipment, diffusion rate has been increased over time, and even for old houses, the equipment is inserted through renewal. For equipment relating to building structure, on the other hand, such a renewal adjustment is not so common. Second, we investigate the degree of economic obsolescence from lacking emerging housing equipment, employing a hedonic regression technique. Old houses without the up-to-date housing equipment exhibit lower price premium among their age cohort, suggesting economic obsolescence. Third, we investigate the effect of reform and renovation on property price and depreciation speed, through similar estimations. Although renewal activities are positively reflected in transaction price for old houses, renovation that fundamentally update the quality of a house rarely occurs. Alternatively, make-up inner-reform is common, which is unable to slow down depreciation. Fourth, subsample analyses are conducted on the locational heterogeneity within the Tokyo metropolitan area. In outer suburbs (far away from the center), diffusion rate of housing equipment tends to be low, renovation rarely takes place, and most of the renewal activities remain to be make-up inner reform. Therefore, the economic obsolescence from lacking sanitary equipment and depreciation tend to be severe, while renewal, if taken place, has a large effect on slowing these down. The above results imply that old houses face a mismatch between their poor housing equipment and contemporary needs for living, and that reconstruction may play a role to fundamentally update the housing quality because of the difficulty in updating through renewal.
4 0 0 0 OA 鼻腔の加温・加湿機能評価の試み―水分回収率という考え方―
- 著者
- 野々田 岳夫 細田 泰男 大谷 真喜子
- 出版者
- Japan Rhinologic Society
- 雑誌
- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4, pp.450-454, 2012 (Released:2012-12-27)
- 参考文献数
- 16
鼻腔の重要な機能に加温・加湿機能があるが,日常診療で簡便に検査できる方法はない。一般に冷たい外気を鼻で吸入しても,上咽頭では温度30°C前後,湿度90%前後に加温加湿され,潤いある空気が下気道に入る。一方,口には鼻腔ほどの加温・加湿機能はないため,冷たい乾燥した空気が直接下気道に入りやすく,気管を痛める原因となる。鼻腔の加温・加湿機能を評価するためには,狭い鼻腔内にセンサーを挿入する必要があるが容易ではない。そこで我々は,呼気に着目した。呼気で肺から鼻や口で呼出されるまでに,どれくらいの呼気中の水分が粘膜に回収されたかを水分回収率と定義した。この呼気の水分回収率が高いほど次の吸気の加湿に有利ではと考えた。(対象と方法)今回,我々は鼻腔所見が正常な18人(男性8人,女性10人)を対象に,鼻と口の水分回収率,鼻へ血管収縮薬噴霧後の鼻の水分回収率を測定し比較した。(結果)鼻の水分回収率は,口より有意に高くなった(p<0.001)。また,鼻に血管収縮薬を噴霧すると,鼻の水分回収率は噴霧前に比べて有意に低下することがわかった(p<0.01)。(まとめ)このことは,通常鼻呼吸のみでは鼻が乾いた感覚は出現ないのに対し,口呼吸や鼻へ血管収縮薬を噴霧すると,口や鼻が乾きやすくなることと矛盾しない。呼気の水分回収率は,次の吸気で利用できる水分を反映するため,鼻腔での加温・加湿機能評価の一助になると考えた。
4 0 0 0 OA 戦間期における京都花街の経済史的考察
- 著者
- 瀧本 哲哉
- 出版者
- 京都大學人文科學研究所
- 雑誌
- 人文學報 (ISSN:04490274)
- 巻号頁・発行日
- vol.115, pp.193-222, 2020-06-30
戦間期の京都には花街(貸座敷免許地)が16か所あり, 京都府内外から大勢の遊客が花街を訪れていた。全国的にみた京都花街の特異性は, 人口や工業生産額との対比でみて娼妓数が他府県と比べて際立って多いことである。当時の京都は「繊維の街」であったが, 「遊廓の街」でもあったのである。1920年代前半に芸娼妓数が急増し, 遊客数や遊興費も増加して, 花街はおおいに賑わった。その背景としては, 府内の繊維産業の業況回復に伴って遊客の遊興費支出額が増加したこと, 1928年(昭和3年)の昭和の大礼による観光客の増加が遊客数の増大につながったことが挙げられる。戦間期の京都府内の花街は, 芸妓主体の花街と娼妓主体の花街(遊廓)に分化していく過程にあった。芸妓主体の花街は, 1930年代に入ってから芸妓数が減少し, 遊興費も落ち込んで地盤沈下していった。一方, 娼妓主体の花街(遊廓)では, 1930年代前半も郡部を中心に娼妓数や遊客数の増加が続いた。京都花街の経済的な位置付けをみると, 芸娼妓は毎月多額の賦金や雑種税を京都府に納付していた。その金額規模は, 商工業者等に課される京都府税の3割前後にまで達しており, 不況期には芸娼妓の税額が府税落ち込みの下支えの役割を果たした。そして, この恩恵を享受していたのは専ら京都府民である。また, 花街が吸い上げた遊興費は, 1920年代前半には京都府歳入総額にほぼ匹敵する規模にまで達していた。さらに, 花街では数多くの芸娼妓が稼業を営んでおり, 衣装代などの多額の支出を行っていたことから, 呉服商など関連業界は大きな恩恵を受けていた。このように, 花街は消費経済の主要な事業体として京都経済に組み込まれており, 地域経済の循環の一翼を担っていた。芸娼妓は賤業と蔑まれながらも, 納税などを通じて京都経済の発展に寄与していた。京都府民も間接的に芸娼妓から搾取していたのである。
4 0 0 0 OA 頭足類の社会性と知性基盤
- 著者
- 池田 譲
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.5, pp.783-784, 2004 (Released:2005-07-08)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
4 0 0 0 OA 演劇活動を通した若者の居場所づくりの可能性
- 著者
- 藤田 仁美
- 巻号頁・発行日
- 2022-03-31
2021年4月、子ども・若者育成支援推進本部は、「子供・若者育成支援推進大綱~全ての子供・若者が自らの居場所を得て、成長・活躍できる社会を目指して~」(以下「大綱」という)を策定した。その経緯には、子ども・若者を取り巻く状況が深刻さを増しているという認識が示されている。大綱において作成、公開された「子供・若者インデックスボード」で、子ども・若者の居場所の数の多さと自己認識の前向きさが概ね相関関係にあるというデータを示した。特に、各国に比して低いとされる日本の高校生の自己肯定感を高めるためには、彼らの居場所の数を確保することが必要であると考えられる。 居場所という言葉は、きわめて現代的なテーマ、教育的な用語として使用されており、概念的定義は一貫していない。先行研究に共通していえることは、ある場所を居場所であるととらえることは当事者の主観・認知に左右されるものであり、居場所概念は心理的な意味を多く含んでいるということである。そして、その中心には、他者とのつながりという関係性がおかれているということが指摘されている。当事者が居場所を認識するときに感じられるものが居場所感であり、その主たる要素に自己肯定感、自己有用感、被受容感、安心感があることも示されている。また、若者の居場所づくり研究が数少ないことも指摘されている。 本稿では、先行研究に拠り、若者の居場所づくりを自己の再認識の機会をもたらし自己肯定感を高める活動とし、大人との関係性を課題ととらえる。若者の居場所づくりの中で、自己肯定感を高める可能性のある演劇活動を通したものに注目し、そこでの若者への大人の関わり方と、それを生みだす仕組みを明らかにすることを目的とした。 東京都杉並区立児童青少年センター「ゆう杉並」の「オフィシャル演劇」と、愛知県豊橋市の穂の国とよはし芸術劇場「PLAT」の「高校生と創る演劇」を調査対象とした事例研究を行い、インタビュー・アンケート・参与観察データを分析した。そこでは、大人が若者の個を尊重して、主体性を促すために「教えない」という関わり方をしていることが明らかになった。その関わり方をうむ仕組みには、目的と情報を共有できる円滑な職場内コミュニケーションのある良好な大人同士の関係性と、キー・パーソンによる人員配置の二つがあり、それらに加えて、演劇活動の非効率的な時間と舞台発表のかたち、特別なスキルや準備の不要な点、スタッフワークを含めて多くの役割を持つ点などが、若者の自己肯定感を高め、主体的参加をうながす可能性をもつ。 事例研究を通して、演劇活動を通した若者の居場所づくりは、その活動の特性から、参加する若者の主体性を重要視し、教えない、個を尊重するという大人の関わり方を生みやすくし、演劇活動を通した居場所は、若者の自己肯定感を高める可能性を持つと示唆された。
4 0 0 0 OA 社会福祉における「貨幣貸付」的方法についての一考察 : 世帯更生資金貸付制度をめぐって
- 著者
- 岩田 正美
- 出版者
- 東京都立大学人文学部
- 雑誌
- 人文学報. 社会福祉学 (ISSN:03868729)
- 巻号頁・発行日
- no.6, pp.133-168, 1990-03-10
4 0 0 0 OA 帝國議会衆議院議員名簿
- 出版者
- [衆議院]
- 巻号頁・発行日
- vol.第29-31,35-47囘, 1912
4 0 0 0 デ・レ・メタリカ : 近世技術の集大成-全訳とその研究
4 0 0 0 OA ジョルダーノ・ブルーノ著, 『英雄的狂気』, エウジェニオ・カノーネ編(論文・新刊紹介)
- 著者
- 岡本 源太
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美学 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.1, pp.183, 2013-06-30 (Released:2017-05-22)
4 0 0 0 OA 日本米食史 : 附・食米と脚気病との史的関係考
4 0 0 0 OA 夫婦成功美談 : 男女修養
- 著者
- 東京実用女学校 編
- 出版者
- 東京実用女学校出版部
- 巻号頁・発行日
- vol.第1編, 1909