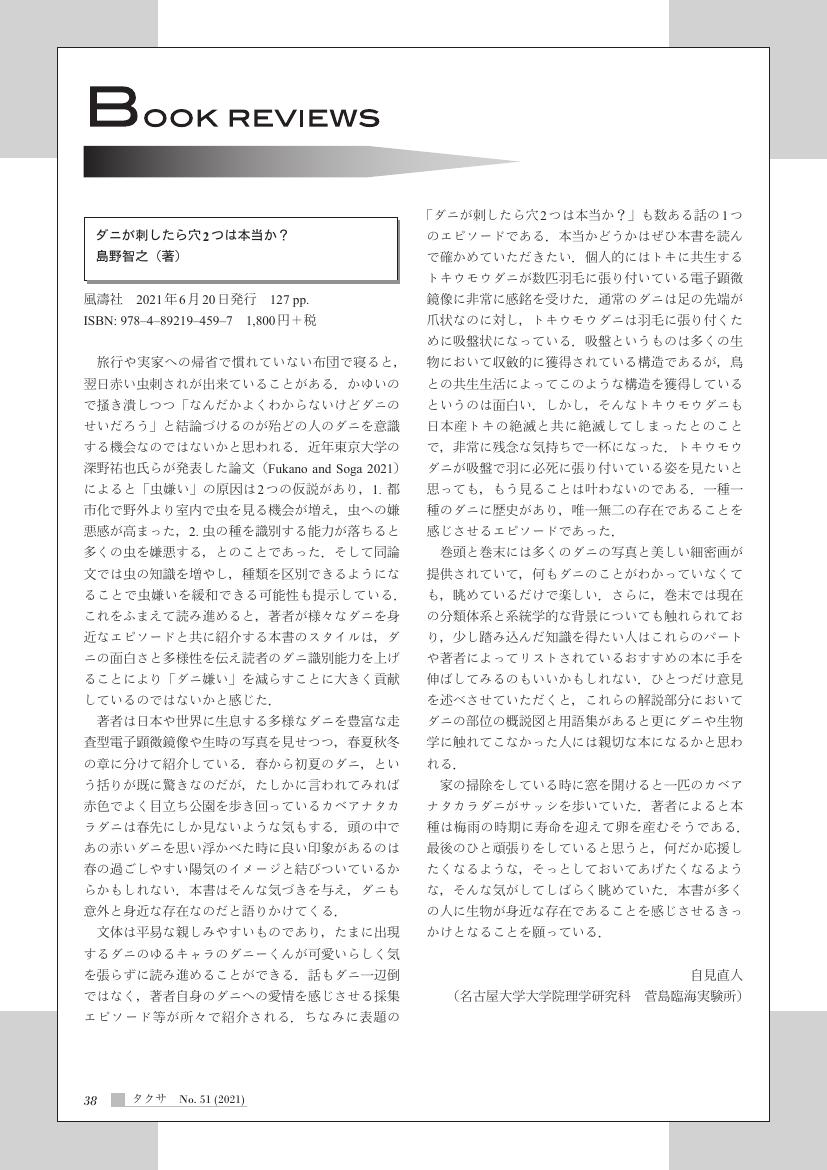4 0 0 0 OA 川柳吉原誌 : 江戸研究
- 著者
- 佐々醒雪, 西原柳雨 編
- 出版者
- 育英書院
- 巻号頁・発行日
- 1916
4 0 0 0 OA 国文学研究資料館概要(和文)2022
- 著者
- 人間文化研究機構国文学研究資料館
- 出版者
- 人間文化研究機構国文学研究資料館
- 雑誌
- 国文学研究資料館概要(和文)2022 = National Institute of Japanese Literature 2022
- 巻号頁・発行日
- pp.1-32, 2022
4 0 0 0 OA 管絃樂:皇子御誕生奉祝行進曲
4 0 0 0 OA 高フレームレート撮像テレビジョンシステムの動画質改善効果
- 著者
- 江本 正喜 菅原 正幸 日下部 裕一 大村 耕平
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.8, pp.1208-1214, 2011-08-01 (Released:2011-11-01)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
In recent years, television systems with a wide field of view that offer an elevated sense of presence have been proposed. They have higher spatial resolutions than conventional systems. On the other hand, the effects of increasing the temporal resolution or frame rate of television systems have not yet been sufficiently investigated, with the exception of the effects of frame interpolation at the receiver. On the assumption that people will enjoy TV with wide field of view displays at home in the future, we conducted a quantitative analysis of the effects of increased frame rate by a subjective evaluation of moving picture quality. The results indicated that an increase in frame rate from 60 frames per second (fps) to 120 fps improved the evaluated quality by 0.46 rank and an increase from 120 to 240 fps improved quality by 0.23 rank, with statistical significance. The degree of improvement depended on the picture content.
4 0 0 0 OA 脳神経科学と社会と倫理
- 著者
- 佐倉 統
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.7, pp.923-929, 2011 (Released:2013-07-01)
- 参考文献数
- 26
4 0 0 0 OA スーパー雑草の出現 ── グリホサート抵抗性ヒユ属雑草を中心に ──
- 著者
- 冨永 達
- 出版者
- 一般社団法人 植物化学調節学会
- 雑誌
- 植物の生長調節 (ISSN:13465406)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.65-67, 2016 (Released:2017-02-15)
- 参考文献数
- 16
Glyphosate is the most widely used herbicide in the world. Resistance to the herbicide in weeds leads to severe yield losses for crop. The resistance to glyphosate of amaranth is due to two mechanisms: target site resistance conferred by amino acid change in a target enzyme or overexpression of a target enzyme, and non-target site resistance conferred by changes in sequestration and/or translocation of the herbicide. Various kinds of weed seeds have been introduced as contaminants in imported grains and some of them are resistant to herbicide. The monitoring of the spread of resistant genes is necessary. Plant hormones that control sexual reproduction will be one of the powerful candidates to control weeds.
4 0 0 0 IR マッカーサー元帥杯スポーツ競技会の成立と廃止
- 著者
- 大久保 英哲 山岸 孝吏
- 出版者
- 金沢大学教育学部
- 雑誌
- 金沢大学教育学部紀要 教育科学編 (ISSN:02882523)
- 巻号頁・発行日
- no.53, pp.89-100, 2004-02
金沢大学教育学研究科修了(福井県敦賀市立敦賀中学校)
4 0 0 0 OA 民法改正による夫婦別姓が、子どもに与える影響と効果
本研究は、「選択的夫婦別姓制度」の導入による民法改正が実現した場合、別姓を選択した家族への影響を考察することを目的としている。特に、子どもが成長するうえでのアイデンティティ形成と氏の関係を質問紙調査、子どもの文字選好実験、親の離婚や再婚等で改姓を経験した子ども(18歳以上)へのインタビュー調査などを行い、検証した。その結果、幼い子どもたちの多くは、自分の氏名から文字に興味関心を持つ。また、離婚や再婚を経験し成長した子どもにとって、氏の変更は周囲へ説明する煩わしさを感じる一方で、実生活を優先に考える傾向が見られ、家族や個人の氏への執着は低く、実際の家族関係を優先するという傾向が見られた。
4 0 0 0 OA ダニが刺したら穴2つは本当か? 島野智之(著)
- 著者
- 自見 直人
- 出版者
- 日本動物分類学会
- 雑誌
- タクサ:日本動物分類学会誌 (ISSN:13422367)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.38, 2021-08-31 (Released:2021-08-31)
4 0 0 0 OA 自閉症者は変化に弱い?
- 著者
- 志村 久
- 出版者
- 心理科学研究会
- 雑誌
- 心理科学 (ISSN:03883299)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.90-104, 2018 (Released:2019-01-26)
- 参考文献数
- 30
4 0 0 0 OA 心理学と科学方法論:ポパーと二人の心理学者(K.ビューラー.A.アドラー)
- 著者
- 立花 希一 TACHIBANA Kiichi
- 出版者
- 秋田大学教育文化学部
- 雑誌
- 秋田大学教育文化学部研究紀要 人文科学・社会科学 (ISSN:1348527X)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, pp.57-66, 2012-03-01
There were two psychologists, Karl Buhler and Alfred Adler, who had taught Popper. Popper rarely confessed his intellectual debt, but he exceptionally said that he owed to Karl Buhler. On the other hand, Popper condemned Adler's Individual Psychology as a pseudo-science. However, as we read Adler, we are surprised to find that Popper was greatly influenced by Adler in various points such as the logic of social situation, optimism, the regulative idea of the absolute truth, the view of science as modified commonsense and so on. Popper accepted Buhler’s psychology of learning. Viewing from these contexts, it seems to us that Popper’s thought was not original at all. However Popper changed the psychology of learning into the logic of scientific learning and proposed falsificationist methodology of science. His originality is found in this point.
- 著者
- 橋本 剛明 唐沢 かおり
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.104-117, 2011 (Released:2012-03-24)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 6
本研究は,侵害者が行う謝罪に対して,実際の被害者と,被害の観察者とが異なる反応を示すという傾向を検討した。特に,謝罪によってもたらされる「許し」の動機づけと,さらにその規定因となる責任帰属や情緒的共感といった変数に注目し,被害者と観察者の謝罪に対する反応の差異を検討した。大学生136名に対して,被害者/観察者の視点を操作した被害場面シナリオ,及び侵害者による自発性を操作した謝罪シナリオを段階的に提示し,各段階で侵害者への反応を測定した。その結果,「許し」の動機づけに関しては,視点と謝罪タイプの交互作用が見られ,非自発的な謝罪は,観察者のみに対して「許し」の促進効果を持っていた。さらに,謝罪が「許し」を規定する媒介過程においても,視点間の非対称性が示された。観察者においては,謝罪は責任判断と情緒的共感の両者の変数と介して「許し」を規定していたのに対して,被害者においては,情緒共感のみがそのような役割を担っていた。以上の結果から,対人葛藤場面においては,その被害者と観察者の判断を動機づける要因が異なることが示唆される。
4 0 0 0 OA 小おもと名寄
- 著者
- 水野忠敬//編,関根雲停//画
- 巻号頁・発行日
- vol.〔1〕, 1832
4 0 0 0 OA 国鉄自動車の概況
- 出版者
- 日本国有鉄道自動車局
- 巻号頁・発行日
- vol.昭和39年版, 1964
4 0 0 0 OA 中国ミャオ族伝統色のシンボル学研究
- 著者
- 鄭 暁紅
- 出版者
- 一般社団法人 日本色彩学会
- 雑誌
- 日本色彩学会誌 (ISSN:03899357)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.3+, pp.110, 2018-05-01 (Released:2018-07-17)
- 参考文献数
- 2
中国ミャオ族の歴史の中,色彩の応用は極めて複雑である.その色彩は記号化され,視覚から意味の多重化までなっている.本論文はシンボル学から,中国ミャオ族色彩を記号として応用する意味を研究する.論文の論理の成立は,ミャオ族の伝統的な色彩に基づいて非常に複雑な記号的な状態を備えている.視学から,ミャオ族の伝統色はあまりにも複雑な表示方式で,歴史を感知次元で,その複雑さは絶えず変化し,最も直接的な身体体験から,微妙な感情体験まで,その記号の表示方式が固定していない.シンボル学の角度から,ミャオ族の伝統色彩が異なる歴史条件の下で,その色彩の感知を考察し,複雑な歴史の霧の中で,相対的にはっきりした伝統色彩の変化道を見つけることができる.ミャオ族服装の色彩は,その伝統文化のなかに特殊な存在である,その色彩象徴の変化プロセスは,ミャオ族色彩の歴史変化の普遍的な意味を持っている,ミャオ族伝統色の秘密を開ける鍵を見つけることができるかもしれない.本論文の研究重点は,ミャオ族服装色の記号的意味を研究し,視覚から中国ミャオ族伝統色彩の多重変身の鍵を研究し,その色彩意義と象徴を解読し,有効的な応用方法を探る.
4 0 0 0 百貨店の次に来るもの : 米国の商売は変ってきた
4 0 0 0 色彩研究 = Studies of color
- 出版者
- 日本色彩研究所
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, 1961-11