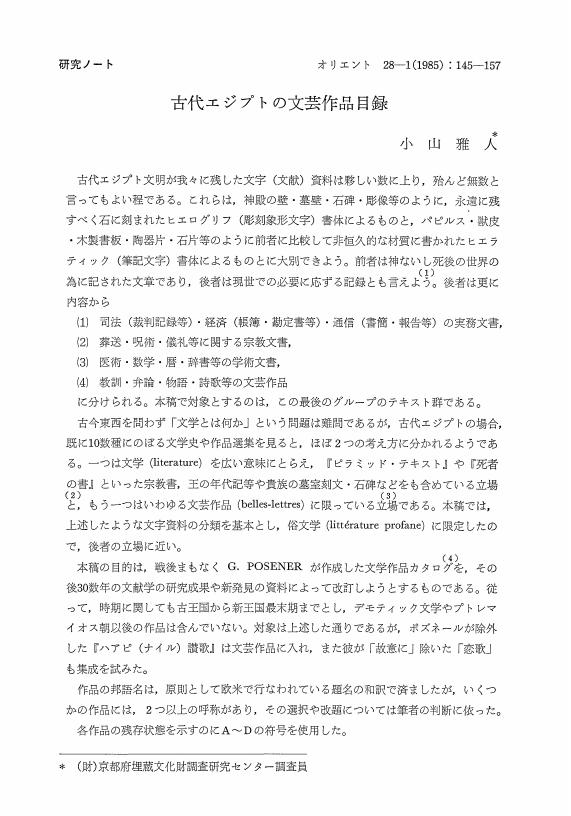4 0 0 0 IR 宮崎駿『魔女の宅急便』の物語構造における「飛行」の意味について
- 著者
- 小池 隆太
- 出版者
- 山形県立米沢女子短期大学
- 雑誌
- 山形県立米沢女子短期大学紀要 (ISSN:02880725)
- 巻号頁・発行日
- no.53, pp.103-112, 2017-12-27
4 0 0 0 どうなる!? 米沿海域戦闘艦建造計画
4 0 0 0 OA 第六十三回智山教学大会記念講演 東国鎌倉の密教
- 著者
- 平 雅行
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, pp.347-376, 2020 (Released:2021-04-06)
- 参考文献数
- 36
4 0 0 0 OA 皇太子殿下御渡欧記念写真帖
- 出版者
- 大日本国民教育会
- 巻号頁・発行日
- vol.[正編], 1921
4 0 0 0 OA 古代エジプトの文芸作品目録
- 著者
- 小山 雅人
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.145-157, 1985-09-30 (Released:2010-03-12)
4 0 0 0 OA <長坂俊成教授インタビュー>「地域でごちゃまぜのデジタルアーカイブをどうつくる?」
- 著者
- 長坂 俊成
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.2, pp.112-118, 2021-04-01 (Released:2021-06-01)
- 参考文献数
- 5
4 0 0 0 現役プロ棋士に勝ち越したコンピュータ将棋 ~第2回電王戦,第23回世界コンピュータ将棋選手権速報~:5. 第23回世界コンピュータ将棋選手権自戦記 -Bonanza選手権バージョンの紹介-
- 著者
- 保木 邦仁
- 出版者
- 情報処理学会 ; 1960-
- 雑誌
- 情報処理 (ISSN:04478053)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.9, pp.928-932, 2013-08-15
The University of Electro-Communications アブストラクト:2005年に拙作のプログラムBonanzaをインターネットに公開,以降2006年からコンピュータ将棋協会が毎年5月に開催する選手権に出場し続けている.今年の5月で8回目の出場となり,戦績は優勝2回,2位1回,3位1回,4位1回,5位2回,9位(予選落ち)1回である.Bonanzaの戦績には実力だけでなく運の要素も強く反映されている.二度優勝してはいるが,それぞれ一局ずつ,将棋の内容では負けていながら相手プログラムの不合理な動作により勝っている.本稿では,選手権においてトップ争いを繰り広げてきたBonanzaに施された工夫の一部をハードウェア構成と評価関数の観点から簡単に紹介する.
- 著者
- 和田 良子
- 出版者
- 敬愛大学・千葉敬愛短期大学
- 雑誌
- 敬愛大学研究論集 (ISSN:09149384)
- 巻号頁・発行日
- no.59, pp.109-125, 2001
endowment effect(授かり効果)とは,一度何かを所有すると,それを手に入れる以前に支払ってもいいと思っていた以上の犠牲を払ってでも,その所有している物を手放したがらない現象をさすものである。Kagel=Roth[1995]では,endowment effectを「買値と売値のギャップ」と定義している。それは損失回避(もしくは現状維持)の心理によって説明される。これは,Knetsch and Sinden[1989],Knetsch[1990]らによる実験結果などをstylized factとしてそれを説明しようとするものである。しかし,それに対してHanemann[1991]は所得効果があるために,何かを手に入れるために支払おうとする金額と,持っているものを手放すために補償してもらいたい金額は常に等しくなるわけではないということを理論的に示している。本稿では授かり効果についての議論をサーベイして所得効果をめぐる論点を明らかにし,実験によって所得効果を取り除いた純粋なendowment effectを測定しようと考えた。実験の結果,実際に買値と売値の間にギャップが生じることをみた。しかしそれがほとんど一種の交渉効果によるものであり,一度手に入れたものを手放すことに痛みを伴うため(つまり損失回避のため)ではないことを同じ実験により確認することとなった。
- 著者
- Mariko NAGASHIMA Daisuke NISHIO–HAMANE Shuichi ITO Takahiro TANAKA
- 出版者
- Japan Association of Mineralogical Sciences
- 雑誌
- Journal of Mineralogical and Petrological Sciences (ISSN:13456296)
- 巻号頁・発行日
- vol.116, no.3, pp.129-139, 2021 (Released:2021-07-17)
- 参考文献数
- 23
Ferriprehnite (IMA2020–057), ideal formula Ca2Fe3+(AlSi3)O10(OH)2, is a new mineral that was found as secondary mineral in druses developed in the hydrothermal altered dolerite from Kouragahana, Shimane Peninsula, Japan. Ferriprehnite is an Fe analogue of prehnite. The crystals consisting of ferriprehnite and prehnite occur as a radial aggregate. The tabular crystals are up to 300 µm long, 100 µm wide, and 50 µm thick. Ferriprehnite is colorless to pale green with white streak and vitreous luster. It has a Mohs hardness of 6½. Its cleavage is good on {100}. The calculated density is 2.97 g/cm3. The empirical formula of ferriprehnite on the basis of 10O + 2OH using the result obtained by electron microprobe analysis is Ca1.99(Fe3+0.66Al0.34)Σ1.00(Al1.02Si2.98)Σ4.00O10(OH)2. Structure refinement converged to R1 = 4.64%. Its space group is orthorhombic Pma2 with unit–cell parameters a = 18.6149(10) Å, b = 5.4882(3) Å, c = 4.6735(3) Å, and V = 477.46(1) Å3. The determined site occupancy at the octahedral M site is Fe0.637(9)Al0.363 indicating that the M site is predominantly occupied by Fe. <M–O> increases with increasing Fe content leading to isotropic expansion of MO6 octahedra. The a– and c– dimensions of ferriprehnite are longer than those of prehnite due to Fe substitution for Al at the M site.
4 0 0 0 OA 「社会」以前と「社会」以後──明治期日本における「社会」概念と社会的想像の編成
- 著者
- 木村 直恵
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 東アジアにおける知的交流──キイ・コンセプトの再検討── = Intellectual Exchange in Modern East Asia: Rethinking Key Concepts (ISSN:09152822)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.267-283, 2013-11-29
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経メディカル = Nikkei medical (ISSN:03851699)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.22-25, 2020-03
- 著者
- 山田 妙韶
- 出版者
- 日本福祉大学社会福祉学部
- 雑誌
- 日本福祉大学社会福祉論集 = Journal social Welfare, Nihon Fukushi University (ISSN:1345174X)
- 巻号頁・発行日
- vol.137, pp.117-131, 2017-09-30
精神保健医療福祉施策が平成16 年に「精神保健医療福祉の改革ビジョン」が発表されて以降,「精神障害者退院促進支援事業」,「精神障害者地域移行・地域定着支援事業」,保護者制度廃止に伴う医療保護入院の見直しによる退院後生活環境相談員の設置など,精神障害者福祉の地域福祉化が進んでいる傾向にある. しかし,精神障害者の中には制度を利用できない人や利用を拒否する者もいる.例えば,精神症状が安定し退院許可が出ているにもかかわらず,再発を恐れて退院しようという決心がつかないまま入院を希望する者がいる.このような患者には,再発への恐怖に対する心理的ケアや再発の対処法・予防法を考えて支援する必要もあろう.つまり,精神保健福祉士(PSW)は,利用者の心理的問題を避けて通れない状況が増えることが予測されよう. 心理的問題の解決はカウンセリングがその専門である.カウンセリングは,言語的および非言語的コミュニケーションを通して,相手の行動の変容を援助する人間関係であり,相手が自らの力で解決する,あるいは解決できるように成長するのを援助することにある1)2)という定義が広く知られているだろう.しかし,近年,「福祉カウンセリング」,「カウンセリングとソーシャルワーク」という書籍やテーマによる論文がみられるように,社会福祉領域の相談援助とカウンセリングの共通性が意識されていると感じる. カウンセリング技法については,精神保健福祉相談援助のための方法として位置づけられている.一般的にいえばカウンセリング技法は,精神保健福祉相談援助ではすでに活用されているが,カウンセリング技法を意識的に活用しているという認識はPSW にはないようである.そのカウンセリングのなかでも近年,ナラティブ・アプローチが福祉や医療保健など幅広い領域で注目を浴びている.福祉や医療保健領域に限らず対人支援の専門職には活用価値のある技法との指摘もある. そこで,精神保健福祉相談援助におけるナラティブ・アプローチの有用性の実証を目指して,事例検討を通して考察することとする.
4 0 0 0 OA 官報
- 著者
- 大蔵省印刷局 [編]
- 出版者
- 日本マイクロ写真
- 巻号頁・発行日
- vol.1902年07月28日, 1902-07-28
- 出版者
- 福祉医療機構 ; 1996-
- 雑誌
- WAM : welfare and medical service
- 巻号頁・発行日
- no.671, pp.10-13, 2020-11
- 著者
- 崎浜 智子
- 出版者
- 中外医学社
- 雑誌
- J-IDEO = ジェイ・イデオ : journal of infectious diseases educational omnibus (ISSN:24327077)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.6, pp.880-882, 2020-11
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ヘルスケア = Nikkei healthcare : 医療・介護の経営情報 (ISSN:18815707)
- 巻号頁・発行日
- no.374, pp.32-34, 2020-12
1人目の感染者発覚から約5カ月後の今年7月末、医療法人堀尾会・熊本託麻台リハビリテーション病院(熊本市中央区)で2人目となる看護師のCOVID-19の陽性が判明した。前回の経験から院内感染の拡大防止には迅速に対応でき、他の感染者は出なかったが、「1病棟20人…
4 0 0 0 OA 皆既日食がつなぐ夢
- 著者
- サイエンスウィンドウ編集部
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- サイエンスウィンドウ (ISSN:18817807)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.6, pp.1-40, 2009-12-20 (Released:2019-04-11)
サイエンスウィンドウ2009増刊号の冊子体一式(PDF版)およびHTML版は下記のURLで閲覧できます。 https://sciencewindow.jst.go.jp/backnumbers/detail/17 目次 【特集】 皆既日食がつなぐ夢 何を見たか p.03 梅雨明けが遅れた夏の日 p.04 晴れた? 曇った? 部分日食 p.06 僕らが感じたくもり一時「闇」 p.08 船上の皆既日食 p.10 皆既日食のときしか見られない光景 p.12 皆既日食はインドから始まった 子どもとどう見たか p.13 離れていても皆既日食の感動を p.14 君たちが主役だよ! p.16 高校生が見た雲の上の日食 p.18 全国各地でさまざまな楽しみ方 p.20 太陽光のエネルギーを発電量で探る p.21 私の好きな先生「雨男」 太陽の謎を追う p.22 コロナを見つめた60 年 p.24 天体観測は厳しい自然との闘い p.25 文芸作品にみる日食 p.28 なぜ起こる? 日食 p.30 太陽活動の影響を受ける地球 p.31 「ひので」の観測で広がる謎 未来への夢 p.32 次の日食はいつ? どこで? p.34 26年後の夢 p.36 教育普及とあいまった科学を地域、世界に p.38 これからも日食を楽しむために p.40 26年後の日食も一緒に見よう
4 0 0 0 IR 日・米・仏の国語教育を読み解く--「読み書き」の歴史社会学的考察
- 著者
- 渡辺 雅子 渡邉 雅子 渡辺 雅子
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.573-619, 2007-05
本稿では、日米仏のことばの教育の特徴を比較しつつ、その歴史的淵源を探り、三カ国の「読み書き」教育の背後にある社会的な要因を明らかにしたい。まず日米仏三カ国の国語教育の特徴を概観した後、作文教育に注目し、各国の書き方の基本様式とその教授法を、近年学校教育で養うべき能力とされている「個性」や「創造力」との関係から比較分析したい。その上で、現行の制度と教授法、作文の様式はどのように形作られてきたのか、その革新と継続の歴史的経緯を明らかにする。結語では、独自の発展を遂げてきた各国の国語教育比較から何を学べるのか、日本の国語教育はいかなる選択をすべきかを、「国語」とそれを超えたグローバルな言語能力に言及しながら考えたい。 個性と創造力の視点から作文教育を見ると、日本とアメリカの作文教育における自由と規模の奇妙なパラドックスが浮かび上がり、また時節の議論からは超然としたフランスの教育の姿が現れる。また評価法の三カ国比較からは、言葉のどの側面を重要視し、何をもって言語能力が高いと認めるのかの違いが明確になる。規範となる文章様式とその評価法には、技術としての言語習得を超えた、言葉の社会的機能が最も顕著に現れている。 社会状況に合わせて常に革新を続けるアメリカの表現様式と、大きな転換点から新たな様式を作り出した日本、伝統様式保持に不断の努力を続けるフランス。三カ国の比較から見えてくるのは、表現様式を通した飽く無き「規範作り」のダイナミズムである。
4 0 0 0 下肢装具による医療関連機器圧迫創傷に関連する要因
- 著者
- 小川 秀幸 西尾 尚倫 牧野 諒平 越前谷 友樹 大塚 三和子 中野 克己
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- pp.20048, (Released:2021-06-26)
- 参考文献数
- 23
目的:回復期脳卒中患者における下肢装具による医療関連機器圧迫創傷(MDRPU)に関連する要因を検討すること.方法:研究デザインは後ろ向きコホート研究とした.対象は回復期リハビリテーション病棟入棟中に下肢装具を作製した脳卒中患者95名とした.調査項目は,基本属性,入棟時のBrunnstrom Recovery Stage,感覚障害の有無,半側空間無視の有無,入棟時と退院時のFunctional Independence Measureとした.メインアウトカムであるMDRPUの発生は,National Pressure Ulcer Advisory Panel分類ステージⅠ以上とした.統計解析では,MDRPUの発生あり群となし群に分けて群間比較を実施し,多重ロジスティック回帰分析を行った.変数の選択には,尤度比検定による変数増加法を用いた.結果:MDRPUの発生要因として抽出されたのは,年齢(オッズ比=1.05,95%信頼区間:1.01~1.10,p<0.05)と,入棟時感覚障害の有無(オッズ比=5.17,95%信頼区間:1.39~19.28,p<0.05)であった.結論:回復期入棟時に若年層で感覚障害を有する場合は,下肢装具によるMDRPU発生の危険性が高く注意が必要であることが示唆された.
- 出版者
- 新潮社
- 雑誌
- 週刊新潮 (ISSN:04887484)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.46, pp.30-32, 2006-12-07