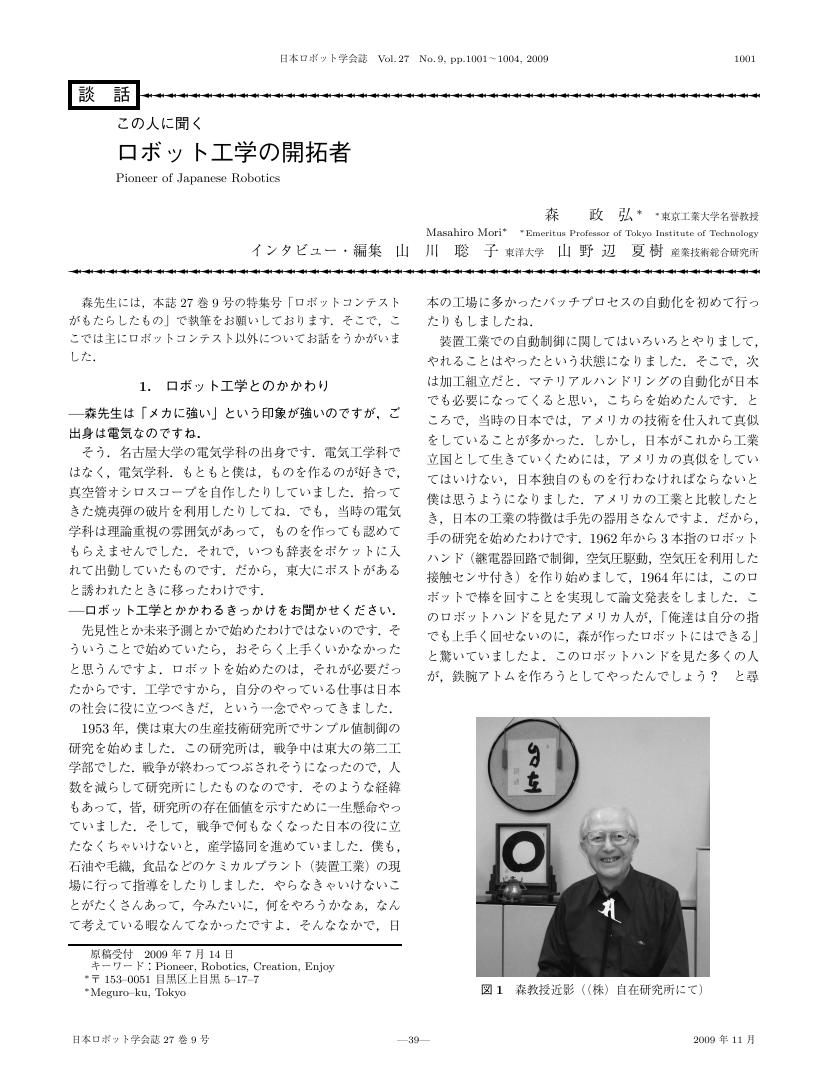4 0 0 0 IR 水辺の異形 : スー・アナス、ジャルマウズ、アルバストゥ、シュリクンについて
- 著者
- 坂井 弘紀
- 出版者
- 和光大学表現学部
- 雑誌
- 表現学部紀要 = The bulletin of the Faculty of Representational Studies (ISSN:13463470)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.35-54, 2021-03-11
中央ユーラシアには、川や湖などに棲み、人間に悪事を働く超自然的存在がいる。「水の世界」は人間の世界とは異なる「異界」、もしくは「境界」を意味し、スー・アナスやジャルマウズ、アルバルストゥといった水辺の存在には、女性性や母性の特徴が強くみられる。母性に関連して、ジャルマウズやアルバストゥは、出産など人間の生にまつわる要素が強く、彼女らが本来は生命にまつわる母神的存在であったという仮説が浮かぶ。人間を苦しめ、命を奪う存在でありながら、反対に人間に善や利をもたらす存在でもあることは、彼女たちが生と死という対立的な両義性をもつことを示す。ジャルマウズとアルバストゥは形状や役割からみると、ロシアのバーバ・ヤガーと同類であり、また、シュルガンとロシアのシュリクンも水に関わるという点やその名称の類似性から深いつながりがあることが推定される。ユーラシア中央部には、言語や「民族」の枠組みを超えた文化的共生があったのである。
4 0 0 0 OA メーカーブランドカラーが購入意向に与える影響
- 著者
- 加藤 拓巳
- 出版者
- 日本感性工学会
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18845258)
- 巻号頁・発行日
- pp.TJSKE-D-20-00016, (Released:2020-10-21)
- 参考文献数
- 36
Color has long been considered important by both the manufacturing industry and academia because it affects people’s perceptions, emotions, and behaviors. However, the evaluation of purchasing behavior until now has mainly been only in an experimental environment, and there have been concerns that differed from the actual consumer behavior. Therefore, the causal effect of the strong impression of a manufacturer’s brand color on the purchase behavior in the Japanese automobile industry was verified. Covariate was homogenized by propensity score matching based on the online survey, and the causal effect on purchase intention was extracted. As a result, the impression of the brand color had a positive effect on the purchase intention. This effect was estimated to be 5.739 in odds ratio. Commercial brands, logos, emblems, car body colors, dealers, showrooms, and even professional baseball teams were found to be factors that foster brand color.
4 0 0 0 OA ロボット工学の開拓者
- 著者
- 森 政弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.9, pp.1001-1004, 2009 (Released:2011-11-15)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 中田 朱美
- 出版者
- 東京藝術大学音楽学部
- 雑誌
- 東京藝術大学音楽学部紀要 = Bulletin, Faculty of Music, Tokyo Geijutsu Daigaku (Tokyo University of the Arts) (ISSN:09148787)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.69-86, 2016
4 0 0 0 OA 教室内音環境が学習効率に及ぼす影響
- 著者
- 辻村 壮平 上野 佳奈子
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.653, pp.561-568, 2010-07-30 (Released:2010-09-03)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 7 6
In order to investigate the effect of indoor sound environment in a classroom on learning efficiency, laboratory experiments were conducted. In the experiment, the percentage of correct answers of each task, subjective judgment on degree of disturbance and the power level of frontal midline theta rhythm (Fmθ) were measured under the three types of sound environmental conditions (no-noise, air-conditioning noise, talking noise) in anechoic room. From the result, it was confirmed that the sound environment condition significantly change the percentage of correct answers, the subjective judgment on degree of disturbance and the power level of Fmθ for listening task and proofreading (under the acoustical condition of signal to noise ratio (SNR) 0 dB). Furthermore, the possibility of improvement on learning efficiency by amplifying speech level was investigated. From the result, it was suggested that the amplification of speech signal level decrease the influence of sound environment in classrooms on learning efficiency.
4 0 0 0 OA 精神障害の社会モデルは可能か?
- 著者
- 寺田 明代 Terada Akiyo
- 雑誌
- 関西福祉科学大学紀要 = Journal of Kansai University of Welfare Sciences
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.137-143, 2009-03-05
4 0 0 0 OA ナイジェリアにおけるフルベ族の移牧と牧畜経済
- 著者
- 池谷 和信
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.7, pp.365-382, 1993-07-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 53
- 被引用文献数
- 4 4
本研究は,ナイジェリアのフルベ族の牧畜経済を,その生態的側面と彼らをとりまく政治経済的側面との両面から分析したものである.なかでもフルベ族の移牧形態,家畜群の管理と販売からなる牧畜経済を記述・分析することが中心となった.調査の結果,移牧フルベは雨季から乾季にかけて約8m下がるベヌエ川の水位の変化に対応して,家族総出で居住地を氾濫原に移動する生活様式をとり,彼らの牧畜活動は,伝統的な薬を利用した牛の繁殖や牛の夜間放牧などに特徴がみられることが明らかになった.また,フルベは牛の価格の高い家畜市を選択するだけではなく,病気の牛,不妊の雌牛など,群れの中で不必要な牛を適宜売却することから,市場経済の原理に強く依拠している.彼らは,結婚式や命名式などで使われる数頭の牛を除くと,3頭分の牛を売却して得た現金によって穀物などを購入して,一年間の生計を維持することができる.ナイジェリアのオイルブームによる経済成長をへて,フルベは伝統的牧畜形態を維持したままの自営牧畜を展開させてきた.
4 0 0 0 OA 植物生体電位を用いた人体活動モニタリング
- 著者
- 広林 茂樹 田村 祐輔 山淵 龍夫 大薮 多可志
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌E(センサ・マイクロマシン部門誌) (ISSN:13418939)
- 巻号頁・発行日
- vol.127, no.4, pp.258-259, 2007-04-01 (Released:2007-07-01)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 5 10
In this paper, we monitored the electromagnetic waves generated by human activity. We investigated a monitoring system that used the bioelectric potential of a plant. Four subjects walked on the spot at a distance of 60 cm from a rubber tree and we measured the variation in the bioelectric potential of the tree produced by the stepping motion. The results confirmed that the electromagnetic waves generated by a person walking on the spot produced a measurable response in the bioelectric potential of a plant. It was also found that this variation in the bioelectric potential varied in synchrony with the subject's walking pace.
4 0 0 0 IR 「イタイガヨ」と「イタイヨサ」 : 鹿児島方言のいくつかの終助詞について
- 著者
- 児玉 望
- 出版者
- 熊本大学文学部言語学研究室
- 雑誌
- ありあけ : 熊本大学言語学論集 (ISSN:21861439)
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.87-110, 2021-03
アクセント以外が共通語化した鹿児島方言の複合終助詞ガヨとヨサについて、前者については終助詞ガのもつさまざまな用法のうち、直接経験を、それを自ら認識できないと話し手が判断した聞き手に伝達する用法に限定するもの、後者については、終助詞ヨの情報伝達用法のうち、特定の聞き手の関心事と話し手が判断した情報について話し手の判断を伝える用法として説明する。この論証のために、前者では終助詞ガ、後者では終助詞サの用法を概観し、さらに、これら二つの終助詞の用法を通時的に解釈することを試みる。終助詞ガが、終助詞ワと並んで、終助詞ヨ/ゾと対立する用法をもつ祖体系から継承されたと比較方言学的に推論できるのに対し、終助詞サは、方言談話録音資料の分析に基づいて,フィラーが接語化を経て終助詞として解釈されるようになった例として、20 世紀半ば以降の改新と説明できると主張する。
4 0 0 0 IR 古典修辞学体系における「生きた」隠喩と「死んだ」濫喩
- 著者
- 木村 裕一
- 出版者
- 学習院大学
- 雑誌
- 学習院大学人文科学論集 (ISSN:09190791)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.19-35, 2010
本論で試みているのは、古典修辞学体系における濫喩の奇妙な位置づけを、アリストテレス、キケロ、クインティリアンにおける隠喩の定義の検証を通じて明らかにすることである。その奇妙さとは、濫喩は一方で非常に周縁的で例外的な修辞形象として隠喩から区別される一方で、反対に修辞体系において最も中心的かつ理想的な形象としての隠喩の定義の際に、避けがたくその特質がついてまわってきてしまうということである。濫喩の特質とはすなわち、言及対象を表現するための言葉が「本来的」には欠如している場合に、代わりの言葉でそれを補完的に表現しようとすることである。そして濫喩のこのような特質は「生きた」隠喩とは反対の価値、すなわち「死んだ」隠喩としてみなされてきた。 このような「生/死」という二項対立的イメージの起源は、アリストテレスによる隠喩の定義にまで遡る。アリストテレスによれば、隠喩とは「生き生きとした」イメージを「眼前に彷彿とさせる(Vor-Augen-Führen)」ことを可能にする修辞形象であり、それによっていかなるものも、たとえそれが不在のものやそもそもそれを表現するべき言葉が欠如してしまっていたとしても、表現することができるものであると定義づけている。すなわち、アリストテレスの修辞体系において、後に濫喩の特質であるとされる「語の欠如の補完」はいまだ隠喩の特質のひとつであり、細分化されてはいない。それに対して「濫喩」を「隠喩」から区別し、細分化し始めるのは、キケロ、ならびにそれに続くクインティリアンである。両者に共通しているのは、「生き生きとした」イメージを「眼前に彷彿とさせる」ことを可能にする隠喩というアリストテレスの定義を引き継ぎ、それを体系の中心的な位置に据えながら、他の修辞形象を差異化していることである。とりわけ、表現すべき言葉の欠如を前提としなければならない「濫喩」的特質は、周縁的で例外的な修辞形象とみなされていくことになる。 つまり古典修辞学の体系の歴史とは、「生き生きとした」イメージによって対象を「眼前に彷彿とさせる」ことができる「良き」隠喩が、体系における理想的かつ中心的な位置を占められるよう、それぞれの修辞形象の定義を細分化・区別していく歴史そのものである。濫喩とは「生き生きとした」イメージの表現を理想とする修辞体系において排除されたものであり、言及対象を表現するための言葉の欠如を覆い隠すことのできない、隠喩の「失敗例」として位置づけられているものである。つまり、濫喩とは「生き生きとした」隠喩の否定的な側面であり、その意味で「死んだ」非─ 隠喩として「良き」隠喩を修辞体系の中心へと位置づけるための「例外的な」修辞形象として必要不可欠なものなのである。
- 著者
- 落合 知美 綿貫 宏史朗 鵜殿 俊史 森村 成樹 平田 聡 友永 雅己 伊谷 原一 松沢 哲郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.19-29, 2015-06-20 (Released:2015-08-07)
- 参考文献数
- 70
- 被引用文献数
- 1 2
The Great Ape Information Network has collated and archived information on captive chimpanzees within Japan since 2002. As of July 1st, 2014, a total of 323 chimpanzees were housed within 52 facilities across Japan, all registered in the Japanese Association of Zoos and Aquariums (JAZA) studbook. JAZA has recorded information on captive chimpanzees within Japan since the 1980s. However, for individuals unregistered and/or deceased prior to this period, JAZA holds scant information. There are very few surviving reports on living conditions and husbandry of such individuals, particularly for the years preceding the Second World War (WWII) (up to 1945). Here we present the first detailed history of captive chimpanzees in Japan before WWII, following a systematic investigation of disparate records. The first record of any live chimpanzee within Japan was a chimpanzee accompanying an Italian travelling circus in 1921. The history of resident captive chimpanzees in Japan began in 1927 when a chimpanzee, imported into Japan by a visitor, was exhibited in Osaka zoo. In the 1930s, many chimpanzee infants were imported to Japanese zoos until in 1941 imports were halted because of WWII. By the end of WWII, there was only one single chimpanzee still alive within Japan, “Bamboo”, housed in Nagoya. In 1951, importation of wild chimpanzees into Japan resumed. In total, we identified 28 individuals housed within Japan before 1945, none listed previously in the JAZA studbook. Of these 28 individuals: 6 entered Japan as pets and/or circus animals, 21 were imported to zoos, and one was stillborn in zoo. Of the 21 zoo-housed individuals, 7 died within one year and 9 of the remaining 14 were dead within 5 years of arriving in Japan. Four individuals are recorded to have lived 7-8 years. Only one male individual, the aforementioned “Bamboo”, lived notably longer, to about 14 years.
4 0 0 0 木庭二郎の生涯と業績 (<回想の木庭二郎>)
- 著者
- 南部 陽一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.8, pp.564-566, 1996
- 参考文献数
- 13
<p></p>
4 0 0 0 OA ゾーエーとしての生と精神医療の一側面
- 著者
- 大宮司 信
- 出版者
- 北翔大学
- 雑誌
- 北翔大学生涯学習システム学部研究紀要 (ISSN:18827675)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.17-25, 2013
4 0 0 0 OA 初期バロック音楽の実践的歌唱法の開発
4 0 0 0 OA 我が国の理科教育におけるメタ認知の研究動向
- 著者
- 久坂 哲也
- 出版者
- 一般社団法人 日本理科教育学会
- 雑誌
- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.397-408, 2016-03-19 (Released:2016-04-23)
- 参考文献数
- 59
- 被引用文献数
- 3 3
メタ認知は学力や動機づけ, 学習方略などと密接な関係にあるため, 我が国の理科教育学研究においてもメタ認知を対象とした研究が数多く見受けられるようになった。しかし, メタ認知の重要性は多くの研究者が認めるところであるが, メタ認知は高次な認知機能であると同時に抽象的な概念であることから研究の遂行が困難な側面も併せもっている。 そこで, 我が国の理科教育学研究におけるメタ認知研究の動向と課題を明らかにするため, 代表的な学術誌から文献を収集して分析を行った。その結果, 観察や実験活動を中心とした理科学習場面における児童生徒のメタ認知的モニタリングやメタ認知的コントロールといったメタ認知的活動を発問や教材教具の工夫によって直接的に促す授業設計や学習方略に関する研究が盛んに行なわれており, 実践的な知見が蓄積されていることが示された。しかし一方, 科学的思考や科学的探究といった科学的な問題解決能力を育成する際に必要なメタ認知的知識の種類やそれらを獲得させるための教授方略に関する研究といったメタ認知の知識的側面に着目した研究が少ないことが明らかになった。また, メタ認知を変数として扱った場合の測定方法に関しても課題が残されており, 今後の研究が待たれるところである。
- 著者
- RS Kahn D Brandt RC Whitaker 一條 智康
- 出版者
- 一般社団法人日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.3, 2005-03-01
母親のうつ病が子の健康にさまざまな影響を及ぼすことは知られている.母親がうつ病であると,その子には発達の遅れ,行動の問題,うつ病,喘息,外傷などが生じる可能性が高いと指摘されている.今までの研究は産後うつ病に焦点が当てられていたが,母親のうっ病が産褥期のあとにも持続すると子の健康に対する影響が大きくなることは明らかである.親の精神的健康状態がその子たちの精神的健康にどのような影響を及ぼすかについて行われた大部分の研究は,母親に焦点を当てており,父親の調査は除外されていた.著者らは,子に及ぼす両親の精神的健康状態の複合的影響をリサーチするために(具体的には,父親の精神的健康状態が子の行動および情緒の健康状態を修飾するか否かを検証するために),822人の子(3〜12歳,平均8.2歳)を含む605家族の調査データを検討した.子は全員,2人の養育者(母親と父親,または母親とそのボーイフレンド)と生活していた.親は妥当性が確認された質問表(K10)で親自身の精神的健康状態に関する症状(例えば,うつ気分,不安)を評価した.子の行動および情緒の健康状態についてはBehavior Problem Indexを用い,母親が主に評価した.その結果,精神的に不健康な2人の養育者をもつと,子の健康状態は精神的に健康な2人の養育者をもつよりも有意に不良であった.母親のみが精神的に不健康な家族では,父親の精神的健康状態のよい場合には子の情緒および行動の問題が有意に減少した.著者らは,母親の精神的健康状態がどのくらい子の健康に影響するかは父親の精神的健康状態により左右されること,すなわち,母親の精神的不健康が子の健康状態に与えるマイナスの影響は精神的健康状態のよい父親によって軽減されることを発見した.また,本研究では親の精神的健康状態に関する質問表によりうつ気分だけではなく不安も含めてチェックしたことは,先行研究にはほとんど見られなかった点であることも,著者らは記述している.結果として,臨床医,特に小児科医が患者(子)の母親のうつ気分や不安を指摘し,適切に対処する役割が特に注目される.また,子を診るときには両親との関係性の中で(両親の精神的健康状態を視野に入れて)子を評価することの重要性を改めて強調している.