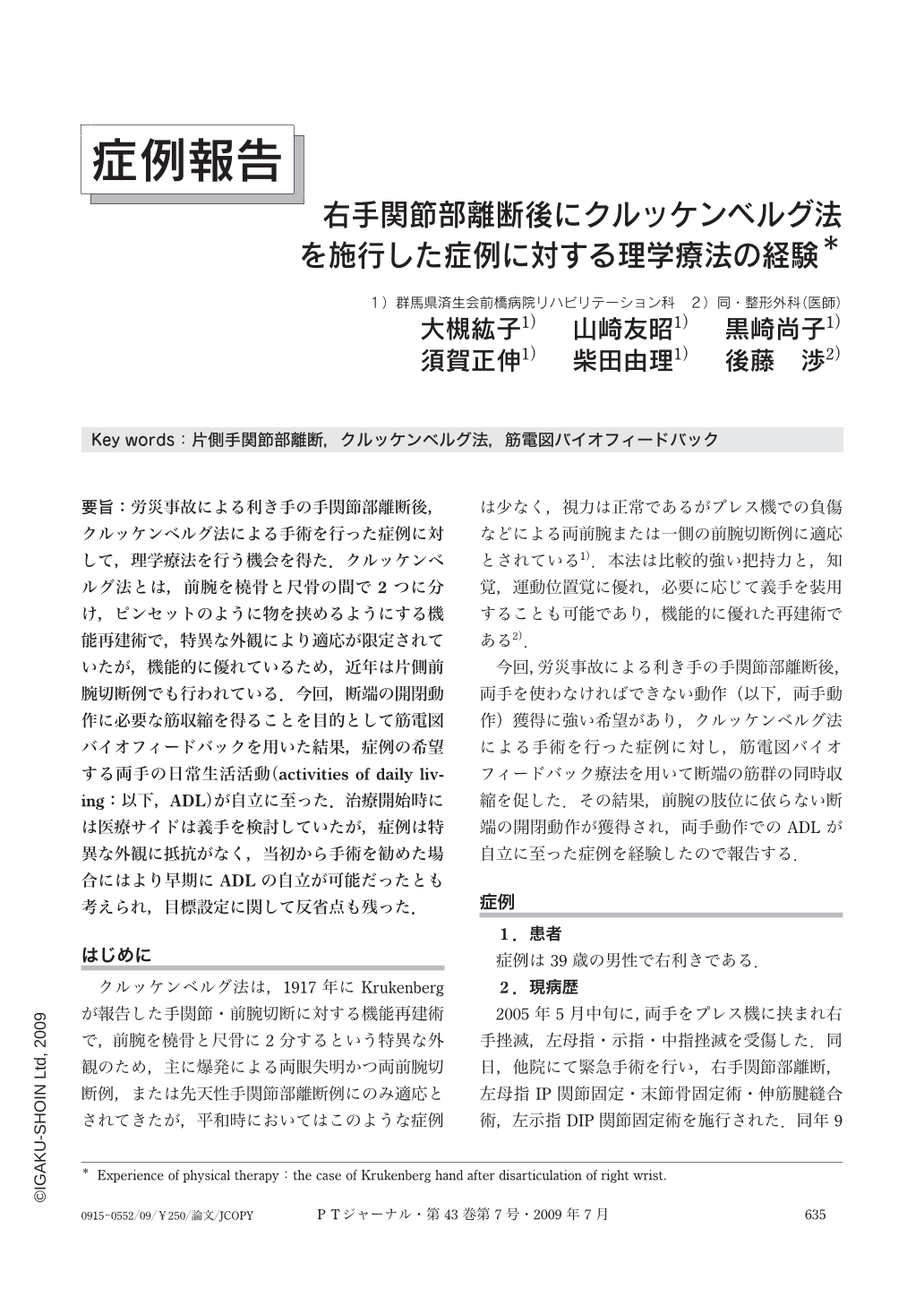3 0 0 0 OA 第41回 血行促進・皮膚保湿剤ビーソフテン外用スプレー0.3%
- 著者
- 井黒 ひとみ 富樫 美津雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.4, pp.349-351, 2015 (Released:2018-08-26)
- 参考文献数
- 3
一般名:へパリン類似物質薬価収載日:2009年11月13日
3 0 0 0 OA 公正としての正義とアファーマティブ・アクション
- 著者
- 花形 恵梨子
- 出版者
- 日本倫理学会
- 雑誌
- 倫理学年報 (ISSN:24344699)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, pp.177-190, 2021 (Released:2021-06-14)
Although Rawls never addressed the issue of affirmative action in his writings, remedying the discrimination-related disadvantages that influence people’s life chances will also likely fall within the purview of justice. This paper discusses the implications of his theory for affirmative action, its justification, and the extent to which it is justified in the framework of justice as fairness. Rawls mainly focuses on ideal theory. He works out the principles of justice under the assumption that people comply with the demands of justice and that favorable circumstances hold, while affirmative action is a problem for a nonideal society. In the framework of justice as fairness, affirmative action is addressed under the principle of equality of opportunity(EO). Formal EO and fair EO together require that people develop their talents regardless of the social circumstances to which they are born. They compete for offices and positions under fair conditions, and motivated, qualified individuals acquire the positions. However, under nonideal circumstances, there are entrenched injustices that hinder the realization of such an ideal. Under nonideal circumstances, principles of ideal theory serve as a guide to a fully just society. It is often claimed that affirmative action is incompatible with fair EO, as it requires differential treatment based on group membership, while fair EO focuses on the qualifications of individuals. By discussing criticisms of affirmative action, I will argue that affirmative action in the form of preferential treatment is justified as a transitional measure to remedy systematic group disadvantages and realize the fair EO ideal. As Rawls’s democratic equality aims not for a meritocratic society but for one in which people can relate as equals, the criticism that affirmative action policies stigmatize the targets of affirmative action can also be answered.
3 0 0 0 OA 中枢セロトニントランスポーターと抗うつ薬
- 出版者
- 日本膜学会
- 雑誌
- 膜 (ISSN:03851036)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.3, pp.94-101, 2008 (Released:2015-06-18)
Serotonin transporter (SERT), a member of Na+/Cl– - dependent transporter family, is predicted to be a protein with a twelve membrane-spanning structure, which terminates the serotonergic neural transmission by re-uptaking serotonin into pre-synapse. It has been well-known that SERT is a target of antidepressants and abusive drugs. Although the pathogenesis of depression and mechanism underlying antidepressants action remains unclear, recent accumulated evidences have revealed that antidepressants promote the regeneration of neurons, which was damaged by repeated stress and recurrences of depression. In addition, analysis of crystal structure of bacterial leucine transporter, a homologue of mammalian Na+/Cl– - dependent neurotransmitter transporter, provides us a new information concerning the interactions of tricyclic antidepressants with serotonin transporter.
- 著者
- 大槻 紘子 山崎 友昭 黒崎 尚子 須賀 正伸 柴田 由理 後藤 渉
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 理学療法ジャーナル (ISSN:09150552)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.7, pp.635-640, 2009-07-15
要旨:労災事故による利き手の手関節部離断後,クルッケンベルグ法による手術を行った症例に対して,理学療法を行う機会を得た.クルッケンベルグ法とは,前腕を橈骨と尺骨の間で2つに分け,ピンセットのように物を挟めるようにする機能再建術で,特異な外観により適応が限定されていたが,機能的に優れているため,近年は片側前腕切断例でも行われている.今回,断端の開閉動作に必要な筋収縮を得ることを目的として筋電図バイオフィードバックを用いた結果,症例の希望する両手の日常生活活動(activities of daily living:以下,ADL)が自立に至った.治療開始時には医療サイドは義手を検討していたが,症例は特異な外観に抵抗がなく,当初から手術を勧めた場合にはより早期にADLの自立が可能だったとも考えられ,目標設定に関して反省点も残った.
3 0 0 0 OA 虚構の社会-メイクビリーヴ説の社会哲学への応用-
- 著者
- 成瀬 翔
- 出版者
- 日本福祉大学全学教育センター
- 雑誌
- 日本福祉大学全学教育センター紀要 = The Journal of Inter-Departmental Education Center (ISSN:2187607X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.59-68, 2017-03-31
When we examine the theory of fiction, we usually consider the impact on arts and literatures. However, the most famous theorist Kendall Walton has attracted the attention other than arts and literatures. This paper considers an application of the Walton's theory in social philosophy. The contents of this paper are as follows. In Section 2, I will examine theory of make-believe. In Section 3, I will purpose an application to sports of theory of make-believe. Finally, in Section 4, I will consider John Searle’s idea: brute and institutional (or social) fact. And, I suggest that theory of make-believe is beneficial in social philosophy.
3 0 0 0 OA 柿胃石症の2例とその生化学的知見
- 著者
- 山本 誠已 和田 信弘 半羽 健二 戸田 慶五郎 中谷 敏英 嶋 義樹 池田 好秀 宮本 長平
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器外科学会
- 雑誌
- 日本消化器外科学会雑誌 (ISSN:03869768)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.10, pp.1196-1200, 1980 (Released:2011-03-02)
- 参考文献数
- 12
3 0 0 0 阪急ブレーブス五十年史
- 著者
- 阪急ブレーブス 阪急電鉄株式会社編
- 出版者
- 阪急ブレーブス
- 巻号頁・発行日
- 1987
- 著者
- 田崎 冬記 宮木 雅美 戸田 秀之 三宅 悠介
- 出版者
- 日本緑化工学会
- 雑誌
- 日本緑化工学会誌 (ISSN:09167439)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.4, pp.503-511, 2013 (Released:2015-02-13)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
知床岬台地草原では,エゾシカ個体数の増加によってササ類の減少,樹皮剥ぎによる特定樹種の激減,実生・稚樹の採食による更新阻害,海岸性の植生群落とそれに含まれる希少植物の減少および土壌侵食等が問題となっている。このような背景からエゾシカの密度操作実験が行われ,同効果の把握や人為介入の開始・終了等の目安となる植生指標の開発が求められている。本調査では,防鹿柵内外のイネ科草本,アメリカオニアザミおよびハンゴンソウ,台地草原全体のイネ科草本およびクマイザサ,台地草原に隣接する森林の木本葉量の調査を行い,植生指標の適用性について検討した。その結果,イネ科草本はエゾシカ密度操作開始後から増加傾向を示し,逆にアメリカオニアザミはエゾシカの影響を排除した場合,直ちに減少した。これらは短期的な植生指標となり得ると考えられた。また,クマイザサは被度・稈高で密度操作実験開始後の変化が異なることから,被度は短期的,稈高は中長期的な植生指標となり得ると考えた。一方,台地草原に隣接する森林葉量は密度操作開始後,その増加量は高さによって異なったため,高さによって異なる時期の植生指標になり得ると考えた。
3 0 0 0 OA 日本におけるスズメの個体数減少の実態
- 著者
- 三上 修
- 出版者
- 日本鳥学会
- 雑誌
- 日本鳥学会誌 (ISSN:0913400X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.161-170, 2009-10-24 (Released:2009-11-01)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 12 8
スズメPasser montanusの数が減っているのではないか,という声を,近年,各所で耳にする.そこで本研究では,スズメの個体数に関する記述および数値データを集め,スズメの個体数が本当に減少しているかどうか,減っているとしたらどれくらい減っているのかを議論した.その結果,現在のスズメの個体数は1990年ごろの個体数の20%から50%程度に減少したと推定された.1960年代と比べると減少の度合いはさらに大きく,現在の個体数は当時の1/10程度になった可能性がある.今後,個体数をモニタリングするとともに,個体数を適切に管理するような方策をとる必要があるだろう.
- 著者
- 中﨑 公仁 岡 真一 佐々木 祐典 本望 修
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, no.2, pp.93-97, 2015-02-20 (Released:2015-03-05)
- 参考文献数
- 17
われわれは基礎研究と臨床研究において, 脳梗塞に対して, 骨髄間葉系幹細胞の経静脈的投与により, 機能回復が得られることを報告してきた. 2007年より自家骨髄間葉系幹細胞を用いた, 脳梗塞に対する臨床研究を行い, 同治療の安全性と有効性を報告した. その結果を踏まえて, 2013年より, 医師主導治験 (Phase III) に取り組んでいる. この治験は, 薬事法 (平成26年11月25日より,「医薬品, 医療機器等の品質, 有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改名) に基づき, 厳格な品質管理のもと, 細胞医薬品 (細胞生物製剤: 自己骨髄間葉系幹細胞) を製造し, 適応となった症例を実薬群, プラセボ群へランダム化二重盲検法で割り付けて, 同治療の有効性を検証し, 薬事承認を目指している. 本稿では, 脳梗塞に対する骨髄間葉系幹細胞移植治療の臨床研究と, 現在進行中の医師主導治験の概要について報告する.
3 0 0 0 OA 性の越境 : 異性装とジェンダー
- 著者
- 佐伯 順子
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 表現における越境と混淆 (ISSN:13466585)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.37-54, 2005-09-01
3 0 0 0 OA 霊長類における群れの成立メカニズムについて
- 著者
- 大浦 宏邦
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.2, pp.129-144, 1996-12-31 (Released:2016-08-26)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 3
現在のヒトはきわめて複雑な社会を構成しているが、もとをたどればそれも、原猿のつくる単純な社会から、真猿類の群れ社会を経て次第に進化してきたものである。霊長類におけるこのような社会進化のメカニズムを知ることは、秩序や規範の起源といった社会学上の基本問題にアプローチする上で不可欠であると考えられる。本研究ではこうしたアプローチの第一歩として、霊長類における群れ社会の形成メカニズムについて検討を行った。いくつかのESS(進化的に安定な戦略)モデルによる検討の結果、捕食者を避ける要因が多くの場合、群れ戦略を有利にする上で有効であることが明らかとなった。また、群れの形成はエサなどの資源を巡る争いを激化させる一方、個体密度が高い場合やエサ資源が不均一に分布している場合には、連合して資源を防衛するために群れを作る戦略が有利になりうることが明らかとなった。
3 0 0 0 OA 文章の評価観点に基づく評価者グルーピングの試み
- 著者
- 宇佐美 洋
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.147, pp.112-119, 2010 (Released:2017-02-15)
- 参考文献数
- 9
日本語母語話者が学習者の日本語作文を評価する際,評価の基本的方針(評価スキーマ)は人によって大きく異なる。評価スキーマのばらつきの全体像をとらえるため,評価観点に関する質問紙への回答傾向によって評価者をグルーピングする試みを行った。 評価者155名に学習者が書いた手紙文(謝罪文)10編を読んでもらい,「最も感じがいいもの」から「悪いもの」まで順位づけを依頼し,作業後,「順位づけの際どういう観点をどの程度重視したか」を問う質問紙(22項目,7段階)に回答してもらった。得られた回答に対して因子分析を実施した結果,「言語形式」,「全体性」「読み手への配慮・態度」「表現力」と名付けられる4因子を得た。さらに,評価者ごとに算出した上記4因子の因子得点に対しクラスタ分析を実施したところ,評価者は「言語重視型」,「非突出型」,「態度・配慮非重視型」,「言語非重視型」という4グループに分類するのが適当と解釈された。
- 著者
- 原田 拓真 猪島 綾子
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.152, no.6, pp.306-318, 2018 (Released:2018-12-08)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 1
パルボシクリブは世界で最初のサイクリン依存性キナーゼ(CDK)4および6阻害薬であり,CDK4または6とサイクリンDから成る複合体の活性を阻害することで細胞周期の進行を停止させ,腫瘍の増殖を抑制すると考えられる.非臨床モデルを用いた検討でパルボシクリブに感受性を示す細胞株の多くがエストロゲン受容体(ER)陽性であることが確認され,パルボシクリブが抗腫瘍効果を示すには網膜芽細胞腫タンパク質(Rb)の発現が必要であることが確認された.また,ER陽性ヒト乳がん細胞株を用いた試験から,抗エストロゲン薬との併用投与による抗腫瘍作用の増強が確認された.これらの非臨床試験データに基づき,ホルモン受容体陽性・ヒト上皮増殖因子受容体2陰性(HR+/HER2-)の進行・再発乳がんに対し抗エストロゲン薬との併用を行う臨床試験を行った.進行乳がんに対する全身抗がん療法歴のないER+/HER2-の閉経後進行乳がん女性患者を対象としてパルボシクリブ+レトロゾール併用投与の効果をレトロゾール単独投与と比較したPALOMA-2試験では,パルボシクリブ併用投与群で主要評価項目である無増悪生存期間(progression-free survival:PFS)の有意な延長が認められた.抗エストロゲン薬を用いた内分泌療法に抵抗性を示したHR+/HER2-の進行乳がん女性患者を対象とし,パルボシクリブ+フルベストラント併用投与の効果をフルベストラント単独投与と比較したPALOMA-3試験では,中間解析において主要評価項目であるPFSに統計学的に有意な延長が認められたため,試験は有効中止となった.また,これらいずれの試験でも,パルボシクリブ投与群において有害事象による減量または休薬の割合は高かったものの,投与中止の割合はプラセボ投与群と大きく変わるものではなかった.
3 0 0 0 OA J・ステュアートとA・スミスの公信用論 : 銀行信用との関連において
- 著者
- 小柳 公洋
- 出版者
- 熊本学園大学経済学会
- 雑誌
- 熊本学園大学経済論集 = Journal of economics, Kumamoto-Gakuen University (ISSN:13410202)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1・2, pp.1-23, 2008-09-30
3 0 0 0 OA 湾岸戦争でテレビは何を伝えたのか
- 著者
- 辻 一郎 Ichiro TSUJI
- 出版者
- 大手前大学
- 雑誌
- 大手前大学社会文化学部論集 = Otemae Journal of Socio-Cultural Studies (ISSN:13462113)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.193-207, 2001-03-25
3 0 0 0 OA 1885年~1925年の日本の地震活動 : M6以上の地震および被害地震の再調査
- 著者
- 宇津 徳治
- 出版者
- 東京大学地震研究所
- 雑誌
- 東京大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo (ISSN:00408972)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.253-308, 1979-12-25
Only one catalog has been available for moderate to large earthquakes occurring in the region of Japan in the years 1885 to 1925. However, this catalog, published by the Central Meteorological Observatory in 1952, has often been criticized as misleading, because no con- sideration is given to the depth of focus and magnitude values are unreasonably large for many earthquakes. A new catalog of earthquakes of M≧6 is prepared in this study to meet the demand in earthquake prediction and earthquake risk studies in Japan. Both instrumental and macroseismic data are used in the determination of focal parameters. Most of the data are taken from either published reports of the Central Meteorological Observatory, the Imperial Earthquake Investigation Committee, or written station reports collected and stored by the Japan Meteorological Agency and the University of Tokyo. The hypocenter location is mainly based on the S-P time intervals and the magnitude determination is mostly due to the maximum amplitude recorded by old-fashioned seismographs. For older events, the determination is more dependent on the seismic intensity distributions. The catalog (Table 7) lists 555 earthquakes of M≧5.9 and 53 destructive earthquakes of M ≧5.8. The procedure for the focal parameter determination is explained in detail using six sample earthquakes. Referring to the epicenter maps constructed from this catalog, characteristics of the seismicity of Japan in the period 1885-1925 are described. More detailed studies using this catalog will be given elsewhere. A special description of 79 selected earthquakes of particular interests is given in the last half of the paper.
- 著者
- Kanamori Hiroo Miyamura Setumi
- 出版者
- 東京大学地震研究所
- 雑誌
- 東京大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo (ISSN:00408972)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.115-125, 1970-06-10
Old seismological data were used to re-evaluate the Great Kanto Earthquake of September 1, 1923. On the basis of reported P times at about one hundred stations the hypocenter parameters were determined as: origin time, 2h58m32s; latitude 35.4°N; longitude, 139.2°E; depth, 0 to 10km. The above epicenter may be uncertain by ±15 km. The surface-wave magnitude was re-evaluated using seismograms from 17 stations. The average value of 8.16 was obtained.|1923年9月1日の関東大地震の震源とマグニチュードを再決定した.震源決定に用いた資料はInternational Seismological Summaryや日本の文献に発表されているP波の発震時で約100の観測点の値を用いた.再決定された震源要素は次の通りである.震源時:02時58分32秒,震央緯度:35.4°N,震央経度:139.2°E,深さ:O~10km.この震央の誤差は±15km位である.マグニチュードの決定は,17ケ所の観測所で記録された周期20秒程度の表面波の振幅を用いて行なつた.平均値として8.16が得られた.
- 著者
- Kanamori Hiroo
- 出版者
- 東京大学地震研究所
- 雑誌
- 東京大學地震研究所彙報 = Bulletin of the Earthquake Research Institute, University of Tokyo (ISSN:00408972)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1-3, pp.13-18, 1971-09-30
The fault parameters of the Great Kanto earthquake of September 1, 1923, are determined on the basis of the first-motion data, aftershock area, and the amplitude of surface waves at teleseismic stations. It is found that the faulting of this earthquake is a reverse right-lateral fault on a plane which dips 34° towards N20°E. The auxiliary plane has a dip of 80° towards S55°E. This means that the foot-wall side moves approximately north-west with respect to the hanging wall side. The strike of the fault plane is almost parallel to that of the Sagami trough, and the slip direction is more or less perpendicular to the trend of the Japan trench. This earthquake is therefore considered to represent a slippage between two crustal blocks bounded by the Sagami trough. A seismic moment of 7.6×1027 dyne-cm is obtained. If the fault dimension is taken to be 130×70 km2, the average slip on the fault plane and the stress drop are estimated to be 2.1m and 18 bars respectively. This slip is about 1/3 of that estimated from geodetic data. This discrepancy may indicate an existence of a pre-seismic deformation which did not contribute to the seismic wave radiation, but the evidence from other observations is not very firm.|関東地震の断層パラメターをP波の初動分布と長周期表面波の振幅からきめた.その結果,この地震はN20°Eの方向に34°傾いた面上での右ずれ・逆断層であらわされることがわかつた.断層面の大きさを130×70km2とすると,断層面上でのすべりは約2m, stress dropは18バールである.断層上でのすべりのむきが相模troughの走向に平行で,日本海溝に垂直であり,また震源が浅く(地殻内)かつ日本海溝から遠くはなれていることを考ると,関東地震は海と陸のリゾスフィアの相互作用の直接の結果とは考えにくい.むしろ,この地震は海と陸のリゾスフィアの相互作用によつて2次的に起つた,相模troughを境とする二つの地塊のずれによるものであると解釈できる.地殻変動の大きさから推定されているすべりの大きさは7mであるが,これは表面波の振幅から推定された値2mよりはるかに大きい.この違いは種々の誤差を考慮にいれてもなお有意義と思われる.このくいちがいは,全体の地殻変動量のうち2分以内の時定数をもつもののみが地震波の発生に関与したと考えれば説明できる.