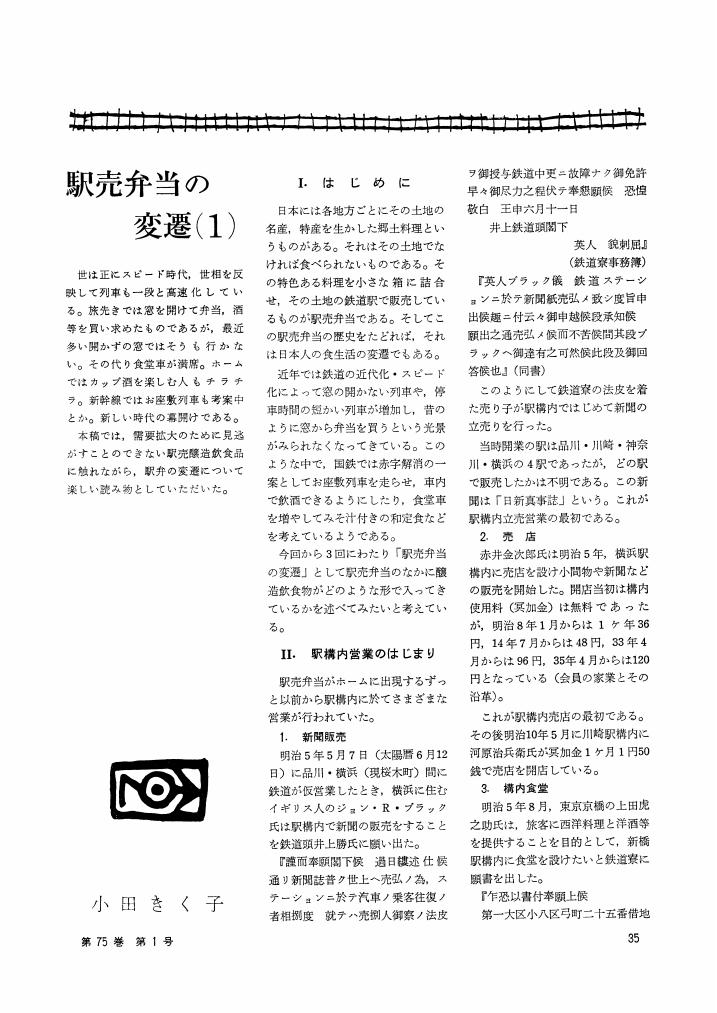2 0 0 0 OA 自傷行為研究の展望と今後の課題について
- 著者
- 浅野 瑞穂 アサノ ミズホ Mizuho Asano
- 雑誌
- 立教大学臨床心理学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.13-23,
2 0 0 0 OA フランス語の「名づけ」の構造
- 著者
- 倉方 秀憲
- 出版者
- 早稲田大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 早稲田大学大学院文学研究科紀要. 第2分冊, 英文学 フランス語フランス文学 ドイツ語ドイツ文学 ロシア語ロシア文化 中国語中国文学 (ISSN:13417525)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, pp.39-54, 2016-02-26
2 0 0 0 OA モートンの環境哲学( 1 )
- 著者
- 竹中 真也
- 出版者
- 中央大学人文科学研究所
- 雑誌
- 人文研紀要 (ISSN:02873877)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, pp.279-304, 2019-09-30
本稿は,ティモシー・モートンの環境哲学の一端を解明することを目指す。そうするにあたって,ここでは鍵概念のmesh とstrange staranger に焦点を当てる。まずはモートンの哲学を生み出した時代背景「人新世」に触れ,しかるのちにmesh とstrange stranger に関する論述を紹介する。最初に豊富な具体的事例を『エコロジーの思想』から取り上げ,次に,『コラプス』に掲載された論文を軸として,それらの事例を哲学的水準から捉え返す。最後に,これらのmesh やstrange stranger の議論を,モートンが与すると言われているオブジェクト指向存在論の旗手ハーマンの議論と接続し,モートンの議論の特徴のひとつを浮き彫りにする。
2 0 0 0 OA 「2000年政党、選挙及び国民投票法」の制定とイギリスにおける政党助成制度
- 著者
- 間柴泰治
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.643, 2004-08
2 0 0 0 OA 日本国憲法制定過程における二院制諸案
- 著者
- 田中嘉彦
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.647, 2004-12
2 0 0 0 OA 米国における金融・資本市場改革の展開
- 著者
- 樋口修
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.635, 2003-12
2 0 0 0 OA 表象としての鳥居 -ブラジル・サンパウロを事例に-
- 著者
- 加藤 里織 カトウ サオリ
- 出版者
- 神奈川大学日本常民文化研究所 非文字資料研究センター
- 雑誌
- 非文字資料研究 = The study of nonwritten cultural materials = The study of nonwritten cultural materials (ISSN:24325481)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.83-91, 2022-03-20
研究ノート
2 0 0 0 OA 最近の進歩(体外循環技術─透析技術)
- 著者
- 村上 淳
- 出版者
- 一般社団法人 日本人工臓器学会
- 雑誌
- 人工臓器 (ISSN:03000818)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.214-217, 2021-12-15 (Released:2022-03-15)
- 参考文献数
- 1
2 0 0 0 OA 抽象化の水準
- 著者
- Jesper Junl 増田 泰子
- 出版者
- 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- デジタルゲーム学研究 (ISSN:18820913)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.85-91, 2008 (Released:2021-07-01)
この論文では抽象化の水準を探求する。表象的なゲームはフィクションの世界を表現するが、その世界の中でプレイヤーは一定の行動しか取れない。そのゲームのフィクションの世界を詳細に実行す るには限りがあるからだ。 本論文ではテレビゲームデザインの中心的要素としての抽象化と、プレイ中にプレイヤーが解読する ものとしての抽象化と、プレイヤーが時間をかけて作っていく一種の最適化としての抽象化を区別する。 最後に本論文では、抽象化がゲームのマジックサークルやルールそれ自体と関連し合っていることを論じる。
2 0 0 0 OA 朝倉郡郷土人物誌
- 著者
- 福岡県朝倉郡教育会 編
- 出版者
- 福岡県朝倉郡教育会
- 巻号頁・発行日
- 1926
- 著者
- 仁科 エミ 大橋 力
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.40.3, pp.169-174, 2005-10-25 (Released:2017-07-01)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
著者らはさきに、自然性の高い環境音に豊富に含まれている可聴域を超える高周波成分が都市環境では大幅に欠乏しており、それが現代病の引き金を引く基幹脳の活性低下を導く可能性を見出した。このことから、高周波成分を豊富に含む熱帯雨林性の森林環境音を市街地環境音に電子的に補完することによって基幹脳の活性を適正化し、都市の病理を克服するという都市情報環境改善の方略が展望される。これを具現化するために著者らは、熱帯雨林の環境音を市街地環境音に補完して、その生理・心理的効果を計測する実験を行った。その結果、ストレスフリーの指標であり脳基幹部の活性と高い相関関係にある脳波α波が増大するとともに、ガン抑制効果やウィルス感染防止効果をもつ血液中のNK細胞活性や免疫グロブリン類の活性が上昇し、ストレス指標となるアドレナリンが低下するなどのポジティブな生理的効果と、環境の快適性が全般的に高まるという心理的効果とが見出された。これにより、著者らの都市情報環境改善方略は、大きな支持材料を得たと考えられる。
- 著者
- Kazuki Nakamura Atsushi Kuge Tetsu Yamaki Kenshi Sano Shinjiro Saito Rei Kondo Yukihiko Sonoda
- 出版者
- The Japanese Society for Neuroendovascular Therapy
- 雑誌
- Journal of Neuroendovascular Therapy (ISSN:18824072)
- 巻号頁・発行日
- pp.cr.2022-0002, (Released:2022-07-22)
- 参考文献数
- 21
Objective: We describe a patient treated with transarterial Onyx embolization for a tentorial dural arteriovenous fistula (DAVF) who presented with hemifacial spasm (HFS).Case Presentation: A 56-year-old man suffered from right blepharospasm for 4 years, and the symptom gradually spread to the right side of his face with oculo-oral synkinesis. MRI of the brain revealed abnormal multiple flow voids at the surface of brainstem and cerebellar hemisphere. MRA (time of flight) and spoiled gradient recalled echo-revealed abnormal vessels at the posterior fossa indicated arteriovenous shunting. 3D-MRI fusion images showed that a dilated vein was in contact with the root exit zone (REZ) of the right facial nerve. The right carotid angiography displayed a complex tentorial DAVF on the right side. There were multiple feeding vessels drained to the tentorial sinus at the point where the inferior cerebellar vermian vein met, and severe venous congestion was noted. We diagnosed a tentorial DAVF and thought that this was responsible for the right HFS. We used neuroendovascular treatment for this lesion. After transarterial Onyx embolization, his right HFS diminished. MRI after treatment showed that the vein in contact with the REZ of the right facial nerve had shrank.Conclusion: We experienced a rare case of HFS associated with a DAVF. Our case supports that transarterial Onyx embolization can treat HFS associated with a tentorial DAVF. It is the first description of successful treatment that could be confirmed through postoperative MRI.
2 0 0 0 OA 駅売弁当の変遷 (1)
- 著者
- 小田 きく子
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.1, pp.35-39, 1980-01-15 (Released:2011-11-04)
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 小泉保先生ありがとうございました(故小泉保先生追悼文)
- 著者
- 上田 功
- 出版者
- 日本音声学会
- 雑誌
- 音声研究 (ISSN:13428675)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.3, pp.1-3, 2009-12-30 (Released:2018-03-31)
2 0 0 0 OA H. Aspergerと「アスペルガー問題」 : アスペルガー症候群理解の前提として
- 著者
- 窪島 務
- 出版者
- 滋賀大学教育学部
- 雑誌
- 滋賀大学教育学部紀要 (ISSN:21887691)
- 巻号頁・発行日
- no.65, pp.101-117, 2016-03-31
In terms of diagnosis category, Asperger-Syndrome has been revised in DSM-5 and moved into one unital diagnosis category as an autistic spectrum disorder(ASD), but this category continues to be used in the clinical situation. To understand this disorder, the DSM and ICD classification systems are neither enough for diagnosis nor educational treatment. Here, apart from the diagnosis viewpoint, another theme exists, Specifically, the kind of educational perspective and methodology used was very important when H. Asperger observed his children, He called himself “Kinderarzt und Heilp?dagoge (pediatrician and remedial-educator)”. Therefore, we think that the background to H. Asperger's thesis about “autistische psychopathen” (autistic psychopathy) must be considered. And, at such a time, the following points should be discussed. (1) Relationship with“Austrian Heilp?dagogik”, (2) His methodological viewpoints, especially, the concept of “Ganzheitlichkeit”(integrated), and (3) His attitude to“NS eugenics”.
2 0 0 0 OA 私の褥瘡診療30年の軌跡
- 著者
- 宮地 良樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本創傷・オストミー・失禁管理学会
- 雑誌
- 日本創傷・オストミー・失禁管理学会誌 (ISSN:1884233X)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.368-374, 2017 (Released:2021-04-30)
- 参考文献数
- 21
- 著者
- 青木 吾郎 寺山 隼矢 西城 直人 西出 航陽 山本 晃平
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.6, pp.498-502, 2022 (Released:2022-07-20)
- 参考文献数
- 5
2 0 0 0 OA Sociophonetics: An Introduction
- 著者
- MASAHIKO KOMATSU
- 出版者
- The English Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- ENGLISH LINGUISTICS (ISSN:09183701)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.671-680, 2014 (Released:2019-03-05)
- 参考文献数
- 15