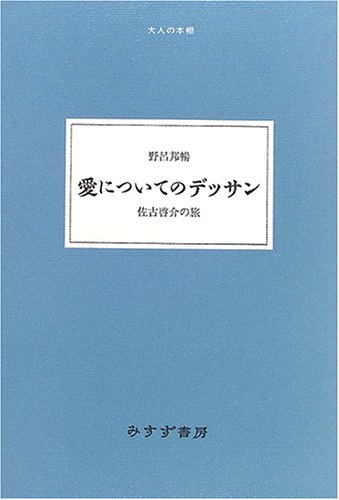1 0 0 0 OA シリアンハムスターの給与飼料および交配週齢が繁殖成績に及ぼす影響
- 著者
- 佐藤 正寛 小畑 太郎
- 出版者
- Japanese Association for Laboratory Animal Science
- 雑誌
- Experimental Animals (ISSN:00075124)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.5, pp.731-735, 1995-10-01 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 11
シリアンハムスターを選抜実験に用いるため, 給与飼料および交配週齢が受胎率や離乳子数などの繁殖成績に及ぼす影響について検討した。雌240匹を2群に分け, 1群には草食動物用飼料ZC-2, 他の1群には繁殖用飼料MB-1を給与して育成した (育成期) 。交配時に各群をさらに2群に分け, 1群は育成期と同一飼料, 他の1群は飼料を変えて繁殖させた (繁殖期) 。交配は各群の半数を8週齢, 残りの半数を12週齢で行った。育成期にZC2を給与し, 繁殖期にMB-1を給与した区が, 雌親の分娩数, 離乳数, 3週齢時における子の匹数および一腹体重において有意に高い値を示した (P<0.01) 。12週齢交配区は8週齢交配区に比べて, 雌親の分娩数, 分娩時における産子数と一腹体重において有意に高い値を示した。しかし, 3週齢における子の匹数や一腹体重には差がみられなかった。以上の結果から, ハムスターの育成期には比較的高繊維質の飼料を給与し, 繁殖期に繁殖用飼料に切り換えることによって高い繁殖成績が得られることが明らかとなった。
1 0 0 0 地域の再生可能エネルギー利用システムの構成に関する研究
- 著者
- 菊池 慎也 高島 幸佑 佐藤 正毅
- 出版者
- 電気関係学会東北支部連合大会実行委員会
- 雑誌
- 電気関係学会東北支部連合大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.326, 2010
1 0 0 0 OA 研究発表要旨
- 著者
- 楊 鶴 Goro(Georges) SATO(VEYSSIÈRE) 渋谷 直樹 山本 明美 野田 農 五味田 泰 嶋野 牧子 菊池 博子 木村 仁志 Kenichiro OTANI 石川 典子 八木橋 久実子 佐藤 正尚 Marie-Noëlle BEAUVIEUX Takeo YAMAMOTO 太田 悠介
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会
- 雑誌
- フランス語フランス文学研究 (ISSN:04254929)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, pp.133-148, 2018 (Released:2018-04-26)
- 著者
- 髙橋 高人 松原 耕平 中野 聡之 佐藤 正二
- 出版者
- 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 = The Japanese journal of educational psychology (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.81-94, 2018-03
- 著者
- 武藤 淳 佐瀬 善一郎 宮澤 正紹 佐藤 正幸 菅野 明弘 蘆野 吉和 松代 隆
- 出版者
- 一般社団法人日本外科学会
- 雑誌
- 日本外科学会雑誌 (ISSN:03014894)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, 2002-03-10
1 0 0 0 OA GONAD:採卵,顕微注入,移植を要しない新規ゲノム編集マウス作製法
- 著者
- 大塚 正人 GURUMURTHY Channabasavaiah 三浦 浩美 佐藤 正宏 和田 健太 高橋 剛
- 出版者
- 日本繁殖生物学会
- 雑誌
- 日本繁殖生物学会 講演要旨集 第108回日本繁殖生物学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.P-83, 2015 (Released:2015-09-15)
【目的】近年,CRISPR/Cas9系を含めたゲノム編集技術の開発によって,簡便にノックアウト(KO)マウス等のゲノム編集マウスを作出できるようになってきた。現行法では,(1)過排卵処理を施した雌マウスを雄マウスと交配して受精卵を採取する,(2)CRISPR関連核酸を受精卵へ直接顕微注入する,(3)顕微注入処理した胚を偽妊娠マウスの卵管へ移植する,という3つのステップを経て作製する方法が一般的である。しかしながら,これらは熟練した技術とmicromanipulatorという高価な設備を必要とするため,誰もが容易に実施できる環境にある訳ではない。そこで我々は,採卵,顕微注入,移植の手間を省くことが可能な,新規ゲノム編集マウス作製法「Genome-editing via Oviductal Nucleic Acids Delivery (GONAD)法」を考案した。【方法】麻酔処置を施された妊娠雌マウスから2細胞期受精卵を有する卵管を体外に露出させ,ガラスピペットを用いてCRISPR関連核酸溶液を卵管内に注入し,その後,直ちに卵管全体に対し電気穿孔法を施す。術後,卵管を雌マウスの体内に戻し,そのまま発生させる。【結果】本手法の妥当性を確認するために,まず,本技術によってRNA導入が可能であるかを検証した。GONAD法を用いてeGFP mRNAの導入を試みたところ,卵管上皮細胞および着床前胚でのeGFPの発現が観察された。そこで,次にCRISPR関連RNA(Cas9 mRNAとsgRNA)の導入を試みた。その結果,着床前胚において複数の内在性遺伝子,およびeGFP遺伝子のKOに成功した。また,着床後胚においてもeGFP遺伝子のKOにも成功した。これらの結果から,卵管内の受精卵に核酸を直接導入することにより,採卵や顕微注入,移植という一連の高度であるが,煩雑な工程を全てスキップしてゲノム編集マウスを簡便に作製できることが示された。
- 著者
- 小松 正憲 西尾 元秀 佐藤 正寛 千田 雅之 広岡 博之
- 出版者
- Japanese Society of Animal Science
- 雑誌
- 日本畜産學會報 = The Japanese journal of zootechnical science (ISSN:1346907X)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.2, pp.157-169, 2009-05-25
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1 2
黒毛和種繁殖肥育一貫経営農家経営において,BMSナンバーや枝肉重量(CW)に関与するQTLアリル型情報はどの程度収益上昇に活用できるかを,初期QTLアリル頻度 (<I>p</I>),計画年数 (<I>T</I>),DNAタイピング料金(<I>C<SUB>TYP</SUB></I>),使用する精液差額(<I>SEM</I>),種雄牛と繁殖雌牛の割合(<I>R (s/d)</I>)を変化させて検討した.その結果,BMSナンバーに関わる<I>Q</I>アリルを1個持つことで得られるBMSランク上昇分(Δ<I>BMS<SUB>QTL</SUB></I>)を1.0,BMSナンバー1ランク上昇分の枝肉単価(<I>CWP<SUB>BMS</SUB></I>)を150円/kg, <I>CW</I>を440 kg, CWに関わる<I>Q</I>アリルを1個持つことで得られる枝肉重量上昇分(Δ<I>C<SUB>WQTL</SUB></I>)を20 kg, 黒毛和種去勢枝肉単価(<I>CW<SUB>PU</SUB></I>)を1,900円/kgとした場合,QTLアリル型情報は,黒毛和種繁殖肥育一貫経営農家の経営に充分活用できると考えられた.また,以下のことが明らかになった.QTLアリル型情報を経営に活用する際,集団における<I>p</I>の頻度,<I>SEM</I>および<I>T</I>数が重要であり,<I>C<SUB>TYP</SUB></I>と<I>R (s/d)</I> の重要性は低かった.<I>C<SUB>TYP</SUB></I>が5千円/頭,<I>SEM</I>が1万円程度以下で,1頭当たり1万円程度の収益上昇を確保するためには,<I>p</I>の頻度は,BMSナンバーでは0.6~0.7以下,CWでは0.4~0.5以下であることが示唆された.繁殖雌牛集団のQTLアリル型情報は,<I>p</I>の頻度が0.5~0.7程度の範囲内,<I>T</I>数がBMSナンバーで6年以上,CWで8年以上であれば,収益上昇に貢献できることが明らかになった.
1 0 0 0 IR 純粋法学の体系、思想的背景及びその実証性(1)
- 著者
- 佐藤 正典 Masanori SATOH 桜美林大学法学・政治学系 J. F. Oberlin University Division of Law and Political Science
- 出版者
- 桜美林大学
- 雑誌
- 桜美林論考. 法・政治・社会 = The journal of J. F. Oberlin University. Law, political science and sociology (ISSN:21850682)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.13-38, 2015-03-01
1 0 0 0 OA 育種改良のためのQTL情報の利用
- 著者
- 佐藤 正寛
- 出版者
- Japanese Society of Animal Breeding and Genetics
- 雑誌
- 動物遺伝育種研究 (ISSN:13459961)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.69-78, 2000-11-15 (Released:2010-03-18)
- 参考文献数
- 14
1 0 0 0 愛についてのデッサン : 佐古啓介の旅
1 0 0 0 OA 社会的スキル訓練による児童の抑うつ症状への長期的効果
- 著者
- 石川 信一 岩永 三智子 山下 文大 佐藤 寛 佐藤 正二
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.372-384, 2010-09-30 (Released:2012-03-07)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 3 8
本研究の目的は, 小学校3年生を対象とした集団社会的スキル訓練(集団SST)の実施による進級後の抑うつ症状への効果を検討することであった。本研究では, ウェイティングリストコントロールデザインが採用された。対象児童は, 先に集団SSTを実施する群(SST群114名)と, SST群の介入終了後, 同一の介入がなされるウェイティングリスト群(WL群75名)に割り付けられた。集団SSTは, 学級単位で実施され, 上手な聞き方, あたたかい言葉かけ, 上手な頼み方, 上手な断り方, 教師に対するスキルの全5回(1回45分)から構成された。加えて, 獲得された社会的スキルの維持促進の手続きとして, 終了後に集団SSTのポイントが記述された下敷きを配布し, 進級後には教室内でのポイントの掲示, ワンポイントセッション, ブースターセッションといった手続きが採用された。その結果, SST群とWL群において, 訓練直後に社会的スキルの上昇がみられ, 進級後もその効果が維持されていることが示された。さらに, 訓練群とWL群は, 1年後の抑うつ症状が有意に低減していることが示された。以上の結果を踏まえ, 早期の抑うつ予防における集団SSTの有効性と有用性に加え, 今後の課題について議論がなされた。
1 0 0 0 8-6 選挙番組, スポーツ番組用グラフィックディスプレイ
- 著者
- 中西 祥二 塩飽 弘 星 与一郎 木村 武 島山 政治 佐藤 正彦
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会全国大会講演予稿集
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.191-192, 1984
脳血管攣縮は、くも膜下出血後の重篤な合併症であり、その原因として、Rhoキナーゼによる血管平滑筋のCa2+非依存性の異常収縮が注目されている。従って、この血管の異常収縮を引き起こすメカニメムとその原因因子を解明する事によって、脳血管攣縮の根本的な予防法や治療法を開発することが、国民衛生上の緊急かつ最重要課題である。本研究では、脳血管において、Ca2+非依存性の異常収縮を制御する細胞内シグナル伝達メカニズムを明らかにし、そのシグナル経路を特異的に阻害する因子を同定する事を目的とする。初年度は、脳血管異常収縮の原因分手として細胞膜スフィンゴ脂質の代謝産物であるスフィンゴシルホスホリルコリン(SPC)を同定し、そのシグナル経路は、RhQキナーゼを介するものであるが、従来言われていたG蛋白質やPKCとは独立した新規のシグナル経路である事を見出した。本年度は、下記のような結果を得た。1)脳血管において、エイコサペンタエン酸(EPA)は、SPCによるCa2+非依存性収縮を著明に抑制したが、Ca2+依存性の正常収縮や細胞質Ca2+濃度レベルには全く影響しなかった。2)SPCは、Srcファミリーチロシンキナーゼを活性化させ、さらにRhoキナーゼを活性化させることによって、脳血管に異常収縮を引き起こしていた。3)SPCは、SrcファミリーチロシンキナーゼおよびRhoキナーゼを細胞質から細胞膜へ移動させた。4)EPAは、Srcファミリーチロシンキナーゼの細胞膜への移動を阻止した。これらの成果により、EPAは、Ca2+シグナル系および血管の正常なCa2+依存性収縮には影響を与える事無く、Srcファミリーチロシンキナーゼの機能を阻害する事によって、特異的に脳血管の異常収縮を阻害することがわかった。
1 0 0 0 OA 麻酔科の立場からみた気管切開の問題点
- 著者
- 鈴木 英弘 佐藤 正光
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本気管食道科学会
- 雑誌
- 日本気管食道科学会会報 (ISSN:00290645)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.175-177, 1985-04-10 (Released:2010-02-22)
1 0 0 0 IR 社会的スキル訓練による児童の抑うつ症状への長期的効果
- 著者
- 石川 信一 岩永 三智子 山下 文大 佐藤 寛 佐藤 正二
- 出版者
- 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.372-384, 2010-09-30
- 被引用文献数
- 8
本研究の目的は,小学校3年生を対象とした集団社会的スキル訓練(集団SST)の実施による進級後の抑うつ症状への効果を検討することであった。本研究では,ウェイティングリストコントロールデザインが採用された。対象児童は,先に集団SSTを実施する群(SST群114名)と,SST群の介入終了後,同一の介入がなされるウェイティングリスト群(WL群75名)に割り付けられた。集団SSTは,学級単位で実施され,上手な聞き方,あたたかい言葉かけ,上手な頼み方,上手な断り方,教師に対するスキルの全5回(1回45分)から構成された。加えて,獲得された社会的スキルの維持促進の手続きとして,終了後に集団SSTのポイントが記述された下敷きを配布し,進級後には教室内でのポイントの掲示,ワンポイントセッション,ブースターセッションといった手続きが採用された。その結果,SST群とWL群において,訓練直後に社会的スキルの上昇がみられ,進級後もその効果が維持されていることが示された。さらに,訓練群とWL群は,1年後の抑うつ症状が有意に低減していることが示された。以上の結果を踏まえ,早期の抑うつ予防における集団SSTの有効性と有用性に加え,今後の課題について議論がなされた。
- 著者
- 渡邊 清高 佐藤 正惠
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.4, pp.284-285, 2017-07-01 (Released:2017-07-01)
高齢者の咀嚼機能は一般的に歯の喪失に伴い低下する。ことに無歯顎者で著しく,総義歯の状況により十分な回復ができず,結果的に食物摂取,栄養確保が困難になる。咀嚼機能レベルに応じて適切な食物摂取が容易かつ確実に行なえるよう噛み易さを考慮し,食物の硬さを調整して栄養バランスの採れた一連の献立を提供し,それを利用しながら個人へ行なう食事指導は健康管理面からも効果的である。そこで可及的に同一食品を用いて普通食,刻み食,五分粥食,三分粥食,ミキサ-食へと展開させた一連の献立群に栄養学的検討を加え,総義歯患者の食事指導に役立つ展開食の開発を試みたところ以下のような結果を得た。1.60歳代前半の高齢者を対象とした展開食に超軟性食の三部粥食を追加検討したところ,(1)各献立とも各栄養素充足率は満たされ.(2)ビタミン類は調理損失をみこしており過剰傾向であり.(3)蛋白質の確保に1700kcal,70gを設定したので一般成人の理想値より多く.また豆・豆製品は各展開食に多く,三部粥食では芋類と砂糖が多い傾向であった。2.高齢者の嗜好の多い和食タイプに,食事選択範囲を広げる目的で洋食タイプを加えて比較検討したところ,(1)各栄養素充足率では,和食タイプ,洋食タイプとも同様の傾向であり,(2)食品群別充足率では,それぞれ異なる傾向がみられ,食品の選択に工夫を要すること,ならびに類似タイプの献立を連続摂取を避けることが示唆された。3.展開食の臨床応用の前準備として,65歳代,70歳代,80歳代を考慮し栄養摂取の観点から展開食構成を調整する際の問題点を検討するため,特別栄養護施設入所者を対象に5日間の昼食の喫食率としてグループ別残菜調査を検討したところ,(1)残菜率は15%から20%の範囲にあり,(2)献立により傾向は異なり,嗜好,盛りや味付け,固さや量,個人の全身状況,咀喝状況などの影響が示唆された。
- 著者
- 佐藤 正惠
- 出版者
- 日本薬学図書館協議会
- 雑誌
- 薬学図書館 = Pharmaceutical library bulletin (ISSN:03862062)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.208-215, 2016
- 著者
- 佐藤 正幸 佐藤 正幸 SATO Masayuki サトウ マサユキ Sato Masayuki
- 出版者
- 山梨県立大学
- 雑誌
- 山梨国際研究 山梨県立大学国際政策学部紀要 = Yamanashi glocal studies : bulletin of Faculty of Glocal Policy Management and Communications (ISSN:21874336)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.82-98, 2016
Situated to the east and the west of the Eurasian continent, the British Isles and Japan both possess cultures with root extending into the distant past. In both areas numerous genealogies have been fashioned from the seventh century, the time from which the first written materials are extant. These genealogies have played a central role in the determination of an awareness of history. This article introduces the Japanese translation of Kathleen Hughes's, The Early Celtic Idea of History and the Modern Historian: An Inaugural Lecture, (Cambridge University Press; Cambridge,1977, 24 pp.). Hughes treats the era during which Christianity, a religion that served on the basis of Celtic culture, was accepted by medieval Ireland. By examining numerous genealogies, Hughes examines the development of historiography. This report introduces Hughes's work in order foster a better understanding from a comparative perspective of the culture of genealogies and the development of historical writings in Japan.
- 著者
- 佐藤 正年
- 出版者
- 広島大学フランス文学研究会
- 雑誌
- 広島大学フランス文学研究 (ISSN:02873567)
- 巻号頁・発行日
- no.34, pp.16-28, 2015