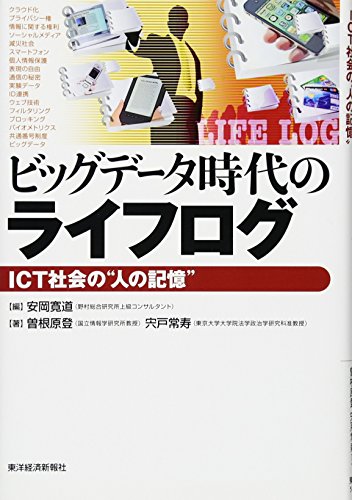1 0 0 0 ミツクリザメ(新稱) : Mitsukurina Owstoni
- 著者
- 宍戸
- 出版者
- 社団法人日本動物学会
- 雑誌
- 動物学雑誌 (ISSN:00445118)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.117, pp.223-226, 1898-07-15
1 0 0 0 第5回 公平分割と公平割当
- 著者
- 宍戸 栄徳 曽 道智
- 出版者
- 公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会
- 雑誌
- オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 = [O]perations research as a management science [r]esearch (ISSN:00303674)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.3, pp.203-209, 2003-03-01
- 参考文献数
- 18
- 著者
- 松本 和彦 宍戸 常寿
- 出版者
- 有斐閣
- 雑誌
- 法学教室 (ISSN:03892220)
- 巻号頁・発行日
- no.412, pp.4-24, 2015-01
1 0 0 0 文献研究・樋口陽一著『憲法1』
- 著者
- 宍戸 常寿
- 出版者
- 東京都立大学法学部
- 雑誌
- 東京都立大学法学会雑誌 (ISSN:03868745)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.331-350, 2001-07
- 著者
- 宍戸 周夫
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理 (ISSN:04478053)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.4, pp.418-419, 2001-04-15
米国経済の急激な減速が,コンピュータ・ベンダの戦略に大きな影響を与えている.これまでのビジネスモデルの延長戦にはない,新たな取組みが求められるようになってきた.そこで,コンピュータ・ベンダの間で浮上してきたのはストレージだ.その背景には,近い将来にはITベンダの売上げに占めるサーバとストレージの割合が逆転するという予想がある.
- 著者
- 相葉 孝充 宍戸 正孝 土屋 和春
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会総合大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.2, 2007-03-07
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 特別支援学校における幼児・児童の協同的学習を育む授業研究
1 0 0 0 外国における医療事故補償制度--ニュージーランドと英国の場合
- 著者
- 宍戸 伴久
- 出版者
- 国立国会図書館調査及び立法考査局
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:00342912)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.7, pp.59-73, 2008-07
- 著者
- 宍戸 常寿
- 出版者
- 岩波書店
- 雑誌
- 世界 (ISSN:05824532)
- 巻号頁・発行日
- no.765, pp.165-173, 2007-05
1 0 0 0 ビッグデータ時代のライフログ : ICT社会の"人の記憶"
- 著者
- 安岡寛道編 曽根原登 宍戸常寿著
- 出版者
- 東洋経済新報社
- 巻号頁・発行日
- 2012
1 0 0 0 現代・コンピュータ市場:プログラミングをしないコンピュータ先進国
- 著者
- 宍戸 周夫
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理 (ISSN:04478053)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.9, pp.934-935, 2001-09-15
- 被引用文献数
- 1
ACMが主催する世界の大学対抗プログラミング・コンテストで,日本の大学はなかなか上位にランクされない.中国,韓国,インドなどアジア諸国にも後塵を拝している.しかしその一方で,日本人はこうした国々の一歩先を行くコンピュータ先進国を自認している.
1 0 0 0 IR 中国宋代における茶の加工法の変化と闘茶
- 著者
- 宍戸 佳織
- 出版者
- 早稲田大学人間科学学術院
- 雑誌
- 人間科学研究 (ISSN:18800270)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.2, pp.153-167, 2005
Tea from all over the world belongs to the same species, "camellia sinensis" and is classified according to differences in processing methods. In China, the country of origin for tea, the habit of drinking tea spread widely during the Song Dynasty (960-1279). During this era, valuable tea was Gong cha (Tribute tea: for offering to the Imperial court), in particular, Fanning tea (solid tea) derived from Pian cha in the Tang Dynasty was used. During the Song Dynasty, tea competitions further increased the popularity of tea among the general population. This gradual change in fashion may be considered as one of the factors responsible for the increased processing of tea during this era. The present research investigates the production, processing, and distribution of tea as depicted in literature, including pictures and statistical records, from the Song Dynasty. In addition, the relationship between competition and processing of tea is discussed. (Waseda Journal of Human Sciences, 18 (2) : 47-61, 2005)
研究目的で日本に留学している学生・研究者の数は年々増加し全国で約10万人に達しており,その出身の国・地城や民族も多様化している。家挨同伴の留学も増加しており,その子育てに対する支援は,留学生本人に対する支援とともに,国際交流の重要な一環を構成している。本研究では,大学関係の保育園について現状と問題点を明らかにすることを主要な日的とした。調査対象として取り上げた保育所は,最初教職員組合による共同保育所として設立され,認可保育所へと展開してきた歴史を持っている。日本における保育運動の発展において先導的役割を果たした,この大学関保保育所の運動について関係各園の資料をもとにその意義と役割について詳細にまとめた。また,私立大学における保育所の実態についてその全てを網羅するには至らなかったが,主要な国立大学の保育所についてその原状と問題点を洗い出した。さらに,留学生支授という意味では大学内にある保育所以上に大きな役創を果たしている香推浜及び愛咲美保育国(福岡市)を対象に多様な視点から調査分析を行った。外国人留学生の子弟を多く受け入れている保育園では,日々さまざまな異(多)文化接触か行われている。次世代を担う子供達に対して実施されている国際理解を促進する手法の実態を明らかにし,そこで育っている子供達のみならず,受け入れた園の保育者及びそこに子どもを預けている外国人の親と日本人の親とが,それをどのように受け取り,自らの国際理解の深化に果たしている役割を明らかにし,その問題点と諸問題解決の支援組織の構築について検討した。こうした保育園で育った子供達自身が,その経験についてどのような意識を持っているか,又,その家族がどのような評価を下しているかなどについての分析が課題として残されている。
1 0 0 0 IR 関係のなかの「老い」 : 大都市郊外に生活する高齢男性の事例分析
- 著者
- 宍戸 邦章 シシド クニアキ Shishido Kuniaki
- 出版者
- 同志社社会学研究学会
- 雑誌
- 同志社社会学研究
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.21-41, 2003-03-20
研究論文(Article)
1 0 0 0 OA 近世の朝廷と賀茂に関する史料(御記・絵巻等)の研究と活用
- 著者
- 所 功 川北 靖之 黒住 祥祐 小林 一彦 宮川 康子 若松 正志 海野 圭介 山口 剛史 飯塚 ひろみ 石田 俊 今江 廣道 宇野 日出生 岸本 香織 京條 寛樹 久世 奈欧 (野村 奈欧) 嵯峨井 建 笹部 昌利 篠田 孝一 宍戸 忠男 末松 剛 土橋 誠 橋本 富太郎 松本 公一 村山 弘太郎 山本 宗尚 吉野 健一 米田 裕之 若杉 準治
- 出版者
- 京都産業大学
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2009
近世(江戸時代)の賀茂大社(上賀茂・下鴨両社)では、世襲の社家神職たちにより、朝廷と幕府の支援をえて、葵祭や社務が運営されてきた。私共は、その実情を伝える社家の記録や祭礼の絵巻などを、朝廷の御記や公家の日記などと照合しながら、相互関係の解明に努めた。その成果は、本学日本文化研究所の紀要や所報などに発表し、また本学図書館所蔵の賀茂関係絵巻などは大半をデジタル化し詞書(ことばがき)の解読も加えて貴重書アーカイブスに公開している。
1 0 0 0 観光概論
- 著者
- 宍戸学 [ほか] 著
- 出版者
- JTB総合研究所
- 巻号頁・発行日
- 2013
- 著者
- 宍戸 周夫
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理 (ISSN:04478053)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.5, pp.442-443, 1998-05-15
- 著者
- 原 耕平 河野 茂 門田 淳一 朝野 和典 平潟 洋一 前崎 繁文 中富 昌夫 浅井 貞宏 水兼 隆介 奥野 一裕 福島 喜代康 伊藤 直美 井上 祐一 小池 隆夫 大西 勝憲 大道 光秀 山田 玄 平賀 洋明 渡辺 彰 貫和 敏博 武内 健一 新妻 一直 柳瀬 賢次 友池 仁暢 中村 秀範 加藤 修一 佐田 誠 池田 英樹 板坂 美代子 荒川 正昭 和田 光一 原口 通比古 星野 重幸 五十嵐 謙一 嶋津 芳典 近 幸吉 瀬賀 弘行 関根 理 鈴木 康稔 青木 信樹 滝沢 敬夫 兼村 俊範 竹村 尚志 長尾 光修 濱島 吉男 坂本 芳雄 坂田 憲史 豊田 丈夫 大角 光彦 小林 宏行 河合 伸 酒寄 享 杉浦 宏詩 押谷 浩 島田 馨 佐野 靖之 荒井 康男 北條 貴子 小川 忠平 柴 孝也 吉田 正樹 岡田 和久 佐藤 哲夫 古田島 太 林 泉 宍戸 春美 松本 文夫 桜井 磐 小田切 繁樹 鈴木 周雄 綿貫 祐司 高橋 健一 吉池 保博 山本 俊幸 鈴木 幹三 下方 薫 川端 原 長谷川 好規 齋藤 英彦 酒井 秀造 西脇 敬祐 山本 雅史 小笠原 智彦 岩田 全充 斉藤 博 三木 文雄 成田 亘啓 三笠 桂一 二木 芳人 河端 聡 松島 敏春 副島 林造 澤江 義郎 高木 宏治 大泉 耕太郎 木下 正治 光武 良幸 川原 正士 竹田 圭介 永正 毅 宇都宮 嘉明 秋山 盛登司 真崎 宏則 渡辺 浩 那須 勝 橋本 敦郎 後藤 純 河野 宏 松倉 茂 平谷 一人 松本 亮 斎藤 厚 健山 正男 新里 敬 伊志嶺 朝彦 上地 博之 比嘉 太 仲本 敦 我謝 道弘 中島 光好
- 雑誌
- 日本化学療法学会雜誌 = Japanese journal of chemotherapy (ISSN:13407007)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.11, pp.901-922, 1997-11-25
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 19