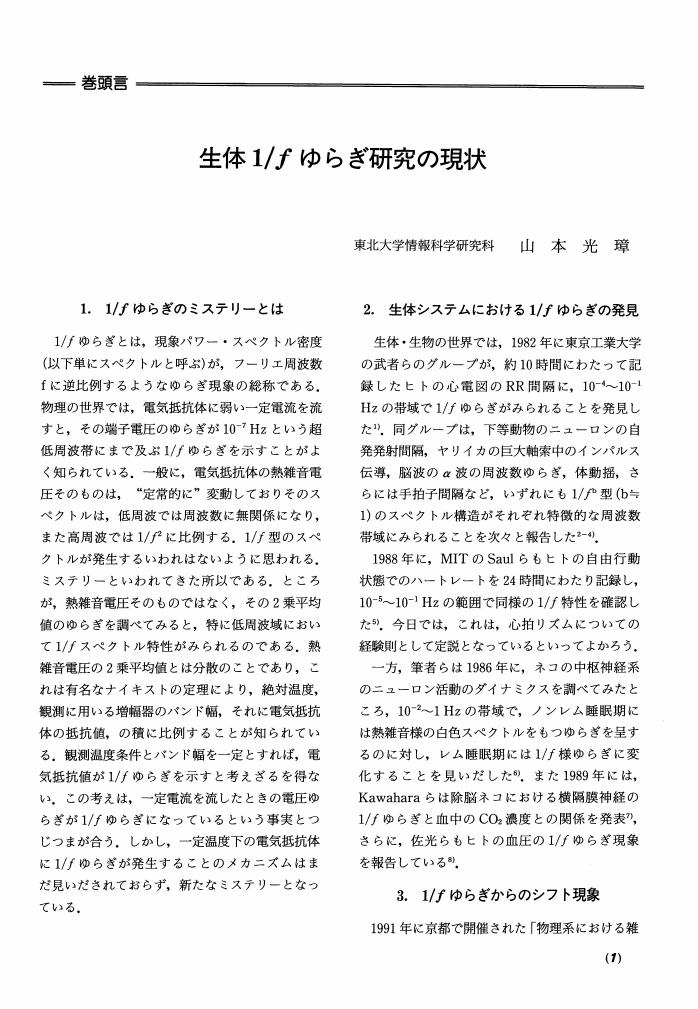109 0 0 0 OA [資料紹介] 永禄六年北国下り遣足帳
- 著者
- 山本 光正 小島 道裕
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.159-179, 1992-03-31
6 0 0 0 OA Deep Learningに基づく画像認識を用いた月および火星表面の擬似不自然構造物探索
- 著者
- 栗原 一貴 笹尾 和宏 山本 光穂 田中 秀樹 奈良部 隆行 國吉 雅人 会田 寅次郎 岡田 裕子 高須 正和 関 治之 飯田 哲 山本 博之 生島 高裕
- 雑誌
- エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2014論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, pp.223-224, 2014-09-12
本論文では,月および火星の衛星画像からあたかも知的生命体によって構築されたかのような構造物(擬似不自然構造物,pseudo-artificial structures)を自動検出する試みについて報告する.NASA Jet Propulsion Laboratory から公開されている観測データを対象として近年発展の著しいパターン認識手法である deep learning を採用し,顔認識技術として Deep Convolutional Network Cascade for Facial Point Detection,およびオブジェクト検出技術として 1000 種類の物体を検出可能な DeCAF (A Deep Convolutional Activation Feature for Generic Visual Recognition)を適用することで,興味深い結果を得た.
5 0 0 0 OA 生体1/fゆらぎ研究の現状
- 著者
- 山本 光璋
- 出版者
- 一般社団法人 日本生体医工学会
- 雑誌
- BME (ISSN:09137556)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.10, pp.1-4, 1994-10-10 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 23
4 0 0 0 OA 鉄道の発達と旧道への回帰 : 東海道を歩くということ
- 著者
- 山本 光正
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, pp.23-58, 1999-03-31
明治二二年に東海道線が開通すると、ほとんど同時にといってよいほど、人々は鉄道を利用するようになったと思われる。鉄道の出現により東海道の旅行も風情がなくなったという声が聞かれるようになるが、一方では鉄道は新しい風景を作り出したと評価する声もあった。しかし鉄道の是非とは関係なく、徒歩による長期の旅行を容認する社会ではなくなってしまった。鉄道旅行が当然のことになると、旧道特に東海道への回帰がみられるようになった。東海道旅行者には身体鍛錬を主とした徒歩旅行と、東海道の風景や文化を見聞しようとするものがおり、東海道を〝宣伝の場〟としても利用している。身体鍛錬の徒歩旅行は無銭旅行とも結びつくが、これは明治期における福島安正のシベリア横断や白瀬矗の千島・南極探検に代表される探検の流行と関連するものであろう。探検や無銭徒歩旅行の手引書すら出版されている。見聞調査は特に画家や漫画家を中心に行われた東海道旅行で、大正期に集中している。大正四年に横山大観・下村観山・小杉未醒・今村紫紅・同じ年に米国の人類学者フレデリック・スタール、年代不詳だが四~五年頃に近藤浩一路、七年に水島爾保布、七~八年頃に大谷尊由と井口華秋そして大正一〇年に行われた岡本一平を中心とする「東京漫画会」同人一八名の東海道旅行で一段落する。昭和に至り岡本かの子は短編『東海道五十三次』を発表するが、これは大正期における東海道旅行を総括するものとして位置付けられる。失われていくもの、大きく変りゆくものに対しては記念碑の如く回顧談的著作物が多く出版される。東海道線開通後旧東海道を歩くことが行われたのもこうした流れの中に位置付けることができるが、それだけでは理解しきれないものを含んでいた。さらに東海道旅行は昭和一〇年代の国威宣揚を意識した研究につながっていく。
3 0 0 0 OA レジリエンスを高めるダンスの有効性に関する研究 ―大学生および教員を対象として―
- 著者
- 髙橋 和子 山本 光
- 出版者
- 公益社団法人 日本女子体育連盟
- 雑誌
- 日本女子体育連盟学術研究 (ISSN:18820980)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.1-16, 2016 (Released:2016-05-31)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 2
レジリエンスは,困難な出来事を経験しても個人を健康へと導く心身の特性である。本研究は,大学生360名と教員200名にダンスを実施し,ダンスがレジリエンスを高める効果があるかを検討することを目的とした。心身の健康の指標は,レジリエンス尺度(精神的健康尺度・精神的回復力尺度)を用い,その解析を行うと共に,質的研究として,ダンス教材「新聞紙」の即興的な表現における自由記述分析を行った。その結果,次のことが明らかになった。①ダンス実習を通して「運動好き」「ダンス好き」「精神的健康」「精神的回復力」が肯定的に変容した。②「精神的健康尺度」は [憂鬱][集中力欠如][怒り][身体的症状]の4因子構造であり,「精神的回復力尺度」は[挑戦的][情緒不安定][感情コントロール]の3因子構造であり,各因子間に相関があった。③「精神的健康尺度」と「精神的回復力尺度」の各々の因子間においても,6つの因子間に相関が認められた。④大学生がダンス教材「新聞紙」で獲得した概念は,レジリエンスを高める要素と類似していた。以上のことから,レジリエンスを高めるダンスの効果が明らかになった。
3 0 0 0 IR 旅と関所--旅日記を中心としてみた庶民男子の関所通行
- 著者
- 山本 光正
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.p239-254, 1991-11
近世における関所の研究は,当然のことながら,幕府諸政策との関連で把えられている。大名統制や入鉄砲に出女に代表されるように,研究の大きな課題の一つは関所設置の目的や意義にある。こうした関所研究の傾向からみると,一般庶民男子の通行はその研究の中で占める位置は極めて小さなものである。一方庶民の旅という観点からみると,庶民男子の通行には,幕府の定めた通過方法とはかなり異なる点がみられる。庶民男子が旅をする場合,往来手形を持参し,手形の改めを受けるだけで関所を通行することができた。もしも手形を持参しない場合でも,取り調べの結果不審な点がなければ通行を許されていたことになっている。ところが旅日記をみると,しばしば関所――主に箱根関所――に手形を「提出」している記事がみられる。提出しているのは往来手形とは別のもののようである。このことを裏付けるように,やはり旅日記には旅の途中で手形を作成・発行してもらっている記述がよくみられる。特に多いのが江戸の旅宿である。東国の人々の多くは伊勢参宮の際江戸に入り,1~2泊して伊勢に向かうが,その際旅宿で手形の発行をしてもらっている。右のような関所手形についての幕府,関所側の記録は極めて少ないようである。このような関所手形について,かろうじて『箱根御関所日記書抜』に途中手形という名称で記されている。その内容も旅の途中での手形発行を禁じたものである。このような手形が自然発生的に成立したとはとても考えられない。恐らく何らかの理由により一時的にとった処置が,途中手形に姿を変え尾を引きずり,これを旅籠屋が利用したのであろう。いずれにせよ庶民男子が関所を通過する時,旅の途中で発行してもらった手形を関所に提出したことは事実として認めざるを得ない。The study of the barrier stations in the Early Modern Period has been, as a matter of course, understood in its relationship to the policies of the Tokugawa Shogunate, as typically seen in the control of the Daimyo (feudal lords), the bringing in of weapons, and women coming out (from Edo, where wives of Daimyo were kept hostage), one of the important subjects of studies lies in the significance of the establishment of barrier stations.Considering this leaning in the study of the barrier stations, passage by men of the common class receives little attention.On the other hand, from the viewpoint of the common people, the passage of barrier stations by men of the common class was considerally different from the manner stipulated by the Shogunate. When a man of common class went on a trip, he carried a traffic bill called "Orai-Tegata", and could pass barriers only on being checked for the bill. Even if he did not possess a bill, if he was not doubted in an interrogation, he would have been permitted to pass the barrier station.When reading travel diaries, however, I often find passages referring to the "filing" of a bill to a barrier station―mostly to that at Hakone. It seems to have been something different from the ordinary traffic bill. In support of these passages, other passages in travel diaries include descriptions of the preparation and issuance of bills during the course of a journey. This was most frequent in travellers' lodges in Edo.People in eastern Japan, on their way to the Ise Shrine, entered Edo and stayed there one or two days before continuing their journey again. At that time, they had the bill issued at their lodge.It seems these bills for passing the station were rarely described in the records of the Shogunate or barrier station. They are mentioned only as "Tochu-Tegata" (part-way bill) in a document called "Extract of Hakone Station Daily Report". The content of this document was a prohibition of the issuance of this type of bill in the course of a journey.It is unbelievable that such a bill came into being spontaneously. It is probable that a temporary measure, which had been taken for some reason, survived in the form of Tochu Tegata.In any case, it was an obvious fact that men of the common class filed a bill which was issued in the course of their trip, in order to pass a barrier station.
2 0 0 0 OA 製鋼スラグを利用した藻場再生技術における腐植物質の鉄溶出への影響
- 著者
- 山本 光夫 福嶋 正巳 劉 丹
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉄鋼協会
- 雑誌
- 鉄と鋼 (ISSN:00211575)
- 巻号頁・発行日
- vol.97, no.3, pp.159-164, 2011-03-01 (Released:2011-03-01)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 16 17
Barren grounds in coastal area are serious problems in Japan and throughout the world. Although several factors have been proposed to account for barren grounds, we have especially focused on lack of dissolved iron for restoring seaweed beds. It has been developed a method that the mixture of steelmaking slag and humus materials, such as composts, were supplied in seawater. A concentration of dissolved iron can be increased by using the method, since complexes, iron-humates, are produced from iron in steelmaking slag and humic substances in compost. In this study, we evaluated the effect of humic substances in this method for increasing dissolved iron concentration. A laboratorial iron elution test by using actual seawaters was attempted. Three kinds of samples for iron elution, only steelmaking slag, only humus materials, and a mixture of steelmaking slag and humus materials, were prepared. The change of iron concentration in each small tank had been monitored. We found that iron elution rate in the case of the mixture of steelmaking slag and compost was faster than that in the case of only steelmaking slag. Furthermore, it was expected that the characteristic of the structure of humic substances were related to increase iron elution from steelmaking slag. The mixture of steelmaking slag and humus materials was more effective not only for increasing iron concentration in seawater and but also for extending the life time of Fe elution.
- 著者
- 山本 光重 佐藤 智和 横矢 直和
- 出版者
- 一般社団法人映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会技術報告 (ISSN:13426893)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.9, pp.55-60, 2002-01-30
花火ショーの演出作業において,花火師は花火の打ち上げ位置,タイミングや音楽との同期などの多くの要素を決定する必要がある.しかし従来,花火師は危険性や金銭的なコストの問題から演出結果を視覚的に確認することができず,演出作業を円滑に行うことが困難であった.そこで,本研究では,効率のよい演出作業を実現するための花火演出支援システムを提案する.ユーザは計算機を用いて打ち上げ位置,花火の種類,打ち上げタイミング,音楽といった情報を入力し,演出作業を行う.演出結果は入力されたデータに沿って,花火の実写映像を利用して計算機上でシミュレートされ,モニタやHMD上に可視化される.これによって,花火師は効率よく作業を進めることが可能となる.
2 0 0 0 IR 警察官によるけん銃の発砲が違法とされた事例
- 著者
- 山本 光英
- 出版者
- 山口大学
- 雑誌
- 山口經濟學雜誌 (ISSN:05131758)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.207-226, 2000-01-31
2 0 0 0 趙良弼と元初の時代
- 著者
- 山本 光朗
- 出版者
- 京都大学大学院人間・環境学研究科
- 雑誌
- アジア史学論集 (ISSN:18835325)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.23-42, 2011-02
2 0 0 0 OA 画像認識と集合知に基づく月および火星表面の人面状構造物探索
- 著者
- 笹尾 和宏 高須 正和 関 治之 奈良部 隆行 山本 光穂 飯田 哲 山本 博之 栗原 一貴
- 雑誌
- エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2013論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, pp.324-329, 2013-09-27
本論文では,顔認識技術と集合知に基づき,主に月および火星表面から俗に「人面岩」とも言われる,人の顔の形をした構造物の探索について報告する.我々はBrightness Binary Feature をはじめとする複数の顔認識アルゴリズムを併用し,NASA が提供した膨大な月および火星表面の衛星画像から人面状構造物を検出した.さらに,検出した映像をユーザが鑑賞,レーティングし,質の良いものを抽出するアプリケーションを試作した.
2 0 0 0 営業活動支援のための情報提供の検討
- 著者
- 都築 涼香 大森 照夫 山本 光三 岡 紀子 杉山 典正 出口 哲也 仲 美津子 松原 智子
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.130-134, 2017-03-01 (Released:2017-03-01)
本研究は,新市場参入を検討している営業部隊のための効果的な情報分析に関するものである。下町ロボットと名付けられた仮想の会社は高感度加速度センサーを製造販売しており,これを武器に成長が期待される介護・支援ロボット市場へ参入するケースを想定した。加速度センサーの販売先として可能性が高い企業6社を選定し,具体的な営業活動をイメージしながら必要な情報を収集・分析した。本稿では,従前の情報分析の提供先としてあまり馴染みのなかった営業部隊に着目し,営業部隊の営業戦略支援のための具体的な情報提供手法について報告する。
- 著者
- 福岡 明 小山 悠子 福岡 博史 上田 恵里子 山本 光祥 貴田 晞照 吉村 ひろ子
- 出版者
- 国際生命情報科学会
- 雑誌
- Journal of International Society of Life Information Science (ISSN:13419226)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.170-175, 2003-03-01
〔目的〕外気功を含めたCAMを積極的に併用することによって、腫瘍の縮小を見た2例について報告する。〔症例I〕A.F.76才♂歯科医師結腸腫瘍自覚的症状無くB.D.0-ring Testにて下行結腸に腫瘍の共鳴あり。内視鏡検査、組織検査にて同部に2.5cm程度のTubular Adenoma(Group3)を確認。その後、約2ヶ月外気功を含めたCAMの併用後、腫瘍が約1cmに縮小し、内視鏡的切除を可能にした。〔症例II〕M.Y.59才♂医師転移性肝内腫瘍排便異常、体重減少を主訴。内視鏡検査にて、大腸悪性腫瘍(ClassV)、画像診断により肝への転移を認める。大腸腫瘍切除手術後、約9ヶ月間、化学療法を施行。その後、外気功を併用し、画像診断により、肝転移性癌腫瘍の縮小傾向良性化が認められた。〔症例III〕T.S.42才♂会社員脳動脈瘤1999年8月2日交通事故の後遺症にてMRI・脳血管造影により動脈瘤2ヶ所を認めた外気功の併用にて動脈瘤の縮小、血流の改善をみた。〔結論〕以上、外気功を併用し、経過良好の3症例について報告する。
1 0 0 0 OA 教育実習のエンゲージメントと教授・学習観の関連
- 著者
- 清水 優菜 山本 光
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.Suppl., pp.57-60, 2020-02-20 (Released:2020-03-23)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
本研究は,教員養成課程の大学生を対象に,小学校での教育実習前後における教授・学習観の変容,および教育実習のエンゲージメントが教授・学習観に与える影響を検討した.はじめに,実習前後での教授・学習観の変化について,実習後に構成主義的教授・学習観は高まるが,直接伝達主義的教授・学習観は低くなることが明らかとなった.次に,教育実習のエンゲージメントと教授・学習観の関連について,実習前の教授・学習観が実習後の教授・学習観に,実習エンゲージメントが実習後の構成主義的教授・学習観に正の影響を与えることが示された.また,実習前の構成主義的教授・学習観は,実習エンゲージメントに正の影響を与えることが示された.
1 0 0 0 OA 女真族の趙良弼一族の漢化(中国化)について
- 著者
- 山本 光朗
- 出版者
- 北海道教育大学
- 雑誌
- 北海道教育大学紀要. 人文科学・社会科学編 (ISSN:13442562)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.59-73, 2012-02
- 著者
- 水野 一枝 水野 康 山本 光璋 松浦 倫子 松尾 藍 岩田 有史 白川 修一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.7, pp.391-397, 2012
Eleven healthy male subjects slept from 13:30 to 15:30 under ambient temperature and humidity maintained at 29℃ and RH70%, using polyurethane foam mattresses (U) and camel mattresses (C). A polysomnography,skin temperature (Tsk), microclimate, bed climate, and subjective sensations were obtained. The rapid eye movement sleep (REM) in the first hour for the U significantly increased compared to that for the C. The leg, arm, and mean Tsks for the C significantly increased compared to those for the U during the later segment of sleep. The microclimate humidity significantly increased, while the microclimate temperature and bed climate significantly increased during the later segment of sleep. The subjective humid sensation and the requirement for decreasing the mattress temperature significantly increased in U compared to the C. These results suggest that bed mattress material can increase the subjective humid sensation and the requirement for decreasing mattress temperature by 1) increasing the bed climate and microclimate temperature and humidity, and 2) changing the REM distribution.
1 0 0 0 近世初期における将軍家御殿・御茶屋跡の考古学的研究
近世において将軍家(大御所・世子を含む)が旅行や外出する際の宿泊・休憩のために、御殿・御茶屋と呼ばれる施設がつくられていた。その用途は旅行用と遊楽用であり、前者には上洛・駿府往復・日光社参等があり、後者には鷹狩等の狩猟や湯治等がある。特に頻繁に外出・旅行を行った徳川家康・秀忠・家光が造営した御殿・御茶屋は関東から近畿にかけて約100ヶ所が史料上で知られている。わずかに残る施設絵図や廃止以降の村絵図等から、それが比較的単純な居館的な構造であったと判るが、中性以来連綿と続いてきた武士の居館の最末期の姿であるとともに、近世の武家屋敷へ繋がるものでもある。しかし、17世紀末までに廃止されたため関連史料が少ない上、近代以降に開発で遺跡も破壊されてきたために、実体の解明はほとんどなされていなかった。このため、本研究では、比較的遺跡の保存が良好である千葉御茶屋御殿跡の発掘調査を契機として、近世初期の将軍家御殿・御茶屋跡の史料を集成し、遺跡の現状調査を行うと共に、千葉御茶屋御殿跡・鴻巣御殿跡・浦和御殿跡の発掘を伴う遺跡の現地調査を実施した。遺跡全体を発掘調査できたのは、千葉御茶屋御殿跡だけであり、他の2ヶ所は部分的な調査にとどまったが、立地や規模の大小に違いはあっても、主として土塁・空堀による外郭施設内に簡単な書院造り風の建物群を中心とした諸施設が配置されているなど、共通性を有することが明らかになった。さらに、多数の施設が列記されている17世紀中葉(寛永年間)以降の御殿目録や御殿絵図と比較すると、17世紀初期の御殿等はより単純であることが判った。このことは、家光治下で御殿・御茶屋の大規模な修築が行われたことを暗示しており、近世史の分野でも文献史料や絵図資料と考古学資料との対比の必要性が明らかとなった。
1 0 0 0 IR サッカーにおける攻撃戦術尺度の作成と妥当性の検討 : レアルマドリードを対象とした分析
- 著者
- 武者 尚志 山本 光 清水 優菜
- 出版者
- 横浜国立大学大学院 教育学研究科
- 雑誌
- 教育デザイン研究 = Journal of education design (ISSN:18847285)
- 巻号頁・発行日
- no.9, pp.100-109, 2018-01
1 0 0 0 OA 新刊紹介: 徳仁親王著『水運史から世界の水へ』
- 著者
- 山本 光正
- 出版者
- 日本学術会議協力学術研究団体 交通史学会
- 雑誌
- 交通史研究 (ISSN:09137300)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, pp.90, 2019 (Released:2021-09-01)
- 著者
- 鳥居 修一 山本 光治 今村 康博 大嶋 康敬 有吉 剛治 田中 茂
- 出版者
- 公益社団法人 日本工学教育協会
- 雑誌
- 工学・工業教育研究講演会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, pp.178-179, 2010
- 被引用文献数
- 1