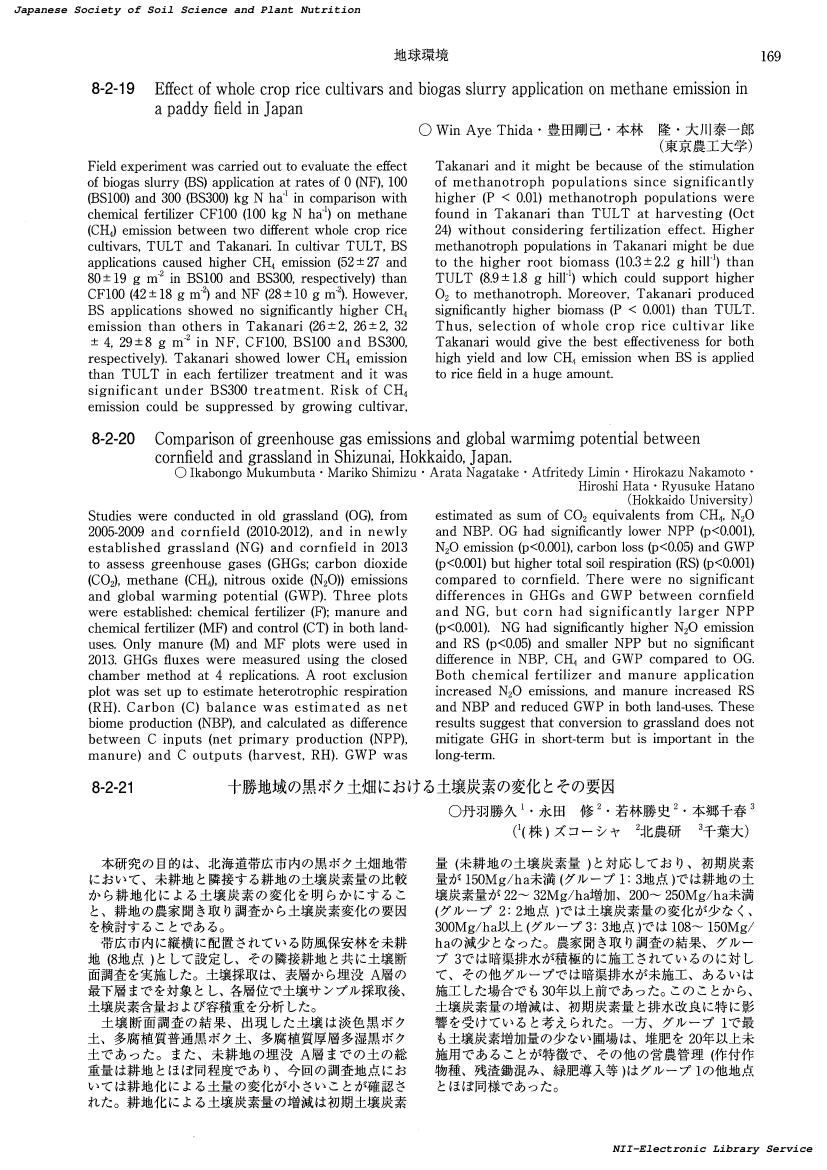1 0 0 0 OA 藤田嗣治の一九二〇年代末の壁画表現 : パリ日本館《欧人日本へ到来の図》の製作プロセス
- 著者
- 林 洋子
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.13-37, 2006-03-31
両大戦間の日本とフランスの間を移動しながら活躍した画家・藤田嗣治(一八八六―一九六八)は、一九二〇年代のパリで描いた裸婦や猫をモティーフとするタブローや太平洋戦争中に描いた「戦争画」で広く知られる。しかしながら、一九二〇年代末から一九三〇年代に壁画の大作をパリと日本で複数手がけている。なかでも一九二九年にパリの日本館のために描いた《欧人日本へ到来の図》は、画家がはじめて本格的に取り組んだ壁画であり、彼にとって最大級のサイズだっただけでなく、注文画ながら異国で初めて取り組んだ「日本表象」であった。近年、この作品は日本とフランスの共同プロジェクトにより修復されたが、その前後の調査により、当時の藤田としては例外的にも作品の完成までに約二年を要しており、相当数のドローイングと複数のヴァリエーション作品が存在することが確認できた。本稿では、この対策の製作プロセスをたどることにより、一九二〇年代の静謐な裸婦表現から一九三〇年代以降の群像表現に移行していくこの画家の転換点を考える。
- 著者
- 丹羽 勝久 永田 修 若林 勝史 本郷 千春
- 出版者
- 一般社団法人 日本土壌肥料学会
- 雑誌
- 日本土壌肥料学会講演要旨集 60 (ISSN:02885840)
- 巻号頁・発行日
- pp.169, 2014-09-09 (Released:2017-06-24)
1 0 0 0 OA 赤城山のマツに関する研究~枯れたクロマツ林に注目して~
- 著者
- 科学部所属 杉山拓、小林勇太、中澤颯、間仁田和樹
- 出版者
- 日本森林学会
- 雑誌
- 日本森林学会大会発表データベース 第125回日本森林学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.197, 2014 (Released:2014-07-16)
群馬県の県木はクロマツであり、かつては赤城山に広く植樹されていたが、多くが枯れてしまった。私たちは、枯れた原因について異なる説を聞いた。そこで、枯れた原因を探るとともに、マツがどのように減少し、今後はどうなるか、調べることにした。 まず、林業試験場などで聞き取り調査や文献調査を行うとともに、マツの現状を現地で確認し、現地で撮影した映像やwebからの情報をもとに、地図上に分布などを記録した。次に、過去の3つの現存植生図を用いて、どのように変化したか調べた。 聞き取り調査、文献調査の結果、赤城山では酸性雨が降っていたがマツの生育には影響しない程度であり、枯れた原因はマツクイムシが道管を破壊するためであると分かった。文献調査から、赤城山のマツ林は90年前と比べ、約90分の1まで面積が減っていたことが分かった。また、現地調査や現存植生図からは、かつては広い林も多くあったが、現在は数本が点在している場所が多くなっていることが分かった。 マツは現在も樹齢やマツクイムシの影響で枯れていくものがあるが、枯れる本数と植林本数がほぼ同じであり、マツクイムシの被害が抑えられれば、本数は増加していくと考えられる。
1 0 0 0 OA 柴犬における血漿中ビタミンC濃度
- 著者
- 林 海鷹 松井 徹 堀江 崇文 菱山 信也 藤瀬 浩 矢野 秀雄
- 出版者
- 日本ペット栄養学会
- 雑誌
- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.53-56, 2003-04-10 (Released:2012-09-24)
- 参考文献数
- 17
一般臨床上健康な48頭の柴犬から採血を行い,高圧液体クロマトグラフィーにより血漿中ビタミンC濃度を測定した。供試犬の年齢構成は1歳未満4頭,1-2歳12頭,2-5歳7頭,5-10歳12頭,10歳以上13頭であり,性の構成は,雄13頭,雌28頭,避妊雌7頭であった。血漿中ビタミンC濃度は年齢の影響を受けたが(P<0.001),性の影響および年齢と性の交互作用は認められなかった。1歳未満の柴犬は,1歳齢以上のイヌと比較し血漿中ビタミンC濃度が高かった(P<0.01)。一方,1歳齢以降では加齢に伴う血漿中ビタミンC濃度の変化は認められなかった。1歳齢以上の柴犬における血漿中ビタミンC濃度は7.00±1.10mg/L(平均±標準偏差)であり,1歳齢以上の柴犬における血漿中ビタミンC濃度の標準的な値は4.8-9.2mg/L(平均±2×標準偏差)程度であることが推察された。
1 0 0 0 OA 日中異文化接触場面における意識調査 : 中国人大学生の場合
- 著者
- 横林 宙世 羅 明坤
- 出版者
- 西南女学院大学
- 雑誌
- 西南女学院大学紀要 = Bulletin of Seinan Jo Gakuin University (ISSN:13426354)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.147-163, 2010-03-01
- 著者
- 秋田 喜代美 斎藤 兆史 藤江 康彦 藤森 千尋 柾木 貴之 王 林鋒 三瓶 ゆき 大井 和彦
- 出版者
- 東京大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 東京大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13421050)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.355-388, 2014
This paper is a brief review of our meta-grammar project with special emphasis on the meta-grammatical activities conducted in Japanese classrooms. The first section describes the research questions and research procedures of the project; the second section reviews the recent history of language education in China with reference to grammar teaching; the third section is an analysis of secondary-school Japanese students' response to the meta-grammar classes as seen in the questionnaire survey; the fourth section considers how teachers found the project by analyzing their answers to the questionnaire and discussions at teachers' meetings; the fifth section presents the teaching materials we actually used in the experimental classes and describes how they were used; and the sixth and final section, based on the discussion up to this point, suggests the way this project can make a great contribution to the curriculum development of language teaching at the level of secondary education in Japan.
1 0 0 0 OA プラスチックスの切削加工上の問題点
- 著者
- 小林 昭
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.155-161, 1960-02-20 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 9
- 著者
- 佐藤 功 小林 宏晨
- 出版者
- 日本評論社
- 雑誌
- 法学セミナー (ISSN:04393295)
- 巻号頁・発行日
- no.147, pp.14-18, 1968-06
1 0 0 0 OA 講演要旨 塩の道--とくに「古代製塩法」について
- 著者
- 大林 淳男
- 出版者
- 豊橋創造大学短期大学部
- 雑誌
- 研究紀要 = Bulletin of Toyohashi Sozo Junior College (ISSN:13427717)
- 巻号頁・発行日
- no.21, pp.79-86, 2004-03-15
1 0 0 0 OA 映像、音楽ビジネス等の著作権及び権利処理(含む二次利用、権利の集中化・管理)( 3 )
- 著者
- 梅林 勲
- 出版者
- 四天王寺大学
- 雑誌
- 四天王寺大学紀要 (ISSN:18833497)
- 巻号頁・発行日
- no.65, pp.313-345, 2018-03-01
1 0 0 0 OA 人工咽頭作製の試み
- 著者
- 三枝 英人 小野 卓哉 林 明聡 豊田 雅基 新美 成二 八木 聰明
- 出版者
- The Japan Broncho-esophagological Society
- 雑誌
- 日本気管食道科学会会報 (ISSN:00290645)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.4, pp.297-302, 1997-08-10 (Released:2010-02-22)
- 参考文献数
- 14
The treatments for patients with severe dysphagia and misdeglutition are very difficult. Some cases must have total laryngectomy or tracheo-esophageal separation to control their severe misdeglutition and prevent serious respiratory distress. However, in such cases, the phonatory function has to be sacrificed, resulting in a poor quality of life.In order to overcome this conflict between deglutition and phonation, we have developed an “artificial pharynx.” The artificial pharynx consists of a soft balloon and a plastic tube. The soft balloon is attached to a tube with an inlet hole. The whole assembly can be inserted through the patient's nose. The tip of the tube remains in the stomach and the balloon is inflated at the level of the pharynx to seal the airway. Our patient could breathe through a tracheal stoma which was created prior to using the artificial pharynx. The bolus was introduced through the inlet hole into the tube and moved down to the stomach by gravity. When the balloon was deflated, the patient could breathe and phonate with a speech valve of the cannula.We treated a patient using an artificial pharynx. He was a 62 years old male diagnosed as having terminal myotonic dystrophy and suffering from severe dysphagia. Because of his poor general condition, any surgical intervention for dysphagia and misdeglutition could not be performed without a tracheotomy. But, since he yearned to take some drinks and to preserve his phonatory function, the artificial pharynx was utilized with some success.
- 著者
- 篠﨑 聡 小林 泰俊 林 芳和 坂本 博次 レフォー アラン 瓦井 山本 博徳
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.6, pp.1272-1281, 2019 (Released:2019-06-20)
- 参考文献数
- 30
【背景と目的】大腸ポリープに対する内視鏡的切除において,熱凝固を加えないでスネアで切除するコールドスネアポリペクトミー(CSP)と熱凝固を加えながらスネアで切除するホットスネアポリペクトミー(HSP)の比較研究がなされてきた.CSPとHSPの有効性と安全性をシステマティックレビューとメタ解析を用いて評価した.【方法】大腸ポリペクトミーに関してCSPとHSPを比較したランダム化比較研究(RCT)のみを解析の対象とした.評価項目は,完全切除率,ポリープ回収率,遅発性出血率,穿孔率および所要時間である.Mantel-Haenszel random effect modelを用いてpooled risk ratio(RR)と95%信頼区間(CI)を算出した.【結果】8つのRCT(症例数1,665名,切除ポリープ3,195個)に対しメタ解析を行った.完全切除率において,CSPとHSPは同程度であった(RR 1.02,95%CI 0.98-1.07,p=0.31).ポリープ回収率もCSPとHSPは同程度であった(RR 1.00,95%CI 1.00-1.01,p=0.60).遅発性出血率は,統計学的有意差を認めなかったもののHSPのほうがCSPより多い傾向にあった(症例単位:RR 7.53,95%CI 0.94-60.24,p=0.06,ポリープ単位:RR 7.35,95%CI 0.91-59.33,p=0.06).すべてのRCTで穿孔は報告されなかった.大腸内視鏡時間はHSPでCSPより有意に長かった(平均差 7.13分,95%CI 5.32-8.94,p<0.001).ポリペクトミー時間もHSPでCSPより有意に長かった(平均差 30.92秒,95%CI 9.15-52.68,p=0.005).【結論】今回のメタ解析ではHSPと比較してCSPで所要時間が有意に短かった.また,遅発性出血率もHSPと比べてCSPで低い傾向にあった.したがって,小さな大腸ポリープに対するポリペクトミーにおいてCSPを標準的治療として推奨する.
- 著者
- 矢部 邦明 林 泰弘
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌) (ISSN:03854213)
- 巻号頁・発行日
- vol.138, no.2, pp.175-182, 2018-02-01 (Released:2018-02-01)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1 3
This paper presents an evaluation of economical capacity of storage batteries equipped with residential PV systems. In around 2019, many of power companies' ten-year contracts with PV system owners will come to expire, pushing down the selling price of PV generated energy. This, if combined with a declining battery price, would make it more economical to self-consume PV generated energy than selling the electricity to the utilities. The authors explore the optimized storage battery capacity and charge-discharge pattern by using load and PV output data of 200 houses, and by linear programming. Results show 5.8kWh battery is suitable for an average house with 4.5kW PV system when the battery system price is about ¥60,000/kWh. The authors analyze the daily storage start timing's impact on reverse power which affects power system operation, the optimum combination of PV and battery capacity, and each house's deciding factors for optimum storage capacity and so on.
1 0 0 0 蓄電池による太陽光発電出力の自家消費増加の経済性評価
- 著者
- 矢部 邦明 林 泰弘
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌) (ISSN:03854213)
- 巻号頁・発行日
- vol.139, no.5, pp.363-371, 2019-05-01 (Released:2019-05-01)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 6
This paper presents economic evaluation of storage battery systems which increase the self-use of PV output at houses and buildings. The selling price of PV generated energy is decreasing. Battery energy storage systems (BESS) can increase the self-use of PV output, and decrease the volume of buying electric power. So, the introduction of BESS to houses and buildings equipped with PV systems will be economical when the price of BESS is decreased enough. Authors investigated the optimum BESS capacity and hourly charge-discharge pattern for a year, then evaluated annual cost. Daily load pattern of each house and building, and time-of-use electric rates affect the conditions to make BESS cost-effective. Such conditions are shown in this paper.
1 0 0 0 OA リチウムイオン蓄電池の経済性推定モデルの検討
- 著者
- 有馬 理仁 林 磊 福井 正博 島田 幸司
- 出版者
- 一般社団法人 エネルギー・資源学会
- 雑誌
- エネルギー・資源学会論文誌 (ISSN:24330531)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.3, pp.11-20, 2018 (Released:2019-02-08)
- 参考文献数
- 19
The penetration of renewable energy is advanced to implement low-carbon society. Especially the increase of the photovoltaic generation energy is remarkable. But as a result, the trend that net electricity demand is decreased in the daytime and is increased suddenly in the evening, which is called ‘Duck-Curve phenomenon’ become apparent, and the destabilization of the utility grid caused by the fluctuation of photovoltaic generation power output. To solve this problem, the virtual power plant is planned as one of the solutions, and the battery aggregation using the distributed and cooperated rechargeable batteries is considered as one of the technical elements. One of the strong candidate of rechargeable battery is lithium ion batteries. To maximize the profit of the battery aggregation, it is necessary to diagnose the degradation in real time and estimate the cost effectiveness of lithium ion batteries. We found the convenient technique of diagnosis which can be done under operation of lithium ion batteries and battery management systems. To contribute to optimum system operation of the distributed and cooperated rechargeable batteries, we propose a new cost effectiveness index of lithium ion batteries based on this technique.
1 0 0 0 OA 化粧秘訣美人になるまで
1 0 0 0 OA イスラーム契約におけるリスク分担のシャリーア適合性
- 著者
- 中野 秀俊 大西 正光 小林 潔司
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.4, pp.227-244, 2014 (Released:2014-12-19)
- 参考文献数
- 30
建設プロジェクト契約には多くの不確実性やリスクが介在する.イスラム法を意味するシャリーアは,不確実性に関わるガラールやマイスィルを禁止する.したがって,プロジェクトに関わる契約は,契約内容によってシャリーアに抵触する危険性を含む.シャリーアに準拠したプロジェクト契約を遂行する場合,契約マネジメントにおける不確実性への対処方法のシャリーア適合性が重要な課題となる.現在のところ,イスラームにおけるシャリーア適合性に関して厳密な定義や普遍的な法解釈が存在するわけではない.また,地域によって適合性の解釈に多大な多様性が介在する.本研究では,プロジェクトに関わる完備契約を対象として,契約のシャリーア適合性を判定する理論モデルを提案し,典型的な契約スキームのシャリーア適合性について考察する.
1 0 0 0 OA 「鎌倉の海」における環境美化活動の現状と課題
- 著者
- 中西 悠 林 宙生 浮貝 侑弥 西田 駿 治田 祐輝
- 出版者
- 愛知教育大学地理学会
- 雑誌
- 地理学報告 (ISSN:05293642)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, pp.141-147, 2017-12-25
- 著者
- 山田 貴之 寺田 光宏 長谷川 敦司 稲田 結美 小林 辰至
- 出版者
- 一般社団法人 日本理科教育学会
- 雑誌
- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.219-229, 2014-07-08 (Released:2014-08-22)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
本研究の目的は, 児童自らに変数の同定と仮説設定を行わせる指導が, 燃焼の仕組みに関する科学的知識の理解と, 燃焼現象を科学的に説明する能力の育成に与える効果について明らかにすることである。この目的を達成するために, 第6学年「ものの燃え方と空気」において, “The Four Question Strategy”に基づく「仮説設定シート」(4QS)を用いた実験群37人と, 用いなかった統制群37人を対象とした授業実践及び学習前後の質問紙調査の分析を行った。その結果, 実験群の方が, 燃焼の仕組みに関する科学的知識を高い水準で理解し維持できることが明らかとなった。また, 燃焼現象を科学的に説明する能力の育成にも有効であることが示唆された。
- 著者
- 栗原 淳一 益田 裕充 濤崎 智佳 小林 辰至
- 出版者
- 一般社団法人 日本理科教育学会
- 雑誌
- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.19-34, 2016-07-12 (Released:2016-08-09)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 3 3
本研究は, 中学校第3学年の「月の満ち欠け」と「金星の満ち欠け」の学習において, 地球と天体の位置関係を作図によって位相角でとらえさせる指導が, 満ち欠けの空間認識的な理解と満ち欠けを科学的に説明する能力の育成に与える効果について明らかにすることを目的とした。そこで, 実験群では地球と天体の位置関係を作図によって位相角でとらえた後に, 満ち欠けの現象を説明する仮説を立てさせて, モデル実験で検証させた。一方, 統制群では作図を行わせないで, 同様の学習に取り組ませた。そして, それぞれの群の満ち欠けの空間認識的な理解度と科学的に説明する能力を質問紙調査によって比較検討した。その結果, 統制群に比べ, 実験群の方が満ち欠けの空間認識的な理解度が有意に高かった。また, 満ち欠けを科学的に説明できる生徒も有意に多かった。このことから, 作図によって地球と天体の位置関係を位相角でとらえさせる指導は, 満ち欠けの現象を空間認識的に理解させたり科学的に説明したりする能力の育成に有効であることが示唆された。