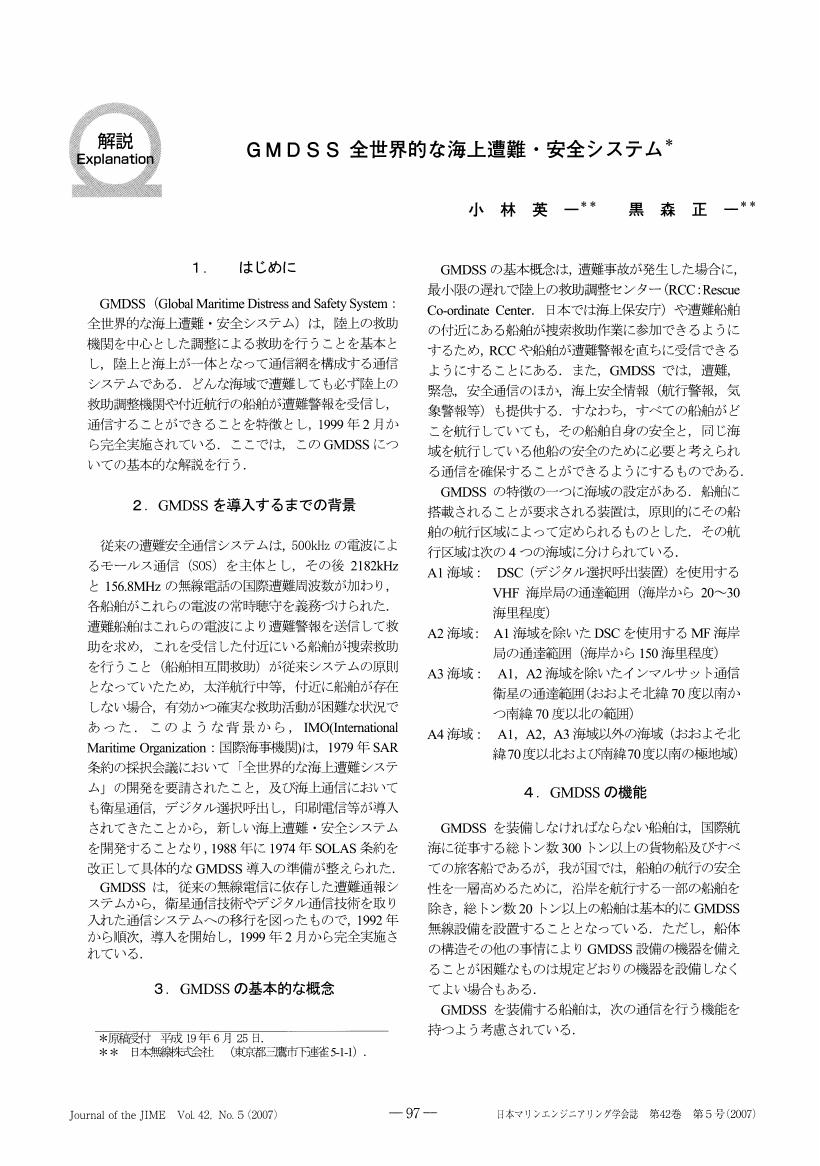- 著者
- 山田 哲雄 倉沢 新一 笠原 久弥 林 淳三
- 出版者
- 日本食生活学会
- 雑誌
- 日本食生活学会誌 (ISSN:13469770)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.23-33, 1996-03-31 (Released:2011-01-31)
- 参考文献数
- 62
本研究は, エネルギー1, 000kca1当たりの栄養素摂取量を維持する食事条件下での5日間の運動 (1時間または2時間/日) 時におけるナトリウム (Na), カリウム (K), カルシウム (Ca), マグネシウム (Mg) およびリン (P) 出納の変動を検討するために行われた.健康な男性5名が被験者となった. 実験は6日間の安静期に続くおのおの5日間の第1運動期および第2運動期から構成された.運動期には, 60%V02maxを目標強度とした自転車エルゴメーターによる60分間 (第1運動期) または120分間 (第2運動期) の運動が負荷された.付加エネルギー摂取量は, 付加運動によるエネルギー消費量に応じて計算された.安静期のレベルを上回るNa, K, CaおよびMgの汗中排泄量の増加分は, これらの摂取量の増加分を下回った. 尿中排泄量の減少によるNaとPの体内保留が観察されたが, K, CaおよびMgの出納は変化しなかった. 尿中アルドステロン排泄量と血清副甲状腺ホルモン (PTH44-68) は, わずかに増大した. 以上のことから, 運動時におけるエネルギー1, 000kca1当たりの栄養素摂取量を維持する食事方法がこれらの無機質については理にかなっていることが示唆された.
1 0 0 0 OA 最近の地震による斜面災害の傾向
- 著者
- 小林 芳正
- 出版者
- The Japan Landslide Society
- 雑誌
- 地すべり (ISSN:02852926)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.30-38, 1980-06-30 (Released:2011-02-25)
- 参考文献数
- 23
The causes of the casualties in the off-Izu-Peninsula earthquake 1974, the near-Izu-Oshima earthquake 1978 and the off-Miyagi-Prefecture earthquake 1978 are investigated and it revealed that the importance of slope hazards has increased remarkably in recent times. Slope hazards classified into those in cuts and fills for hig hways, those in newly developed residential lands and those in almost natural slopes are discussed. It is poin ted out that a more careful planning and designing is desirable not to increase hazard potential unreasonably, and also that an administrative control is necessary in locating various projects or in other respects where technical improvement at present is difficult. Further progress in recognizing slopes with high hazard potential is desirable for minimizing hazards in natural-slopes.
1 0 0 0 短歌と俳句
- 著者
- 渡辺順三, 栗林農夫 著
- 出版者
- 青木書店
- 巻号頁・発行日
- 1955
1 0 0 0 IR 日英地域社会比較文化論
- 著者
- 小林 照夫
- 出版者
- 関東学院大学[文学部]人文学会
- 雑誌
- 関東学院大学文学部紀要 (ISSN:02861216)
- 巻号頁・発行日
- no.113, pp.147-168, 2008
「神戸淡路大震災」、「中越地震」と言った大地震をはじめ、日本の各所では大小の地震が発生している。一部の地震学者が言うように、日本は「地殻大変動の時代に入った」のではないかと、危機感を抱いている人も多い。そうした状況を反映して、昨今の町内会の課題は、「自主防災」にあると言っても過言ではない。勿論、それは、地震の脅威に対する地域社会の取り組みであるが、その背景では、NPO「帰宅難民の会」の誕生をみると、戦後の郊外住宅団地の造成に伴う日本的職と住の遠隔地化による震災時の危機感が、強く作用しているように思える。そこで、本稿では、同一コミュニティ内での職住一体化乃至は近接のタウンづくりが現在でも都市構造の本質をなしている英国の都市の歴史を検証しながら、日英地域社会比較文化論と題して、コミュニティの在り方について言及を試みることにした。
- 著者
- 宗廣 孝継 小林 潤一 吉田 満 松岡 順一 上田 芳信 開沼 聡
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告 = IEICE technical report : 信学技報 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.113, no.257, pp.53-57, 2013-10-22
通信やレーダ用途において,フェーズドアレー方式のシステムが検討されている.この方式では,指向性の高い電磁波ビームを形成するため,アレー素子の小型化と高出力化,高効率化の要求がある.そこで,これらの要求を同時に満たす増幅器として,フェーズドアレーレーダシステムへの応用を念頭に置いたMPM(マイクロ波増幅モジュール)に適する9〜10GHzの周波数範囲で高周波出力800W以上,総合効率41%,寸法20mm(W)×20mm(H)×213mm(L),質量0.4kgのミニTWT(小型進行波管)を開発したので報告する.
- 著者
- 影山 隆之 藤井 沙織 小林 敏生
- 出版者
- 公益社団法人 日本産業衛生学会
- 雑誌
- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.Special, pp.685, 2006-05-09 (Released:2017-10-05)
1 0 0 0 レシピメタデータに基づく料理動画の共有法
- 著者
- 槙野 理恵 和泉 憲明 小林 一郎 橋田 浩一
- 出版者
- 社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.138-138, 2008
レシピ動画を適切に組み合わせて再生するために,本稿では,既存のレシピを組み合わせ可能な工程に分割し,各工程の成果物の型をメタデータとして分割したレシピに付与する.そして分割したレシピの組み合わせ方を問題解決プロセスとしてモデル化することで,個人化したレシピに応じた動画を合成する.
1 0 0 0 OA GMDSS全世界的な海上遭難・安全システム
- 著者
- 小林 英一 黒森 正一
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.5, pp.858-863, 2007-09-01 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 OA ヨーロッパでのリヨセル繊維事情
- 著者
- 奥林 里子
- 出版者
- 社団法人 繊維学会
- 雑誌
- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.P_79-P_82, 2006 (Released:2006-05-01)
1 0 0 0 海面水温温暖化実験による淀川流域を対象とした台風の降水影響評価
2013年9月,台風第18号が日本に上陸し,近畿地方においては,淀川水系の桂川や宇治川などが氾濫し,京都府,滋賀県を中心に大規模な浸水被害が生じた.日本は地形的に洪水災害が発生しやすくなっており,突発的な豪雨に備えた防災体制が必要であると考えられる.本研究は,淀川流域における将来的な大雨の影響評価を行うことを目的とし,最新のメソ気象モデルであるWRFを用いて,平成25年台風第18号による大雨の再現実験と温暖化差分を加算した海面水温を境界値とする海面水温温暖化実験を行う.本来温暖化の影響を厳密にシミュレーションするためには,気温,水蒸気量,気圧などのあらゆる諸物理量の気候変動の影響を考慮した擬似温暖化実験の手法が用いられるべきという報告がある.しかし,今回は海面水温の上昇だけを考えた海面水温温暖化実験を行うことにより,海面水温の変動がもたらす影響を定量的に評価することとした.本研究で行った実験では,海面水温を上昇させると時間降水量,積算降水量ともに大きく増加した.このことから,将来的な台風第18号を超える大雨の発生を想定し,河川計画の策定なども含めた防災体制を整える必要があると考える.
1 0 0 0 OA 当院における周術期口腔機能管理患者の口腔内状況および介入効果
- 著者
- 小林 義和 松尾 浩一郎 渡邉 理沙 藤井 航 金森 大輔 永田 千里 角 保徳 水谷 英樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年歯科医学会
- 雑誌
- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.69-78, 2013-09-30 (Released:2013-10-18)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 3
近年,周術期口腔機能管理による全身合併症の予防効果が明らかになり,平成 24 年度から周術期口腔機能管理が保険診療報酬としても評価されるようになった。今回われわれは,周術期口腔機能管理(口腔管理)を行った患者における口腔内の特徴と,歯科的介入が肺炎予防に及ぼす影響を明らかにすることを目的に,当院で平成 24 年の 1 年間に口腔管理を行った患者 196 名について後方視的に調査した。原疾患への治療法や実施した歯科処置の内容について調査し,依頼の 82% を占めた上部消化管外科,心臓血管外科・循環器内科,耳鼻咽喉科,血液内科の上位 4 科においては,診療科によって口腔内状況や歯科治療に差があるか統計的に分析した。また,上部消化管外科から口腔管理依頼のあった 35 例(口腔管理群)を対象に,口腔管理を行っていない上部消化管外科手術症例(非口腔管理群)129 名と比較して,術後肺炎発症に差があるか検討した。歯科処置に関しては,どの診療科の患者に対しても歯周処置が多く実施されていた一方で,抜歯,義歯への対応は,耳鼻科,心臓血管外科・循環器内科の患者で有意に高かった。上部消化管手術後の肺炎発症率は,非口腔管理群では 7.8%(10/129 例)であったが,口腔管理群では 5.7%(2/35 例)と統計学的に有意に低かった(p=0.04)。 以上の結果より,周術期口腔機能管理の対象者では,何らかの歯科的介入が必要であり,また,依頼元の診療科ごとに口腔内の問題や対応に特徴が現れることが示唆された。さらに,周術期口腔機能管理が全身合併症の予防に効果的であることが改めて示唆された。
1 0 0 0 IR スラム街と難民キャンプの子どもたち
- 著者
- 林詳悟 山本達哉 全邦釘 林和彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学年次大会2018(神戸)
- 巻号頁・発行日
- 2018-06-20
筆者らはトンネル覆工コンクリートの点検効率化の取り組みとして,可視画像から得られるひび割れの長さや幅などの情報と,覆工表面の三次元形状からはく落の危険性を推定する手法の確立に取り組んでいる。本文は,ひび割れには発生原因によって,表面のひび割れ形状と,内部のひび割れ面の形状には密接な関係性があると考え,ひび割れ表面形状とひび割れ面に発生するせん断強度の関係を明示することで,ひび割れの形状から,はく落危険性を評価する手法を提案するものである。
1 0 0 0 OA EU-NATO関係の現在:ソマリア沖海賊対策作戦の事例を中心に
- 著者
- 小林 正英 Masahide KOBAYASHI 尚美学園大学総合政策学部 Shobi University
- 出版者
- 尚美学園大学総合政策学部総合政策学会
- 雑誌
- 尚美学園大学総合政策論集 = Shobi Journal Of Policy Studies,Shobi University (ISSN:13497049)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.19-32, 2017-12-25
EU-NATO関係は「死に体」と化していると言われる。そうであるとするならば、いつ、どのようにしてそうなったのだろうか。冷戦後、EUが安全保障政策分野に乗り出したことで、NATOとの競合の種は蒔かれていた。しかしながら、ベルリン・プラス合意策定によって競合は回避され、分業と協調の欧州・大西洋安全保障ガバナンスの枠組みが構築されるかに見えた。本論は、ソマリア沖海賊対策作戦に焦点を当てながら2008-2012年のEU-NATO関係の転機について分析するものである。
1 0 0 0 IR 三陸沖の海底地震計で観測された1968年十勝沖地震の前震現象
- 著者
- 南雲 昭三郎 小林 平八郎 是沢 定之
- 出版者
- 東京大学地震研究所
- 雑誌
- 東京大学地震研究所彙報 (ISSN:00408972)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.6, pp.1355-1368, 1969-03
1968年5月,三陸沖の微小地震活動を調べる目的をもつて三陸沖にて海底地震観測を行つていたところ,偶々1968年十勝沖地震(M=7.9)と称せられる地震が発生し,海底地震計はその本震の前数日間の前震現象を記録したことになつた.現在までの解析の結果,次のようなことが判明してきた.(1)5月11日から16日における前説の活動度は,観測点て観測された地震の中で30μkine以上の最大速度振幅を持つ地震の数の日別頻度で表わすと,約20ケ/day程度であつた.(2)この前震の地震活動変に1967年における相模湾,1957年の筑波等,他の地域の常時微小地震活動度にくらべて約10倍程度高いものである.(3)前震域は非常に広く,余震域の殆ど全域に対応しているようである.(4)これらの前震のある観測点て記録された地震動の最大振幅別頻度分布はベキ分布では表わすことが出来ない.これら微小地震の前震活動は,青森県東方沖から三陸沖にいたる日本海溝西側部において,1968年4月中旬以来統いている異常な地震活動と一連のものと考えられる.|While the ocean-bottom seismographic observation was being performed off Sanriku in May of 1968 in order to investigate the seismicity of micro-earthquakes of that area, the 1968 Tokachi-Oki Earthquake (M=7.9) happened to occur. The ocean-bottom seismographs have recorded foreshock phenomena during several days before the main shock.
1 0 0 0 OA 特集「物理学とAI」にあたって
1 0 0 0 透析導入時の腎性貧血に対し宗教的理由で輸血拒否した1例
- 著者
- 本城 保菜美 竹口 文博 加藤 美帆 林野 翔 長島 敦子 櫻井 進 渡邊 カンナ 宮岡 良卓 長岡 由女 菅野 義彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本透析医学会
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.6, pp.409-413, 2018 (Released:2018-06-28)
- 参考文献数
- 9
症例は61歳女性. 2型糖尿病およびそれに伴う慢性腎臓病のため通院していたが, 7か月前の最終外来以降, 治療を自己中断していた. 労作時呼吸困難, 食欲低下が出現し, 緊急入院時にはHb 6.0g/dLと高度貧血を伴う末期腎不全の状態だった. 本人のみ宗教上の理由により輸血を拒否していたが, 夫を含めて話し合いをした結果, 相対的無輸血治療に同意したため緊急透析導入した. 貧血に対して赤血球造血刺激因子 (ESA) 製剤であるダルベエポチンαの増量, 鉄補充療法を中心とした治療で管理可能であった. 血液透析患者の導入期にはESA抵抗性因子が多数存在するが, 緊急を要しない貧血であれば適切な治療により無輸血で管理可能であることが示唆された.
1 0 0 0 OA 腱板関節面不全断裂に対する手術療法: 鏡視下デブリードマンと腱板修復術の比較
- 著者
- 林田 賢治 米田 稔 岡村 健司 広岡 淳 脇谷 滋之 妻木 範行
- 出版者
- 日本肩関節学会
- 雑誌
- 肩関節 (ISSN:09104461)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.315-319, 1993-09-01 (Released:2012-11-20)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
To decide the appropriate treatment for articular-side partial rotator cuff tears (APRCT),31patients with arthroscopically documented APRCT were surgically treated and reviewed retrospectively. The mean age at time of operation was 31 years old (13-62) and the mean post-operative follow-up period was 22.5 months (12-66). APRCT was classified into three groups according to the depth of the cuff tear, the superficial tear (S-tear), the intermediate tear (I-tear), and the deep tear (D-tear).8 patients with a S-tear were treated by arthroscopic debridement of the lesion (S-tear &debridement group).23 patients had an I-tear.16 of them had an arthroscopic debridement of the lesion (I-tear & debridement group) performed of time, and 7 of them were treated by open repair procedure (I-tear & repair group).3 patients with a D-tear were treated by open repair procedure (D-tear & repair group). Arthroscopic or open subacromial decompression were simulteneously performed in all of the cases. The functional results were graded by Constant's shoulder rating scale (1987) which consisted of the evaluation of pain, function, range of motion, and strength of abduction. Clinical results were evaluated by the ratio of the rating scale; the involved side / the healthy side (%). Statistic significances were calculated by Student's t-test.According to the ratio of total clinical evaluation, the S-tear & debridement group was 99.3 +2.9%, the I-tear & debridement group was 97.4 + 4.4%, the I-tear & repair group was 87.3 + 7.7%, and the D-tear & repair group was 87.5 + 14.0%. There were no significant differences between the S-tear & debridement group to 2 and the I-tear & repair group to 4, but there was a significant difference between the I-tear & debridement group to the I-tear & repair group (p <0.01). The results of the strength of abduction were the S-tear & debridement group was 93.6 + 11.4%, the I-tear & debridement group was 98.4 + 18.7%, the I-tear & repair group was 78.6 + 11.2%, and the D-tear & repair group was 97.6 + 4.1%. A significant difference was also seen between the I-tear &debridement group to the I-tear & repair group (p <0.01).In this follow-up study, two things were clarified. Firstly, the clinical outcome of an arthroscopic debridement for APRCT was not influenced by the depth of a lesion with less than half of a rotator cuff thickness. Secondly, the arthroscopic debridement for an intermediate type APRCT with subacromial decompression provided a more favorable clinical outcome than did the open repair technique.
- 著者
- 幸村 貴臣 桐林 星河 永谷 圭司
- 出版者
- 公益社団法人 計測自動制御学会
- 雑誌
- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.2-12, 2017
- 被引用文献数
- 1
In order to perform surveillance missions in case of natural/human-caused disasters, all-terrain mobile manipulators are useful tools for rescue crews' safety. It has a capability to traverse on rough terrain, and to handle objects with the mounted manipulator. For example, the mobile manipulator “Packbot” opened a door in Fukushima Daiichi Nuclear accident in 2011. However, it is well-known that it requires a lot of skill for its teleoperation, particularly in case of missions in narrow and rough terrain. Based on our ex-researches, we found the following issues: (1) According to the rough terrain, the pose of the manipulator is not fitted with the inertial frame of reference, and it prevents an intuitive teleoperation. (2) In narrow areas, the manipulator contacts with the environment because of the lack of environmental information. (3) Communication delay makes more difficult for teleoperation. To solve the above issues, in this research, we implemented a base-altitude synchronous type master-slave controller for the issue (1), teleoperation system with vision and 3D information for the issue (2), and anti-communication-delay-system with 3D point cloud information for the issue (3). To evaluate the above system, we conducted some experiments with non-skilled operators. In this paper, we describe the above system implementation, and report the experimental results to evaluate the above system.