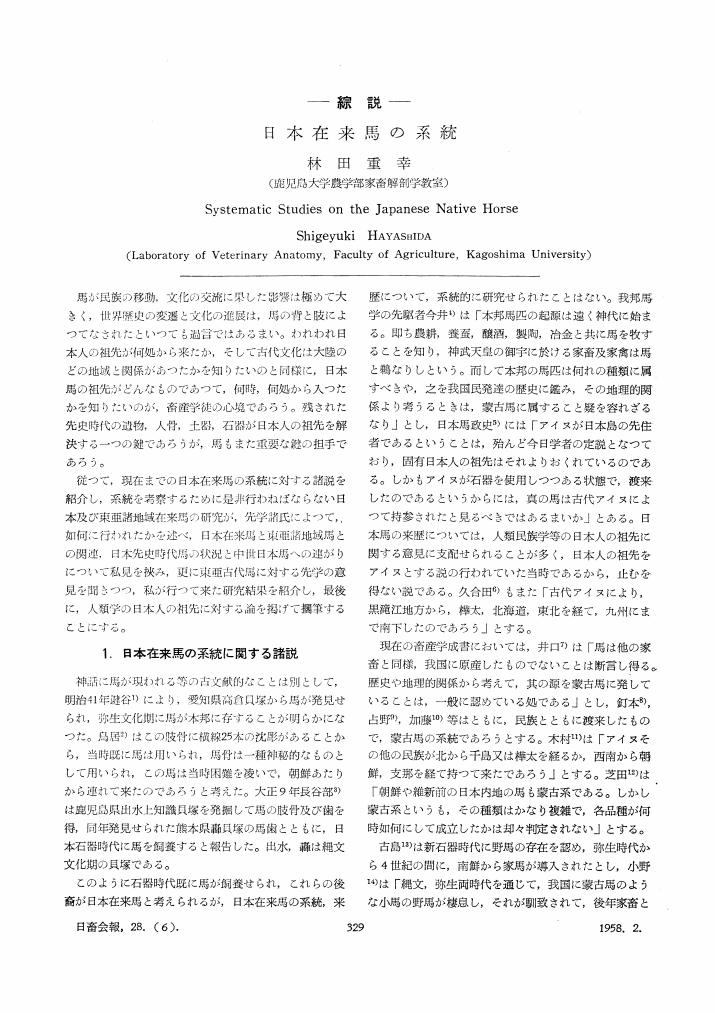1 0 0 0 OA 週1回8週間のサーキットトレーニングが大学生の体力および感情に与える影響
- 著者
- 内田 英二 神林 勲
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究 (ISSN:04846710)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.11-20, 2006 (Released:2008-01-25)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 2 4
This study was conducted to clarify the influence of circuit training carried out once a week on the mood state and physical fitness of college students. Thirty-five healthy college students (6 males, 29 females) participated. Students completed an exercise set consisting of six items, and repeated these in sets of three during physical education class once per week for 8 weeks. The effect of the training was evaluated by comparison of the maximal repetition (MR) values in the maximum score test (MST) carried out one week before and one week after a training period. Mood state was determined by Mood Check List-Short Form 1 (MCL-S.1), by which mood state is assessed as a pleasant feeling, a relaxed feeling, and a feeling of anxiety. The students made these assessments immediately before and 5 minutes after every exercise. The influence of the physical fitness level was assessed in female students with high TS values (HG, n=6) and in female students with low TS values (LG, n=6). All of the MR values in the MSTs and the height of a vertical jump were increased significantly after the training period. The results of repeated measures ANOVA performed on data obtained from all of the students showed that the pleasant feeling score increased significantly after the exercise (p<0.05), whereas the relaxed feeling and the feeling of anxiety scores did not change. The mood state scores before and after exercise did not show a significant difference between the HG and the LG. The pleasant feeling scores for both groups were positive in both the HG and LG, indicating that the exercise resulted in a desirable mood state. These results showed that the circuit training program was effective for increasing the level of physical fitness and that it improved the pleasant feeling of individuals, regardless of their physical fitness level.
- 著者
- 中島 松一 小野 史郎 林 宏仁
- 出版者
- The Japanese Cancer Association
- 雑誌
- GANN Japanese Journal of Cancer Research (ISSN:0016450X)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.5, pp.411-416, 1974-10-31 (Released:2008-10-23)
- 参考文献数
- 25
Both humoral and cell-mediated immunity were suppressed by four intravenous injections of 100μg each of 4-hydroxyaminoquinoline 1-oxide, employing bacterial α-amylase and picryl chloride as antigens. Preimmunization of mice with diazotized 4-aminoquinoline 1-oxide-conjugated rabbit serum protein by the use of complete Freund's adjuvant prevented immunosuppression by 4-hydroxyaminoquinoline 1-oxide. Anti-hapten titers of these mice were 25 to 28 estimated by passive hemagglutination during the course of the experiments. Passive immunization by transfer of the specific anti-hapten antibody induced prevention from immunosuppression by the reagent. Therefore, it was suggested that the humoral anti-hapten antibody might play an important role in preventing mice from immunosuppression by the reagent by preimmunization with the hapten-carrier conjugate.
- 著者
- 鈴木 一平 竹林 純 梅垣 敬三
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.141-145, 2018-06-25 (Released:2018-07-21)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2
複数の化合物から構成される微量のビタミンを,一括して定量する際に微生物学的定量法(microbiological assay, MBA)が広く用いられている.MBAは試料溶液中ビタミン濃度と菌体の生育量の関係が通常シグモイドを描くため,一般的な直線回帰で求めた検量線では定量性に問題が生じる場合がある.そこで,本研究では乳児用調製粉乳中のビタミンB6定量をモデルケースとして,回帰モデルの選択(直線,2次,3次回帰モデルおよび4パラメーターロジスティックモデル(4PLM))が定量結果に及ぼす影響について検討した.その結果,4PLMに基づく検量線を用いることにより,試料溶液中のビタミン濃度が標準溶液の範囲を逸脱した際にある程度妥当な定量値を得ることができることから,信頼性の高いビタミンB6定量が可能となった.同様の結果はナイアシンの定量でも確認できた.以上の結果から,MBAにおいて4PLMに基づく検量線を用いることで,ビタミン定量値の信頼性向上が期待される.
1 0 0 0 OA マルチスケール精神病態の構成的理解
- 著者
- 林 朗子
- 雑誌
- 新学術領域研究(研究領域提案型)
- 巻号頁・発行日
- 2018-06-29
1 0 0 0 OA 日本在来馬の系統
- 著者
- 林田 重幸
- 出版者
- 公益社団法人 日本畜産学会
- 雑誌
- 日本畜産学会報 (ISSN:1346907X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.6, pp.329-334, 1958-02-28 (Released:2011-01-25)
- 参考文献数
- 74
1 0 0 0 滞在地の特徴量を利用した「特別な日」検索方式の検討
- 著者
- 林啓吾 原直 阿部匡伸
- 雑誌
- 第76回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, no.1, pp.459-460, 2014-03-11
ライフログとは,人間の行動をデジタルデータとして記録に残すことである.ライフログデータを用いて自分の行動を振り返ることを考える.例えば,現在広く普及しているSocial Networking Service(SNS)の過去の発言や写真を見返すことで,振り返りが可能であるが,それらに記録するのは自分の意志で記録したいと思ったことに限られてしまうという問題点がある.無意識に記録できるライフログデータの一つに,Global Positioning System (GPS) による位置情報データ(GPS データ)があげられる.本研究では,GPSデータから得られる滞在地の特徴量を利用し,振り返りたいと感じる「特別な日」を検索する方式を提案した.評価実験により,提案方式で「特別な日」が高い精度で検索可能であることが示された.
- 著者
- 栗林 睦美 野﨑 美保 和田 充紀
- 出版者
- 富山大学人間発達科学部
- 雑誌
- 富山大学人間発達科学部紀要 = Memoirs of the Faculty of Human Development University of Toyama (ISSN:1881316X)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.135-149, 2018-03-16
本研究では,知的障害者の学校卒業後が豊かで充実したものとなるためには,卒業前にどのような取組が求められているのかについて検討することを目的として,就労・生活・余暇の視点で卒業生の保護者を対象とした実態調査を行った。就労では人間関係・コミュニケーションなどで困難はあるが,職場の人が相談相手となることで,就労の安心充実につながっている現状がうかがえた。生活や余暇については家族と一緒にすごし,困難には家族が対応している割合が高かった。「親亡き後の将来の生活への不安」や「家族とだけではなく友達や支援者と余暇を過ごすこと」「余暇のレパートリーを増やすこと」等の生活や余暇に対する課題も見出された。卒業後の長い生活を見据え「相談できる機関等の情報」「余暇に関する学習の機会」など,学校教育に求められることや取り入れていくべき内容についての示唆が得られた。
1 0 0 0 OA 強度行動障害を示す人の地域生活の取り組みについて考える
- 著者
- 荒川 哲郎 西野 貴善 野村 省吾 林 淑美 ARAKAWA Tetsuro NISHINO Takayoshi NOMURA Shougo HAYASHI Toshimi
- 出版者
- 三重大学教育学部
- 雑誌
- 三重大学教育学部研究紀要. 自然科学・人文科学・社会科学・教育科学・教育実践 = BULLETIN OF THE FACULTY OF EDUCATION MIE UNIVERSITY. Natural Science,Humanities,Social Science,Education,Educational Practice (ISSN:18802419)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, pp.145-155, 2018-01-04
- 著者
- 佐藤 陽治 江口 淳一 岩嶋 孝夫 久保田 秀明 岩本 淳 梅林 薫
- 出版者
- 学習院大学
- 雑誌
- 学習院大学スポーツ・健康科学センター紀要 (ISSN:13447521)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.1-26, 2003-03-31
According as the rally tempo is accelerated remarkablely in recent tennis the service stroke that carrys out a preemptive oppotunity to attack takes on acqire importance more than ever. The tactics on a conbination of the service in tennis consisites of two factors controling the ball that are the speed (pace) and the course (placement or direction) in order to attack and make the open court (space). The present study was designed to investigate the actual conditions of a conbination on the service speed by the male professional tennis players and to throw some light on the tactical effect of a conbination of the service speed. The service speed indicated with the apparatus set up in a corner of the court was taken note. The service speed of the all points for 6 to 9 consecutive service games by six players in three singles matches was recorded. The numerical value of service speed indicated the initial speed. Those three matches were played at the first and second round in Australia Open taken place in 2001. The courts of these three games were the center court (Rod Laver Arena) and the first court (Vodafone Arena). The numbers 8 (ATP ranking is 23 rd.), 9. (ditto 2 nd.) and 28 (ditto 6 th.) seed players were included in these three matches. The investigations yielded the following results. a) There is a significant correlationsip between the first service speed and the height of the players. b) Winners' ratio for gaining point started from the first service ratio are higher than losers. c) The maximum or mean first service speed of winners was rapider than one of lossers. d) The number 28 (ATP ranking is 6 th.)seed player (G. Rusedoski : GBR) who had a rapid first service of prominence among the players participating in the championships did not make frequent use of high speed first services, and made freely use of slow speed first services. e) The player who competed with the number 28 seed player also had high speed first services, maximum and mean speed of his firstservice were respectively 214 (km/h) and 192. 7 (km/h), he made however few use of slow first service, so that his services showed no combination and monotony of first services f) The number 8 seed and 23 rd. ATP ranking player (P. Sampras) had the rapidest mean 2 nd. service speed of significance and the amplitude of speed was also largest. g) A decline in successful ratio of first service developed a tendency to lead the game of confusion, strain and loss. h) There was no common trend in the first service speed of all six players under any point situations. Three players that had the high speed service showed however respective peculiarities of significance under some point situations. From these results mentioned above, following tactical knowledges were noted. As the point percentage from the first service is ordinarily higher than from the 2 nd. service, it is important to raise the ratio of first service for average players in first service speed, and especialy for smaller players. And it is more effectual to use a change-up first service and to make a show of the combination with various service speeds in oder to keep the service game for the players who can hit even high speed first services over 200 (km/h).
1 0 0 0 警察官が対応する精神科事例
- 著者
- 瀬戸 秀文 藤林 武史 松永 昌宏 吉住 昭 井本 誠司 松島 道人 國政 允
- 雑誌
- 病院・地域精神医学 = The Japanese journal of hospital and community psychiatry (ISSN:09104798)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.23-24, 1999-03-31
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 OA 酵素法による清酒の遊離脂肪酸の定量
- 著者
- 栗林 喬 金桶 光起 渡邊 健一
- 出版者
- Brewing Society of Japan
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.9, pp.624-631, 2012 (Released:2017-12-15)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
セルレニン耐性を指標としたカプロン酸エチル高生産酵母の育種方法は,日本醸造協会をはじめ,各県公設研究機関,酒造メーカーなどで幅広く利用されている。しかし本法による酵母を用いた吟醸酒は,カプロン酸によるオフフレーバーが問題となる場合もある。著者らは,カプロン酸エチル高生産酵母を用いた吟醸酒において総脂肪酸の大部分をカプロン酸が占めるという知見に基づき,酵素法によるカプロン酸の定量法を設定するとともに,本法がカプロン酸エチル濃度の推定にも有効であることを示した。製造現場でも利用できる簡易な方法なので,吟醸酒の品質管理の参考にしていただきたい。
自然状態下の土壌中では,液体水と水蒸気が局所熱力学的平衡状態にあると見なせることは既に確認されている(Milly, 1982).本報では,蒸発時には,土壌表面およびその近傍においても局所平衡が成り立つと見なせることが明らかにされる.この結果は,数値気象・気候モデルにおいて土壌表面の含水率から"表面湿度"を推定するために提案された多くの実験公式が,熱力学的平衡公式(本文式(7))に代わるもの(Lee and Pielke, 1992)ではなく,水蒸気の移動に対する抵抗の影響を強く受けた物理的意味の乏しい経験公式であることを示唆する.
- 著者
- 林 秀臣 米田 泰博
- 出版者
- 社団法人エレクトロニクス実装学会
- 雑誌
- エレクトロニクス実装学会誌 (ISSN:13439677)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.5, pp.366-369, 2005-08-01
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 4
1 0 0 0 OA ドイツ教養小説について
- 著者
- 林 久博 HAYASHI Hisahiro
- 出版者
- 名古屋大学大学院文学研究科
- 雑誌
- 名古屋大学人文科学研究 (ISSN:09109803)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.67-78, 2002-03
1 0 0 0 映像情報メディアに期待する
1 0 0 0 私の友人
- 著者
- 小林 信次
- 出版者
- 公益社団法人 全国大学体育連合
- 雑誌
- 体育・スポーツ・レクリエーション
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, 1975
1 0 0 0 IR 耶馬溪の墓 : 回顧録(二)
- 著者
- 上林 曉 カンバヤシ アカツキ 上林 暁 Kanbayashi Akatsuki
- 出版者
- 龍南會
- 雑誌
- 龍南
- 巻号頁・発行日
- vol.238, pp.64-68, 1937-10-30
1 0 0 0 IR ヒュームと「徳倫理学」
- 著者
- 林 誓雄 ハヤシ セイユウ Hayashi Seiyu
- 出版者
- 熊本大学
- 雑誌
- 先端倫理研究 : 熊本大学倫理学研究室紀要 (ISSN:18807879)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.44-64, 2018-03
In my book (Virtue in rugs, 2015), I insisted that Hume's moral theory could be read as a kind of virtue ethics. But, that might be an insufficient interpretation, because, at that time, I didn't have the exact criterion or definition of virtue ethics, so it can be thought that Hume's theory is included not within "virtue ethics" but within "virtue theory". Which category should be Hume's theory included within? Or what kind of virtue ethics (theory) is Hume's theory? In this paper, I explore and consider the criterion or definition of virtue ethics in some (neo-Aristotelian) virtue ethics. In the course of it, I try to make it clear that it is important to shed light on the conception of virtue, in order to answer those questions.
1 0 0 0 渥美半島における縄文時代後半の生活環境と生活様式
- 著者
- 林 哲志
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2003, pp.78, 2003
_I_.はじめに 愛知県の最南部に位置する渥美半島は、我が国では数少ない東西方向に伸びた半島である。半島の南側は太平洋で、暖流の黒潮が流れているため「常春の岬」と宣伝に謳われる。しかし、風が強く、特に冬期の北西風は体感気温を下げている。そして、ここには縄文時代の貝塚などの遺跡がいくつか展開している。渥美半島の3大貝塚(拠点貝塚)といわれる、吉胡貝塚・伊川津貝塚・保美貝塚の他、北屋敷貝塚・下地貝塚・八幡上貝塚・川地貝塚などが、おもに半島北側の三河湾に面した地域に分布している。この発表は、縄文時代の後半、後期・晩期と区分された時期の渥美半島における縄文人の生活環境や生活様式について考察するものである。そして、今回は主に、人骨出土数日本一といわれる吉胡貝塚の発掘データや周辺環境についてのフィールド調査の結果から、人々がどのような環境で生活を営んでいたか、「暮らし振り」をまとめてみたい。_II_.これまでの発掘調査の経緯吉胡貝塚の発掘は、大正11・12年の清野謙次による多数の縄文人骨発見にはじまり、昭和26年には文化財保護委員会と愛知県教育委員会による「国営発掘第1号」となる調査が行われた。その後、昭和55年に田原町教育委員会による遺跡の範囲を確定するための発掘が行われ、昭和58年には同じく町教委が貝層断面模型を作成するための調査が実施された。最近では、平成7・8年度に貝塚の北西側で区画整理事業にともなう調査が行われた。そして、平成13・14・15年度には史跡整備のための範囲確認調査が実施され、「現況地形」「貝塚範囲」「居住域」「当時の自然環境」「過去の調査区位置」「保存状況」の解明を進めている。以上のように、度重なる発掘調査ごとに報告書や論文などの文献が発行され、基礎データとして活用することができた。_III_.結果の概要今回の考察は、これまで考古学や人類学・民族学などの分野の研究者が行なってきた調査やそこから得られたデータを活用し、人文地理学的な見地から吉胡貝塚における「暮らし振り」をまとめたものである。それを列挙すると次のとおりである。_丸1_柱穴の遺構より、住居址はあったが集落が形成された根拠までは見出せない。_丸2_貝塚や墓があることから生活の場であったことは確実である。_丸3_段丘上は礫質の土壌であるため、柱が容易に建てられず、住居址は認められない。_丸4_貝塚が立地する背景に、河川と海の接点である干潟の存在があるが、吉胡においても汐川干潟が生活の舞台であった。_丸5_貝層の含有物より、人々の食生活は海・川・山(陸地)など周辺環境すべてに依存していた。_丸6_貝塚は段丘崖下に位置しており、そのあたりでは水利が良い。_丸7_段丘上と崖下では気候環境が異なり、前者は冬の季節風が強く、後者は夏の風通しが悪い。季節間の移住が考えられる。
- 著者
- 松尾 翔平 井川 大輔 宮本 幸典 齋藤 泰洋 松下 洋介 青木 秀之 野村 誠治 林崎 秀幸 宮下 重人
- 出版者
- 一般社団法人 日本エネルギー学会
- 雑誌
- 石炭科学会議発表論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.14-15, 2014
The fracture analyses for coke models reproducing the form of the non-adhesion grain boundaries were performed using the rigid bodies-spring model. The coke model was developed by the random arrangement of the coal particle polygons and expansion of the polygons based on experimental results. As a result, many springs at the gap or edge of the non-adhesion grain boundaries were fractured, and the arrangement and shape of the non-adhesion grain boundaries were supposed to affect the fracture of the coke. Furthermore, the coke with the larger blending ratio of the low-quality coal fractures with the weaker strength. This is because the number of the non-adhesion grain boundaries increases, and the size of the boundaries becomes larger and the shape of the boundaries becomes complex.