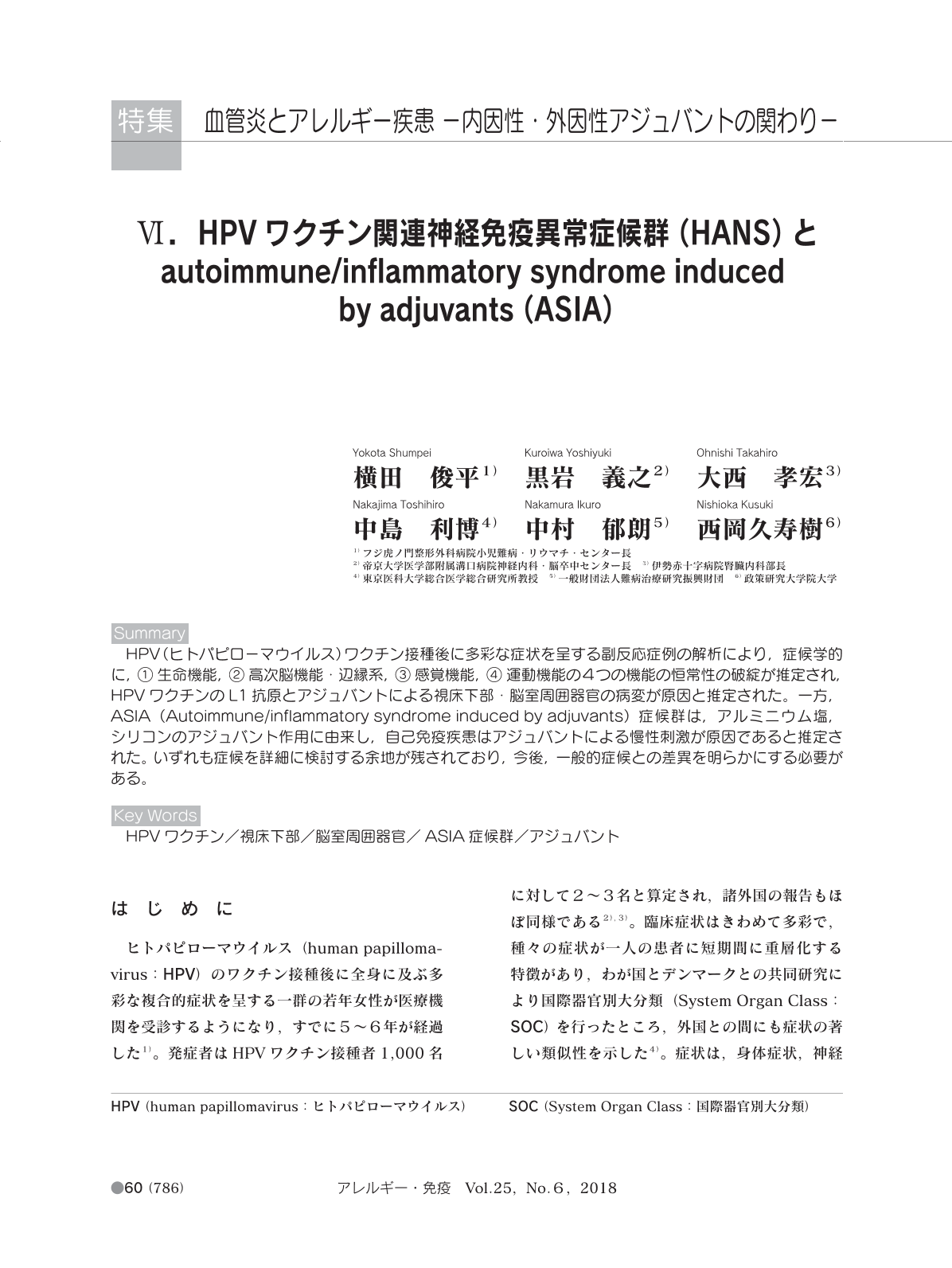42 0 0 0 OA 横浜市の小学生9万人を対象としたそばアレルギー罹患率調査 : 養護教諭へのアンケートから
- 著者
- 高橋 由利子 市川 誠一 相原 雄幸 横田 俊平
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.26-33, 1998-01-30 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
そばアレルギーは蕁麻疹, 喘鳴, 呼吸困難などアナフィラキシー型の反応を呈する頻度が高く, 注意深い対応が必要である疾患であるが, その羅患率は明らかではない.今回横浜市の全小学校341校の養護教諭にアンケート調査を行い, 回答のあった166校, 92680名の児童について, 学童期のそばアレルギー羅患状況を検討した.同時に調査したアレルギー疾患の羅患率は, 気管支喘息5.6%, アトピー性皮膚炎4.2%, アレルギー性鼻炎3.1%, アレルギー性結膜炎1.6%, 食物アレルギー1.3%であった.これに対しそばアレルギー児童は男子140名, 女子54名, 計194名で, 羅患率は0.22%であった.症状は蕁麻疹が最も頻度が高く(37.3%), ついで皮膚〓痒感(33.3%), 喘鳴(26.5%)で, アナフィラキシーショックは4名(3.9%)が経験しており, 卵・牛乳アレルギーより高率であった.また, 学校給食で7名, 校外活動で1名の児童がそばアレルギー症状の出現を経験していた.養護教諭を中心とした小学校児童のアレルギー歴の把握が積極的に実施されている実態が明らかになり, これによりそばアレルギーは稀な疾患では無いことが明らかになった.学校生活においても十分な予防対策を講じる必要がある.
- 著者
- 横田俊平 黒岩義之 大西孝宏 中島利博 中村郁朗 西岡久寿樹
- 出版者
- 医薬ジャーナル社
- 雑誌
- アレルギー・免疫 (ISSN:13446932)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.6, pp.786-793, 2018-05-15
HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン接種後に多彩な症状を呈する副反応症例の解析により,症候学的に,① 生命機能,② 高次脳機能・辺縁系,③ 感覚機能,④ 運動機能の4つの機能の恒常性の破綻が推定され,HPVワクチンのL1抗原とアジュバントによる視床下部・脳室周囲器官の病変が原因と推定された。一方,ASIA(Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants)症候群は,アルミニウム塩,シリコンのアジュバント作用に由来し,自己免疫疾患はアジュバントによる慢性刺激が原因であると推定された。いずれも症候を詳細に検討する余地が残されており,今後,一般的症候との差異を明らかにする必要がある。
32 0 0 0 OA WS2-3 HPVワクチン副反応発症の臨床症候と中枢神経病巣の考え方
- 著者
- 横田 俊平 黒岩 義之 西岡 久寿樹
- 出版者
- 日本臨床免疫学会
- 雑誌
- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.288a-288a, 2015 (Released:2015-10-25)
ヒト・パピローマウイルス(HPV)は一般的な感染因子であり,子宮頸部基底細胞への感染は部分的には癌発症の契機になる.子宮頸癌を予防する目的でHPVワクチンが開発され(CervarixとGardasil),約340万人の若年女性に接種が行われた.しかし,HPVワクチン接種後より全身痛,頭痛,生理異常,病的だるさ・脱力・不随意運動,立ちくらみ・繰り返す便秘・下痢,光過敏・音過敏,集中力低下・計算力と書字力の低下・記憶障害などを呈する思春期女性が増加している.「HPVワクチン関連神経免疫異常症候群(HANS)」と仮称し,当科外来を受診した51例の臨床症状の把握とその体系化を行った.すべての症例は,HPVワクチン接種前は良好な健康状態・知的状態にあり,接種後,全例が一様に一連の症候の重層化,すなわち,疼痛性障害,不随意運動を含む運動器機能障害,感覚障害,生理異常,自律神経障害,高次脳機能障害と進展することを確認した.このように幅広いスペクトラムの疾患の記載はこれまでになく,これらの症候を同時に呈する中枢神経障害部位についての検討をすすめ,「視床下部 下垂体病変」と捉えられることが判明した.病態形成にはミクログリアが関わる自然免疫,HPVワクチン抗原のペプチドと特異なHLAが関わる適応免疫の両者が,強力なアジバントの刺激を受けて視床下部の炎症を繰り返し誘導していると考えている.治療にはramelteon(circadian rhythmの回復),memantine(シナプス伝達の改善),theophylin(phosphodiesterase inhibitorの抑制)を用い対症的には対応が可能となったが,病態に根本的に介入できる薬剤はいまだ手にしていない.
30 0 0 0 OA 自律神経科学からみた視床下部症候群(脳室周囲器官制御破綻症候群)の意義
- 著者
- 黒岩 義之 平井 利明 横田 俊平 鈴木 可奈子 中村 郁朗 西岡 久寿樹
- 出版者
- 日本自律神経学会
- 雑誌
- 自律神経 (ISSN:02889250)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.185-202, 2019 (Released:2019-12-27)
- 参考文献数
- 50
脳室周囲器官と視床下部は恒常性維持器官であり,自律神経,概日リズム,神経内分泌(ストレス反応),情動・記憶・認知,感覚閾値・疼痛抑制,歩行・運動,神経代謝・神経免疫(熱エネルギー代謝,老廃物排出,自然免疫・腫瘍免疫)を制御する.血液脳関門を欠く有窓性毛細血管が密集する感覚性脳室周囲器官が感知した信号(光,匂い,音,電磁波,レプチン,グレリン)は視索前野,背内側視床下部を経て,休息型視床下部(摂食行動抑制中枢)と活動型視床下部(摂食行動促進中枢)に伝達される.心理ストレス情報は扁桃体から,概日リズム情報は視交叉上核から視床下部に入り,視床下部からオレキシン,バゾプレシン,オキシトシンが分泌される.視床下部症候群(脳室周囲器官制御破綻症候群)の背景疾患として,ヒトパピローマウィルスワクチン接種関連神経免疫症候群,慢性疲労症候群,脳脊髄液減少症,メトロニダゾール脳症,化学物質過敏症,電磁過敏症などがある.
28 0 0 0 OA 視床下部性ストレス不耐・疲労症候群としての環境ストレス過敏症(環境ストレス不耐症)
- 著者
- 黒岩 義之 平井 利明 水越 厚史 中里 直美 鈴木 高弘 横田 俊平 北條 祥子
- 出版者
- 日本自律神経学会
- 雑誌
- 自律神経 (ISSN:02889250)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.72-81, 2022 (Released:2022-04-23)
- 参考文献数
- 34
環境ストレスには物理的感覚ストレス,化学的感覚ストレス,免疫・凝固系ストレス,心理社会的ストレス,内部環境ストレスがある.環境ストレスに対して生体が過敏症(ストレス感覚入力系の過敏状態)や不耐症(ストレス反応出力系の不全状態)を呈する病態を環境ストレス過敏症(不耐症)と定義した.その病像は視床下部性ストレス不耐・疲労症候群(脳室周囲器官制御破綻症候群)であり,自律神経・内分泌・免疫症状,筋痛,疲労,記憶障害等の多彩な症状が重層的に起こる.基礎疾患が明らかでない特発性タイプと,筋痛性脳脊髄炎・慢性疲労症候群,脳脊髄液漏出症,HPVワクチン後遺症,COVID-19後遺症,シックハウス症候群,ネオニコチノイド暴露など,基礎疾患が明らかな症候性タイプがある.3ステージ仮説(遺伝的要因,発症要因,トリガー要因)に基づき,その病態や予防について論じた.分子病態仮説としてプリン作動性神経伝達障害を考えた.
- 著者
- 琴寄 剛 高橋 由利子 横田 俊平 相原 雄幸 大砂 博之 大沼 すみ 池澤 善郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2-3, pp.293, 1998-03-30 (Released:2017-02-10)
13 0 0 0 OA 薬剤師から見た脳脊髄液減少症の感覚・免疫過敏症―4つの中核症状に関する221例の検討―
- 著者
- 中里 直美 北條 祥子 菅野 洋 鈴木 高弘 平井 利明 横田 俊平 黒岩 義之
- 出版者
- 日本自律神経学会
- 雑誌
- 自律神経 (ISSN:02889250)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.132-143, 2022 (Released:2022-04-23)
- 参考文献数
- 50
脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)は交通事故やスポーツ外傷のような外傷性の発症イベントに引きつづき,多彩な全身的体調不良がみられる後天的な慢性疾患であるが,発症イベント要因が不明なこともある.本症は脊髄神経根部での脳脊髄液の漏出(吸収過多)で起こるといわれているが,その病態に関しては不明な点が多い.4つの中核症状(自律神経症状,情動・認知症状,疼痛・感覚過敏症状,免疫過敏症状)が個々の患者で重層的に起こる.本症には性差があり,女性の方が男性よりも各症状の出現頻度や重症度が高い.本症は環境ストレスに対して生体が過敏症(ストレス感覚入力系の過敏状態)や不耐症(ストレス反応出力系の不全状態)を呈する.本症と筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群,子宮頚癌ワクチン副反応,COVID-19慢性後遺症との類似性が注目され,それらの病像は視床下部性ストレス不耐・疲労症候群(脳室周囲器官制御破綻症候群)といえる.
10 0 0 0 WS2-3 HPVワクチン副反応発症の臨床症候と中枢神経病巣の考え方
- 著者
- 横田 俊平 黒岩 義之 西岡 久寿樹
- 出版者
- The Japan Society for Clinical Immunology
- 雑誌
- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.288a-288a, 2015
ヒト・パピローマウイルス(HPV)は一般的な感染因子であり,子宮頸部基底細胞への感染は部分的には癌発症の契機になる.子宮頸癌を予防する目的でHPVワクチンが開発され(CervarixとGardasil),約340万人の若年女性に接種が行われた.しかし,HPVワクチン接種後より全身痛,頭痛,生理異常,病的だるさ・脱力・不随意運動,立ちくらみ・繰り返す便秘・下痢,光過敏・音過敏,集中力低下・計算力と書字力の低下・記憶障害などを呈する思春期女性が増加している.「HPVワクチン関連神経免疫異常症候群(HANS)」と仮称し,当科外来を受診した51例の臨床症状の把握とその体系化を行った.すべての症例は,HPVワクチン接種前は良好な健康状態・知的状態にあり,接種後,全例が一様に一連の症候の重層化,すなわち,疼痛性障害,不随意運動を含む運動器機能障害,感覚障害,生理異常,自律神経障害,高次脳機能障害と進展することを確認した.このように幅広いスペクトラムの疾患の記載はこれまでになく,これらの症候を同時に呈する中枢神経障害部位についての検討をすすめ,「視床下部 下垂体病変」と捉えられることが判明した.病態形成にはミクログリアが関わる自然免疫,HPVワクチン抗原のペプチドと特異なHLAが関わる適応免疫の両者が,強力なアジバントの刺激を受けて視床下部の炎症を繰り返し誘導していると考えている.治療にはramelteon(circadian rhythmの回復),memantine(シナプス伝達の改善),theophylin(phosphodiesterase inhibitorの抑制)を用い対症的には対応が可能となったが,病態に根本的に介入できる薬剤はいまだ手にしていない.
6 0 0 0 OA 自律神経科学元年の幕開け:今後の動向を考える
- 著者
- 黒岩 義之 平井 利明 横田 俊平 藤野 公裕 山﨑 敏正
- 出版者
- 日本自律神経学会
- 雑誌
- 自律神経 (ISSN:02889250)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.1-9, 2021 (Released:2021-04-15)
- 参考文献数
- 38
自律神経科学はストレス反応の科学と言って過言でない.ストレスには外部環境ストレスと内部環境ストレスがある.生体の細胞膜には環境ストレスを感知するバイオ・センサーがある.ストレス中枢のセキュリテイ・ゲート(脳の窓)は視床下部と脳室周囲器官である.ストレス・シグナルの伝達経路には神経制御系,液性制御系,細胞シグナル伝達系がある.ストレスから生体を守る視床下部・辺縁系の攪乱によって不眠,内臓症状,慢性疲労,記憶学習障害,筋痛,感覚過敏など多彩な症状が起こる(視床下部症候群,脳室周囲器官制御破綻症候群).ストレス反応の制御はテロメア損傷,老化,発癌,フレイルの予防につながる.一方,慢性腎臓病などの内部環境ストレスはテロメアを攻撃して,寿命短縮や発癌を誘発する.ストレスに関して基礎と臨床の両面から総合的にアプローチできるのが自律神経科学である.自律神経科学元年の幕開けとルネッサンスの到来を期待する.
3 0 0 0 OA インフリキシマブが奏効した壊疽性膿皮症の1例
- 著者
- 野澤 智 原 良紀 木下 順平 佐野 史絵 宮前 多佳子 今川 智之 森 雅亮 廣門 未知子 高橋 一夫 稲山 嘉明 横田 俊平
- 出版者
- 日本臨床免疫学会
- 雑誌
- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.6, pp.454-459, 2008 (Released:2008-12-31)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 5 9
壊疸性膿皮症は,稀な原因不明の慢性皮膚潰瘍性疾患で小児例もわずか4%であるが存在する.クローン病や潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患,大動脈炎症候群(高安病),関節リウマチなどに合併する例もあるが,本症単独発症例が約半数を占める.壊疽性膿皮症の標準的な治療であるステロイド薬,シクロスポリンに抵抗を示す難治例に対し,近年タクロリムス,マイコフェノレート・モフェチール,そして抗TNFαモノクローナル抗体の効果が報告されている.今回,壊疽性膿皮症の12歳女児例を経験した.合併する全身性疾患は認められなかったが,皮膚に多発する潰瘍性病変はプレドニゾロン,メチルプレドニゾロン・パルス,シクロスポリンなどの治療に抵抗性で長期の入院を余儀なくされていた.インフリキシマブの導入をしたところ潰瘍局面の著しい改善を認めた.最初の3回の投与で劇的な効果をみせ,投与開始1年3ヶ月後の現在,ステロイド薬の減量も順調に進み,過去のすべての皮膚潰瘍部は閉鎖し,新規皮膚病変の出現をみることはなく,経過は安定している.壊疽性膿皮症にインフリキシマブが奏効した小児例は本邦では初めての報告である.本症難治例に対するステロイドの長期大量投与は,小児にとっては成長障害が大きな問題であり,長期入院生活は患児のQOLを著しく阻害する.本報告により小児壊疽性膿皮症の難治例に対する治療に新しい局面を切り開く可能性が示唆された.
3 0 0 0 インフルエンザ脳症の脳内サイトカイン蓄積からみた病態解析
インフルエンシザ関連脳症は5歳以下の乳幼児に好発し、その約30%が予後不良となる重天な疾患である。原因は不明で米国との共同の調査研究でもReye症候群とは異なりわが国独特の疾患であることを平成12年度の研究で明らかにした。またこの研究から中枢神経障害は全身への致死的病態の波及前に出現していることも明らかになり、平成13年度の研究では中枢神経内に誘導される炎症性サイトカインの異常産生に焦点を当てた。Wisterラット(8〜12週齢、雌)の脳室内にInjection Pype(IP)を留置した後、髄腔内へlipopolysaccharide(LPS ; E.coli由来)を30ugまたは300ug投与し、径時的にIPより脳室液を採取して液中の炎症性サイトカイン(IL-1β、IL-6、 TNFα)をELISA法にて測定した。その結果、髄液中のIL-1β、IL-6、TNFαは投与2時間後に著しく上昇した。血清中ではLPS300ug投与により同様にIL-1β、IL-6、TNFαの上昇をみたが、30ug投与では上昇しなかった。このことはLPS髄腔内投与が脳内に高サイトカイン状態を惹起することを示したが、LPS30ugでは高サイトカイン状態は脳内に留まり、LPS300ug投与により脳血管門の破綻が生じ全身性の高サイトカイン状態に至ることが推察された。次に脳組織からmRNAを抽出しIL-1β、1L-6、TNFαそれぞれのmRNAをRPA法により検討した。いずれのmRNAも著しい発現増強を認め、脳内サイトカインは脳実質細胞に由来することが判明した。脳実質内においてLPS受容体をもつ細胞はGliaであることが知られており,以上の実験結果から炎症性サイトカインはGlia活性化に由来することが想定され、インフルエンザ関連脳症では脳内Glia細胞の異常活性化と脳血管門の破綻が病態を形成していることが推定された。
- 著者
- 横田 俊平 名古 希実 金田 宜子 土田 博和 森 雅亮
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床リウマチ学会
- 雑誌
- 臨床リウマチ (ISSN:09148760)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.98-107, 2020 (Released:2020-07-11)
- 参考文献数
- 41
2019年12月中国武漢市から始まった新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の感染症(COVID-19)はパンデミックとなり,世界215か国に広がり,多くの感染者,重症者,死亡者を出しつつその勢いを減じる気配はない.臨床的特徴は,発熱,乾性咳嗽,倦怠感を訴える例が多く,また,病態的には無症状から急性呼吸窮迫症候群や多臓器不全まで幅が広い.小児例は罹患数が少なく重症化することが少ないとされるが,一方,こども病院に搬送される例を詳細に検討すると多くの低年齢児が罹患しており,呼吸不全や多臓器不全を呈する例が少なくない.また,アメリカにおいて重篤感染例から逆算したSARS-CoV-2感染例はきわめて多く,早急の対策が求められている.妊娠中の母親がCOVID-19を発症した場合,帝王切開による分娩が勧められ,また,児への垂直感染は稀であることが明らかになった.他方,出生直後から感染が高頻度に起こるため,出生後直ちに母子分離を図り母乳栄養は避けることが推奨されている.小児期の慢性疾患の中でもステロイド薬,免疫抑制薬,生物学的製剤などを使用している小児リウマチ性疾患児は感染症に対して高感受性群と考えられるが,一方で,抗IL-6受容体モノクローナル抗体やhydroxychloroquineなどの抗リウマチ薬がCOVID-19の呼吸窮迫症候群から多臓器不全への移行期におけるcytokine storm interventionに有効であることが報告されている.免疫抑制薬をこのような慢性炎症性疾患の小児に継続投与を維持するかどうかは大きな問題である.最近,欧米においてSARS-CoV-2感染と川崎病発症との関連性が疑われているが,報告も少なく診断の点で問題があり,川崎病ではなく全身性血管炎として推移を見守ればよいと思われる.
- 著者
- 森島 恒雄 富樫 武弘 中村 祐輔 横田 俊平 田代 眞人 岡部 信彦 奥野 良信 布井 博幸 山口 〓次 細矢 光亮 市川 光太郎 水口 雅 河島 尚志 塩見 正司 市山 高志 玉腰 暁子 佐多 徹太郎 木村 宏 山田 至康 宮崎 千明 黒木 春郎 鍵本 聖一 岩崎 琢也 栗原 まな 奥村 彰久 前田 明彦 中野 貴司 荒川 浩一 尾内 一信 藤井 史敏 安井 良則 坂下 裕子 黒川 雅代子 瀬藤 万里子 井上 ひとみ 多屋 馨子 岡田 晴恵 二宮 伸介 山下 信子 長尾 隆志 和田 智顕
- 雑誌
- 小児感染免疫 (ISSN:09174931)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.4, pp.343-366, 2005-12-01
- 参考文献数
- 20
1 0 0 0 OA 身体症状を呈する登校障害児の症候学的検討
- 著者
- 横田 俊平 黒岩 義之
- 出版者
- 日本自律神経学会
- 雑誌
- 自律神経 (ISSN:02889250)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.51-59, 2022 (Released:2022-04-23)
- 参考文献数
- 47
身体症状を呈し登校障害を主訴に受診した学童・生徒28名の身体症状の特徴を調査した.「朝の起床困難」は睡眠障害に加えて身体感覚とそれを調整する中枢機能の障害が,「睡眠障害」は視床下部の概日リズム制御破綻が推察された.「だるさ,易疲労感」は身体的homeostasisの障害に対して視床下部のエネルギー代謝促進系の抑制的制御が機能していない状態が考えられ,内的・外的ストレスに対する調節機能の障害が推察された.「腹痛・吐き気・下痢」などは機能性dyspepsia,過敏性腸症候群などが考えられ,感覚系では視覚・聴覚・嗅覚などに過敏状態を認めた.診察では諸筋の硬化・圧痛を認め,若年性線維筋痛症にみられる18圧痛点が全例で陽性であり登校障害児には視床下部・辺縁系の障害が推定された.成人の線維筋痛症ではFDG-PETにより視床周囲領域に炎症の存在が指摘されている.登校障害児においても同様の病巣の存在が推察され,併せて諸外国の報告をまとめた.
- 著者
- 横田 俊平 黒岩 義之
- 出版者
- 一般社団法人 室内環境学会
- 雑誌
- 室内環境 (ISSN:18820395)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.63-73, 2022 (Released:2022-04-01)
- 参考文献数
- 48
全身的な身体症状と登校障害を主訴に受診した学童・生徒28名の臨床症状の特徴を調査した。全身の持続的な骨格筋痛, 関節痛, 種々の頭痛が全例に認められた。睡眠障害と朝の起床困難, 倦怠感・少しの動作で感じる疲労感, 食後の胃部痛・胃もたれ, 反復性の下痢と便秘, 通常の室内環境レベルでの光・音・匂いに対する感覚過敏とそれに伴う嘔気・頭痛を認めた。登校時に体調が悪化する例では眩暈, 動悸・息苦しさ, 頭痛, 腹痛等の訴えが多かった。理学的診察では全例に身体諸筋のこわばりと圧痛を認め, 線維筋痛症18圧痛点が陽性であった。血液検査では病巣を特定できる異常所見は得られなかった。これらの所見は若年性線維筋痛症に類似し, 登校障害児には若年性線維筋痛症の未診断例が含まれる可能性がある。自律神経症状, 疼痛・感覚過敏症状, 情動症状をコアとする視床下部性ストレス不耐・疲労症候群の病像が浮き彫りになり, 概日リズムの制御破綻, エネルギー代謝系の機能不全, 内的・外的環境ストレスに対する環境過敏とストレス不耐がある。線維筋痛症成人例でPositron-Emission Tomography(PET)で, 視床とその周囲にミクログリア由来の炎症が確認されており, 登校障害児においても視床-視床下部-辺縁系に病的プロセスが推察された。健常児では全く問題とならないレベルの室内環境等の身体的ストレスや心理的ストレスが登校障害児では顕著な環境過敏・ストレス不耐と易疲労性を起こし, 不登校の原因と推察された。
- 著者
- 島田 純 保富 宗城 九鬼 清典 山中 昇 満田 年宏 横田 俊平
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科學會會報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, no.5, pp.552-559, 2000-05-20
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 7
近年,市中においてペニシリン耐性肺炎球菌による上気道感染症が急速に蔓延し治療に難渋する疲例に遭遇する機会が増えてきている.急性中耳炎は鼻咽腔から中耳への細菌の侵入と増殖によって発症するとされているが,耐性菌感染症の病態を考える上では,感染源としての鼻咽腔細菌の状態を把握することは重要である.<br>小児急性中耳炎患児の鼻咽腔より検出された肺炎球菌80株についてPCR法によりペニシリン結合蛋白(penicillin binding protein: PBP)遺伝子の変異を検索したところ,pbp1a, pbp2x, pbp2bの3つの遺伝子すべてが変異した株が30%にみられ,74%が何らかの遺伝子変異を有するものであった.またこれらの遺伝子変異株は1歳児から最も多く検出された.最小発育阻止濃度(minimum inhibitory concentration:MIC)が0.06μg/mL以下を示す菌株群(46株)のうち,セフェム耐性化に関わるpbp2x遺伝子の変異を有する株が43%(20/46)を占めていた.<br>また,急性中耳炎を繰り返した11組のエピソードについて,エピソード毎に鼻咽腔から分離された肺炎球菌の遺伝子型をパルスフィールドゲル電気泳動法を用いて比較したところ9組(82%)において菌株が異なっていた.さらにpbp遺伝子の変異パターンから菌株を識別した場合には,8組(72%)において菌株が異なつておりほぼ同様の結果が得られた.<br>以上のことから,急性中耳炎患児の鼻咽腔においてはpbp遺伝子に変異を有する菌株が大きく関与しており,エピソード毎に異なる菌株によって感染が起こりやすいことが判明した.したがって急性中耳炎においては鼻咽腔検出菌の各種薬剤に対する感受性をエピソード毎に評価していくことが重要である.また,PCR法によるpbp遺伝子検索方法は分離菌の薬剤耐性判定を迅速に行えるだけでなく,個々の菌株を識別する上でも有用であると思われる.
1 0 0 0 若年性線維筋痛症患児の入院治療の実際と効果
- 著者
- 菊地 雅子 野澤 智 佐藤 知美 西村 謙一 金高 太一 櫻井 のどか 原 良紀 山崎 和子 横田 俊平
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児リウマチ学会
- 雑誌
- 小児リウマチ (ISSN:24351105)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.26-31, 2014 (Released:2020-12-15)
- 参考文献数
- 10
当科では,若年性線維筋痛症 juvenile fibromyalgja:JFM)に対して,環境分離を主軸とする入院治療 を行ってきた.入院の適応は,重症例もしくは社会的因子が病状に強く影響している場合である. 入院では,規則正しい生活と院内学級通学,リハビリテーションが治療の中心であり,同時に環境調 整(家族や学校との面談)を進め,必要に応じて薬物療法を併用する. 2001年3月~2012年12月までの期間に,当科で入院加療したJFM患児32例について,その効果と 実際について検討した.結果は,臨床症状と重症度において,退院時のステージが17例(53%)で改 善し増悪は1例のみだった.また,入院中9例(31%)に圧痛点の減少があり,うち6例(19%)は退 院時に圧痛点が消失した.入院時に不登校の患児は25例(78%)で,うち9例(36%)が退院後3か月 の時点で登校可能となった. 入院治療による多面的なアプローチは,JFMの症状改善に有効と考えられた.
- 著者
- 横田 俊平
- 出版者
- 一般社団法人 日本アレルギー学会
- 雑誌
- アレルギー (ISSN:00214884)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3-4, pp.273, 2007-04-30 (Released:2017-02-10)