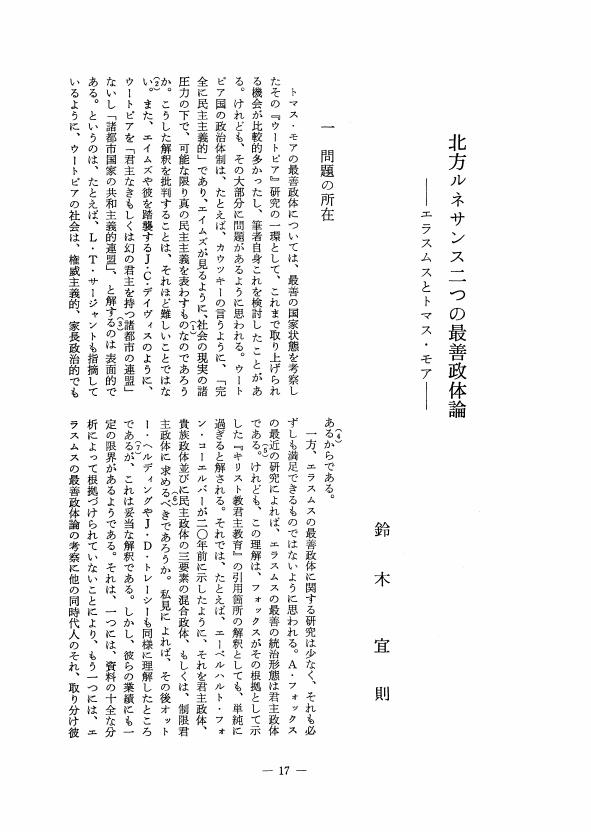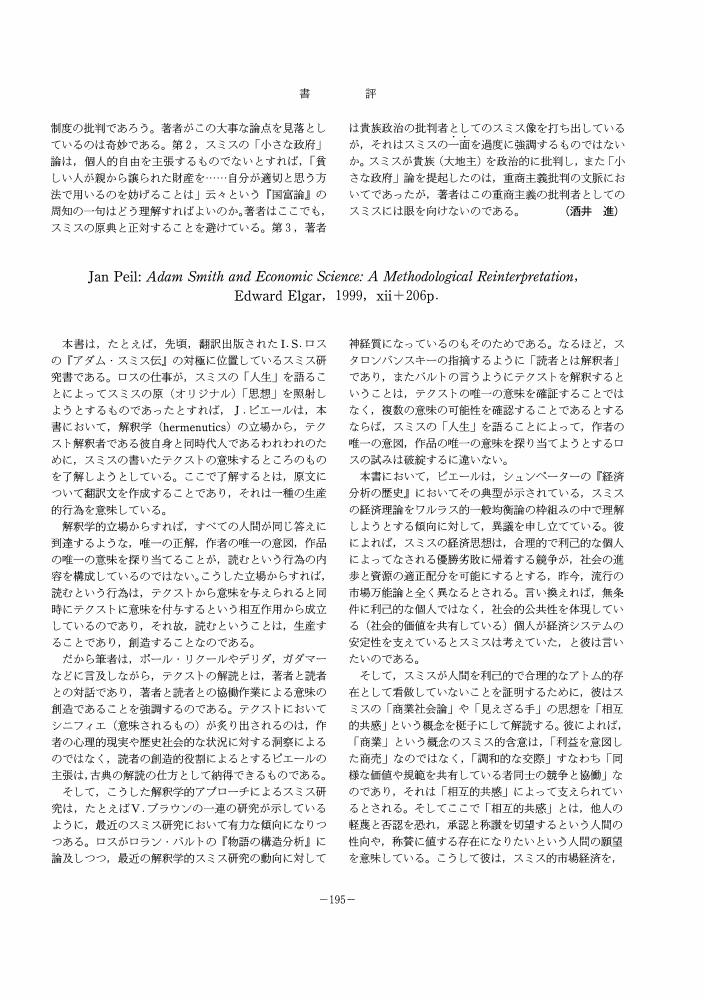1 0 0 0 OA 金子裕介著『新版 心の論理』 ─現代哲学による動機説の展開』
- 著者
- 鈴木 雄大
- 出版者
- The Philosophy of Science Society, Japan
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.86-91, 2018-12-30 (Released:2019-11-27)
1 0 0 0 OA 地域愛着が地域への協力行動に及ぼす影響に関する研究
- 著者
- 鈴木 春菜 藤井 聡
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木計画学研究・論文集 (ISSN:09134034)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.357-362, 2008-09-30 (Released:2010-06-04)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 14 17
地域愛着のインパクトについての研究はこれまで, 主として環境心理学をはじめとする他領域の中で各種の分析が進められてきたため, 土木計画に直接かかわる諸変数に対する地域愛着の影響は, 十分に検討されているとは言い難いものであった. 本研究では, このような背景のもと, 地域愛着と地域への協力行動をはじめとする土木計画にかかわる諸変数との間の統計的関係を質問紙調査の結果をもとに分析した. その結果, 地域愛着が高い人ほど, 町内会活動やまちづくり活動などの地域への活動に熱心で, 行政を信頼する傾向が示された.
1 0 0 0 OA 機械と身体
- 著者
- 鈴木 登
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.49-62, 1983-11-26 (Released:2009-05-29)
1 0 0 0 OA 現代韓国・台湾における法学哲学の潮流
- 著者
- 鈴木 敬夫
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1978, pp.190-199, 1979-10-15 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 31
1 0 0 0 OA 沈黙の地理学界
- 著者
- 渡辺 満久 鈴木 康弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.4, pp.390-393, 2011-07-01 (Released:2015-09-28)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 1
1 0 0 0 OA 防災・減災への貢献に向けた内なる提言
- 著者
- 鈴木 康弘
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Series A (ISSN:18834388)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.4, pp.393-395, 2011-07-01 (Released:2015-09-28)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 各報告へのコメント 佐伯刑事法学について
- 著者
- 鈴木 茂嗣
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.160-168, 2008-08-01 (Released:2020-11-05)
1 0 0 0 OA 平野龍一博士の刑事訴訟法学 いわゆる基礎理論を中心に
- 著者
- 鈴木 茂嗣
- 出版者
- 日本刑法学会
- 雑誌
- 刑法雑誌 (ISSN:00220191)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.2, pp.297-307, 2006-01-30 (Released:2020-11-05)
1 0 0 0 OA 日本における水文誌研究の動向
- 著者
- 新見 治 鈴木 裕一 肥田 登
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- Geographical review of Japan, Series B (ISSN:02896001)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.23-34, 1988-05-31 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 90
- 被引用文献数
- 1 1
わが国の地理学研究者による最近の水文学研究には, 2つの潮流が存在する。一つは水文循環の物理的過程を究明する水文学研究であり,もう一つは水文環境,すなわち水と人間の関係を総合的に扱う水文誌的研究である。この報文では,特に水文誌の基礎となる地理学分野での研究動向を把握し,今後の研究上の課題について考察した。 地域レベルでは,日本の水収支や水文環境の特性のほか,降水の時空間的な変動特性が研究されてきた。水利用に関しては,高度経済成長期の水資源開発や水問題,工業用水道事業の成立と展開,都市化と農業用水などについて論議が深められた。 流域レベルにおいては,マンボなどの在来の地下水利用技術,地下水を利用した融雪システム,水利用と環境問題,地下水管理など,地域の地下水環境と水利用に関する研究が数多く行われた。都市化と水との関係に着目し,水利秩序の再編成過程,水利転用の展開,灌漑用溜池の潰廃のほか,都市化地域の水文環境と水利用に関する事例研究も進められた。このほか,洪水と水害,ダム建設と社会問題,離島の水などにも関心が向けられた。 このように,水と人間の関係を扱った研究は地理学の様々な分野において多数存在するにもかかわらず,これら基礎的研究によって得られた地理学的情報は水文誌の視点から総合的に整理されていないのが現状である。水文環境や水利用に関する情報の表現方法の開発,水循環と水収支を基本的概念とする水文誌記載の具体的な試み,そして水文誌の記載方法の確立などが,今後のこの分野での重要な研究課題である。
1 0 0 0 酸化ダイヤモンド : 種々の触媒反応に対する新規担体物質
- 著者
- 鈴木 俊光 中川 清晴
- 出版者
- 公益社団法人 石油学会
- 雑誌
- Journal of the Japan Petroleum Institute (ISSN:13468804)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.66-79, 2011-03-01
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 6
世界で最初に,ダイヤモンド微粒子を触媒担体に用いるいくつかの触媒反応を行った。ダイヤモンドは長年安定な物質と考えられていたが,その表面は水素や酸素と反応し,C–H結合や,C–O–C,C=O結合などが最表面に生成することが知られるようになった。我々は,酸素で表面処理したダイヤモンド(酸化ダイヤ,以下O-Diaと呼ぶ)を触媒担体に用いて,金属酸化物,金属を担持した触媒を調製し,次の反応にO-Dia担持触媒が高い活性を示すことを見出した。本論文では以下の反応に関する著者等の研究をまとめた。(1)酸化クロム/O-Dia触媒によるエタン,プロパンなどのアルカンの脱水素反応,(2)酸化バナジウム/O-Dia触媒によるエチルベンゼンの脱水素反応,(3)メタン,エタンの酸化バナジウム/O-Dia触媒上での二酸化炭素を酸化剤とする酸化反応によるアルデヒド生成反応,(4)Ni/O-Dia,Co/O-Diaを用いたメタンの部分酸化による合成ガス生成反応,(5)NiまたはPd/O-Dia触媒上でのカーボンナノフィラメント生成反応,(6)Ru/O-Dia触媒によるアンモニア合成反応。
1 0 0 0 OA 北方ルネサンスニつの最善政体論 ―エラスムスとトマス・モア―
- 著者
- 鈴木 宜則
- 出版者
- 日本イギリス哲学会
- 雑誌
- イギリス哲学研究 (ISSN:03877450)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.17-30, 1989-04-01 (Released:2018-05-25)
1 0 0 0 OA スミスとビュフォン ―スミスの思想形成の一局面―
- 著者
- 鈴木 信雄
- 出版者
- 日本イギリス哲学会
- 雑誌
- イギリス哲学研究 (ISSN:03877450)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.29-41, 1988-04-01 (Released:2018-05-25)
1 0 0 0 OA トマス・モアにおける職業としての政治
- 著者
- 鈴木 宜則
- 出版者
- 日本イギリス哲学会
- 雑誌
- イギリス哲学研究 (ISSN:03877450)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.21-30, 1984-04-01 (Released:2018-06-25)
1 0 0 0 OA 初期モアの社会諸観念 ―『ユートピア』の基礎―
- 著者
- 鈴木 宜則
- 出版者
- 日本イギリス哲学会
- 雑誌
- イギリス哲学研究 (ISSN:03877450)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.15-24, 1982-03-28 (Released:2018-06-25)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 OA 新殺菌剤フルアジナムのハクサイ根こぶ病に対する作用特性
- 著者
- 鈴木 一実 杉本 光二 林 博之 光明寺 輝正
- 出版者
- The Phytopathological Society of Japan
- 雑誌
- 日本植物病理学会報 (ISSN:00319473)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.4, pp.395-398, 1995-08-25 (Released:2009-02-19)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 16 22
フルアジナム(フロンサイド®)のハクサイ根こぶ病に対する作用特性を検討した。1ppm以上のフルアジナム存在下で休眠胞子を培養したとき,遊走子発芽はほとんど観察されなかった。フルアジナムに接触させた休眠胞子を接種した場合には根毛感染の頻度が減少した。フルアジナムを土壌施用したところ,根毛感染および根こぶ形成は著しく阻害された。根毛感染成立後,第二次遊走子放出前にフルアジナム含有非汚染土壌にハクサイ苗を移植した場合,根こぶ形成は阻害されたが,皮層感染成立後では防除効果は認められなかった。以上から,フルアジナムは休眠胞子に殺菌的に作用するとともに根毛感染および皮層感染を阻害し,その結果根こぶ形成阻害をもたらすことが示唆された。
1 0 0 0 OA Uchida Yoshihiko:
- 著者
- 鈴木 信雄
- 出版者
- The Japanease Society for the History of Economic Thought
- 雑誌
- 経済学史研究 (ISSN:18803164)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.1-17, 2013 (Released:2019-08-23)
Abstract: It is very difficult to summarize the thought of Uchida Yoshihiko (1913-1989), one of the representative intellectuals of postwar Japan, but, we could describe the pursuit of Uchida as a search for a way to foster independent and self-reliant individuals of Japanese citizenship and to realize a fair and flexible society in Japan. He started his pursuit by resisting the authoritarianism prevalent in academic circles and the main left-wing groups of Japanese society. He made strenuous efforts to find signs of Homo economicus in modern Japanese society and enthusiastically advocated the ac-ademic and educational need of cultivating the spirit of developing and fostering democratic system, while believing in the civilizing influence of capital: “Everything old and outdated will be thoroughly recast and rebuilt according to the requirement of capital,” he argued, believing this to be an inevitable result of the advancement of economic law and the development of productivity. We can see key ideas underlying his lifelong works in his contribution to Daigaku Shinbun (University Papers) of November 1945, “Newspapers and Democracy”: “The nature of decision forming of a democratic society . . . should be seen in such a society where the people themselves obtain and activate huge, multiple social perspectives by exchanging and carefully examining the ideas expressed by the people of various positions who responsibly see and think for themselves.” Thus, his aim was to actualize an antiauthoritarian and enlightened idea of our society. JEL classification numbers: B 12, B 14, B 41.
1 0 0 0 OA D. デフォーの奢侈論 ジェントルマン論からの再考
- 著者
- 鈴木 康治
- 出版者
- 経済学史学会
- 雑誌
- 経済学史研究 (ISSN:18803164)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.83-99, 2011 (Released:2019-08-20)
Defoe definitely agrees that luxury is a vice, though he also recognizes that luxury as a consumptive action entails economic benefits for the political society. Furthermore, he realizes that the conspicuousness of riches in consumptive actions can have morally restraining effects on the common people. The central theme of this article is to distinguish Defoe’s implications for the consumption theory from his discourses on luxury. For this purpose, it is expedient to focus on Defoe’s considerable regards for the English gentry, because it can clarify his luxury discourse in the social context wherein luxury is to be clearly comprehended as a consumptive action. When logically integrated with the gentry discourse, the luxury discourse represents the consumption theory in eighteenth-century England. Moreover, it is notable that morality is included in economic activities in Defoe’s luxury discourse. Defoe struggles to find a cohesive logic in his social theory closely relevant with the structural change of his time. In this contemporary dynamics, it is the gentry comprising virtuous individuals with riches and intelligence that he expects to find as the leading entity governing the new hierarchical order to be settled with the quality and quantity of their consumptive actions. Thus, it is safe to say that Defoe’s theory of consumption correctly grasps the social order newly established in eighteenth-century England. JEL classification numbers: B 31, Z 19.
- 著者
- 鈴木 信雄
- 出版者
- The Japanese Society for the History of Economic Thought
- 雑誌
- 経済学史学会年報 (ISSN:04534786)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.38, pp.195-196, 2000 (Released:2010-08-05)
1 0 0 0 OA Bradley W. Bateman, Keynes's Uncertain Revolution, The University of Michigan Press, 1996, xi+183 p.
- 著者
- 鈴木 典夫
- 出版者
- The Japanese Society for the History of Economic Thought
- 雑誌
- 経済学史学会年報 (ISSN:04534786)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.35, pp.200-202, 1997 (Released:2010-08-05)
- 著者
- 鈴木 信雄
- 出版者
- The Japanese Society for the History of Economic Thought
- 雑誌
- 経済学史学会年報 (ISSN:04534786)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.32, pp.137, 1994 (Released:2010-08-05)