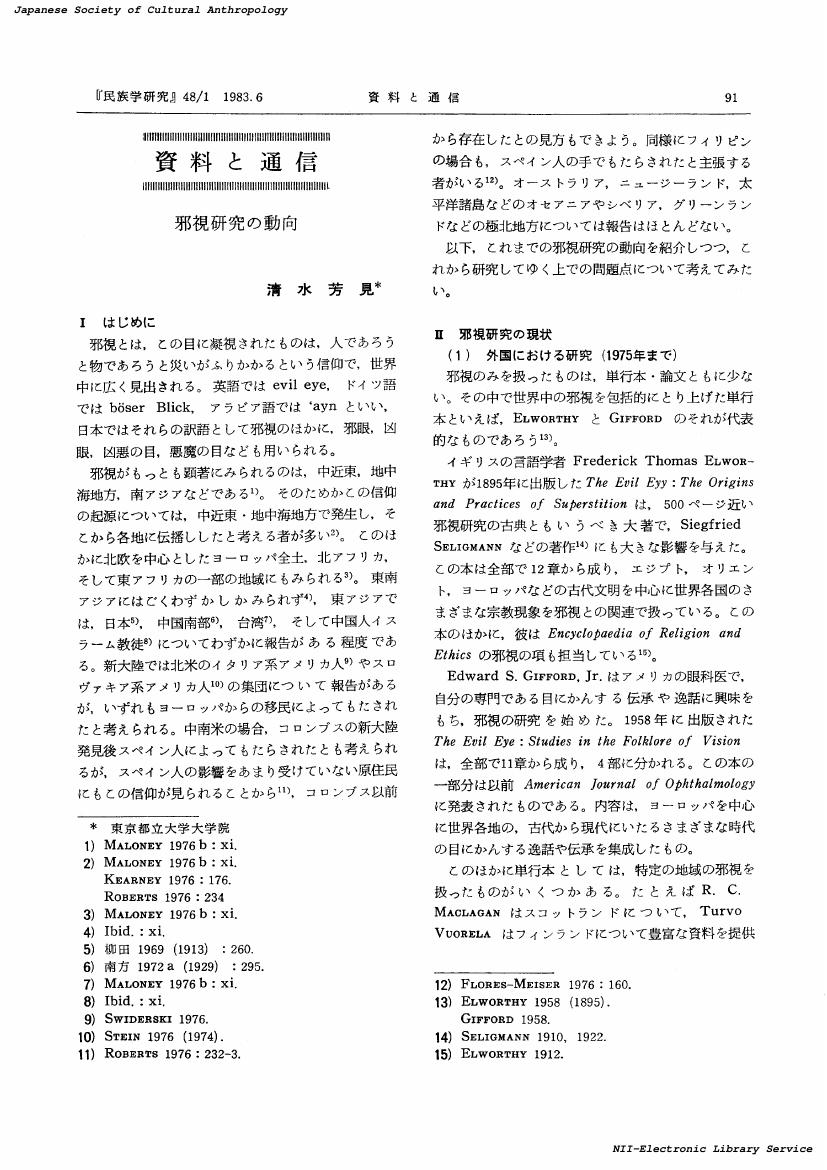9 0 0 0 OA ファースト・コンタクトの人類学
- 著者
- 木村 大治
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第47回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.141, 2013 (Released:2013-05-27)
この発表では,SFの一ジャンルである「ファースト・コンタクト」,すなわち,異星人との最初の接触の「事例」を梃子として,出会いとコミュニケーションにおける「理解」の成立について論じる。
- 著者
- 吉田 ゆか子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.1, pp.11-32, 2011-06-30
モノやモノと人の関わりに注目する人類学では、人とモノの関係を主体-客体と位置づける一元的な視点に疑問を呈してきた。一方、仮面劇の世界では、演者は仮面というモノに導かれながら自分ではない何者かになろうとし、そこでは自己-他者(仮面)、人-モノ、主体-客体といった対立は常に揺るがされる。本論では、バリ島の仮面舞踊劇トペンに注目する。トペン上演を、具体的な人とモノとの相互作用によってたちあがるアッサンブラージュと位置づけその特徴を指摘し、またその中で演者と仮面の主-客の関係がどのように撹乱されるのかを考察する。くわえて仮面の物としての多様な性質(=物性)が、そのアッサンブラージュにいかに作用するのかを考察する。台本も大掛かりな舞台装置もなく即興的に演じられるトペンは、演者、仮面、伴奏楽器、伴奏者、観客が集うことから上演がたちあがる。先行研究によれば、上演中の演者は仮面を操りつつ仮面に操られるという二重の意識を有する。しかし、演技のモードによって、演者は仮面と一体化するよりも、むしろ仮面の物性を暴露するなど、両者の関係性は可変的である。また伴奏者や伴奏音楽との駆け引きや、移り気な観客たちの態度によって、仮面と演者のみならず、その他の人やモノの間の関係性もダイナミックに変化する。ここに発生的で移ろいやすく、脆さをも含むトペン上演というアッサンブラージュの特徴をみてとれる。本論では、その中で仮面が物理的に演者の身体に作用することや、不動で命なきモノであるという仮面の物性が、トペンの多様な表現と実践を生むことなどを指摘する。加えて、一定時間存在し続けるという物性をもつ仮面は、演技後も演者宅に持ち帰られて人々と関わる。この長期的に維持される仮面と人々とのもう一つのアッサンブラージュが、トペン上演というアッサンブラージュといかなる関係にあるのかを考察する。
9 0 0 0 OA 調査者のライフイベントとフィールドワーク人生
- 著者
- 椎野 若菜
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第50回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.A01, 2016 (Released:2016-04-22)
本分科会の目的は、女性調査者の多くが自らのキャリア形成と同時に直面する結婚、妊娠、出産、介護、また未婚、離婚、死別といったライフイベントによる調査者自身の属性の変化と、それに伴う調査地との関係やポジショナリティの変化、そして調査を続けるための困難や工夫について焦点をあて、そうした経験をも民族誌的データとしていく試みの提案と、またそうした困難や情報を共有するネットワーキングの提案を行うことである。
- 著者
- 石田 智恵
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, 2016
本報告は、アルゼンチン最後の軍事政権(1976-83)の弾圧によって生み出された「失踪者(行方不明者)」という存在の特殊性を論じる。生と死の間に突如挿入され延長される「失踪」という個人の欠如、その不確定性は、親族にとってどのような現実なのか、またその「失踪者」の「死」が確定されることは、家族にどのような変化をもたらすのかといった問いについて、失踪者家族会のメンバーへの聞き取りを基に考察する。
9 0 0 0 同一嗜好の女子コミュニティにおける評価と「愛」
- 著者
- 大戸 朋子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, 2016
本発表は、「腐女子」と呼ばれる男性同性愛を主題とするフィクションや想像などを嗜好する少女/女性たちの二次創作活動とメディア利用を対象として、メディアを含むモノとの連関の中で形成される腐女子のつながりとはどのようなものであるのかを明らかにするものである。調査からは、二次創作を行う腐女子のつながりが、個々人の「愛」という不可視のモノを中心に形成され、メディアを通して評価されていることが明らかとなった。
9 0 0 0 OA 東北の関西人
- 著者
- 川口 幸大
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第52回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.93, 2018 (Released:2018-05-22)
本発表では、日本の内なるエスニシティへの他者化、および、それを内面化した自己他者化のプロセスに作用する文化認識と実態の所在について、「東北地方で暮らす関西人」である発表者のオートエスノグラフィーをもとに考察する。それをもとに、文化人類学における文化の捉え方を今ひとたび考え直してみたい。
8 0 0 0 OA 無文字社会における「歴史」の構造 : エチオピア南部ボラナにおける口頭年代史を事例として
- 著者
- 大場 千景
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.1, pp.26-49, 2013-06-30 (Released:2017-04-03)
本稿の目的は、エチオピア南部で主に牧畜を営んで暮らすボラナの人々の口承史に関する語りの分析を通して、無文字社会に生きる人々が生起してきた無数の出来事をいかにして集団の「歴史」として構築し、その膨大な出来事に関する記憶を一致させ継承しているのか、そのメカニズムを解明することである。II章では、社会構造と密接に結びつきながら構築されてきた過去5世紀に及ぶボラナの口承史、その語りの場、語り手や聞き手たちについて明らかにした。また近年の学校教育や人類学者の介入、録音機器の普及に伴って語りの場が多元化していることを背景に口承史が新たに再編されながら語られているという現象について論じた。皿章では、広域で居住する14人の語り手から収集した口承史に関する語りを比較しながら、語り手間で共通に見られる語りのカテゴリーとパターンを統計的に整理した。その上で歴史語りの中で頻繁に言及され、出来事の生起を説明する因果関係論であるマカバーサに関する言説に焦点を当てながら、人々が出来事をある一定の周期によって回帰すると考えているということを明らかにした。さらに人々が共有している出来事の周期説が「歴史」を構築すると同時に記憶する役割をも果たしている点を指摘した。本稿の目的に対して得られた成果は以下にまとめられる。ボラナのもつ永劫回帰的な史観によって(1)生起した出来事のうちどの出来事を記憶するのかが決められてしまうこと、従って回帰史観は「歴史」に関する記憶を一致させるが、同時に、(2)回帰史観に支配されるがゆえに「歴史」が新たに創出され複数の「歴史」を生み出してしまうこと、さらに、(3)過去のみならず現在や未来までもが回帰史観に巻き込まれ、「歴史」化されていることが明らかになった。
8 0 0 0 OA 多文化主義という暴力 カナダ先住民サーニッチにとっての言語復興、アート復興、そして格差
- 著者
- 渥美 一弥
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.3, pp.504-521, 2016 (Released:2018-02-23)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
本稿では、カナダにおける多文化主義政策の先住民への影響について、カナダのブリティッシュ・コロンビア州の先住民族、サーニッチを事例として検討する。そして、現時点において「多文化主義」がカナダ先住民にとって、社会的地位や経済的状態の改善に寄与している状況を評価する立場をとりつつ、先住民集団内においても、その受け取り方は複数存在することを指摘する。サーニッチの場合、多文化主義の政策を活用して経済的な自立をめざす人々と、従来の社会福祉政策に依存した暮らしを望む人々に大きく二分されているように筆者のような部外者には見える。 多文化主義は、「言語」あるいは「アート」を守ってきた先住民に対し経済的後押しをしている。独立し た学校区が生み出され、学校が建設され、教員や職員としての雇用が生まれた。トーテム・ポール等の先住民アートは、非先住民の地域住民を対象に含む市場を創造し、その作品に対する注文は増加し続けている。このような先住民の経済的自立の背景にカナダの多文化主義が存在する。しかし、それは同時に、「言語」や「アート」を身につけた人々と、そうでない人々との間に経済的な「格差」を生む結果となった。 かつて「白人」から銃火器などの「武器」を手に入れた集団と手に入れなかった集団との間で格差が生まれたように、サーニッチの間で「多文化主義」の恩恵を受けることができる人々と受けられない人々の間に格差が生じている。多文化主義においても、結果として主流社会との関係が先住民の運命を左右する決定的要素となっている。 本稿はまずカナダの多文化主義を歴史的に確認する。次に多文化主義が先住民にとって持つ意味を考察する。そして、具体例として、筆者が調査を行っているサーニッチの事例を紹介しながら、多文化主義政策が先住民の人々の間に「格差」を生じさせている状況があることを指摘する。しかし同時に、現在のサーニッチはその「格差」を乗り越えて結束している。最後に、その彼らを結びつけているのは同化教育という名の暴力に対する「記憶」であることを明示する。
8 0 0 0 OA 古代中國における太陽説話 : 特に扶桑傳説について
- 著者
- 杉本 直治郎 御手洗 勝
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3-4, pp.304-327, 1951-03-15 (Released:2018-03-27)
Over 2, 000 years ago the Fu-sang legend appeared in Chinese literature in the form of a treelegend, also having some connection with the sun. The authors, tracing the legend back to its original form, make it clear that its original form must have been a pure sun-legend. The Jo-mu (若木) which was identified with the Fu-sang means a sun-tree, the sound of 若 (^*njiak) being that of 日 (^*njiet), "sun", and both Jo-mu and Fu-sang are associated with the legend of "Ten Suns." As the character of "sang" (桑)="mulberry" in Fu-sang resembles that of "jo" (若=〓) in Jo-mu, there has been a misreading since the Chou period. But 扶桑=扶〓=扶若=扶日 seems to have been the proper series, and the last of the series 扶日 (Fu-jih) is identical with the Fu-jih (拂日 "striking the sun") which is seen in old Chinese documents combined with the Jo-mu (若木). Furthermore, as we have the legend of the Pi-jih (〓日 "shooting the sun") in which the archer I (〓) shot nine suns down out of the ten, the Pih-jih ("shooting the sun") must have been the original meaning of the word Fu-sang (扶桑) which can be identified with the Fu-jih (拂日 "striking the sun"). We find examples of such a rite of invigoration as "helping the sun" in the eclipse or shooting for the same purpose wang shih (枉矢)=huang shih (黄矢), fire-arrow, at the sun not only in the old Chinese documents, but also in modern ethnological literature. The Shantung peninsula was the principal field of activities of I, the hero of the legend of "Ten Suns." The legend itself seems to have derived from the institution of "Ten Days" which was prevalent among the Tung-i (東夷) in Shantung. The authors assume that the Fu-sang legend was first formed among this people and then transmitted southward by the migration of the Ch'u (楚) tribe belonging to the Tung-i. According to Chinese legends, there is the Hsiliu (細柳 "slender willow") in the west where the sun sets, in contrast to the Fu-sang in the east where the sun rises. The epithet hsi ("slender") being added only from the association with the meaning "willow" which the character liu has, the real meaning of the Hsi-liu must lie in the sound liu. While the place where the sun rises in the east is called T'ang-ku (湯谷), the place where the sun sets in the west is called Liu-ku (柳谷). Liu-ku is called also Mei-ku (昧谷), Meng-ku (蒙谷), Meng-ssu (蒙〓), etc. As the liu here is demonstrated to be mei (昧)=meng (蒙)=an (暗)=yin (陰), meaning "dark, " the Liu-ku must be Mei-ku=Meng-ku=Meng-ssu=An-ssu (暗〓)=Yin-ssu (陰〓), "the valley wherein the sun sets, " opposite to the T'ang-ku (湯谷)=Yang-ku (陽谷), "the valley from where the sun rises." Therefore, the proper meaning of such a name as Yen-tsu (〓〓) where the sun sets, which has been a riddle to sinologists, is Yin-ssu (陰〓), the valley wherein the sun sets. The Hsien-ch'ih (咸池) and Kan-yuan (甘淵), in which the sun is said to bathe, are also respectively nothing else than the An-ch'ih (暗池)=Yin-ch'ih (陰池), "the pond in which the sun sets, " and An-yuan (暗淵), "the deep in which the sun sets."
8 0 0 0 OA 植民地台湾から米軍統治下沖縄への「帰還」
- 著者
- 松田 ヒロ子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.4, pp.549-568, 2016 (Released:2017-02-28)
- 参考文献数
- 54
1945年8月に日本が無条件降伏した際、台湾には約3万人の沖縄系日本人移民(沖縄県出身かあるいは出身者の子孫)がいたといわれている。そのなかには、1895年に日本が植民地化して以来、就職や進学等のために台湾に移住してきた人びととその家族や親族、戦時中に疎開目的で台湾にきた人びとや、日本軍人・軍属として台湾で戦争を迎えた沖縄県出身者が含まれる。本稿はこれらの人びとの戦後引揚げを「帰還移民」として捉え、その帰還経験の実態を明らかにする。沖縄系移民は日本植民地期には日本人コミュニティに同化して生活し、エスニックな共同体は大きな意味を持っていなかった。にもかかわらず、米軍統治下沖縄に引揚げの見通しが立たないまま、台湾で難民状態におかれた沖縄系移民らは、はじめて職業や地域を超えて全島的な互助団体「沖縄同郷会連合会」を結成した。中華民国政府からは「日僑」とよばれた日本人移民らは、原則 として日本本土に引揚げなくてはならなかったが、米軍統治下沖縄への帰還を希望した人びとは、 沖縄同郷会連合会によって「琉僑」と認定されることによって引揚げまで台湾に滞在することが特別に許可された。すなわち、帝国が崩壊し引揚げ先を選択することが迫られたときに、それまで日本人移民コミュニティに同化して生活していた人びとにとって「沖縄(琉球)」というアイデンティティが極めて重要な意味を持ったのである。しかしながら、「琉僑」として引揚げた人びとが須らく米軍統治下沖縄社会を「故郷」と認識し、また既存の住民に同郷人として受け入れられたわけではなかった。とりわけ台湾で幼少期を過ごして成長した引揚者たちは、異なる環境に適応するのに苦労を感じることが多かった。また、たとえ自分自身は沖縄社会に愛着と帰属意識を持っていたとしても、台湾引揚者は「悲惨な戦争体験をしていない人」と見なされ、「戦後」沖縄社会の「他者」として定着していったのである。
- 著者
- 森田 敦郎
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.1, pp.33-52, 2011
本論文では、19世紀フランスの社会学者ガブリエル・タルドに着想を得た「モノ」への新しいアプローチを構想を試みる。近年、タルドへの関心が人類学で復活しつつある。この関心は、人間の行為の所与の条件となる単一の「自然」と、人間の創造的行為の産物である多数の「文化」の二項対立という従来の枠組みを乗り越える方法を模索する中から生まれてきた。そこで暗示されているのはモノについての言説ではなく、その構成そのものに焦点を当てた人類学の可能性である。本論文では、「相互所有」というモノ相互の特異な関係に注目したタルドの現代的な意味を確認した後、タイにもたらされた日本製の農業機械の事例を取り上げて、モノの内側にどのような関係が取り込まれており、それが移動の過程をへていかにして展開するのかを考察する。この事例では、設計の段階で機械に刻み込まれた日本の環境との関係が、タイの環境との不適応をとおして人々の前に浮かび上がってきた。このようにモノがその内に含み込んだ潜在的な関係を顕在化するプロセスを考察することは、人類学の鍵概念である比較や文脈といった概念に新しい角度から光を当てることでもある。
- 著者
- 奥野 克巳
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.4, pp.417-438, 2012
マレーシア・サラワク州(ボルネオ島)の狩猟民・プナン社会において、人は「身体」「魂」「名前」という三つの要素から構成されるが、他方で、それらは、人以外の諸存在を構成する要素ともなっている。人以外の諸存在は、それらの三つの要素によって、どのように構成され、人と人以外の諸存在はどのように関係づけられるのだろうか。その記述考察が、本稿の主題である。「乳児」には、身体と魂があるものの、まだ名前がない。生後しばらくしてから、個人名が授けられて「人」と成った後、人は、個人名、様々な親名(テクノニム)、様々な喪名で呼ばれるようになる。その意味において、身体、魂、名前が完備された存在が人なのである。人は死ぬと、身体と名前を失い、「死者」は魂だけの存在と成る。これに対して、身体を持たない「神霊」には魂があるが、名前があるものもいれば、ないものもいる。「動物」は、身体と魂に加えて、種の名前を持つ。「イヌ」は、イヌの固有名とともに身体と魂を持つ、人に近い存在である。本稿で取り上げた諸存在はすべて魂を持つことによって、内面的に連続する一方で、身体と名前は多様なかたちで、諸存在の組成に関わっている。諸存在とは、身体と魂と名前という要素構成の変化のなかでの存在の様態を示している。言い換えれば、諸存在は、時間や対他との関係において生成し、変化するものとして理解されなければならない。人類学は、これまで、精神と物質、人間と動物、主体と客体という区切りに基づく自然と社会の二元論を手がかりとして、研究対象の社会を理解しようとしてきた一方で、複数の存在論の可能性については認めてこなかった。そうした問題に挑戦し、研究対象の社会の存在論について論じることが、今日の人類学の新たな課題である。本稿では、身体、魂、名前という要素の内容および構成をずらしながら諸存在が生み出されるという、プナン社会における存在論のあり方が示される。
8 0 0 0 OA 世俗主義批判の射程 : イスラーム復興に関する人類学の最前線
- 著者
- 谷 憲一
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.4, pp.417-428, 2015-03-31 (Released:2017-04-03)
The aim of this paper is to shed light on a new approach to examining the Islamic revival in modern societies. This approach is often articulated by means of what I identify as the "critiques of secularism," insofar as it encompasses a wide range of criticism for secular societies. The Islamic revival has attracted the attention of many social scientists, since it contradicts the idea that modernization is accompanied by secularization. Some scholars make sense of the Islamic revival by studying the rise and growth of certain elements of modernity in Islamic societies. In the process, they tend to engage in the 'objectification of Islam' and thereupon establish some kind of relationship between the simultaneous historical processes of modernity and Islamic revival. Their approaches open a line of inquiry for comparative research, often pursued as a form of "multiple modernities." In contrast, the "critiques of secularism" approach reveals the problems of the "multiple modernities" theory, and inquires other aspects of Islamic revival through the West/Islam binary. Asad and his followers inquire into the problem of why we tend to see Islamic revival as a strange political development. Asad argued that in trying to define religion and its difference with other realms of religious societies, one is not only engaging in a theoretical question, but also simultaneously grappling with the political agenda of 'secularism,' eventually marking out a conceptual distinction between politics and religion. Secularism as an ideal concept often determines an anthropologist's work, so we must conspicuously describe how Islam is a mix of religion and otherwise related sociopolitical realms. In an interesting way, therefore, they problematize the asymmetry inherent in the binary of the West (as liberal secularism) and Islam, and by juxtaposing the West and Islam, criticize Western assumptions about liberalism and secularism. As a remedy to the incongruent binary, they use two distinct concepts for comparing Islam with the West symmetrically: Islamic discursive traditions and their practices of self-cultivation are contrasted with the beliefs and practices of secularism. Thus, their conceptual apparatus, which is inclusive of diverse beliefs and practices, urges us to rethink our assumptions about modern liberal secularism as well as about Islam. Mahmood and Hirschkind also admit that modern developments of Islamic revival in Cairo can be comprehended only by ethnographically describing specific aspects of pious Muslims' everyday activities. The critiques of secularism proffer a novel approach to exploring the phenomenon of modern Islamic revival movements. That is a major contribution to the disciplines of anthropology and Islamic studies, which we must appreciate appropriately to harness deep insights into modern societies. At the same time, one must not disregard how such ethnographies may be criticized by other intellectual perspectives. In other words, we must recognize what may become invisible in the wake of new insights, while committing coherently to various critiques of secularism and the attendant binary.
- 著者
- 深田 淳太郎
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.4, pp.535-559, 2009-03-31 (Released:2017-08-21)
パプアニューギニア、トーライ社会ではタブと呼ばれる貝殻貨幣が、婚資の支払いから秘密結社の加入の手続、役所での税金の支払いまで広い用途で用いられている。このように貨幣がなんらかの意味を持ち、その意味を様々に変え、また実効的な役割を果たすということはいったいどのような事態として考えられるだろうか。本稿では、貨幣やそれを用いた実践が特定の意味を持つことを、それが何であるのかが周囲の人々から見て分かり、説明(アカウント)できることと捉えるエスノメソドロジーの視点を採用する。ここで問うべきは、そのようなアカウンタブルな事態がいかにして出来上がっているのかということである。この問いを具体的に考えていくための事例としてトーライ社会の葬式を取りあげる。葬式においてトーライの人々はタブを用いて、死者への弔意を表し、自らの豊かさを誇示し、他の親族集団と良好な関係を築くなど様々なことを行なう。周囲から見て、個々のタブ使用実践がこれらの様々な意味や効果を持つものと分かるのは、それがなんらかの秩序だったコンテクストの中に位置付けられることによってである。だが同時に、そのようなコンテクストは個々の実践を通して可視化され生成されるものでもある。本稿では葬式におけるタブ使用実践が、そのときどきのコンテクストに沿った適切なやり方でなされながら、同時に周囲の様々な要素との関係の中で当のコンテクストを生成していく相互反照的な生成の過程を記述し、その過程から貝貨タブが具体的な意味や効果を持つものとして可視化されてくる様子を明らかにする。
- 著者
- 中生 勝美
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, 2016
第二次世界大戦中に、アメリカの人類学者の90%が軍事・政治組織にかかわっていた。人類学者を、軍事的な活動の必要に応じて差配していたのはクラックホーンであった。アメリカの対日戦を理解するためには、日本語資料を駆使する必要がある。今回、4つの事例から日本との戦争を通じて、アメリカの人類学がどのように変容し、国家機関や軍事部門に如何にかかわっていったのかという観点から、アメリカの人類学史を描いてみる。
7 0 0 0 OA 脱-薬剤化と「現れつつある生のかたち」
- 著者
- 牛山 美穂
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.4, pp.670-689, 2017 (Released:2018-02-23)
- 参考文献数
- 26
本稿では、「生物学的シチズンシップ」の活動のひとつの事例として、東京のアトピー性皮膚炎患者にみられる脱-薬剤化の現象について論じる。アトピー性皮膚炎の標準治療においては、通常ステロイド外用薬が用いられるが、これが効かなくなってくるなどの問題を訴える患者が一定数存在する。しかし、こうした患者の経験は「迷信」に基づくものと捉えられ、既存の医学知のなかでは適切な位置づけがなされていない。そのため、一部の患者は標準治療に背を向け、脱ステロイド療法と呼ばれる脱-薬剤化の道を選択する。 薬剤を摂取すること、そして薬剤から離脱することは、薬剤の成分を体内に取り入れる、またはそれを中止するということ以上の意味をもつ。薬剤化および脱-薬剤化は、それ自体、生物学的-社会的な自己形成の過程でもある。薬からの離脱は、患者の知覚の仕方を規定し、価値観や判断に影響を与える。そして、そうした判断がさらに身体や価値観を変化させていく。 本稿では、脱-薬剤化の現象がどのように患者に経験されるのかをミクロな視点から描き出すとともに、患者の身体的な経験がいかなる知として位置づけられうるかという点について考察を行う。標準治療を行うにしても脱ステロイド療法を行うにしても、アトピー性皮膚炎治療は患者の身体と生活を巻き込んだ生社会における実験という形をとって現われる。本稿では、薬剤化が進行していくなかで出現してきた脱-薬剤化を試みる患者のあり方を、実験社会におけるひとつの「現れつつある生のかたち」として描き出す。
7 0 0 0 OA 邪視研究の動向
- 著者
- 清水 芳見
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.91-100, 1983-06-30 (Released:2018-03-27)
7 0 0 0 OA アラブ・ムスリムの幽霊観 : エジプトの事例を中心に(<特集>イスラーム)
- 著者
- 清水 芳見
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.333-341, 1985-12-30 (Released:2018-03-27)
- 著者
- 箭内 匡
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.180-199, 2008-09-30 (Released:2017-08-21)
- 被引用文献数
- 1
本稿は、人類学的実践を言葉のみならずイメージの実践として再考しつつ、そうした「イメージの人類学」の中で、民族誌映像(写真、映画、ビデオ)の役割を考えることを提案するものである。ここでイメージとは、我々の意識に現前するすべてを指し、例えば人類学者のフィールド経験のすべては、一つのイメージの総体と見ることができる。民族誌映像は、こうしたフィールド経験のイメージ(より正確には、それに近いもの)の一部を定着させ、言葉による人類学的実践が見えにくくしてしまうような経験の直接的部分を我々に垣間見せてくれる。そうした視角から本稿でまず考察するのは、マリノフスキー、ベイトソン、レヴィ=ストロースの民族誌写真であり、そのショットの検討を通じ、各々の理論的実践がその下部で独自の「イメージの人類学」によって支えられていることを示す。そのあと、フラハティ、ルーシュ、ガードナー、現代ブラジルの先住民ビデオ制作運動の作品を取り上げ、映像による表現が、言葉による人類学が見逃してきたような民族誌的現実の微妙な動きや質感、また調査者と被調査者の間の関係を直接的に示しうることを示す。このように「イメージの人類学」を構想し、その中で民族誌映像の役割を拡大することは、「科学」と「芸術」が未分化な場所に人類学を引き戻し、それによって言葉による人類学的実践をも豊かにするであろう。
7 0 0 0 OA 「失伝」の研究 家元制下の「古武道」を事例として
- 著者
- 足立 賢二
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第57回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.A12, 2023 (Released:2023-06-19)
コロナ後における「日本の伝統」の継承のあり方を議論する上での基礎資料を抽出することを目的として、特に「古武道」を対象とし、近現代において家元制を採用していた古武道流派にかかる①門人帳の分析と②関係者への聞き取り調査の結果の分析により、その流派の「失伝」の過程を検討した。検討結果からは、「古武道」という伝統にあっては、入門者の低年齢化が「失伝」を加速させた可能性があることが判明した。