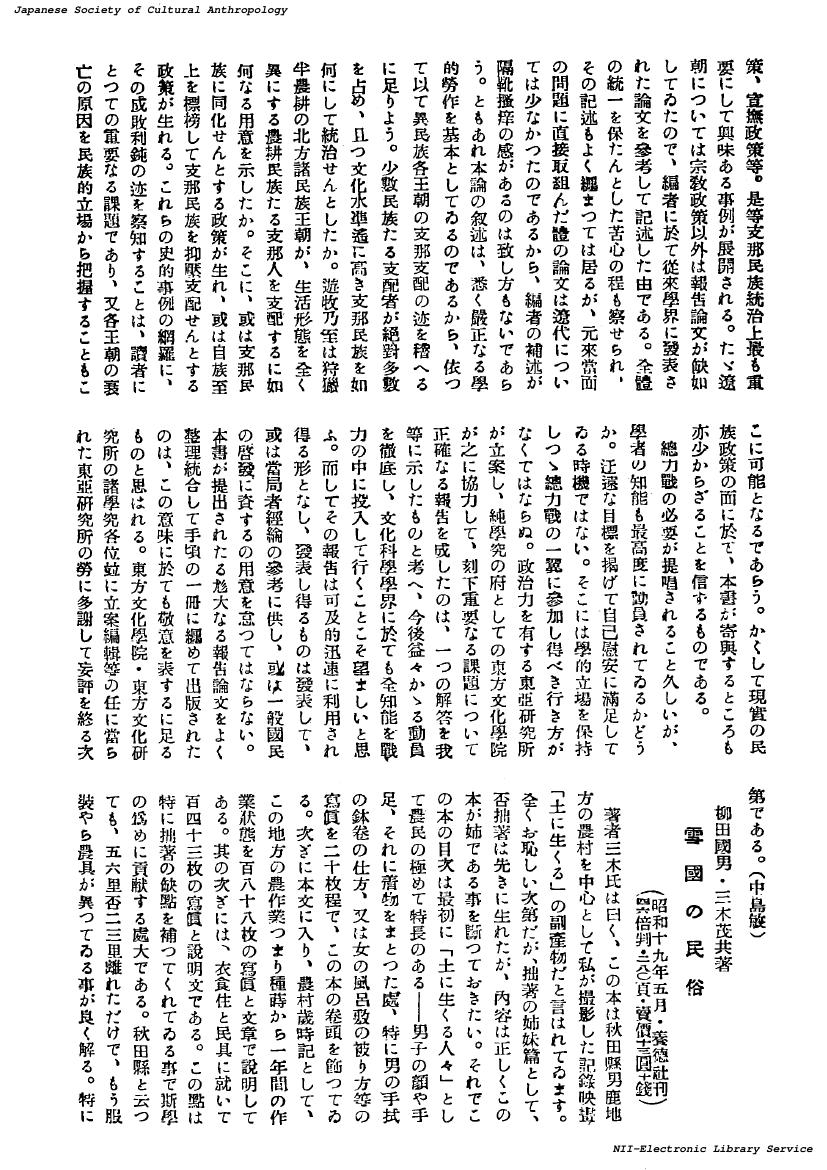- 著者
- 森下 翔
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.1, pp.005-021, 2020 (Released:2020-10-08)
- 参考文献数
- 30
本論の目的は、人間と実在の峻別を前提とする「自然主義的な」科学とは異なるものとして自らの実践を定位する科学者たちの実践を記述することにある。西欧近代を支配する自然主義的な存在論は、自然科学における表象主義的認識論と平行して形成されてきた。近年の科学論では、自然主義的存在論の特徴である実在の連続性と内的世界の離散性はさまざまな仕方で批判されてきた。しかし現在もなお、物理を代表とする科学実践は表象主義的認識論を、少なくとも部分的には自らの実践の妥当な記述として受け入れることが可能であり続けている。本論では、「物理」を表象主義的な実践として捉えながら、自らの実践を「物理」とは異なる「非自然主義的」なものとして捉える固体地球物理学者たちの実践の特徴を、「融合」という概念のもとに描き出す。決定論的な予測が困難な複雑系を扱う固体地球科学者たちは、ベイズ統計学を基礎とする確率論的な手法に基づき地球の内部状態を推定する。彼らの実践は、「観測データへの不信」や「ア・プリオリなデータ」といった一見すると奇妙な観念によって特徴づけられる。「融合」の科学においては人間の仮定や評価が一種の「データ」として扱われ、モデルとデータは単純に「比較」されるのではなく、「インバージョン」や「データ同化」によって観測データがモデルへと「取り込」まれる。このことにより、人間の評価と観測データが渾然一体となった「成果」が生み出される。そのような「成果」は、もはや世界と人間の二元論を前提とした「客観的な表象」ではなく、観測データと人間のモデル評価が独特の仕方で入り混じったハイブリッドなイメージである。
- 著者
- シンジルト
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.4, pp.439-462, 2012-03-31 (Released:2017-04-17)
- 被引用文献数
- 1
他のチベット仏教系の牧畜地域と同様に、河南蒙旗でも、ある家畜個体を屠らず売らず、その命を自由にするツェタル実践がみられる。ツェタル実践の動機は多様であるが、そのほとんどは、牧畜民と家畜個体との間に共有される日常的な喜怒哀楽に基づく経験である。家畜の種を問わず、原理的にあらゆる個体がツェタルの対象になりうる。この実践は、仏教の教義に基づく放生や功徳を目的としたものだとする説明もありえよう。だが河南蒙旗におけるツェタル実践をみる限りこうした説明に還元できない、特定の個人と特定の家畜との特定の出来事を契機に結ばれる固有の関係が確認される。こうした関係は、ツェタル家畜の個体を人と神の関係を表す象徴的存在だとする見方、個体を分類体系の種的範疇の延長や限界だとする見方では、捉えきれない。むしろ、人間個人と家畜個体との固有の関係が、ツェタル実践のそのものであると捉えるべきである。一方で、ツェタル家畜は、そうした関係のインデクスとして働き、自らの外見や経験をもって、自分と特定の人間との関係を結ぶ当事者となり、個体性を獲得する。他方、人間がツェタルに選ばれる家畜に言及する際に用いる有力な表現の一つは、絶対的幸運を意味するヤンである。ツェタルすることで、人間も家畜もヤンを高めることができるという。これがツェタル実践の論理となる。ヤンは、人間や家畜に限らず万物の中に遍在し、一般性をもつ。他方、ヤンは種の範疇を素通りし、万物の個体の中へ内在して、具体性ももつ。ヤンの具体性が人間と家畜の固有の関係の反映であり、ヤンの一般性はそうした固有の関係を屠らず売らないという行為と結合させ、ツェタルという名の実践を形成維持していく。この実践において、人間と家畜の固有の関係がヤンによって形象化されると同時に、ヤンの循環によって、家畜同士、人間と家畜の間に連続性が打ちたてられる。
6 0 0 0 文化の客体化--観光をとおした文化とアイデンティティの創造
- 著者
- 太田 好信
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族学研究 (ISSN:00215023)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.4, pp.p383-410, 1993-03
- 被引用文献数
- 4
本論は、文化の担い手が自己の文化を操作の対象として客体化し,その客体化のプロセスにより生産された文化をとおして自己のアイデンティティを形成する過程についての分析である。現代社会において,文化やアイデンティティについて語ることは,きわめて政治的にならざるをえない。したがって,この客体化の過程も,その対象や方法,またその権利などをめぐる闘争に満ちている。文化の客体化を促す社会的要因の一つは観光である。観光は「純粋な文化」の形骸化した姿を見せ物にするという批判もあるが,ここでは,観光を担う「ホスト」側の人々が,観光という力関係の編目を利用しながら,自己の文化ならびにアイデンティティを創造していることを確認する。つまり「ホスト」側の主体性に立脚した視点から観光を捉え直す。国内からの三事例を分析し,「真正さ(authenticity)」や「純粋な文化」という諸概念の政治性を再考する。
- 著者
- 新本 万里子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.1, pp.25-45, 2018
<p>本稿は、モノの受容を要因とするケガレ観の変容を、女性の月経経験に対する意識とその世代間の違いに着目して明らかにすることを目的とする。パプアニューギニア、アベラム社会における月経処置の道具の変遷にしたがって、月経期間の女性たちがどのような身体感覚を経験し、月経期間をどのように過ごしているのかについて民族誌的な資料を提示する。その上で、月経を処置する道具を身体と外部の社会的環境を媒介するものとみなし、そこにどのような意識が生じるのかを考察する。これまで、パプアニューギニアにおいて象徴的に解釈されてきた月経のケガレ観を、女性たちの月経経験とケガレに対する意識との関連という日常生活のレベルから捉え直す。</p><p>本稿では、月経処置の道具の変遷にしたがい、女性たちを四世代に分類した。第一世代は、月経小屋とその背後の森、谷部の泉という場で月経期間を過ごした世代である。第二世代の女性たちは、布に座るという月経処置を経験した。この世代は、月経小屋が土間式から高床式に変化し、さらには月経小屋が作られなくなるという変化も経験している。第三世代は、下着に布を挟むという月経処置をした女性たちである。第四世代は、ナプキンを使用した女性たちである。各世代の女性たちの月経経験とケガレに対する意識との関係の分析を行い、第一世代の女性たちは、男性の生産の場から排除される自分の身体にマイナスの価値づけだけをしていたのではなく、むしろ男性の生産の場に入らないことによって、男性の生産に協力するという意識をもっていたことを明らかにする。第二世代、第三世代を経て、第四世代の女性たちは、月経のケガレに対する意識を維持しながらも、月経期間の禁忌をやり過ごすことができるようになったことを論じる。</p>
- 著者
- 野元 美佐
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3, pp.353-372, 2004-12-31
本研究は、カメルーンの商売民として有名な「バミレケ」が活発に行っている金融システム「トンチン(頼母子講、講、無尽)」を、貨幣に着目して考察し、ひとびとがなぜトンチンを行うのかを明らかにしたものである。バミレケは、露天商から大企業家まで、銀行がたちならぶ都市においてもトンチンを積極的に行っており、トンチンは彼らの経済的成功の要因のひとつとされている。しかしトンチンには、資金創出以外にも大きな役割がある。バミレケは都市で同郷会を組織しているが、そこではトンチン参加が義務付けられている。トンチン参加を強いることは、トンチンに支払うためにカネを稼ぐことを強いることである。つまりカネを稼ぐという「個人的行為」を、トンチンにリンクすることにより「集団的行為」へと変化させている。ではなぜトンチンが集団的行為であり、相互扶助だと考えられるのであろうか。それは、トンチンが贈与交換だからである。みなのカネをまとめて、一人の人に与えるトンチンは、贈与であるからこそ、「助け合い」であり「善きもの」と言われるのである。そして重要なのは、そこに持ち寄られ、「贈与」される貨幣も善となることである。個人的で利己的な貨幣は、集団的資源としての貨幣へと意味を変える。平等化の圧力が強く、資本蓄積が難しいとされるカメルーンにおいて、バミレケはトンチンを介すことでカネを稼ぐことを正当化し、資本蓄積の場を獲得する。これが、人びとがトンチンを好む理由であると考える。またこれまで貨幣は、ひとびとの連帯を破壊するものと考えられる傾向にあったが、バミレケの事例で、トンチンによって貨幣が人と人をつなぐ道具として用いられていることを明らかにできた。
- 著者
- 細谷 広美
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.4, pp.566-587, 2013-03-31
冷戦の終結以降、国際社会では人権の尊重とデモクラシーに対する説明責任(accountability)が国家に要求される傾向が強まっている。しかしながら、人権やデモクラシーは元来西欧で生まれた概念であり、グローバル化の進展にともない、多様な歴史や文化的背景をもつ地域に人権概念が適用されるようになることで、地域のコンテクストやそれぞれの文化にみられる人権概念との間の相違が顕在化してきている。このようなことから近年、人権概念の普遍性を問う議論が生まれている。本稿は紛争後の移行期正義とかかわり真実委員会が設置されたペルーを事例として扱う。ペルーでは1980年に毛沢東系の集団「ペルー共産党-輝ける道」(PCP-SL)が武装闘争を開始したことで、国家機関(政府軍、警察、自警団)と反政府組織による住民の大規模な虐殺が展開した。2003年に提出された真実和解委員会(真実和解委員会は真実委員会として総称される)の最終報告書によると、1980年から2000年の死者及び行方不明者数は、独立後最大の約7万人に及び、このうち75%が先住民言語の話者であった。また死者及び行方不明者のうち40%が、国内で最も貧しく先住民人口が多い県の一つである山岳部のアヤクチョ県に集中していた。このようなことから、本稿では文化、人種・民族的多様性と不平等を抱える社会における紛争と平和構築のプロセスを、人権や市民権をめぐる議論を視野に入れつつ、先住民と紛争及び真実委員会の関係に焦点をあてて分析した。そして、紛争時及び紛争後の平和構築のプロセスにおいて、国際社会の人権レジームと国家が接合される一方、国内の特定集団がこのプロセスから排除される可能性があることを明らかにした。さらに、「真実」や「和解」の意味も紛争の性質や社会の特質によって多様であることを論じた。以上のことから、人権や人間の安全保障を適用するうえでは、合わせて当該社会における「人間」の意味や範囲を検証する必要性があることを指摘した。
6 0 0 0 OA 身体に発現する呪いと軋轢の解消
- 著者
- 深川 宏樹
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第45回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.92, 2011 (Released:2011-05-20)
本発表では、ニューギニア高地エンガ州における呪いの事例から、軋轢の解消と身体の社会的構築の関係について論じる。エンガ州では、ある人が軋轢を理由に他人に悪意を抱いて死ぬと、それが呪いとなって相手を重病におとしいれる。人は重い病にかかると、故人との軋轢を想起し、故人の息子との仲裁で軋轢の解消を試みる。この事例から本発表では、個人の身体の変調や死が、軋轢の解消を導く社会的過程の要となっていることを論じる。
6 0 0 0 OA 見えないタトゥーをもつこと
- 著者
- 津村 文彦
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 日本文化人類学会研究大会発表要旨集 日本文化人類学会第50回研究大会 (ISSN:21897964)
- 巻号頁・発行日
- pp.H12, 2016 (Released:2016-04-23)
タイ王国では現在も若者を中心にタトゥーが流行し、大きくファッション・タトゥーと呪術タトゥーに二分できる。呪術タトゥーは、通常黒色インクを用いて、文様や動物、神々、経文を身体に刻みこむ。しかしときにインクを用いない「見えないタトゥー」が実践される。本報告では、東北タイのタトゥー事例を通して、「見えるタトゥー」との比較のもと、「見えないタトゥー」を取り巻く物質的、宗教的、および社会的状況を検討する。
- 著者
- Inose Kohei
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- Japanese review of cultural anthropology
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.141-150, 2014
The experience of facing radioactive contamination caused by the accident at the Fukushima No. 1 nuclear power plant has touched the hearts and minds of the effected people. The nature of radiation, which is silent, invisible, and untouchable, has impeded people's clear understanding of its reality, dividing their opinions and attitudes about its impacts on their lives. The conventions holidng the people together around a shared sense of reality broke down, and consequently, they began to combine fragments of knowledge at hand in order to live in an uncertain world. This article is based on observations of a community farm in Saitama Prefecture where I have been volunteering. In this crisis, members of this community contingently modify their own ideas through heterogeneously networked connections including scientific knowledge, the farming method of organic farmers in Fukushima and their own local history. I explore how people construct counter-practices in the face of nuclear accidents and discuss what the public function of ethnographic description is in this case.
5 0 0 0 OA 対抗的な〈世界〉の制作 アメリカにおけるファット・アクセプタンス運動の実践を事例に
- 著者
- 碇 陽子
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.4, pp.513-533, 2016 (Released:2017-02-28)
- 参考文献数
- 34
本稿の目的は、アメリカを中心に展開する肥満差別の廃絶を訴えるファット・アクセプタンス 運動の実践を、哲学者ネルソン・グッドマンの世界制作論に依拠しながら、〈世界〉の制作として記述することである。 ファット・アクセプタンス運動は、公民権運動が盛り上がりを見せる時期のアメリカで1969年 に誕生した。しかし、これまで肥満差別は、人種差別やジェンダー差別などに比べ、廃絶すべき差別として捉えられてこなかった。なぜなら、体重やサイズをあらわす「ファット」カテゴリーは、「公民権法」が擁護する「人種」や「性別」などの公民権カテゴリーと比べ、「本質的」なカテゴリーではないと考えられてきたからだ。 ところが、1980年代後半から、アメリカでは肥満者の急増が社会問題化された。肥満は、病気を引き起こすリスク要因として公衆衛生の予防介入政策の対象となり、健康を自己管理し病気を 予防することは個人の「義務」となりつつある。本稿では、こうした時代を、一方で、不確実性の忌避やリスク管理を志向しながらも、他方では、未来は完全に管理できないという矛盾した事実に直面しながら生きなければならない時代と位置付けた。そして、こうした時代状況で、運動参加者が、肥満を病理化する医学的疫学的な知に対抗し、「ファット」カテゴリーが属する新たな知の体系を再構築していく実践を、対抗的な〈世界〉の制作として描写した。 描写を通じて明らかにされたのは、対抗的な二つの世界は、隔絶しているように見えて、むしろ、近接しているのではないかということである。その近さゆえに、ファット・アクセプタンス運動の人々は、二つの世界をどちらも不完全なまま部分的に通約(不)可能な存在として生きなければならない。この考察から、結論では、文化相対主義を再考し、あらゆる視点から離れた世界はないという「徹底した相対主義」から世界を理解することの意義が明らかになった。
- 著者
- 中川 理
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.4, pp.586-609, 2009-03-31 (Released:2017-08-21)
- 被引用文献数
- 3
本論は、よりアカウンタブルになっていく世界における人々の経験の不確実性のゆくえを、フランスにおける連帯経済という事例を通して問うものである。連帯経済とは市場経済の全面化に対抗して互酬性や贈与の理念にもとづいた経済を作り出していこうとする動きである。本論では、この動きをよりアカウンタブルな世界の構築として分析する。そのためにまず、よりアカウンタブルな世界の構築とは何かを先行研究の解読を通して明らかにする。そこで明らかにされるのは、人びとの認知を標準化し媒介するもの(本論ではそれをディスポジティフと呼ぶ)がつくられ配置されていくことによって、不確実だった日常世界をより客観的なかたちで認識することが可能になるという意味でのアカウンタビリティと、人びとの活動をなぜそうするのがよいのかはっきりと言葉で説明できるという意味でのアカウンタビリティを同時に作り出していくということである。この観点から連帯経済は、互酬性や贈与の価値にもとづくアカウンタブルな世界を作り出していくものとして理解できる。しかし、そこでは人々の経験は確実で説明可能なものへと飲み込まれていくのだろうか?これが本論の問いである。日常的文脈における交換の事例を通して、本論ではディスポジティフが世界を説明可能にする力は限定的であり、状況は多くの場合あいまい、不透明、不確実であることを示す。そして、このような状況での行為はアカウンタブルではない「賭け」となると論じる。
5 0 0 0 コミュニティを想像する : 人類学的省察(学会賞受賞記念論文)
- 著者
- 田辺 繁治
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.3, pp.289-308, 2008-12-31
本稿は日本文化人類学会第42回研究大会(2008年6月1日、於京都大学)における第3回日本文化人類学会賞受賞記念講演の内容を書き改めたものである。その目的は、1960年代末から今日にいたる私自身の人類学研究をふり返りながら、人びとが想像的、再帰的な実践のなかでコミュニティを構成していく過程を考察することにある。ここではコミュニティとは、すでにそこに存在するものばかりでなく、人びとの欲望、想像や思考の展開のなかで実践的に創られていくという視角から考える。そこでまず1970年代以降に現れたブルデューやレイヴ/ウェンガーらの実践理論を批判的に検討しながら、コミュニティが多様な権力作用のなかで形成されることに注目する。ここでいう権力作用とは他者にたいする外部からの支配だけでなく、イデオロギーや言説のように、人びとの認知様式や価値評価に影響をおよぼし、秩序の承認へと導く効果を含んでいる。そうした権力作用にたいする抵抗あるいは闘争を描くことは20世紀末の民族誌の重要なテーマであり、そこには西欧近代の主体概念とは異なったエージェンシーの躍動が浮き彫りになった。私が取り組んだ北タイの霊媒カルトやエイズ自助グループの研究も、病者や感染者たちがコミュニティのなかで自己と他者、権力の諸関係を想像的、再帰的な実践をとおして創りなおしていく過程に焦点をあてるものであった。彼らの実践の資源となるのは合理主義的知であるよりは、むしろコミュニティに埋め込まれた自分たちの<生>にかかわる解釈学的知である。しかし他方、近年の社会的マネージメントの展開において、こうしたコミュニティのなかに形成される共同性そのものが、国家、企業、NGOなどを含む多様な権力が介入する回路や標的となっていることに注目しなければならない。そこでフーコーの統治性の概念は、権力がそうしたコミュニティの枠組みをとおして介入し、自己規律化するフレキシブルな主体を構築していくことを分析するにあたって有効だと考えられる。このようにして人びとが想像力によってコミュニティを新たな共同性として構成してゆく道筋は、統治テクノロジーの作用による自己規律化と重なりあっているのであり、人類学はそうした重層的過程にアプローチする必要があるだろう。
- 著者
- 関根 康正
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.3, pp.478-484, 2013-01-31 (Released:2017-04-10)
5 0 0 0 OA 杖のみたま : 十勝アイヌ故老談話記録
- 著者
- 吉田 巖
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:24240508)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3-4, pp.313-334, 1956-03-25 (Released:2018-03-27)
- 著者
- 吉田 三郎
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族研究彙報 (ISSN:24330760)
- 巻号頁・発行日
- vol.Research3, no.1-2, pp.36-37, 1945-08-30 (Released:2018-02-23)
- 著者
- 野澤 豊一
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.3, pp.417-439, 2010-12-31
本稿では、米国黒人ペンテコステ派キリスト教会で実践される儀礼的トランスダンス「シャウト」の成立過程を例に、トランスダンス出現のメカニズムとその表現上の特性について考察する。従来の研究では、トランスダンスは文化的に構築された表象として理解されてきたが、この接近法はペンテコステ派の実践の核心にある「非決定性」を正しく把握するのに重大な余地を残している。「非決定性」とは、礼拝におけるシャウトの即興性やペンテコステ的な信仰を支える受動性を包含する概念である。この非決定的なプロセスを可視化するために、本稿では、シャウト出現時の即興的な信者間のやりとり(及びそこで成立する関係性)に注目し、シャウトが出現するメカニズムを「相互行為の構造」として把握する。それによりシャウトは、<没入者(シャウトする者)>とそれに対する<関与者>との間の、「<没入-関与>関係」から出現すると記述することが可能になる。こうした用語が有意味なのは、シャウトの正しい成立にあって、シャウトが踊られること自体よりも、<没入-関与>関係の十全な成立の方が有意な場面があるからである。これらの場面からは、対面相互行為における個人の没入行為が、他者との相互的な自発性によってはじめて達成されるという事実が確認できる。これが相互行為の相におけるシャウトの「非決定性」の内実であり、これには対面相互行為に本来的な「ユーフォリア」が伴う。シャウトという身体的表現は宗教的には「聖霊の働き」と解釈しうる。だが、その出現過程を関係性から記述することは、シャウトが、他者との関係性の切り結びを希求する、「表情性」豊かな身ぶりでもあるという発見につながる。相互行為としての非決定性と身ぶり表現としての表情性という2つの特性は、シャウトという超越体験と日常性とのつながりを視野に入れることによって、はじめて意義深いものとして発見されるといえる。
5 0 0 0 OA ジェノサイドへの序曲 : 内モンゴルと中国文化大革命(<特集>先住民と<国民の歴史>)
- 著者
- 楊 海英
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.3, pp.419-453, 2008-12-31 (Released:2017-08-21)
社会主義者たちは「民族の消滅」を理想に掲げ、そのために闘争してきた歴史がある。中国共産党は文化大革命中に、彼らが得意としてきた暴力で以て「民族の消滅」を実現させようとした。内モンゴル自治区では、この地域が中国領とされたがゆえに、モンゴル人を対象とした大量虐殺事件が発生した。本稿は、中国文化大革命中の1967年末期から1970年初頭にかけて、内モンゴル自治区で発生した「内モンゴル人民革命党員大量虐殺事件」をジェノサイド研究の視点からアプローチしたものである。内モンゴル人民革命党は、モンゴル族の自決と独立のために、1925年にモンゴル人民共和国とコミンテルンの支持と関与のもとで成立した政党である。その後、日本統治時代を経て、第二次世界大戦後にモンゴル人民共和国との統一を目指したが、中国共産党によって阻止された。文化大革命中に「内モンゴル人民革命党の歴史は偉大な祖国を分裂させる運動である」と毛澤東・中国共産党中央委員会から断罪され、モンゴル人のエリートたちを根こそぎ粛清する殺戮が発動されたのである。本研究は、従来から研究者たちによって指摘されている「国民国家型ジェノサイド」理論に沿って、ジェノサイドと近代の諸原理とりわけ国民国家と民族自決の問題との関連性に焦点をあてている。国民国家たる中国からの統合と、その統合に反対して別の国民国家を建設しようとしたモンゴル人たちが大量虐殺の対象にされた経緯を分析したものである。「モンゴル人ジェノサイド」に社会主義中国の対少数民族政策の強権的、暴力的な本質が内包されている。
- 著者
- 内山田 康
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.158-179, 2008-09-30
アルフレッド・ジェルは、美学的な芸術の人類学の方法は行き止まりに突き当たると言った。それはどのような行き止まりだったのか。この行き止まりを超えることはどのようにして可能だとジェルは考えていたのか。このような疑問に突き動かされて本稿は書かれている。ジェルのArt&Agency(以下AA)を批判したロバート・レイトンは、ジェルが芸術の人類学を議論する時、文化や視覚コミュニケーションを重要視しない点を批判した。もしも見直す時間が残っていたら、ジェルは、このような点を書き改めたに違いないとレイトンは言う。レイトンはジェルの作品全体の中にAAを位置づけなかったから、このような仮定が立てられたのだろう。私はAAをジェルのより大きな作品群の中に位置づけなおして、ジェルの芸術の人類学が前提とした認識論へ接近しつつ、その芸術の人類学で重要な役割を果たした再帰的経路の働きと、図式の転移について考察する。
- 著者
- 近藤 祉秋
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.4, pp.463-474, 2012-03-31
This paper aims to discuss the human-animal continuity through theoretical and ethnographic perspectives on the relationship between humans and animals in Japan. Pamela Asquith and Arne Kalland proposed a nature continuum in which humans perceive and act upon nature in two opposite directions: on one hand, domesticated nature, whose beauty is cherished, and on the other, wild nature, that must be tamed by human interventions. However, the model of nature continuum proposed by Asquith and Kalland is not necessarily compatible with theories of the human-animal relationship in Japan. John Knight argued that Japanese people show enmity toward wild animals that feed on the crops they have grown, but also mentioned that interactions with pests give them an opportunity to realize a continuity between humans and animals. Kenichi Tanigawa likewise stressed the fact that the human-animal (-spirit) continuity is based on competitions among them. While Asquith and Kalland assumed the existence of two perceptions of "nature" among the Japanese, and stressed the human intervention that transforms wild nature into a domesticated one, Knight and Tanigawa's discussions called for a more sophisticated analysis on human-wildlife continuity that can even accommodate rivalry between the two. Moreover, as I try to demonstrate in the discussion to follow, the model of nature continuum proposed by Asquith and Kalland cannot explain the seemingly "cultural" characteristics that cats in Oki Islands were said to possess, leaving the impression that this model has limited applicability for studying the human-animal relationship. Based on the case study of the human-cat relationship in the Oki Islands, I argue that humans and cats share "one culture," in that both compete for fish, have a linguistic capacity, engage in dancing and singing with other fellows, formulate stable marital bonds with another individual of the same species, sometimes try to modify their environments through manipulation, and do "sumo wrestling" between the two species. It is then suggested that the human-cat relationship in the Oki Islands can be understood in terms of a human-animal continuity based not only on human-animal competition over the same food, but also on the sharing of "one culture" between the two species. I then argue that Amerindian "multinaturalism," a term proposed by Eduarudo Viveiros de Castro as a possible cosmological model of Amerindians, has an analogy with the human-cat relationship in the Oki Islands, in that humans and non-humans share "one culture" in both cases. Since Viveiros de Castro mentioned the sharing of "one culture" as "animism," it is suggested that the human-cat relationship in the Oki Islands can be characterized as "animism" in his sense. In spite of the abovementioned similarity, there exists an important contrast in those two examples: the "many natures" in Amerindian "multinaturalism," and the Japanese human-animal continuity that is revealed through human-animal competition over common staples, a point already mentioned by John Knight and Kenichi Tanigawa in their studies on human-animal relationship in Japan. Therefore, the tentative conclusion of this paper is that the human-animal relationship in Japan should be analyzed with the two interconnected dimensions of the human-animal continuity in mind, and that recent discussions on "animism" should offer valuable insights to an investigation of the topic.
- 著者
- 橋本 裕之
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:00215023)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.4, pp.537-562, 1998-03
- 被引用文献数
- 2
近年, 人文科学および社会科学の諸領域において文化の政治性や歴史性に対する関心が急速に高まった結果として, 博物館についても展示を巨大な言説の空間に見立てた上でテクストとしての展示, もしくは表象としての展示に埋めこまれたイデオロギー的な意味を解読した成果が数多く見られる。だが, 展示をとりあげることによって表象の政治学を展開する試みは, 理論的にも実践的にも限界を内在しているように思われる。そこで決定的に欠落している要素は, 来館者が構築する意味に対する視座であろう。展示がどう読めるものであったとしても, 来館者が展示された物をどう解釈しているのかという問題は, 必ずしも十分に検討されていないといわざるを得ないのである。本稿は以上の視座に依拠しながら, 博物館において現実に生起している出来事, つまり来館者のパフォーマンスを視野に収めることによって, 博物館における物を介したコミュニケーションの構造について検討するものであり, 同時に展示のエスノグラフィーのための諸前提を提出しておきたい。実際は欧米で急成長しているミュージアム・スタディーズの成果を批判的に継承しつつも, 私が国立歴史民俗博物館に勤務している間に知ることができた内外の若干のデータを演劇のメタファーによって理解するという方法を採用する。じじつ博物館は演劇における屈折したコミュニケーションにきわめて近似した構造を持っており, そもそも物を介したインターラクティヴ・ミスコミュニケーションに根ざした物質文化の劇場として存在しているということができる。こうした事態を理解することは民族学・文化人類学における博物館の場所を再考するためにも有益であると思われる。