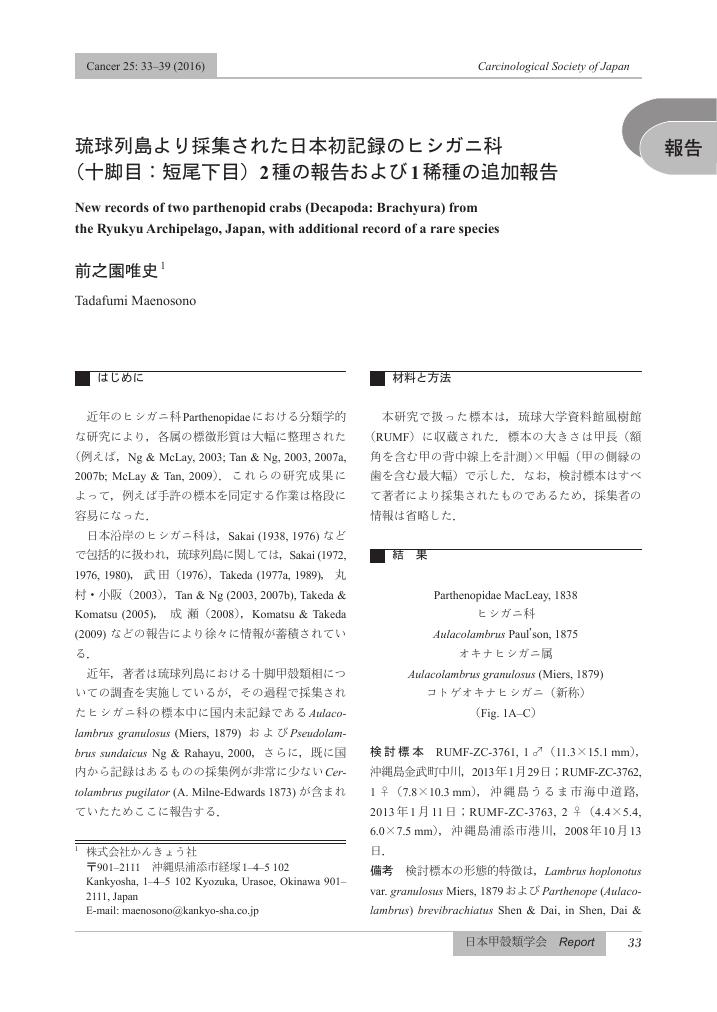- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経ビジネス (ISSN:00290491)
- 巻号頁・発行日
- no.1724, pp.24-31, 2014-01-13
日進月歩で姿を変える、経済成長著しい中国・上海市。賑やかな繁華街を歩けば、見慣れた看板を目にすることになる。セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート──。国内コンビニエンスストア3強が出揃い、覇を競う。
2 0 0 0 食品リサイクル 再資源化率向上迫られる外食、チェーン超えた連携も
- 著者
- 相馬 隆宏
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経エコロジー (ISSN:13449001)
- 巻号頁・発行日
- no.96, pp.62-65, 2007-06
ファミリーレストランの「ロイヤルホスト」は今年4月13日から、九州地区と広島地区の53店舗でジャガイモのポタージュを期間限定メニューに加えた。珍しいものではないが、原料のジャガイモにほかとは違う特徴がある。実はこのジャガイモは、店舗から出た食べ残しなどを混ぜた堆肥を利用して作られたものだ。
2 0 0 0 OA 平成20-22年度 吉野山サクラ調査報告書
- 著者
- 石倉 和将 松本 光広
- 出版者
- 一般社団法人映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 : 映像情報メディア (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.8, pp.698-701, 2012-08-01
2 0 0 0 気胸に対するドレナージで肺の再膨張後に発症した血胸の1例
- 著者
- 川井 廉之 星 永進 高橋 伸政 池谷 朋彦 村井 克己
- 出版者
- Japan Surgical Association
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.8, pp.1978-1981, 2011
症例は30歳,男性.前医にて緊張性気胸に対する胸腔ドレナージ後に血胸を呈し,医原性の血胸が疑われ当センターへ緊急搬送された.胸部X線写真にて右胸腔に大量胸水貯留を認め,ドレーンからの出血が続いていたため,血気胸の診断で胸腔鏡下緊急止血術を施行した.出血は肺尖部対側の胸壁の断裂した血管からであり,自然血気胸と診断した.術後,再膨張性肺水腫を発症したが,その後の経過は良好で,術後第7病日に軽快退院となった.自然血気胸の中には本例のように初回胸部X線写真で胸水貯留が認められない症例があり,早期の診断と治療のためには,ドレナージ後の注意深い経過観察が重要である.
2 0 0 0 IR Ghost Chimneys
- 著者
- Charlton David Demaine Erik D. Demaine Martin L. Dujmovic Vida Morin Pat Uehara Ryuhei
- 出版者
- World Scientific Publishing
- 雑誌
- International Journal of Computational Geometry and Applications (ISSN:02181959)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.207-214, 2012
A planar point set S is an (i, t) set of ghost chimneys if there exist lines H_0, H_1,…,H_<t-1> such that the orthogonal projection of S onto H_j consists of exactly i + j distinct points. We give upper and lower bounds on the maximum value of t in an (i, t) set of ghost chimneys, showing that it is linear in i.
- 著者
- 朝永聖也 中島伸介 稲垣陽一 中本レン 小倉僚 張建偉
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 研究報告データベースシステム(DBS)
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, no.1, pp.1-8, 2013-11-19
有望な流行語候補を早期に発見する手法の一つとして,流行語先読みブロガーの発見を目指している.この流行語先読みブロガーの発見を行うために,過去の流行語に対してどの程度早くから言及していたのかを分析することによる,ブロガー先読み度判定手法を提案する.具体的には,その流行語が語り始められた時点を推測し,その時点から流行のピークを迎えるまでの期間において,対象となる流行語に関してどの程度早期に言及していたのかを評価する.本稿では,提案する先読み度判定手法について説明すると共に,本手法で必要となる流行語候補のカテゴリ分類について評価を行ったので,報告する.The purpose of this study is to discover good predictors in blogosphere, as one of methods to detect promising buzzwords. In order to find good predictors, we propose a method for evaluating bloggers' buzzword prediction ability by analyzing how early bloggers mentioned past buzzwords. Concretely, we predict the time when a buzzword began to be mentioned, and evaluate how early the buzzword was mentioned in the period from the beginning time to the peak. In this paper, we describe the analysis method of bloggers' buzzword prediction ability, and report the evaluation on buzzword classification.
2 0 0 0 OA 社会教育と民衆娯楽 : 権田保之助の問題提起
- 著者
- 坂内 夏子
- 出版者
- 早稲田大学
- 雑誌
- 学術研究. 教育・生涯教育学編 (ISSN:13477870)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.15-28, 2005-02-25
- 著者
- 前之園 唯史
- 出版者
- 日本甲殻類学会
- 雑誌
- CANCER (ISSN:09181989)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.33-39, 2016-08-01 (Released:2016-10-20)
- 参考文献数
- 43
2 0 0 0 OA 鐵嶺漫筆(其二)(文苑)
2 0 0 0 洞春寺歴史資料仮目録 : 山口大学との共同調査
- 著者
- [山口市教育委員会文化財保護課 山口大学人文学部日本史研究室編]
- 出版者
- 山口市教育委員会
- 巻号頁・発行日
- 2016
2 0 0 0 OA 我國は如何にして歐洲人に知られしか(文苑)
2 0 0 0 IR 日本出土のオリーブ壺と歴史的意義
- 著者
- 川口 洋平
- 出版者
- 総合研究大学院大学文化科学研究科
- 雑誌
- 総研大文化科学研究 (ISSN:1883096X)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.123-132[含 日本語文要旨], 2011-03
近年、長崎と大阪においてスペイン産とされる「オリーブ壺」の出土を日本で初めて確認した。この壺は、北米の遺跡や世界各地の沈没船で存在が確認されているが、考古資料として本格的な研究が始まったのは1960年のアメリカのゴギン氏以降のことである。「オリーブ壺」という呼称であるが、文献からは内容物を完全には特定できず、オリーブ油とワインを中心に様々な容器として用いられたと考えられている。しかし、現在では球形で小さな口のつく容器の型式名として広く定着している。ゴギン氏は、基本的な型式分類を行ったが、その後、沈船資料を中心に研究が進み、口縁部の形態変化などの細かい研究がなされている。 長崎では二つの破片が出土した。内外面に黄色の釉がかかり赤褐色の胎土からなる球形の体部、および断面三角形を呈する口縁部である。この形はゴギン氏のB類に相当するが、胎土と釉は、他地域で出土しているものとは異なっており、マーケン氏の指摘するモンバサ沖で沈没したポルトガル船のものと似ていることから、ポルトガル産である可能性がある。出土状況から、それぞれ17世紀初期および17世紀代の年代が想定されるが、17世紀初頭には付近に教会があった記録があり、キリスト教との関連も指摘される。 大阪では、口縁部を欠く楕円形の体部が出土した。ゴギン氏の分類ではA類で19世紀以降とする後期の型式に近い。大阪の資料は1614年の大坂夏の陣に伴う火災層以前と思われ、年代的には一致せず、マーケン氏の指摘する「16世紀タイプ」(バハマ沖沈船など)や1600年にマニラ沖で沈没したサン・ディエゴ号の資料に近い。また付近からは、東南アジアを含む輸入陶磁も出土しており、貿易に関わった商人との関連が指摘される。 これらの本来の中身については、前述のとおり厳密には特定できないが、オリーブ油やワインを運んだものとして搬入経路や運搬者について考えてみたい。搬入経路については、長崎出土のものは、ポルトガル産の可能性があることから、ポルトガル船が運んだと推測される。大阪のものは、マニラにおいて引き揚げ資料があることから、第一にマニラ経由でスペイン船が日本に運んだ可能性が考えられる。第二に、ポルトガル船が、マカオ経由で運んだ可能性がある。岡美穂子の研究によれば、ゴアから中国(マカオ)行きのポルトガル船の貿易品の中にスペイン産のワインとオリーブ油がみられることから、マカオにはこれらが存在したことがうかがわれる。第三に日本人が直接海外から持ち帰った可能性が考えられる。フィリピンに駐在したモルガの記録にもマニラに来航した日本人がワインを買って帰る記録がみられる。 では、日本においてワインやオリーブ油はどのような需要があったのであろうか。長崎と大阪の出土状況は、キリスト教や貿易商との関わりを示唆しているが、ポルトガル国王とゴアのインド副王の往復書簡である「モンスーン文書」には、17世紀初めの段階で日本司教からミサ用のワインやオリーブ油の俸禄を請求している記述があり、この頃にはキリスト教で行われるミサなどに関連して一定の需要があったことがわかる。また、オランダ商館長の日記には、ワインを長崎奉行へ贈った記録がある。さらにオリーブ油については、18世紀初頭の長崎奉行の記録にオランダの産出品として「アセトウナノ油」(スペイン語でオリーブ油の意)と記され、オランダによって間接的に輸入されていた可能性がある。16世紀終わり頃から18世紀にかけての日本において、ワインやオリーブ油に関して様々な需要があったことが、今回の考古学的発見や文献史料から判明する。 さらに、これらに関連してオリーブ壺を実際に描いたと考えられる南蛮屏風を確認した(出光美術館蔵)。この屏風には、黒船から降り立った南蛮人が細長いに棒の両端に壺をつり下げて歩く様子が描かれているが、この壺のひとつが、ゴギン氏分類のA類あるいはC類に酷似している。さらに、竹を編んだと推測される籠によって運搬している様子が描かれている。一説には黒船来航の光景は、長崎を描いたとも言われ、オリーブ壺が南蛮船によって長崎へ運ばれた可能性を示唆している。 本研究は、16世紀から17世紀にかけての歴史研究に対して以下のような学際的な意義を持つ。第一に、我が国におけるオリーブ壺に関する研究の端緒であり、今後考古学の分野でオリーブ壺の出土が確認され、詳細な分布が明らかになることが期待される。第二に、文献史学から検討されていた東西の貿易品の流通が考古学から具体的に実証されたことがあげられる。第三に、今回の検討から南蛮屏風の歴史資料としての可能性が明らかになったことである。今後、そこに描かれた品々についての実証的な研究が期待される。The newly found olive jars in Japan were most likely manufactured in Spain or Portugal from the late 16<sup>th</sup> century to the 17<sup>th</sup> century, based on the earlier studies. According to the documents and "Nanban screen" depicting the arrival of nanban-jin (Portuguese and Spanish) in Japan, it is said that they were brought to Japan by "Black Ship" and used among Christians and so on. They were archaeologically proven to be traded between the East and the West, and more such olive jars are sure to be found. Furthermore, Nanban screens might have the possibility of use as historical sources; empirical study of painted items is expected in the future.