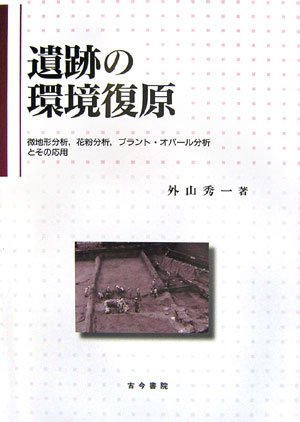2 0 0 0 OA Intersections, Social Change, and "Engaged" Theories : Implications of North American Feminism
- 著者
- Garry Ann
- 出版者
- 東京大学大学院総合文化研究科附属アメリカ太平洋地域研究センター
- 雑誌
- アメリカ太平洋研究 (ISSN:13462989)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.99-111, 2008-03
寄稿
2 0 0 0 IR コンピュータを用いたハイランド円線図の作図
- 著者
- 古賀 亜彦
- 出版者
- 鹿児島工業高等専門学校
- 雑誌
- 鹿児島工業高等専門学校研究報告 (ISSN:03899314)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, pp.1-7, 2001-08
誘導電動機の諸特性を表すものにハイランド円線図がある。この円線図は誘導電動機の簡易等価回路図に立脚したものであり簡便なためによく利用される。大型の誘導電動機の場合、大きな実負荷をかけることは困難な場合が多い。そのような時、ハイランド円線図を利用すれば任意の負荷に対するすべての特性がわかる。ハイランド円線図を描くのは、かなり難しいことである。そこで、このハイランド円線図をコンピュータで描き、コンピュータ上で任意の負荷に対する誘導電動機の諸特性を求める事が今回の目的である。この研究は誘導電動機の特性をパソコン上でビジュアルに追跡できるので、誘導電動機の授業および実験において非常に有益であると考える。The purpose of this paper is to draw the Heyland circle diagram by using a computer. This diagram shows us various kinds of characteristics of an induction motor. It is very important for us to get many kinds of characteristics of an induction motor without applying real load to it. This diagram is based on a simple equivalent circuit of an induction motor and named Heyland circle diagram. It is very difficult to draw the Heyland's circle diagram, but by observing this program displayed, we can understand and master how to draw the diagram. This program is very useful for studying of the electric machinery. Visual C++6.O was used to write this program.
- 著者
- 上田 哲司
- 出版者
- 北海道出版企画センター
- 雑誌
- 北海道・東北史研究
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.9-29, 2014
2 0 0 0 OA 水生動物がアミノ酸を飲む -見落とされていた窒素循環プロセスの解明-
本研究の目的は、「水生動物が溶存アミノ酸をエネルギーとして利用する可能性」を孵化直後のエゾサンショウウオ幼生を用いて示すことである。実験の結果、アミノ酸を添加した環境水で飼育したエゾサンショウウオ幼生は、アミノ酸由来の窒素を体内に取り込み、成長を促進させることが分かった。細菌などの微生物が溶存アミノ酸を直接利用し増殖することは一般に認知されているが、脊椎動物による溶存アミノ酸の利用はこれまで想定されてこなかった。本研究の成果は、「これまでの慣習的な栄養伝達経路の有り様」の変更を促すものである。
2 0 0 0 政党政治家大野伴睦の軌跡と政治理念(1)
- 著者
- 松本 秀章
- 出版者
- 滋賀文教短期大学
- 雑誌
- 滋賀文教短期大学紀要 (ISSN:09126759)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.1-31, 2005-01
2 0 0 0 アリールビニルスルホン類の合成とその反応性
- 著者
- 北尾 弟次郎 黒木 宣彦 小西 謙三
- 出版者
- 社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 工業化学雑誌 (ISSN:00232734)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.6, pp.825-828, 1959
- 被引用文献数
- 3
アリール-β-クロルエチルスルホン類は対応するアリールメルカプタンにエチレンクロルヒドリンを作用せしめるか,あるいは活性ハロゲンを有する化合物にメルカプトエタノールを処理して得られるβ-オキシエチルスルフィドを塩化チオニルまたは五塩化リンで塩素化してクロルエチルスルフィドを得,更にこれを過酸化水素で酸化して得られる。また対応アリールスルフィン酸にエチレンクロルヒドリンを処理し, 後塩素化しても得られる。<BR>β-クロルエチルスルホンをアルカリ性で脱塩化水素化するとアリールビニルスルホン類が合成される。このように合成した置換フェニル-β-クロルエチルスルホンおよび置換フェニルビニルスルホン類はメタノール,エタノール,ブタノールなどのアルコール類と弱アルカリ性でミハエル様付加反応を行うことを確かめた。またアミンとしてモルホリンを用い,同様の付加反応がアミン類にも容易に行われることを確かめた。
2 0 0 0 降雨量による洪水予報の一方法
- 著者
- 伊藤 令二
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:00471798)
- 巻号頁・発行日
- vol.1952, no.14, pp.29-36, 1952
- 被引用文献数
- 1
河川の洪水量と流域の累加雨量及び降雨継続時間との関係が図化し得る事に着目し, 太田川 (広島) を例にとり, 広島の総雨量が流域の総雨量を代表し得る推計学的検定のもとに, 広島雨量による太田川の洪水予報の可能を示したものである。
2 0 0 0 性的パ-トナ-告知を促すHIVカウンセリングの技法と倫理に関して
- 著者
- 児玉 憲一 一円 禎紀
- 出版者
- 日本心理臨床学会 誠信書房(発売)
- 雑誌
- 心理臨床学研究 (ISSN:02891921)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.98-103, 1997-04
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 秋葉 和温
- 出版者
- 養賢堂
- 雑誌
- 畜産の研究 (ISSN:00093874)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.4, pp.485-492, 2013-04
1906年(明治39年)の春,Lissabonで開かれたIntemationaler Medizinischer Kongressに出席し,たまたま重症を発して帰り,直ちにHamburgのEppendorf(エツペンドルフ)病院に入院した。その病気の原因は遠くさかのぼって,彼の自家実験にあったもので,激烈な肛門周囲炎を起こしたのであった。大腸の膿瘍は腹腔に溢れ,Notoperation(救急手術)のかいもなく,同年6月20日(1906年6月22日‐高田)昇天,彼の霊はこの世を去った。わずかに35歳の壮者は,わが学術界に大きな足跡を残して,昇天したのである。Hamburgの研究所より出版した615SeiteのSammelausgabeは,この天才的研究者の最後を飾るものである(1911出版)。この若い堅実な学者を失ったのは,測り知れぬ人類の不幸,かつ大きな損失で,世界の学界はみなこの不幸を悲しみ弔ったのであった。トーマス・D・ブロック著,長木大三・添川正男訳「ローベルト・コッホ」の236ページにはノーベル賞の項で,「1905年(明治38年)にはフリッツ・シャウディン(1871‐1906)が受賞者として指名されていた。シャウディンは原生動物について重要な報告を出していたが(その中のいくつかはのちに誤りとわかった),1905年春,エリッヒ・ホフマン(1866‐1959)と協力し梅毒の病原体としてスピロヘータ・バリダ(のちにトレポネーマ・パリドムと命名)を発見したと報告した。1905年4月末,当時パストウール研究所長であったエリー・メチニコフはシャウディンの指名についてノーベル賞委員会へ書簡を出した。私はシャウディンの仕事を高く評価はするが,ノーベル賞の候補者として支持することはできません。私は多年にわたりコッホを受賞者として推薦してきましたが,コッホが受賞しないかぎり,他の候補者を支持することはできません。私の意見では,ローベルト・コッホの医学への貢献は,他のすべての可能性のある候補者よりもはるかに超越したものであります。」と記載されている。そして「ノーベル賞委員会もついに決意した。1905年12月12日,彼の誕生日の翌日,コッホは受賞した。(当時の金額で15万ドイツマルク)。"ドイツ医学週報"には次のように記述されている。「"これ以上受賞にふさわしい人は考えられない"」と。
2 0 0 0 ミルダース朝の外交政策 : 西暦十一世紀のアレッポを中心として
- 著者
- 太田 敬子
- 出版者
- 公益財団法人史学会
- 雑誌
- 史學雜誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.3, pp.327-366, 490-491, 1992-03-20
The Mirdasid dynasty ruled Aleppo and its region in northern Syria from 415 A.H./1025 A.D. to 473 A.H./1080 A.D.. The Mirdasid was a family of the Kilab tribe (Banu Kilab) which belonged to the northern Arab tribes. Banu Kilab, taking advantage of political disorder caused by the decline of the 'Abbasid's rule, had extended their influence into the Aleppo region. The Mirdasid principality was founded upon their strong military power. This paper aims to investigate the first period of the Mirdasid dynasty on the point of foreign policy and influence in the international relations. From the middle of the tenth century, the Aleppo region had been threatened by two powerful foreign states; the Fatimid Caliphate in Egypt and the Byzantine empire, both of which aimed to annex this region. Under such circumstances, Salih b. Mirdas, the first prince of the Mirdasid dynasty succeeded in gaining control of Aleppo city with support of a Syrian Arab alliance. To extend their power, the Mirdasides made use of the balance of power between these Great Powers and their limited ability to advance their territorial ambitions into Syria. The principal approach to their foreign policy was to negotiate with each of them, receive their recognition for possession of Aleppo, and then nominally establish an independent state under their patronage. However, before receiving their recognition, the Mirdasides had to engage in some battles with them. As a result, Thimal, the third prince, succeeded in obtaining recognition as the ruler of Aleppo from both of the Great Powers and stabilized the supremacy of the Mirdasid dynasty in the Aleppo region. However, the author has also ascertained that this success owed much to the internal affairs of the Fatimid caliphate and the Byzantine empire and changes that occured in the diplomatic relations between them. The author also examines concretely the position of the Mirdasid princes in international relations. As a result, she has found that their subordinate posture in the diplomatic negotiations did not mean a dependent character. It should be noted that recognition from foreign powers to be the governor of Aleppo was indispensable for the Mirdasid princes to achieve stability within their states ; and to receive such recognition was the principal purpose of their foreign policy.
2 0 0 0 OA Down症児の早期療育とシャフリングベビーの検討
- 著者
- 齋藤 和代 渡邉 幸恵
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児神経学会
- 雑誌
- 脳と発達 (ISSN:00290831)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.2, pp.122-128, 2016 (Released:2016-03-26)
- 参考文献数
- 19
【目的】Down症児は早期からの療育が開始されることが多く, 運動発達促進やシャフリングベビーの減少が知られている. また, Down症児と自閉症スペクトラム (autism spectrum disorder ; ASD) の合併に関する報告も注目されている. そこで, 今回, Down症児の早期療育における問題点を調査する目的で, シャフリングベビーを含む粗大運動発達と精神発達について調査した. 【方法】対象は, 外来診察を行ったDown症児のうち, 1歳以上の男児79例女児42名の計121例で, 診療録による後方視的調査を行った. 【結果】シャフリングベビーは14例 (11.6%) であった. 粗大運動発達では, シャフリングベビー群で, 頚定, 四つ這い, 独歩が遅い傾向にあった. 精神発達の調査では, シャフリングベビー群で, ASD傾向が認められることが多かった. 【結論】早期介入にも関わらずシャフリングベビー群に移行する症例では, ASD傾向の合併に注意を払い, その特性に合わせた療育的介入が望ましい.
2 0 0 0 ニーチェのヘラクレイトス解釈における「人格」の問題について
- 著者
- 内藤 可夫
- 出版者
- 人間環境大学
- 雑誌
- 人間環境論集 (ISSN:13473395)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.1-13, 2009
『悲劇の誕生』の刊行直後に書かれている『ギリシアの悲劇時代における哲学』には、後にニーチェ独自の思想の中心ともなった「生成」を説くヘラクレイトスが解釈されている。ニーチェは解釈に際して「人格」の理解を求めており、一方、哲学体系自体は中心的なテーマになっていない。ハイデッガーによるこの解釈に対する批判は元初の思索に誤解を与えた点にある。だが、それにもかかわらず、ニーチェの古代ギリシアへの思索に意義があるのは、異文化のもっとも深い認識に達した人間の理解への試みを通じて、彼自身が、自分自身の内に全体的なものへと関わる仕方(人格のあり方)を見出そうとした点にある。ニーチェにとっての人格とは、理性と生の全体との関係のあり方のことを意味しているのである。
2 0 0 0 IR 『悲劇の誕生』におけるアポロ的なるもの
- 著者
- 今崎 高秀
- 出版者
- 法政大学大学院
- 雑誌
- 法政大学大学院紀要 (ISSN:03872610)
- 巻号頁・発行日
- no.56, pp.1-15, 2006
2 0 0 0 OA オリーブアナアキゾウムシ成虫の存在場所および行動の日周的・季節的変化
- 著者
- 市川 俊英 岡本 秀俊 藤本 能弘 川西 良雄 壼井 洋一
- 出版者
- 日本応用動物昆虫学会
- 雑誌
- 日本応用動物昆虫学会誌 (ISSN:00214914)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.6-16, 1987-02-25 (Released:2009-02-12)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 7
1982年4月から1983年5月にかけて,研究室内とオリーブ樹を取り囲む野外網室(3×3×3m)を中心とする野外のオリーブ植栽地でオリーブアナアキゾウムシ成虫の存在場所と行動について調査した。この間に確認された成虫の行動を不活動,静止,歩行,摂食,マウント,交尾および産卵状態に大別した。野外網室での調査によると,長命な成虫の活動期は概略4月から10月までで,おもに夜間オリーブ樹上で活動し,日中には大部分が不活動状態で発見された。ただし,晴天の日中には大部分の成虫が枯草で被覆したオリーブ樹根元周辺の地面(被覆地)で発見され,マウントや交尾を繰り返していた雌雄や根元で産卵中の雌も少数ながら認められた。また,曇天の日中には夜間から引き続きオリーブ樹上にとどまっている個体と裸地で発見される個体が多かった。成虫は野外網室内で越冬可能であることが確認され,11月から3月までの越冬期の成虫は全般に不活発で,被覆地に潜伏する個体が日中,夜間を通じて多かった。しかし,成虫の活動が完全に停止したわけではなく,地面を移動する個体がかなり多く,越冬期の初期と後期にはオリーブ樹に登る個体もかなり多かった。
- 著者
- 奥平 敦也
- 出版者
- 鹿児島国際大学
- 雑誌
- 鹿児島経済論集 (ISSN:13460226)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.43-75, 2008-03
Linux2.6のNFSroot機能を利用してディスクレスクライアントを作成した。クライアントの起動はフロッピーディスクから行う。LILOで起動する。クライアントは/usrと/optと/homeを共有するという通常の設定である。ログインの管理と/etc/hostsの共有のためにNISを利用し,時刻同期のためにNTPを利用した。ネットワークパラメーターはLILOの設定ファイルで与えている。ブートスクリプトは少し修正が必要である。ディストリビューターは小さい構成もサポートして欲しい。クライアントを作成するのにはあまり手間はかからない。我々はSUSE9.2ベースのシステムをIUKで教育目的で3年間運用した。XEON 3.40GHz,2GiBメモリーの通常のNFS(とNIS)サーバーと100Mbpsのネットワークで,クライアント(Pentium4の3GHz,500MiBメモリー)を20〜30台は特に支障無く運用できることがわかった。運用に必要なマンパワーは通常のディスクのあるクライアントに比べて少なくて済む。また,openSUSE 10.3に基づくクライアントをこの春から運用する予定である。事前の性能テストによると,このシステムのボトルネックはNFSサーバーのディスクまわりの性能である。Linux 2.6のNFSroot機能を利用したディスクレスクライアントは,サーバーとネットワークが低性能でないかぎり,大学教育での使用に実用的である。
2 0 0 0 IR ヨーロッパ思想と霊性
- 著者
- 金子 晴勇
- 出版者
- 聖学院大学
- 雑誌
- 聖学院大学総合研究所紀要 (ISSN:09178856)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.107-133, 2011-03-30