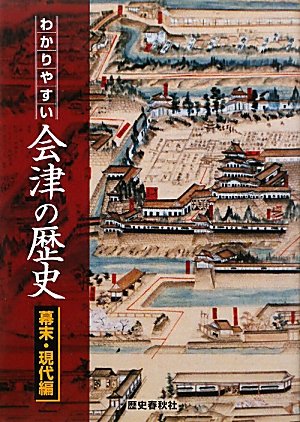2 0 0 0 IR 日本の常緑及び落葉広葉樹の耐凍牲
- 著者
- 酒井 昭
- 出版者
- 北海道大学
- 雑誌
- 低温科學. 生物篇 (ISSN:04393546)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.15-43, 1978-03
- 著者
- 漆崎 正人
- 出版者
- 藤女子大学日本語・日本文学会
- 雑誌
- 藤女子大学国文学雑誌 (ISSN:02869454)
- 巻号頁・発行日
- no.81, pp.57-67, 2009-11
2 0 0 0 OA 日本の宗教とジェンダーの研究-近世社会における尼僧と尼寺の役割-
本研究は、日本の宗教とジェンダーを考えるうえで重要な尼門跡文書の分析を通じて、近世社会における尼僧と尼寺の役割を明らかにすることを目的に、(1)慈受院門跡所蔵の「総持院触留」の研究、(2)尼僧を中心とした女性ネットワークの研究(3)比丘尼御所、霊鑑寺門跡の工芸品の調査、以上の3点から研究活動を行った。4ヶ年の期間内に33回の尼寺研究会を開催し、元禄11年~享保21年までの「総持院触留」28冊を講読し、6回の霊鑑寺工芸品調査を実施して人形約170件・染織品約70件・陶磁器約100件の調査データを得ることができた。その成果を纏め、2013年3月に、研究論文6、「総持院触留史料集」を収載した研究報告書を刊行した。本研究によって尼寺を背負う立場にある尼僧たちが積極的に社会に関わっていく姿が明確になった。
- 著者
- 平澤 由平 鈴木 正司 伊丹 儀友 大平 整爾 水野 紹夫 米良 健太郎 芳賀 良春 河合 弘進 真下 啓一 小原 功裕 黒澤 範夫 中本 安 沼澤 和夫 古橋 三義 丸山 行孝 三木 隆治 小池 茂文 勢納 八郎 川原 弘久 小林 裕之 小野 利彦 奥野 仙二 金 昌雄 宮崎 良一 雑賀 保至 本宮 善恢 谷合 一陽 碓井 公治 重本 憲一郎 水口 隆 川島 周 湯浅 健司 大田 和道 佐藤 隆 福成 健一 木村 祐三 高橋 尚 由宇 宏貴
- 出版者
- The Japanese Society for Dialysis Therapy
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 = Journal of Japanese Society for Dialysis Therapy (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.7, pp.1265-1272, 2003-07-28
- 被引用文献数
- 2 12 4
遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤 (rHuEPO) が6か月以上継続投与されている慢性維持血液透析患者 (血液透析導入後6か月以上経過例) 2,654例を対象に, 維持Ht値と生命予後との関係をretrospectiveに調査, 検討した. Cox回帰分析による1年死亡リスクは, 平均Ht値27%以上30%未満の群を対照 [Relative Risk (RR): 1.000] とした場合にHt 30%以上33%未満の群でRR: 0.447 [95%信頼区間 (95% CI): 0.290-0.689 p=0.0003] と有意に良好であったが, Ht 33%以上36%未満の群ではRR: 0.605 [95% CI: 0.320-1.146 p=0.1231] と有意差を認めなかった. 一方, Ht 27%未満の群ではRR: 1.657 [95% CI: 1.161-2.367 p=0.0054] と有意に予後不良であった. また, 3年死亡リスクも1年死亡リスクと同様, Ht 30%以上33%未満の群ではRR: 0.677 [95% CI: 0.537-0.855 p=0.0010] と有意に良好であったが, Ht 33%以上36%未満の群ではRR: 1.111 [95% CI: 0.816-1.514 p=0.5036] と有意差を認めず, Ht 27%未満の群ではRR: 1.604 [95% CI: 1.275-2.019 p<0.0001] と有意に不良であった.<br>これらの調査結果より, 1年および3年死亡リスクはともにHt値30%以上33%未満の群で有意に低値であり, 生命予後の観点からみた血液透析患者のrHuEPO治療における至適維持目標Ht値はこの範囲にあると考えられた. ただし, 1年死亡リスクは, 例数が少ないもののHt値33%以上の群についても低値であったことから, このレベルについては今後再検討の余地があると考えられた.
2 0 0 0 次世代計算資源上のカイラルクォークシミュレーション
- 著者
- 出渕 卓
- 出版者
- 独立行政法人理化学研究所
- 雑誌
- 新学術領域研究(研究領域提案型)
- 巻号頁・発行日
- 2011-04-01
本年度は 新たに導入された BlueGene/Q (3.5 rack 700 TFLOPS peak)上で、自然界のクォーク質量に等しい物理点上の アップ、ダウン、ストレンジ の軽いクォークの関わる物理量の計算を、効率良く行うための研究を行った結果、5倍から40倍もの計算効率化を果たすことが出来た。 目的とする正確な物理量(高コスト)とその近似計算(低コスト)の両方を、後者の近似計算をより頻繁(正確な計算の~100倍程度の頻度)行うことによって統計誤差を下げ、なおかつ格子理論の対称性を使うことに計算結果にバイアスを入れない All-Mode Averaging (AMA) という 方法を提案した。物理量の骨組みとなるクォークの伝搬関数を計算する際に、長距離の伝搬を支配するクォークの低エネルギーモードを固有ベクトルを求めることにより正確に扱い、短距離伝搬を担う 高エネルギーモードは多項式近似を行う。新しい計算資源である BlueGene/Q や GPU 上で、それぞれの資源の特長を生かした固有ベクトル計算を高効率で行うためのアルゴリズム implicitly restarting Lanczos with Chebyshev acceleration を開発・実装した。BlueGene/Q 上での計算コードは 理論絶対ピークの 30%の速度を超えており、この世代のメニコア環境下では満足のいく効率だと思われる。現在の方法では、より大体積の格子計算では、より大きなメモリ容量が必要 (体積の2乗に比例)であり、ドメイン分割法などの方法で必要メモリを減らすことが現在の課題であるが、これに関しても今現在進展を得つつある。
2 0 0 0 キリスト教のアメリカ化と社会文化生成についての研究
本研究は、17世紀植民地時代から21世紀に至るまでのアメリカ史におけるキリスト教の果たした歴史的、社会的、文化的役割を特に土着化(Contextuahzation;Americanization)の視点から通史的かつトピカルに分析研究することを目指した。従来の神学的キリスト教研究や教派研究というよりも、キリスト教の果たした役割を宗教史の狭い領域的研究の枠組みから解放し、より広い歴史的、地理的、社会的状況におけるダイナミズムの中で検証し、アメリカ的キリスト教の特性、さらにアメリカ化の過程を詳細に検討することとした。さらに、アメリカ人宣教師による日本における宣教活動を追うことにより、アメリカニズムとキリスト教との関係にも注目した。タイムスパンを長期に設定することで、通事的な研究を目指し、日米から多様な研究者を集めた。初年度には、初期アメリカ研究者David D.Hall教授を招聘し、植民地時代ピューリタニズムについての研究会を開催した。平成18年度は、Richard W.Fox教授を迎え、アメリカ文化とキリスト教についての研究会を開いた。両教授とも、専門研究者との交流だけでなく、ひろく一般、学生に向けた講演も行ない、本領域における学的関心を広く喚起できた。Mark A.Noll教授は来日は果たせなかったが、福音主義とアメリカ政治の関係についての論文を最終報告書に寄稿した。研究代表者、分担者共に、日本とアメリカを往復し、国内外での研究交流をはかると共に、リサーチを勢力的に行ない、学会発表、論文出版により成果を発表した。報告書は今後、研究書としてまとめ、出版を予定している。
2 0 0 0 OA 身体を使った遊びを通して自然現象を理解する動く遊具の開発
2 0 0 0 OA 世代間の技能伝承を中心に,地域の教育力をものづくり教育に定着させる題材の開発
本研究は伝統技能を教育学的な検証を経て学校教育の現場で活用できる題材として開発し、実践によって評価しようとしたものである。具体的には3つの代表的な取り組みを行った。第1に、伝統の刃物づくりの調査とそれを題材としたDVDの製作、第2に銅鏡の製造過程の調査と製作マニュアルとしてのCD製作、第3に伝統的な養蚕の実践とできた繭から絹糸を取り出し小型のランプシェードをつくる題材の開発と実践をおこなった。DVDとCDは千葉県下の市教育委員会へ配布し、その教育的評価を調査した。実践的な検証の取り組みでは、附属小学校において、銅鏡づくりは鋳型づくりと研磨を主に体験して製作し、ものをつくるにはいろいろな道具と時間がかかることを体得した感想が多かった。教員養成学部の授業実践として銅鏡づくりと行灯づくりに取り組み、教員資質にとってものづくりが重要であることを実証した。技能に裏付けられたものを作る能力を定着させる方法論が次の課題である。
2 0 0 0 幕末・現代編
- 著者
- 鈴木荘一 笹川壽夫著
- 出版者
- 歴史春秋社
- 巻号頁・発行日
- 2011
2 0 0 0 古代・中世・近世編
- 著者
- 長尾修 [ほか] 著
- 出版者
- 歴史春秋社
- 巻号頁・発行日
- 2011
2 0 0 0 OA 中国盗掘事情
- 著者
- 横田 恭三
- 出版者
- 跡見学園女子大学
- 雑誌
- 跡見学園女子大学人文学フォーラム (ISSN:13481436)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.73-80, 2005-03-15
- 著者
- 神 繁司
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 参考書誌研究 (ISSN:03853306)
- 巻号頁・発行日
- no.66, pp.1-91, 2007-03
2 0 0 0 OA C105 1.5層準地衡系におけるシアー流中の孤立渦について(大気力学)
- 著者
- 隅田 勝将 石岡 圭一
- 出版者
- 社団法人日本気象学会
- 雑誌
- 大会講演予講集
- 巻号頁・発行日
- vol.96, 2009-10-31
- 著者
- 今井 信治
- 出版者
- 北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院観光創造専攻文化資源マネジメント研究室
- 雑誌
- 北海道大学文化資源マネジメント論集
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.1-22, 2009-03-03
- 著者
- 藤川 祥子
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.3, pp.119-120, 2006
- 著者
- 小菅 雅行
- 出版者
- 大阪大学大学院文学研究科臨床哲学研究室
- 雑誌
- 臨床哲学 (ISSN:13499904)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.47-58, 2011-03-31
2 0 0 0 複数勝者KFM連想メモリを用いた強化学習の実現
- 著者
- 鶴見 太郎
- 出版者
- ロシア史研究会
- 雑誌
- ロシア史研究 (ISSN:03869229)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, pp.78-95, 2011
When Zionists in Late Imperial Russia spoke about Palestine, they did not usually rely on traditional discourses and hardly showed their emotional attachment to Palestine. In fact, many Zionists even had an aversion to any essentialist discourse on nationality. Why, then, did they chose Palestine, a particular land? Especially focusing on the arguments of Daniel Pasmanik, a prominent ideologist of "Synthetic" Zionism, this paper explores an imagery that the Zionists at that time in the Russian Empire had in mind, by which the Zionists considered Palestine necessary for their project. When we read Pasmanik's Wandering Israel (1910) and some other articles by him, it becomes evident that his thoughts were based on an evolutionary perspective, underlining the role of environments that created characteristics of the Jewish people. While he also highlighted people's "will" to life, he considered that without a free social environment, free national creation would be impossible. For him, ancient Palestinian Jews created valuable culture for humanity, proving potential capacity of Jews for creation. He believed that Palestine would be an environment where a part of Jews would resurge to be such people liberating Jews in the Diaspora from the evil influence of the Galut (Exile).