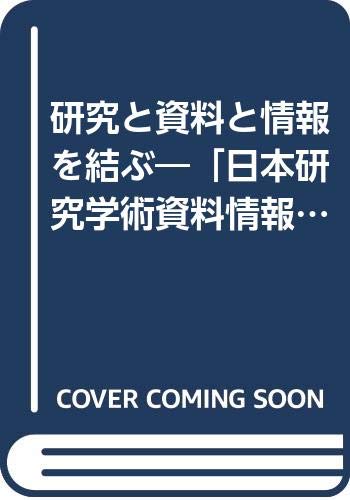2 0 0 0 OA 北海道渡島半島地域におけるヘア・トラップ調査の実施例
- 著者
- 釣賀 一二三
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.119-123, 2008 (Released:2008-07-16)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 10
これまでに北海道で試みられたヒグマの個体数推定は,その推定値に大きな誤差を含むものであった.現在,より精度の高い推定を行うために,ヘア・トラップ法を応用することが可能かどうかの検討を実施しており,本稿では検討の概要とその過程で明らかになった課題について述べる.ヘア・トラップ法を用いた個体数推定法の本格的な検討に先立って行った3カ年の予備調査では,誘因餌を中央につり下げて周囲に有刺鉄線を張ったヘア・トラップによって試料採取が可能なこと,試料の保管には紙封筒を用いて十分な乾燥をした後に保管する必要があることなどが明らかになった.さらに,分析対象の遺伝子座の選択に関する課題の整理が行われた.その後の3年間の本格調査では,ヘア・トラップ配置のデザインと構造を検討するために,メッシュ単位で29箇所あるいは39箇所に設置したヘア・トラップの適用試験を実施した.この結果については現在解析途中であるものの,ヘア・トラップを設置する場所の均一性を検証することや,ヘア・トラップの設置密度の基準となるメッシュの適切な大きさに関する検討の必要性が課題としてあげられた.
2 0 0 0 OA 各都道府県のヘア・トラップ調査の実施状況と長野県における実施例
- 著者
- 森光 由樹
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.1, pp.133-138, 2008 (Released:2008-07-16)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 8
これまでに,全国20の自治体で,ヘア・トラップを用いた調査が行われてきた.調査の目的は「クマの個体数の算出」,「個体識別」,「生息の確認」など,それぞれの自治体で異なっている(2007年9月現在).すでに,ヘア・トラップ調査を「特定鳥獣保護管理計画のモニタリングの手法」として,利用している自治体もある.ヘア・トラップ調査は,トラップ設置の数,トラップ間の距離,材料採取の方法,トラップ見回り頻度,分析実施数,DNA分析技術,個体数算出法などの課題があり,手法の改善が必要である.2002年に長野県で実施された調査では,定点観察調査,痕跡確認調査から長野県関東山地のツキノワグマの生息密度を,0.01~0.03頭/km2と推定している.2003年からは,長野県関東山地でヘア・トラップによる調査が実施された.100 km2の調査地に100トラップを設置し,679本の試料が分析された.識別された個体は33頭で,分析成功率は26.3%であった.定点観察や痕跡調査では,ツキノワグマの生息密度を過小評価している可能性があることが示唆された.今後,ヘア・トラップ法を特定鳥獣保護管理計画のモニタリングの手法として確立するには,いくつかの問題点を改善しない限り導入は困難であると思われる.そのために,手法の開発が急務である.
- 著者
- 国際文化会館図書室編集
- 出版者
- 日本図書館協会 (発売)
- 巻号頁・発行日
- 2002
- 著者
- 城山 智子 PENG Juanjuan PENG JUANJUAN
- 出版者
- 一橋大学
- 雑誌
- 特別研究員奨励費
- 巻号頁・発行日
- 2009
本研究は、裕大華紡績公司の1880年代から1960年代までの事業展開を事例として、近現代中国に於ける企業の態様を明らかにしようとするものである。本研究は、特に、裕大華が、現代中国で「集団」と呼ばれる、多業種にまたがる複数の会社の集合体のプロトタイプと看做されることに注目している。清朝から中華民国を経て中華人民共和国に至る政治体制の変化の下で、企業への投資と経営とがどのような変容を遂げたか、という時系列の分析を行うと同時に、日本の財閥や韓国のチョボルといったアジアの企業形態との比較から、中国の企業の特質を明らかにし、平成22年度は、平成21年度の資料調査の成果を踏まえて、事例研究をまとめた。6月には台湾中央研究院近代史研究所で、中華民国期の産業振興に関する資料調査、7月には京都大学経済学部図書室で戦前期中国企業に関する調査報告の収集を行い、より網羅的なデータの収集を行った。また現代中国史研究会では研究発表、"Crossing the 1949 divide : changes and continuities in a Chinese Textile Company"(一个中国紡績企業在1949年前后的変化与延續)を行い、武漢、石家荘、西安、重慶、成都で展開した、裕大華紡績公司の事業について、20世紀委はじめから1950年代までを対象として分析した結果を明らかにした。そこでは、1920年代には未整備だった企業をめぐる経営環境が、1930年代の法整備を経て、1940年代の戦時統制下で大きく政府・党の影響を受けるようになり、さらに、そうした傾向が1950年代の中国共産党政権下でも引き継がれたことを論じた。
2 0 0 0 「びぶろす」と図書館と私
- 著者
- 熊田 淳美
- 出版者
- 国立国会図書館図書館協力部
- 雑誌
- びぶろす (ISSN:00062030)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.8, pp.173-175, 1998-08
2 0 0 0 びぶろす誕生の前後
- 著者
- 酒井 悌
- 出版者
- 国立国会図書館図書館協力部
- 雑誌
- びぶろす (ISSN:00062030)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.p85-90, 1987-04
2 0 0 0 OA 固相抽出による海水中有機スズ化合物の濃縮分離
- 著者
- 郡 宗幸 井上 嘉則 井出 邦和 佐藤 幸一 大河内 春乃
- 出版者
- 公益社団法人日本分析化学会
- 雑誌
- 分析化学 (ISSN:05251931)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.11, pp.933-938, 1994-11-05
- 被引用文献数
- 6 3
有機スズ化合物の固相抽出法について検討した.固相抽出剤としてスチレン誘導体-メタクリル酸エステル重合体を用い, AASで有機スズの回収率を求めた.分析操作は次のとおりである.海水試料のpHを硝酸で1〜0.5に調整し, 試料と等量のメタノールを加えて, pH0.5〜0.25に再調整する, 試料溶液を固相抽出カートリッジに流量4.5〜5ml/minで流す, 10%メタノール溶液15mlで洗浄し, 溶離液としてメタノール10mlを流して有機スズを溶出させる.人工海水100ml{トリフェニルスズ(TPT), トリブチルスズ(TBT);20mgl^<-1>}を用いて分析精度(n=5)を求めた.平均値は20.0mgl^<-1>(TPT)及び20.3mgl^<-1>(TBT), RSDは1.8%(TPT)及び1.7%(TBT)と良好な結果を得た.
2 0 0 0 動画共有サイトにおけるコメントを用いた動画分類の細分化手法
2 0 0 0 OA 神経生理学の勉強の指針
- 著者
- 宮川 博義
- 出版者
- 日本神経回路学会
- 雑誌
- 日本神経回路学会誌 (ISSN:1340766X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.43-47, 1995-06-05 (Released:2010-12-01)
脳の動作原理を理解するための戦略には大きく分けて, 分析的戦略と構成的戦略とがある. 理学的と工学的, あるいは実験的と理論的といってもよい. 神経回路学会の会員諸氏の多くは構成的戦略も取っておられるであろう. 構成的戦略を取る研究者が, 分析的戦略から得られた成果, すなわち神経細胞の特性や脳の動作様式に関する最新の, あるいは一般的な知見を得たいと思っても, なかなか容易ではない. 分析的手法を取る者と構成的手法を取る者との間のギャップは意外に深いのである. このギャップをうめるためには教育システムの改変が必要なのだと筆者は考えるが, 現時点では, 各研究者が個人的な努力をして勉強せざるをえない. 本稿は, その様な研究者のための勉強の指針である. 筆者は細胞および局所回路網レベルでの神経生理学的研究をしている. その立場から, 1)どのようなギャップが深刻かという現状の(一人よがりな)分析をまず述べ, 2)神経回路学会の会員諸氏がそのギャップをうめるには, 何処から情報を引き出せばよいのかを示すことにしたい.
2 0 0 0 OA <判例研究>米軍用地小作人訴訟沖縄土地住宅株式会社対小作人事件
- 著者
- 小川 竹一
- 出版者
- 沖縄大学
- 雑誌
- 沖縄大学地域研究所所報
- 巻号頁・発行日
- vol.4, pp.15-30, 1991-08-26
2 0 0 0 天井照明を用いた起床前漸増光照射による目覚めの改善
- 著者
- 野口 公喜 白川 修一郎 駒田 陽子 小山 恵美 阪口 敏彦
- 出版者
- 一般社団法人照明学会
- 雑誌
- 照明学会誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.85, no.5, pp.315-322, 2001-05-01
- 被引用文献数
- 6
The effects of simulating dawn lighting with an ordinary ceiling light on the quality of awakening were investigated. The subjects were healthy men, aged 24-27. After sleep for about 7 hours with polysomnographic recordings in a climatic chamber kept at a temperature of 25℃ and a relative humidity of 50%, each subject was awakened by an alarm. For the 30 minutes immediately before the subject was awakened, the illumination in the chamber was gradually increased, simulating the condition of waking up as the sun rises. Alpha attenuation test, measuring blood pressure and awakening feelings were conducted after awakening. The time of sleep stage 2 appearing during the 30 minute simulating dawn lighting was significantly less (p < 0.05; Wilcoxon test) than during typical waking conditions (i.e., waking up in the dark), while the time of stage W was higher (p = 0.0796). The mood after awakening in the simulating dawn lighting condition was significantly better (p < 0.05). There were no significant differences in the alpha attenuation coefficients and blood pressures after awakening between the two conditions. These results suggest that simulating dawn lighting arouses subjects to light sleep, which makes awakening less sudden and more pleasant. There was no evidence that the light sleep immediately before awakening decreased the subjects' cerebral cortex activity or sympathetic nervous activity after awakening.
- 著者
- 塚崎 崇史 亀田 達也
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.37-51, 2004-03-31 (Released:2008-12-22)
- 参考文献数
- 51
社会心理学において、エージェント・ベースト・モデルは、社会的影響過程や社会的交換などの対人・集合現象に関する研究で展開されてきた。これらの先行研究におけるモデルでは、集団極化や住み分けが発生する社会的メカニズムを明らかにしたり、また、利他行動が集団内で合理的となる状況の範囲を同定することに成功している。本稿では、これらの展開について議論した後、不確実環境下での社会的学習方略の進化可能性や、集団意思決定における多数決規則の適応価について、エージェント・ベースト・モデルを用いて検討を行った最近の研究を紹介した。そして、エージェント・ベーストの進化シミュレーションを用いた研究を行うことで、様々な社会心理学的現象に関する理論的仮説を組織的に導き出せること、また、生物学や経済学など異なった分野との交流を促進できることを議論した。
2 0 0 0 OA 上方落語『無いもの買い』考 : 比較文化論とコミュニケーション論の視点から
- 著者
- 西村 大志
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.183-200, 2003-03-31
本稿は、落語を比較文化論的視座とコミュニケーション論的視座から研究するものである。落語には江戸落語と上方落語という二つのスタイルがある。本稿では特に上方落語の『無いもの買い』という作品を中心に研究する。その際に速記本などの文字化された資料ではなく、録音されたものを用い分析する。純粋芸術化してしまった怪談噺・人情噺のような落語ではなく、大衆芸術として笑いの作品を対象とする。
2 0 0 0 都市域森林群落における外来種トウネズミモチ Ligustrum lucidum Ait.の分布と生態的特性 : 在来種ネズミモチLigustrum japonicum Thunb.と比較して
- 著者
- 伊藤 千恵 藤原 一繪
- 出版者
- 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.143-150, 2007-11-30
- 被引用文献数
- 6
トウネズミモチは、中国原産の外来種で、街路樹などに植樹されてきたが、その後植栽地から逸出し分布拡大している。また、都市域の森林群落ではトウネズミモチの実生個体が多く、将来群生地を形成する可能性のある種である。そのため、生活形の似ている常緑小高木で同属在来種のネズミモチとの比較から、トウネズミモチの侵入の実態をとらえ、生態学的特性を解明するため、都市域森林群落における生育地、種子散布特性、発芽特性、初期生存率についての調査・実験を行った。調査の結果、トウネズミモチはネズミモチに比べ小さな果実(長径:6.55±0.68mm、短径:5.53±0.55mm)を多数つけており、ヒヨドリ、メジロ、シジュウカラなど205個体(総観察時間22.5時間)の採餌が確認でき、ネズミモチに比べ果実採餌鳥類種数、個体数ともに多く観察され、多数の種子が鳥類により野外に散布されていると考えられる。トウネズミモチの発芽は、光条件の影響を受けないことが示されたため、森林群落の林床においても発芽可能であると考えられる。一方、実生の生存率は林内(相対光量子束密度4.1%)と林縁(相対光量子束密度16.4%)で有意な違いがみられた。また、トウネズミモチはロジスティック回帰分析の結果、相対光量子束密度6.3%以上で出現頻度が50%(コドラート面積25m^2)を超えることを示した。DBHも相対光量子束密度と正の相関が得られた。トウネズミモチの出現、成長には、光量が重要な要因としてかかわっていたことから、トウネズミモチは実生の成長段階において光要求性の高い種であることが示された。すなわち、閉鎖林冠下などの光条件が悪い場所では成長の段階で枯死する可能性が高く、新たな定着は難しいと考えられる。一方、実生の生存率が高い光条件が良好な場所では、高い定着率であることが予想され、実生は成木へと成長していくことが十分に可能であり、今後新たに個体数が増加する可能性が考えられる。
2 0 0 0 平和構築と国際刑事法廷 : 人道的介入としての国際司法介入
- 著者
- 篠田 英朗
- 出版者
- 広島大学
- 雑誌
- 広島大学総合科学部紀要. II, 社会文化研究 (ISSN:0385146X)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.91-111, 2001-12-31
- 著者
- 岡本 健
- 巻号頁・発行日
- 2010-11-21
日本情報経営学会(JSIM)第61回全国大会. 平成22年11月20日~11月21日. 熊本学園大学. 熊本.
2 0 0 0 OA 建文帝の諡号について(1)
- 著者
- 滝野 邦雄
- 出版者
- 和歌山大学
- 雑誌
- 経済理論 (ISSN:04516222)
- 巻号頁・発行日
- vol.355, pp.141-152, 2010-05