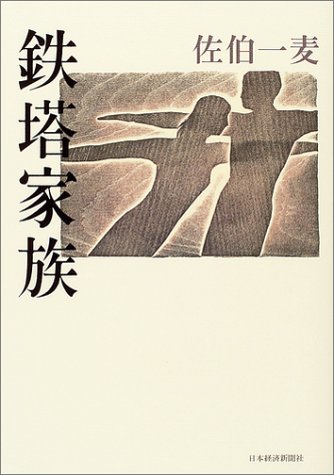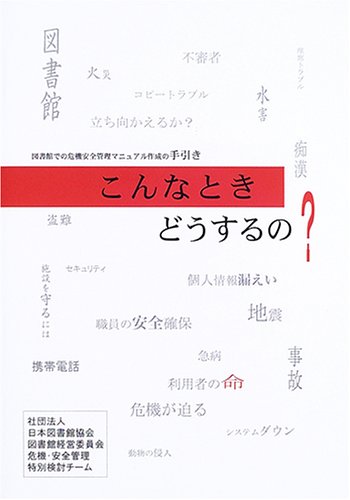2 0 0 0 OA 復帰前後の沖縄自治州(特別自治体)構想
- 著者
- 江上 能義
- 出版者
- 沖縄自治研究会
- 雑誌
- 自治基本条例の比較的・理論的・実践的総合研究- No6 最終報告書 沖縄の自治の新たな構想 研究論文・研究録・構想案
- 巻号頁・発行日
- pp.36-50, 2005-03
平成16年度文部科学省科学研究費補助金基盤研究(B)(2) / 課題番号14320008 / 期間:2004年10月~2005年3月 / 場所:琉球大学
2 0 0 0 OA 早稲田大学と近代台湾 ~大正期在京台湾人留学生の啓蒙運動を手がかりとして~
- 著者
- 紀 旭峰
- 出版者
- 早稲田大学アジア太平洋研究センター
- 雑誌
- アジア太平洋討究 (ISSN:1347149X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.165-187, 2011-05-01
2 0 0 0 OA 消費者ニーズをつかんだ中古ビジネス
- 著者
- 石原 司郎
- 出版者
- 早稲田大学産業経営研究所
- 雑誌
- 産研公開講演会 (ISSN:13481355)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.27-34, 2004-12-25
2004年10月15日 於:早稲田大学国際会議場「井深大記念ホール」
2 0 0 0 認知症患者の談話分析
- 著者
- 山根 智恵
- 出版者
- 学校法人山陽学園 山陽学園大学・山陽学園短期大学
- 雑誌
- 山陽論叢 (ISSN:13410350)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.45-59, 2008
- 著者
- 森 博嗣
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 建築雑誌 (ISSN:00038555)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, no.1314, 1991-06-20
2 0 0 0 武道流派と修験道の関係
- 著者
- 黒木 俊弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本体育学会
- 雑誌
- 体育学研究
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.5, 1967
2 0 0 0 チャット会話の秩序:インターバル解析による会話構造の研究
- 著者
- 水上 悦雄 右田 正夫
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 = Cognitive studies : bulletin of the Japanese Cognitive Science Society (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.1, pp.77-88, 2002-03-01
- 被引用文献数
- 4 4
It has been suggested that chat system provides real time communication like direct conversation. However, chat conversation has distinctive complexity compared with direct and telephone conversation. One often has difficulty in determining whether he is the <i>talker</i> or the <i>watcher</i>. Furthermore, it is not always clear for one that which topic appearing on the record should be referred to. In the present paper, the authors investigated how the order in chat conversation is established, and what kind of efforts are made by the participants. Generally speaking, the couples of subjects maintained the order by sending messages alternately, suggesting that they could basically determine whether they were the <i>talker</i> or the <i>watcher</i>. However, the order was easily broken down when one sent a message so as to interrupt the other's sending. It is discussed that one of the reasons that such interrupting messages were sent was duality of the meaning of an interval between two successive messages; the interval might simultaneously be a sign of the other participant's <i>silence</i> and that of the other's taking time to prepare his/her message. Breaking down of the order were often followed by the situation that several threads appeared on the display were maintained for a while, implying that order with more complicated interaction could emerge through the failure at taking the roles of <i>talker</i> and <i>watcher</i> alternately.
- 著者
- 大場 高志
- 出版者
- 日本図書館協会
- 雑誌
- 図書館雑誌 (ISSN:03854000)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.10, pp.660-662, 2010-10
- 著者
- 土屋 明仁 宮寺 庸造 夜久 竹夫
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. ET, 教育工学 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.41, pp.19-24, 2001-05-04
- 被引用文献数
- 1
URLの登録/再利用を行う際の問題として, URLは階層構造をなす分類項目に一意に類別されるが複数の内容を含むURLの類別が困難, URL相互の関連が欠落するなどがあげられる. 本研究では多変最解析の手法を用いて上記の問題点の解決を試みた. 開発にはクロスプラットフォーム, ネットワーク型のソフトウェア開発が比較的容易に行えるJAVA言語と, WWWブラウザにはNetscapeナビゲータを用いた. 新しいURLナビゲータではキーワードによるURLの意味付けが可能で, またURL相互の関連性が提示される. 利用者の思考状態に対応して動的に変化するURL集合を操作することによって, 思考活動に対して自然でURL相互の関連に基づいたウェブコンテンツの参照を支援できると考えられ, これまでにないURL資産の運用が実現できる可能性がある.
2 0 0 0 OA 江戸文学と木更津 : 地方文化の再認識への序論
- 著者
- 高橋 俊夫
- 出版者
- 清和大学短期大学部
- 雑誌
- 清和女子短期大学紀要 (ISSN:02873141)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.I-XII, 1980-03-15
2 0 0 0 IR 学級規模と教育効果
- 著者
- 杉江 修治 Shuji Sugie
- 出版者
- 中京大学教養部
- 雑誌
- 中京大学教養論叢 (ISSN:02867982)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.147-190, 1996-06
2 0 0 0 ポスドクのすすめ(5)論文の"速い"仕上げ方
- 著者
- 河合 潤
- 出版者
- 化学同人
- 雑誌
- 化学 (ISSN:04511964)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.5, pp.23-25, 2007-05
2 0 0 0 IR ケアマネジャーからみた在宅ケア利用者の自立支援・介護予防の条件
- 著者
- 内田 陽子
- 出版者
- 北関東医学会
- 雑誌
- The KITAKANTO Medical Journal (ISSN:13432826)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.105-111, 2006
- 被引用文献数
- 1
<B>【背景・目的】</B> 本研究の目的は, ケアマネジャーからみた自立支援, 介護予防の条件を明らかにすることである. <B>【対象と方法】</B> 対象は群馬県主催のリーダー研修に参加したケアマネジャー 67人に対して, 自立支援, 介護予防ができたと判断された事例の調査表の記入を依頼した. 分析対象はそのなかで同意を得られた35事例とした. 方法は利用者背景条件, アウトカム, 利用サービス, ケアプランの内容から構成する調査表をもとにケアマネジャーに条件分析のグループワークを行った. <B>【結 果】</B> 自立支援・介護予防できたとケアマネジャーが判断した事例は, 寝たきりになる前の認知症が軽度の者が多かった. また, 主疾患は筋骨格疾患が多く, 主介護者の健康状態や本人との人間関係も良好なものが多かった. サービスは全員福祉用具を利用し, アウトカムの内容には本人の介護度, 歩行, 閉じこもり, 入浴, 意欲, 在宅生活の継続, 排泄, 転倒の改善が記述されていた. その条件の占める割合で高かったものは(1)ケア提供者, (2)本人・家族, (3)ケアマネジャーの条件の順であった. ケア提供者の条件ではサービスの工夫, 状態に合わせた福祉用具の活用, スタッフの声かけ, 訪問介護やリハビリが適切であった. 本人・家族の条件には家族の協力, 本人の意欲があった. ケアマネジャーの条件には, 本人・家族及び事業所との連絡, 効果的なサービスの組み合わせ, 量の調整をした等が明らかになった. <B>【結論】</B> 今後, これらの条件を考慮したケアマネジメント, サービス提供を行う必要がある.
2 0 0 0 OA ラヂウム密封線源の放射能漏洩に関する調査
- 著者
- 樋口 喜代治 新 健治 及川 昭弘 松本 健 萩原 淳 松平 正道 山田 勝彦 光田 秀雄 砂屋敷 忠 高田 卓雄
- 出版者
- 公益社団法人日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術學會雜誌 (ISSN:03694305)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.4, pp.390-392, 1973-01-31
- 著者
- 青山 幹雄
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理 (ISSN:04478053)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.93-95, 2000-01-15
- 被引用文献数
- 2
- 著者
- 日本図書館協会図書館経営委員会危機・安全管理特別検討チーム編集
- 出版者
- 日本図書館協会
- 巻号頁・発行日
- 2005
2 0 0 0 OA コモン・ロー・システム発展史研究-日本民法典への影響を手がかりに-
- 著者
- 高 友希子
- 出版者
- 法政大学
- 雑誌
- 若手研究(スタートアップ)
- 巻号頁・発行日
- 2008
『法典調査会民法議事速記録』を見ると、参考文献として英判例の記載があるにもかかわらず、英法の日本民法典への影響に関する研究は極めて少ない状況である。そこで本研究では、民法716条が立法されるきっかけとなった英国における独立契約者概念の形成・発展のプロセスを、判例の検討を通じて解明することにより、英法の日本民法典への影響について検討を加えた。
2 0 0 0 ニッポン食材風土記 安芸津のジャガイモ(広島県東広島市)
- 著者
- 水野 孝彦
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経レストラン (ISSN:09147845)
- 巻号頁・発行日
- no.392, pp.142-144, 2007-12
「肉じゃが」は日本人にとって特別な料理の一つではないだろうか。例えば、「得意料理は肉じゃが」と聞くだけで、日本人のほとんどは、その人に家庭的なイメージを抱いてしまう。 この肉じゃが、戦前の日本海軍で考案されたものという。発祥地として、海軍の港だった広島県の呉と福井県の舞鶴が名乗りを上げている。 今回訪ねたのは、その呉市の隣、東広島市の安芸津町。
2 0 0 0 OA サウンドスケープデザインにおける住民の参加と主体性に関するフォーマル理論の構築
- 著者
- 西村 篤
- 出版者
- 沖縄工業高等専門学校
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2008
本研究はサウンドスケープデザインにおける住民の参加と主体性の意義について示すことを目的とし、関連する3つの国内事例、すなわち「平野の音博物館」(大阪市)、「瀧廉太郎記念館庭園デザイン」(大分県竹田市)、「長崎サウンドデザイン塾」(長崎市)に対する現地調査が行われた。調査結果の分析から、これらの事例には、形式的な違いはあれども、住民による参加と主体性が不可欠であったことが明らかになった。