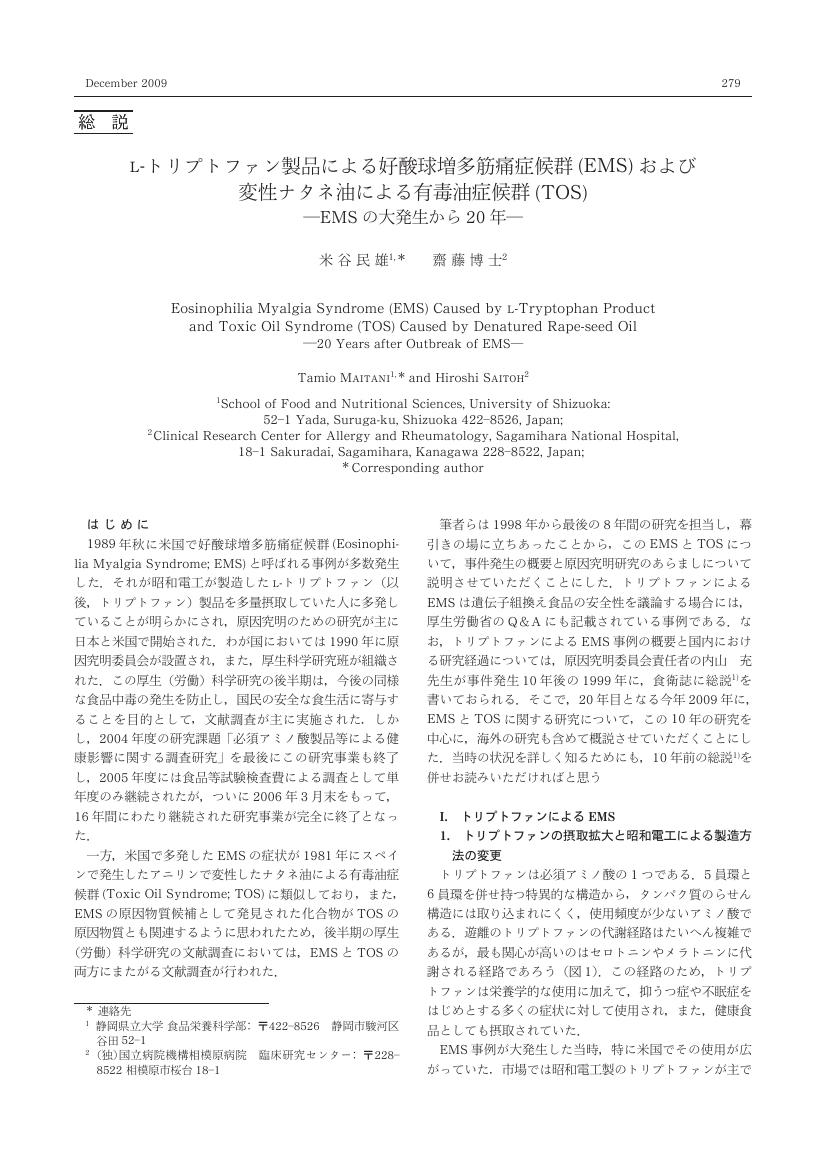2 0 0 0 OA 艾未未2011
- 著者
- 牧 陽一
- 出版者
- 埼玉大学教養学部
- 雑誌
- 埼玉大学紀要. 教養学部 (ISSN:1349824X)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.1, pp.179-192, 2011 (Released:2011-10-28)
- 著者
- 山田 昌弘
- 出版者
- 生協総合研究所
- 雑誌
- 生活協同組合研究 (ISSN:09111042)
- 巻号頁・発行日
- no.273, pp.13-18, 1998-10
2 0 0 0 書評
- 著者
- 山田 昌弘
- 出版者
- Japan Society of Family Sociology
- 雑誌
- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.8, pp.199-201, 1996
2 0 0 0 現代大学生の恋愛意識--「恋愛」概念の主観的定義をめぐって
- 著者
- 山田 昌弘
- 出版者
- 昭和大学教養部
- 雑誌
- 昭和大学教養部紀要 (ISSN:02862719)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.p29-39, 1991
2 0 0 0 ドル防衛と日米関係 一九六三-一九六五
- 著者
- 高橋 和宏
- 出版者
- 外務省外交史料館
- 雑誌
- 外交史料館報 (ISSN:09160558)
- 巻号頁・発行日
- no.24, pp.79-101, 2011-03
2 0 0 0 OA 児童労働と義務教育 : メキシコおよびペルーの事例より
- 著者
- 杉本 均 櫻井 里穂 工藤 瞳
- 出版者
- 京都大学大学院教育学研究科
- 雑誌
- 京都大学大学院教育学研究科紀要 (ISSN:13452142)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.15-39, 2009-03-31
This paper explores the politics of child labour and compulsory education in Mexico and Peru. highlighting the trajectories of compulsory education and the worldwide childrights movements. Mexico and Peru are selected as they have contrasting child labour policies despite the similarities in geography and child labour profiles. While Mexico extended compulsory education starting the age of three, and the government has been strongly encouraging children's human rights, the country has not yet ratified the ILO's Minimum Age Convention 138, which forbids labour for children less than 15 years of age. Lenient standards for child labour result partially from disseminated cultural traditions that children's work is beneficial for their personal and social development. Peru ratified the Minimum Age Convention 138 in 2002, yet the concept of protagonismo, the capacity to participate in society and transform it forcibly remains. Major advocates are the local NGOs and working children who argue that children should be perceived as independent individuals who can judge and design their own lives, including continuation of work. The paper concludes that child labour and education policies are complex and that examining the relationship between compulsory education and child labour requires in-depth cultural analysis as well as policy analysis.
2 0 0 0 OA 福島県の水田土壌における放射性セシウムの深度別濃度と移流速度
- 著者
- 塩沢 昌 田野井 慶太朗 根本 圭介 吉田 修一郎 西田 和弘 橋本 健 桜井 健太 中西 友子 二瓶 直登 小野 勇治
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.8, pp.323-328, 2011 (Released:2011-08-29)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 28 31
福島第一原子力発電所事故で放射性物質が多量に降下してから約2か月後に,耕起されていない水田の深さ15cmまでの表土を厚さ1~5cmの6層に分割してサンプリングし,放射性セシウム(134Csと137Cs)の鉛直濃度分布を求めた結果,放射性Csの88%が0~3cmに,96%が0~5cmに止まっていた。しかし,量的に大半は表面付近に存在するものの,15~20cmの層まで新たに降下した放射性Csの影響が及んでいた。濃度分布から求めた放射性Csの平均移動距離は約1.7cmで,70日間の雨量(148mm)から蒸発散量を引いて体積含水率で割った水分子の平均移動距離は約20cmと推定され,土壌への収着により,Csの移流速度は水の移流速度に比べて1/10であった。しかし,文献にみられる実験室で測定した収着平衡時の土壌固相と土壌水との間の分配係数から計算される移流速度よりは2~3桁大きく,現場の移動現象が収着平衡からほど遠いことを示している。一方,耕起された水田では,表層の高濃度の放射性セシウムが0~15cmの作土層内に混合されて平均値(約4000Bq/kg)となっていた。
- 著者
- 二瓶 真理子
- 出版者
- 東北大学文学会
- 雑誌
- 文化 (ISSN:03854841)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.3, pp.361-343, 2010
2 0 0 0 OA 現代イタリア美術について
- 著者
- ブッカレルリ パルマ 野上 素一
- 出版者
- イタリア学会
- 雑誌
- イタリア学会誌 (ISSN:03872947)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.101-110, 1968-01-20
Questo e un brevissimo riassunto della conferenza della Dottoressa Palma Bucarelli, direttrice della Galleria d'arte moderna di Roma. Ha illustrato molto chiaramente la storia dell'arte italiana cominciando dal 1910. Prima di tutto ha spiegato il movimento futurista, concludendo che il futurismo ha avuto un aspetto polemico, violentemente agressivo e distruttivo, e un aspetto positivo e costruttivo. Poi essa e passata a spiegare il destino di questo movimento che si e trasmutato. Per esempio essa ha parlato di Umberto Boccioni, Antonio Sant'Elia, Giorgio De Chirico. In quanto ai metafisici italiani, essa ha detto che essi sono stati fenomeno parallelo al "rappel a l'ordre" francese. Ha parlato di Amedeo Modigliani, Alberto Magnelli, Gino Severini, Massimo Campigli. Essa ha detto giustamente che il periodo che va dal 1930 all' inizio della seconda guerra mondiale non e stato un tempo felice per l'arte italiana. Essa ha detto poi come e trascorso questo tempo infelice per i grandi artisti come Giorgio Morandi, Tosi, De pisis, Arturo Martini, Marino Marini, Giacomo Manzu ecc. Secondo essa tutti questi artisti si impegnano soprattutto ad opporre una tradizione seria, autentica, fatta di valori concreti, alla falsa tradizione classicistica dell'arte ufficiale. Con la guerra e la fine del fascismo cadono tutte le barriere tra l'arte italiana e la cultura europea. Gli elementi risolutivi dell'intricata problematica del dopoguerra sono da cercarsi special mente nelle opere di tre artisti: Lucio Fontana, Alberto Burri e Giuseppe Capogrossi. Essa ha chiuso la conferenza mostrando lo sforzo compiuto dagli italiani di questo secolo per diventare cittadini del mondo.
- 著者
- Brunner Otto 千脇 修
- 出版者
- 早稲田大学西洋史研究会
- 雑誌
- 西洋史論叢 (ISSN:03882586)
- 巻号頁・発行日
- no.26, pp.49-64, 2004-12
- 著者
- 米谷 民雄 齋藤 博士
- 出版者
- 公益社団法人 日本食品衛生学会
- 雑誌
- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.6, pp.279-291, 2009-12-25 (Released:2010-01-09)
- 参考文献数
- 62
- 被引用文献数
- 2 4 1
2 0 0 0 IR 欧米に於ける日本史研究の現状と動向
- 著者
- 今谷 明
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.201-214, 2007-05
アメリカ、フランス、オランダ、ドイツ各国に於ける日本史研究の現状と特色をスケッチしたもの。研究者数、研究機関(大学など)とも圧倒的にアメリカが多い。ここ十年余の期間の顕著な特色は、各国の研究水準が大幅にアップし、殆どの研究者が、翻訳資料でなく、日本語のナマの資料を用いて研究を行い、論文を作成していることで、日本人の研究者と比して遜色ないのみか、医史学など一部の分野では日本の研究レベルを凌駕しているところもある。このための調査旅行として、二〇〇六年八~十月の期間、アメリカのハーバード大学、南カリフォルニア大学、カリフォルニア大学ロスアンゼルス校、およびオランダのライデン大学を訪問し、ハーバード大学歴史学部長ゴードン氏以下、幾人かの日本史研究者と面談し、第一線の研究状況を直接に聴取することができた。なお、アメリカについては、日文研バクスター教授の研究を参考とし、フランスは総研大院生ハイエク君の調査を、ドイツについては日文研リュッターマン助教授の助力を仰いだことを付け加えておく。
2 0 0 0 IR オーストラリアにおける日本研究(続)
- 著者
- 池田 俊一
- 出版者
- 東京大学大学院教育学研究科教育学研究室
- 雑誌
- 研究室紀要 (ISSN:02857766)
- 巻号頁・発行日
- no.35, pp.87-95, 2009-03
研究動向
2 0 0 0 IR 海外調査 : アメリカにおける日本研究の動向調査
- 著者
- 山本 義彦
- 出版者
- 静岡大学
- 雑誌
- 静岡大学経済研究 (ISSN:13422251)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.69-84, 2009-12
2 0 0 0 IWCS2007報告
- 著者
- 服部 知之
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. OFT, 光ファイバ応用技術 (ISSN:09135685)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.451, pp.5-8, 2008-01-17
2007年11月11日〜14日に米国フロリダ州ブエナ・ビスタで開催された第56回International Wire and Cable Symposiumの概要を報告する。
- 著者
- 小松 善雄
- 出版者
- 立教大学
- 雑誌
- 立教経済学研究 (ISSN:00355356)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.4, pp.155-183, 2001-03
2 0 0 0 IR 高濱虚子・横光利一らの洋上句会 : 宮崎市定のサイン帳と『楠窓を偲ぶ』を中心に
- 著者
- 礪波 美和子
- 出版者
- 奈良女子大学
- 雑誌
- 叙説 (ISSN:0386359X)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.152-171, 2011-03-31
2 0 0 0 感覚的協和理論の作曲への応用
- 著者
- 小畑 郁男
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告音楽情報科学(MUS) (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, no.123, pp.29-34, 2002-12-22
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
多くの音楽様式が混在する現代においては、どのような音楽様式にも適用することができ、音楽の聴覚的な把握に貢献する中立的な音楽理論の必要性は高いといえる。このような状況を背景として、本報告では、量的に不協和度を算出する感覚的協和理論の作曲技法への三つの応用例が提示される。この12等分平均率を前提とする三つの例は、(1) 感覚的不協和度の差異による音高構成の設計、(2) 声部の澄明性の差異による音高構成の設計、そして (3)「R協和音列」に関する応用例である。R協和音列は、基準音を中心とした上下に対称的な音程構造を持ち、「和声二元論」を例証する音響現象である。Music today having a great variety of styles, new music theory that is based on auditory sense and able to apply to every musical style is needed. With the background of necessity for such new theory, three applications of sensory consonance theory to the design of pitch combination are presented based on the following three criteria. They are (1) difference of sensory dissonance, (2) the clearness of voice part in music, and (3) sensory consonance tone series, which consists of symmetrical interval structure centering around optional base tone and illustrates "Harmonic Dualism".