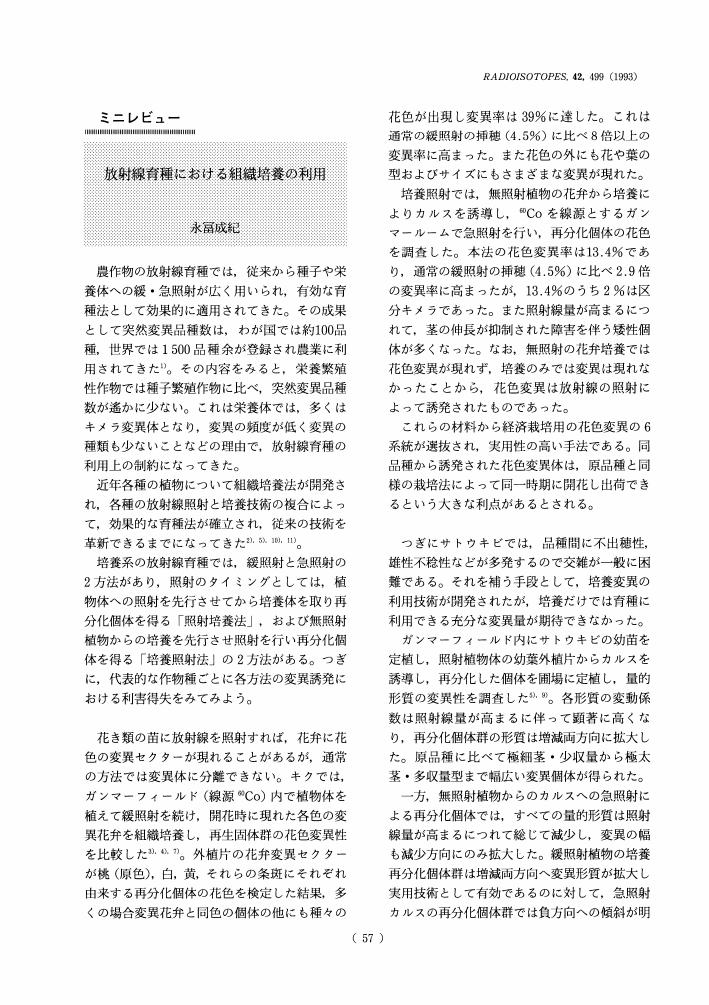1 0 0 0 OA フィヒテとスピノザ主義―ライプニッツ受容史に向けて
- 著者
- 平尾 昌宏
- 出版者
- 日本ライプニッツ協会
- 雑誌
- ライプニッツ研究 (ISSN:21857288)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.69-87, 2012-11-03 (Released:2023-11-14)
1 0 0 0 OA 『結合法論』におけるライプニッツ
- 著者
- 清水 高志
- 出版者
- 日本ライプニッツ協会
- 雑誌
- ライプニッツ研究 (ISSN:21857288)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.53-67, 2012-11-03 (Released:2023-11-14)
1 0 0 0 OA いつもそこにライプニッツがいる
- 著者
- 黒崎 政男
- 出版者
- 日本ライプニッツ協会
- 雑誌
- ライプニッツ研究 (ISSN:21857288)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.153-169, 2010-12-15 (Released:2023-11-14)
1 0 0 0 OA ライプニッツと西田――複雑系を媒介にして――
- 著者
- 大西 光弘
- 出版者
- 日本ライプニッツ協会
- 雑誌
- ライプニッツ研究 (ISSN:21857288)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.135-151, 2010-12-15 (Released:2023-11-14)
1 0 0 0 OA 『百科全書』の哲学史関連諸項目に見るディドロのライプニッツ主義
- 著者
- フォヴェルグ クレール
- 出版者
- 日本ライプニッツ協会
- 雑誌
- ライプニッツ研究 (ISSN:21857288)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.99-114, 2010-12-15 (Released:2023-11-14)
1 0 0 0 OA ライプニッツは歴史をどう語るか
- 著者
- 佐々木 能章
- 出版者
- 日本ライプニッツ協会
- 雑誌
- ライプニッツ研究 (ISSN:21857288)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.79-98, 2010-12-15 (Released:2023-11-14)
1 0 0 0 OA 想像と秩序―ライプニッツの想像力の理論に向けての試論―
- 著者
- 池田 真治
- 出版者
- 日本ライプニッツ協会
- 雑誌
- ライプニッツ研究 (ISSN:21857288)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.37-58, 2010-12-15 (Released:2023-11-14)
1 0 0 0 OA 日本の医療保険制度の歩みとその今日的課題
- 著者
- 井伊 雅子
- 出版者
- 公益財団法人 医療科学研究所
- 雑誌
- 医療と社会 (ISSN:09169202)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.205-218, 2008 (Released:2010-05-26)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 3 2
第2次世界大戦後,多くの途上国は先進国型の医療・保健システムを導入しようとした。しかしその対象は主に都市部に限られ,人口の多くを占める農村のための医療は軽視されてきた。日本では1961年に国民皆保険が達成されたが,1922年に制定された健康保険法に次ぎ1938年に国民健康保険法が成立し,戦前に農村を含む医療保険制度の骨格が形成された。インフォーマルセクターが相対的に多い経済構造の中でどのようにしてその取り組みを行い,社会保険を構築してきたのか,その歴史的な経緯を考察することは,現在公的医療保険制度の設立に取り組んでいる途上国への重要な示唆となる。 この小論では,明治の近代産業の勃興とともに大きな問題となった労働者保護のために始まった工場法,本格的な社会立法である健康保険法,戦時体制の中で急速に整えられた国民健康保険法などを紹介しながら,1961年の皆保険制度への布石を分析する。また,皆保険達成後の日本の医療保険制度について,国民健康保険の問題(経済構造の変化や高齢化といった社会状況の変化に対応していないために引き起こされた制度疲労,場当たり的な制度変更の積み重ねによる制度の複雑化と責任所在の不明化),公平な制度と言われる中で比較的議論されることの少ない負担の不公平の問題,高齢者医療保険制度への対応,保険者の役割という4つの視点から考察する。
1 0 0 0 OA ヒューマンライフテクノロジー (3) ゆらぎの本質とその美学
- 著者
- 堀川 明
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.11, pp.517-520, 1989-11-25 (Released:2010-09-30)
1 0 0 0 OA 放射線育種における組織培養の利用
- 著者
- 永冨 成紀
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.8, pp.499-500, 1993-08-15 (Released:2010-07-21)
- 参考文献数
- 11
1 0 0 0 OA 水稲原々種の栄養繁殖法に関する研究
- 著者
- 白倉 治一 国武 正彦
- 出版者
- 北陸作物・育種学会
- 雑誌
- 日本作物学会北陸支部会報 (ISSN:0388791X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.35-37, 1965-03-15 (Released:2017-08-02)
1 本研究は水稲品種の遺伝的特性を永年維持する目的で, 原々種株の保存ならびに増殖法について検討したものである。2 秋季の株上げ予定株は稈基部の蓄積澱粉量が多いと考えられるものが再生力が強く, 穂肥の過用または乳熟期ころの早刈り, 刈取り後温室への早期搬入が有効である。3 温室内の温度は, 10℃以下になると株枯死の危険が伴なう。4 再生茎の出穂期を揃え, 増殖率を高めるには全期終夜照明よりも, 2月始めころから1ヵ月間の8時間曝光短日処理を行なうがよい。5 温室内では元株から生じた再生茎を株分けして移植しなおせば, 増殖倍率が高まる。
1 0 0 0 OA 伊那谷における蜂の子食慣行のいま
- 著者
- 浦山 佳恵
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2021年度日本地理学会春季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.95, 2021 (Released:2021-03-29)
日本には,かつて地中に巣を作るクロスズメバチVespula sp.の幼虫や蛹を「蜂の子」と呼び食す慣行が広くあった.明治以降,全国的に蜂の子の商品化が進み,1980年以降生息数の減少が指摘されるようになると、1990年以降各地で蜂追いを楽しむ同好会が設立され,1999年には全国地蜂愛好会が結成され情報交換を通じて資源保護や増殖活動が行われるようになった.2006年現在,30余りの会が蜂追いや巣の大きさを競うコンテスト,増殖活動をしているという.1980年代までの伊那谷は,全国的にも積極的な蜂の子食慣行がみられた地域の一つで,蜂の子はご馳走にもなり,煮たり煎ったりするだけでなく蜂の子飯や五目飯,寿司等にもされていた.採取方法も蜂追いや透かしという方法で見つけたり,夏に小さい巣を採り自宅周辺で飼育する飼い巣を行ったりしていた.蜂追いや飼い巣は貴重な蛋白源を得るための生業であるとともに,大人や青少年にとっては娯楽の一つでもあった.現在、伊那谷北部に位置する伊那市にも,「伊那市地蜂愛好会」が存在する.また,伊那谷では蜂の子の佃煮が土産物や日常のおかずとしてサービスエリア,道の駅,スーパー等で販売されているが,それらの原料の多くは県外・海外から輸入されたものであるという.食生活が豊かになった今,伊那谷の地域住民にとってクロスズメバチはどのようなものになっているのだろうか.2018〜2020年に,伊那市の地蜂愛好家5名への蜂の子食慣行に関する聞取り調査及び飼い巣の見学,伊那市地蜂愛好会の活動への同行を行い,現在の伊那谷のクロスズメバチがもたらす自然の恵みについて考察したので報告する.
1 0 0 0 OA 科学報道に思うこと
- 著者
- 宮川 剛
- 出版者
- 日本科学技術ジャーナリスト会議
- 雑誌
- 日本科学技術ジャーナリスト会議 会報 (ISSN:24364525)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023, no.108, pp.1, 2023 (Released:2023-10-01)
1 0 0 0 OA 科学的探究における疑問から問いへの変換過程に関する小学生の実態
- 著者
- 吉田 美穂 川崎 弘作
- 出版者
- 一般社団法人 日本理科教育学会
- 雑誌
- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.675-685, 2020-03-30 (Released:2020-04-15)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 4
本研究は小学校理科の問題設定場面における,「なぜ」という探究の見通しを持たない疑問を「何が」や「どのように」といった探究の見通しを含む問いに変換する際の思考力に着目し,その育成を目指している。このような疑問から問いへの変換における思考力を育成するにあたり,その変換過程は「疑問を認識した後に仮説を形成し,形成された仮説を踏まえて問いを設定する」(「疑問の認識→仮説の形成→問いの生成」)というように先行研究により整理されているが,これを基にした小学生を対象とする実態調査は行われていない。このため,本研究は疑問から問いへの変換過程の中でもとりわけ「仮説から問いへの変換」(「仮説の形成→問いの生成」)に着目して評価問題及び質問紙を作成し,小学生の実態調査を行った。その結果,小学生は仮説から問いへ変換することができないということ,また,その原因として,問いの形式に関する知識や問いへの変換に関する知識が不足しているということが実態として明らかになった。
1 0 0 0 OA 二次元自然対流問題による前処理形陰的流束分離スキームの検証
- 著者
- 坂倉 圭 山本 悟
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 B編 (ISSN:03875016)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.709, pp.2213-2217, 2005-09-25 (Released:2011-03-03)
- 参考文献数
- 12
The preconditioned flux-splitting method developed by our group is applied to the computation of two-dimensional natural convections. This method is based on the Roe's flux-difference splitting, the LU-SGS scheme, and the preconditioning method. In the present study, the natural convection in a cavity at Ra=103-106 were calculated by the present method, and the numerical results are compared with the benchmark results already reported by Davis, Okanaga and Chenoweth. Finally, the reliability and the limitation of the present preconditioning method applied to the convection problems are discussed in detail.
1 0 0 0 甲殻類アレルギー
- 著者
- 平口 雪子
- 出版者
- 一般社団法人日本小児アレルギー学会
- 雑誌
- 日本小児アレルギー学会誌 (ISSN:09142649)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.70-74, 2023-03-20 (Released:2023-03-20)
- 参考文献数
- 20
甲殻類とは節足動物門に属する甲殻亜門(Crustacea)の一群で,エビ・カニ・シャコなどが含まれる.2022年即時型食物アレルギー全国モニタリング調査では全年齢における食物アレルギーの原因食品として8位,初発例の原因食品として7~17歳で1位,18歳以上で2位と,甲殻類アレルギーの多くは学童期以降で発症する.即時型症状が多く,食物依存性運動誘発アナフィラキシーの原因食品としても頻度が高い.予後についての報告はほぼないが,耐性獲得は少ないと考えられている.甲殻亜門の主要アレルゲンはトロポミオシンとされるが,他にアルギニンキナーゼ,ミオシン軽鎖,筋形質カルシウム結合タンパクなどが報告されている.これらのコンポーネントは節足動物門でアミノ酸配列の相同性が高く,交差抗原性は甲殻亜門内だけでなく,節足動物門の鋏角亜門・六脚亜門と甲殻亜門間でも確認されている.粗抽出抗原特異的IgE抗体検査は感度,特異度共に不十分で,コンポーネント特異的IgE抗体検査の有用性が検討されているが地域差など課題も多い.
- 著者
- 永光 輝義
- 出版者
- 森林遺伝育種学会
- 雑誌
- 森林遺伝育種 (ISSN:21873453)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.4, pp.187-191, 2022-10-25 (Released:2022-10-25)
- 参考文献数
- 25
歩行障害者(要歩行リハビリ者、寝たきり高齢者、脊髄損傷者)の方を対象として、自律制御およびパワーアシスト制御の両機能を有する超軽量外骨格系パワードスーツに組み込み障害の程度(筋力の個人差やリハビリ状況)に応じて適応的かつ自律的装着者と協調して歩行支援を行なうパワードスーツを開発することを目的として、研究を実施し以下のような研究成果を得た。現時点で世界最新鋭のシステムである。1)本パワードスーツを軽量化のため部分的にシェル構造として製作し、完成度の高いメカニカルシステムとすることが出来た。2)完全自立システムとするために、搭載型小型コンピュータのオペレーションシステムをRT-Linuxで構築し、安定かつ信頼性の高い計測・制御系を開発する事ができた3)運動学的・機構学的観点からシステム設計を実施するため、シミュレータを用いて適応的運動制御系の検証および制御アルゴリズムの実装を行った。4)人間の意思を反映したシステムであることが求められる為、新たなアルゴリズムを開発するとともに、カセンサ、筋電信号(EMG)、COGセンサによる自律制御系およびパワーアシスト系が混在する複合システムを構築し、実験によりその有効性を示すことが出来た。5)予測制御を組み込み、更に、人間との親和性を高めるため、人間の動作パターンのデータベース化を行い、これを用いた自律・パワーアシスト複合系を開発することができた
1 0 0 0 OA 1940年度に於ける世界石油の需給關係
- 著者
- 牛塚 統六
- 出版者
- 石油技術協会
- 雑誌
- 石油技術協会誌 (ISSN:03709868)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.4, pp.358-365, 1941-07-30 (Released:2008-06-30)