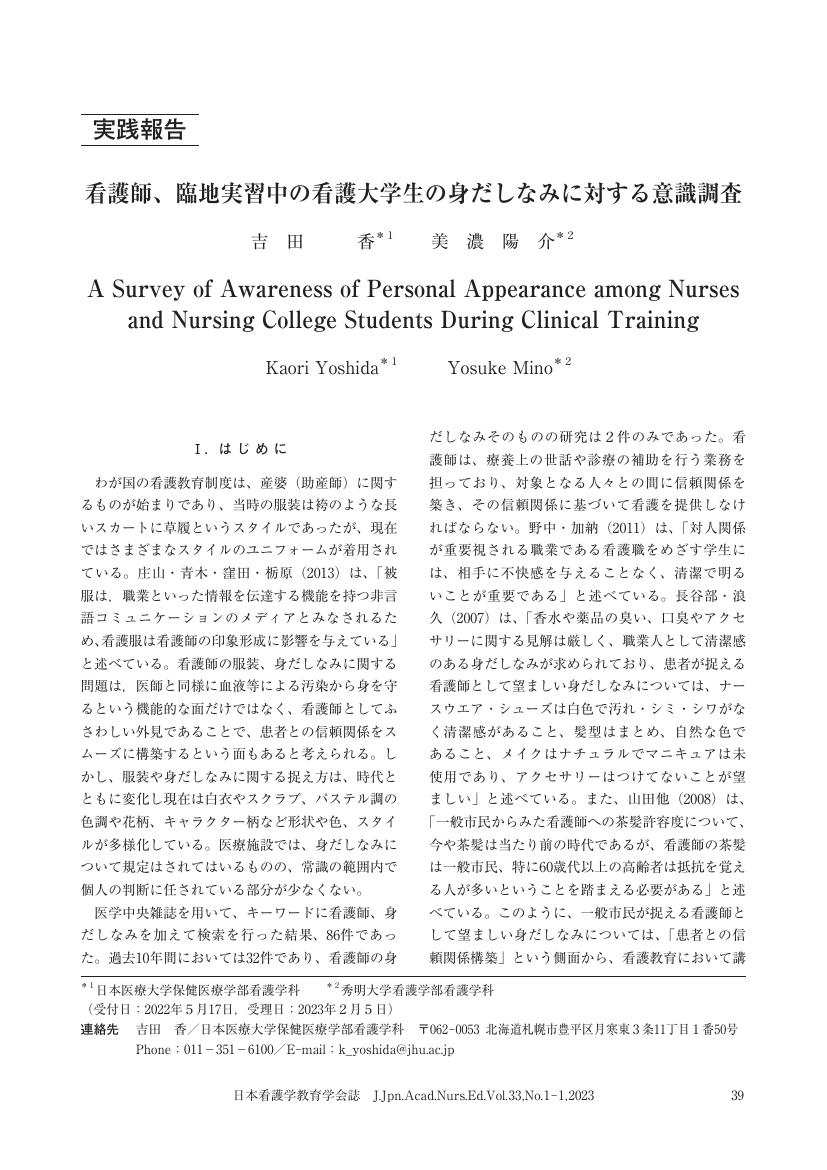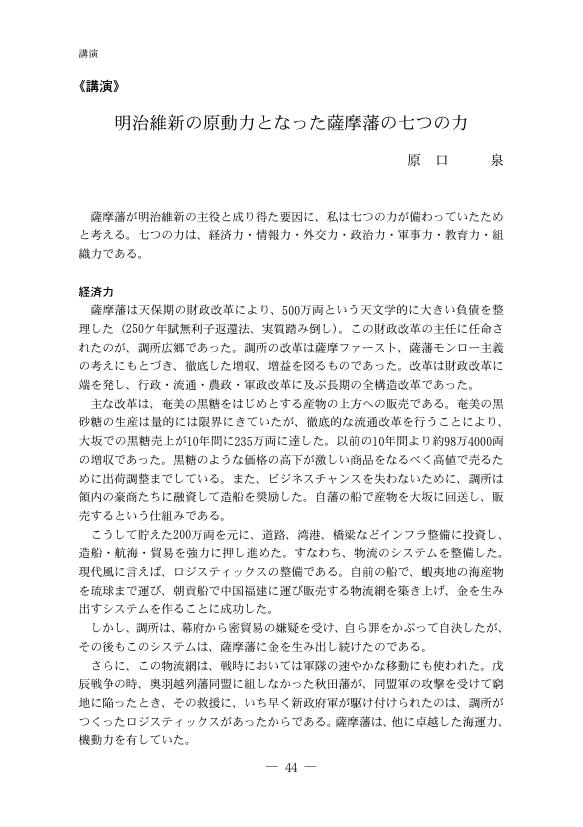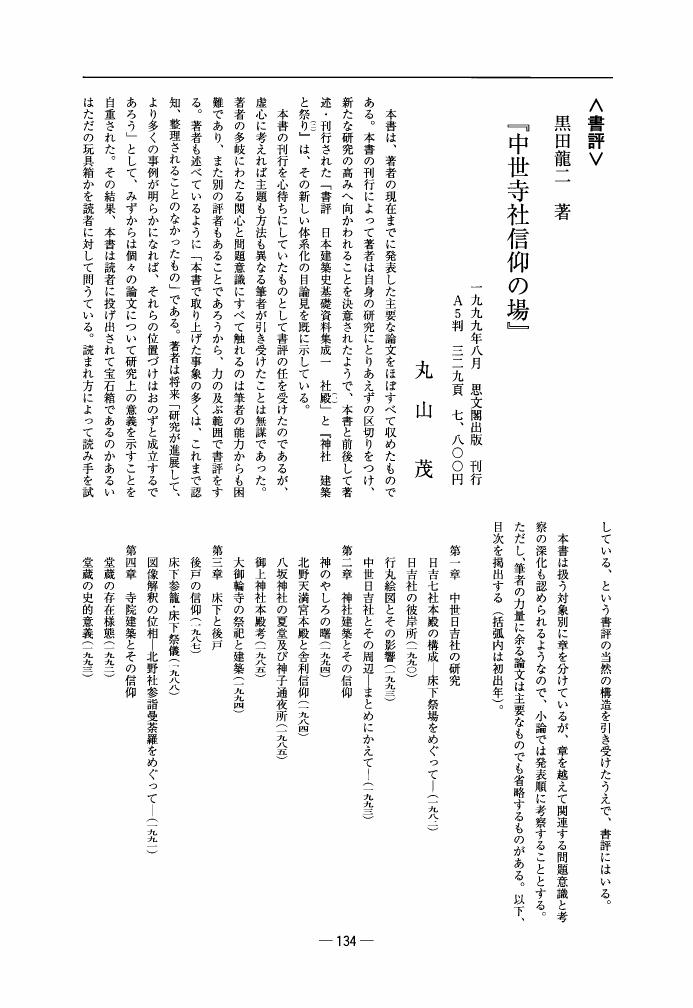1 0 0 0 OA 過酸化尿素の齲蝕原因菌に対する抗菌効果
- 著者
- 鈴木 英明 鈴木 義純 岡田 珠美 神谷 直孝 森 俊幸 藤田 光 池見 宅司
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会
- 雑誌
- 日本歯科保存学雑誌 (ISSN:03872343)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.6, pp.373-380, 2012-12-31 (Released:2018-03-15)
- 参考文献数
- 44
目的:過酸化尿素は,ホワイトニングに使用する薬剤に含まれており,主にホームホワイトニング剤に用いられている薬剤である.過酸化尿素の作用機序は,尿素と過酸化水素に解離し,活性酸素を放出することにより,着色や変色の原因になっている物質に作用し漂白することで歯を白くさせることが知られている.元来,この過酸化水素・過酸化尿素の両薬剤はホワイトニング用としてではなく,口腔用殺菌剤として使用されており,そのうえ,毒性や副作用をもたない安全性の高い薬剤といわれている.ホームホワイトニングで頻用されている過酸化尿素の齲蝕予防の可能性を検討する目的で,その抗菌作用についてin vitroにて実験を行った.材料と方法:実験には,Streptococcus mutans PS-14 (c)株,Streptococcus sobrinus 6715 (d)株,Actinomyces naeslundii ATCC 19246株を用い,10倍段階法にて最小発育阻止濃度の計測を行った.また,Resting cellに対する殺菌作用を濃度的変化ならびに経時的変化について検討した.さらに,不溶性グルカン生成阻害試験としてglucosyltransferase活性値の測定を行った.成績:1.S. mutansに対する最小発育阻止濃度は250μg/mlであった.2.S. sobyinusに対する最小発育阻止濃度は300μg/mlであった.3.A. naeslundiiに対する最小発育阻止濃度は300μg/mlであった.4.過酸化尿素の抗菌作用はS. mutans, S. sobrinusおよびA. naeslundiiのResting cellに対して殺菌的であった.5.過酸化尿素はS. mutans PS-14株ならびにS. sobrinus 6715株産生粗glucosyltransferaseのsucrose依存性不溶性グルカン合成活性を顕著に阻害した.結論:以上のことより過酸化尿素は,齲蝕原因菌に対して顕著な殺菌作用が認められ,抗齲蝕作用を有することが示唆された.
- 著者
- Takashi Yada Fuminari Ito
- 出版者
- The Japanese Society of Fisheries Science
- 雑誌
- Fisheries science (ISSN:09199268)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.5, pp.694-699, 1998 (Released:2008-06-30)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 6 6
Sexual differences in survival and changes in plasma ion levels after transfer from neutral water to acid water prepared with sulfuric acid were examined in medaka Oryzias latipes. In acid water at pH 3.5 and 3.8, survival of female fish was better than male. During exposure to acid water at pH 4.1, there was no mortality in either sex. Male fish showed a transient decrease in the plasma sodium level 24 h after transfer to pH 4.1, whereas there was no change in the female. The plasma level of sulfate was not affected in the female, but a significantly high level was consistently observed during the exposure in the male. In both sexes, the activity of gill Na+, K+-ATPase increased within 24 h after transfer to pH 4.1, and this high level was maintained for 1 month. Treatment with short day-photoperiod (8L:16D) caused a cessation of spawning due to inactivation of the testis and ovary. Transfer to acid water caused a decline in plasma sodium only in male fish, but not in female even under a short photoperiod. These results indicate that female medaka are more tolerant to acidic environment, possibly with a greater osmoregulatory ability than male fish.
1 0 0 0 OA 看護師、臨地実習中の看護大学生の身だしなみに対する意識調査
- 著者
- 吉田 香 美濃 陽介
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護学教育学会
- 雑誌
- 日本看護学教育学会誌 (ISSN:09167536)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1-1, pp.39-48, 2023 (Released:2023-04-28)
- 参考文献数
- 12
1 0 0 0 OA 療養病床の代替施設の必要性―経管栄養者の10年間の推移―
- 著者
- 出口 晃 川口 恵生
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.1, pp.148-149, 2018-01-25 (Released:2018-03-05)
- 参考文献数
- 3
在宅以外で行われている経管栄養の実態を知るため,特養,老健,介護療養型医療施設(介護型),医療型療養病床(医療型)入所者を対象とし,経管栄養患者数と胃瘻造設後の年数を2006年,11年,16年に調べた.経管栄養者の割合は,介護型・医療型で21.9~44.4%であり,特養・老健の4.4~11.7%よりも高かった.造設3年,5年以上経過者は最近5年間で17.4%,18.1%増えていた.経管栄養開始後長期間経過した者の受け皿である療養病床の代替が必要である.
1 0 0 0 OA 北方樹木の寒冷環境適応機構の解明
- 著者
- 春日 純
- 出版者
- 低温生物工学会
- 雑誌
- 低温生物工学会誌 (ISSN:13407902)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.1-6, 2019 (Released:2019-09-01)
In order to survive severe winters without snow cover, boreal tree species have evolved superior freezing adaptation mechanisms. The freezing resistance of living cells in their aerial parts is well-controlled seasonally and exceeds -30°C in mid-winter. Although freeze–thawing can cause functional failure of their water transport system, boreal tree species have abilities to solve the problem and resume growth in spring. In this review, I introduce two topics on freezing responses of boreal tree species: (1) freezing adaptation mechanisms of xylem parenchyma cells which avoid intracellular freezing by deep supercooling, and (2) winter embolism formation mechanisms by which hydraulic architectures, vessels and tracheids, lose their function. In addition, possible relationship between freezing behavior of xylem parenchyma and their roles in embolism repair in early-spring is discussed.
1 0 0 0 OA カフレス血圧計開発の現状と今後
- 著者
- 田村 俊世
- 出版者
- 一般社団法人日本医療機器学会
- 雑誌
- 医療機器学 (ISSN:18824978)
- 巻号頁・発行日
- vol.90, no.1, pp.24-31, 2020 (Released:2020-04-11)
- 参考文献数
- 28
1 0 0 0 OA 神戸市におけるショック症例の病院前静脈路確保の実態
1 0 0 0 OA 大学教育の「PDCA化」をめぐる創造的誤解と破滅的誤解(第1部)
- 著者
- 佐藤 郁哉 Ikuya Sato
- 出版者
- 同志社大学商学会
- 雑誌
- 同志社商学 = Doshisha Shogaku (The Doshisha Business Review) (ISSN:03872858)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.27-63, 2018-07-20
本論文では、2000年前後から日本の高等教育セクターにおいて頻繁に使用されるようになったPDCAという用語の普及過程とその用法について検討を加えていく。また、その事例の分析を通して日本におけるニュー・パブリック・マネジメント(NPM:新公共経営)が陥りがちな落とし穴について明らかにしていくことを目指す。事例分析の結果は、業務の効率化を目指して導入されたPDCAの発想がその本来の意図とは正反対の極端な非効率と不経済をもたらす可能性があることを示している。
- 著者
- 中谷 素之 赤羽 さつき 的場 淳 田中 瑛津子 田中 康博
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集 第49回総会発表論文集 (ISSN:21895538)
- 巻号頁・発行日
- pp.255, 2007 (Released:2017-03-30)
1 0 0 0 OA 都心上空到着機の先進的管制処理システム導入効果の分析
- 著者
- 作中 祐介 阪本 真 屋井 鉄雄
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.6, pp.I_657-I_666, 2020 (Released:2020-04-08)
- 参考文献数
- 13
新興経済国を中心に世界の航空需要は年々増加しており,首都圏空港では早急な機能強化が最優先課題となっている.海外では効率的な管制処理システムの導入といったソフト面の整備が進んでおり,管制官のワークロード改善や燃料消費の削減,環境負荷の低減などの効果を上げている.本研究では,羽田空港に適した新たな管制処理システムを検討し,その導入効果を分析することを目的とする.そこで,管制処理システムの導入効果を管制面や運航面,環境面に関して,定量的に評価できる空域シミュレータの開発を行った.次に,都心上空を活用した管制処理システム案を作成し,その導入効果について開発した空域シミュレータによるシミュレーション分析を行った.分析結果から管制処理システムの導入効果に関して検討を行った.
1 0 0 0 OA ADHD児童における表情認知の神経基盤—近赤外分光法による検討
- 著者
- 小林 恵 池田 尚広 徳田 竜也 長嶋 雅子 門田 行史 金沢 創 山口 真美 作田 亮一 山形 崇倫 檀 一平太
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第83回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.1D-041, 2019-09-11 (Released:2020-09-26)
1 0 0 0 OA 黒田龍二著『纒向から伊勢・出雲へ』
- 著者
- 上野 勝久
- 出版者
- 建築史学会
- 雑誌
- 建築史学 (ISSN:02892839)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, pp.211-217, 2012 (Released:2018-06-28)
1 0 0 0 OA 明治維新の原動力となった薩摩藩の七つの力
- 著者
- 原口 泉
- 出版者
- 九州法学会
- 雑誌
- 九州法学会会報 九州法学会会報 2019 (ISSN:24241814)
- 巻号頁・発行日
- pp.44-48, 2019 (Released:2019-12-26)
1 0 0 0 OA 黒田龍二著『中世寺社信仰の場』
- 著者
- 丸山 茂
- 出版者
- 建築史学会
- 雑誌
- 建築史学 (ISSN:02892839)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.134-141, 2000 (Released:2018-08-17)
1 0 0 0 OA 病院前救護における救急救命士の経験が静脈路確保成功に与える影響について
- 著者
- 西 大樹 清水 光治 矢敷 和也
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.5, pp.782-788, 2022-10-31 (Released:2022-10-31)
- 参考文献数
- 11
目的:病院前救護の場において,救急救命士の経験数など,静脈路確保成功に影響を与える因子を明らかにする。方法:白山野々市広域消防本部の2013年4月〜2019年3月までの7年間で静脈路確保が実施された1,141件を対象とした。結果:年齢,心停止有無,実施場所,留置針口径,救急救命士経験年数,年間静脈路確保経験回数が静脈路確保成功に影響を与えていた。また,救急救命士経験年数3年以下と比較して4年以上,年間経験回数14回以下と比較して15回以上の成功率が有意に高かった。結論:本研究から救急救命士経験年数と年間静脈路確保経験回数が病院前救護における救急救命士の静脈路確保成功に影響していると明らかになった。また,今回の研究内容が当消防本部と同規模で病院研修カリキュラムの再構築を考えておられる方々の一助になれば幸いである。
1 0 0 0 OA 完新統/完新世の細分と気候変動
- 著者
- 平林 頌子 横山 祐典
- 出版者
- 日本第四紀学会
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.6, pp.129-157, 2020-12-01 (Released:2020-12-12)
- 参考文献数
- 236
- 被引用文献数
- 1 2
完新世の気候は,最終氷期に比べて安定で穏やかであるが,完新世にも数百年から千年スケールでの気候変動は起きている.特に,8.2kaと4.2kaに全球スケールで起きた急激な気候変動は完新世の気候変動イベントとして注目され,完新世を区分するためのイベントとして慣例的に使用されてきた.2018年7月13日に国際地質科学連合(IUGS)国際層序委員会(ICS)により,新たに国際年代層序表が発表され,完新統/完新世を,下部完新統/前期完新世,中部完新統/中期完新世,上部完新統/後期完新世に細分することを正式に決定した.本小論では,それらの区分の定義に使用された上記の気候イベントについてレビューを行う.
1 0 0 0 OA 5.チューブ関連インシデント・アクシデントの頻度と予防
- 著者
- 林 泰広 中野 由美子
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.12, pp.3404-3412, 2012 (Released:2013-12-10)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
チューブ関連インシデント・アクシデントの頻度は全体の15~20%程度で,薬剤関連の約30%,療養上の世話(転倒・転落など)の約20%に次ぐ.末梢点滴ルートの自己抜去が約半数で,自然抜去,接続はずれ,切断・破損がこれに続く.アクシデント事例は多くはないが死亡事故の報告もある.予防には患者状態の適切な評価,身体抑制・鎮静を含めた対策が強調されているが,事故防止のために医師が関与すべき点について述べた.
1 0 0 0 OA 戦前日本オーケストラの一運営
- 著者
- 徳永 高志
- 出版者
- Japan Association for Cultural Economics
- 雑誌
- 文化経済学 (ISSN:13441442)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.4, pp.65-81, 1999-09-30 (Released:2009-12-08)
- 参考文献数
- 29
宝塚少女歌劇の伴奏オーケストラから発展し、1926年に設立された宝塚交響楽団は、戦前の関西地方における唯一のプロオーケストラであった。このオーケストラは、大資本阪急の後ろ盾を得たことにより、急速な発展を遂げたものの、それゆえに、1930年代半ばになると、阪急と少女歌劇の動向によって活動の停滞をも余儀なくされた。本稿では、今まで、ほとんど知られていなかった宝塚交響楽団の運営の実態を、未刊行史料を用いて明らかにする。
1 0 0 0 OA 飲酒量低減薬ナルメフェンの薬理学的特徴―アルコール依存症とオピオイド受容体―
- 著者
- 大木 雄太
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.155, no.3, pp.145-148, 2020 (Released:2020-05-01)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 3 3
アルコールは,身近に存在する嗜癖性を有する物質であり,多量飲酒はアルコール依存症の発症につながりうる.アルコールをはじめ依存症形成に共通して重要と考えられているのは,脳内の報酬系回路といわれる中脳腹側被蓋野から側坐核に投射するドパミン神経系の活性化であり,側坐核におけるドパミンの遊離により快の情動が生じる.アルコール依存症においては,内因性オピオイドとその受容体であるオピオイド受容体が報酬系回路の制御に重要な役割を果たす.アルコールを摂取すると,腹側被蓋野や側坐核においてβ-エンドルフィンやダイノルフィンなどの内在性オピオイドペプチドが遊離される.β-エンドルフィンはμオピオイド受容体を活性化し,報酬系回路を賦活することで,正の強化効果を生じさせる.一方で,ダイノルフィンはκオピオイド受容体を活性化し,負の強化効果を生じさせる.アルコールによるオピオイド受容体を介したこれらの作用が,アルコールの摂取欲求を高め,アルコール依存症に関与すると考えられている.ナルメフェンはオピオイド受容体調節薬であり,オピオイド受容体に作用することで,報酬系回路を制御し,アルコール依存症患者における飲酒量低減効果を示すと考えられている.アルコール依存症の治療の原則は,断酒の継続であるが,近年は,ハームリダクションの概念が提唱され,ヨーロッパでは2013年からナルメフェンが飲酒量低減薬として使用されてきた.日本においても,アルコール依存症治療における飲酒量低減を治療目標に加えることが,2018年の治療ガイドラインにより示された.本総説では,最初に,アルコール依存症における脳内報酬系回路とオピオイド受容体との関連についてまとめ,次に,ナルメフェンの薬理学的作用について,非臨床試験及び臨床試験の結果をまとめる.