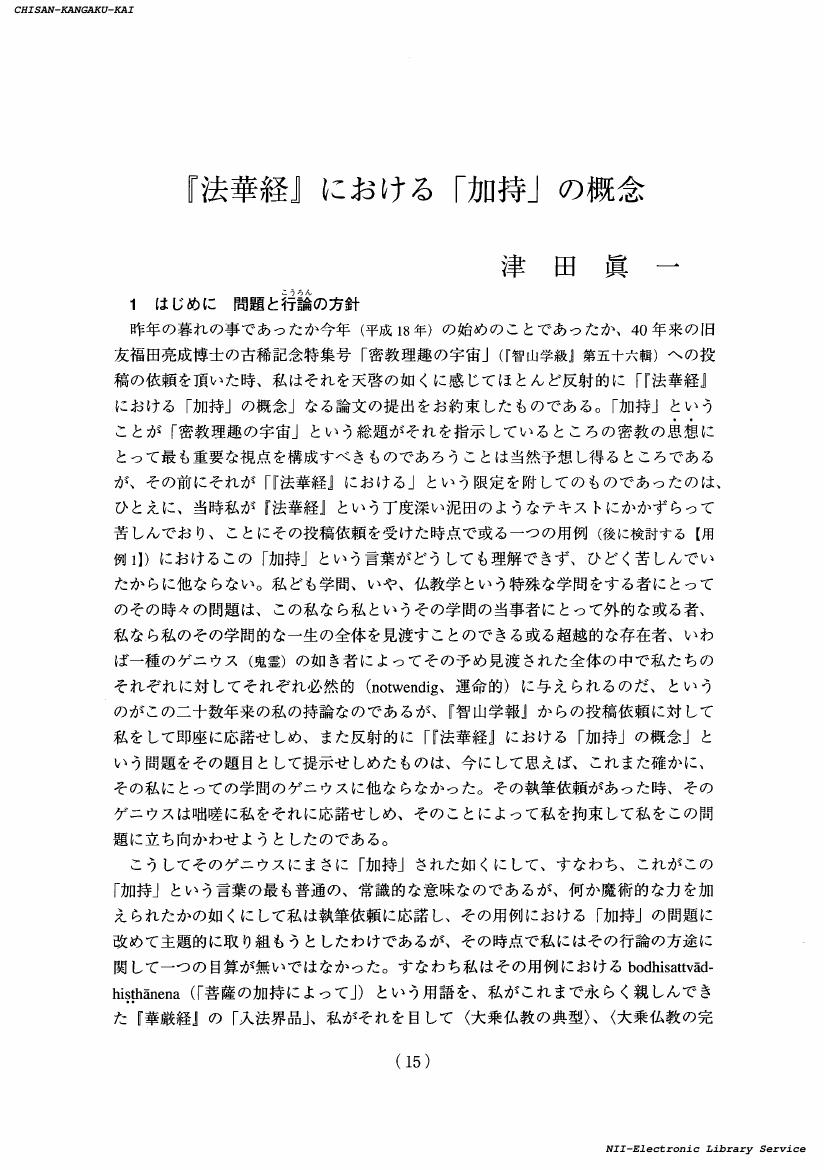- 著者
- MAKOTO KONDO
- 出版者
- The English Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- ENGLISH LINGUISTICS (ISSN:09183701)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.591-613, 2000 (Released:2009-12-24)
- 参考文献数
- 27
1 0 0 0 カフェイン摂取が筋出力および筋交感神経活動に及ぼす影響
【目的】日常生活における食事の中には、嗜好品としてコーヒーや紅茶のようにカフェインを含む食物がたくさんあり、スポーツ選手も容易にカフェインを摂取するこができる。しかし、カフェインは運動中の糖質および脂質代謝を変動させ、持久性種目の持続時間を延長させるというドーピング作用を持つことが知られてきている。さらに、カフェインが中枢神経を覚醒させることから、中枢神経の興奮水準の相違により大きくパフォーマンスが変わる、重量上げなどにおける力発揮にもドーピング作用を持つのではないのかと注目されてきている。本研究の第1の目的は、種々の強度の力を繰り返し発揮させた際におけるカフェイン摂取が力発揮に与える影響について検討し、力発揮に及ぼすカフェインの影響が交感神経活動を代表する心拍数及び動脈血圧にみられるカフェイン摂取に伴う変動とどのように対応するのかについて検討することである。さらに、筋交感神経活動を実際に計測し対応関係を明きらかにすることを第2の実験目的とした(しかし、数名の被験者について筋交感神経活動を記録したが、プリアンプの性能に問題があり、ノイズの混入を回避できなかった。このため、再現性のある信頼できるデータの収集ができなかったので、第2の実験結果については省略する)。【方法】健康な成人女子15名を被験者とし、静的握力発揮による随意最大筋力(MVC)を測定し、その25%、50%、75%、100%MVCに相当する握力を被験者の主観的感覚尺度により分けて出力させる。4段階の握力を5分間にわたり20秒間隔で8回繰り返し発揮させた。このような力発揮を同一被験者にたいし、体重あたり6mgのカフェインをコーヒーとして摂取した場合とカフェインを含まないコーヒーを摂取した場合とにおいて繰り返し実験を行った。【結果】(1)100%MVCのように高い張力の発揮時には、カフェインの摂取により発揮される握力が有意に増大することが示された。(2)繰り返し発揮される力の減衰を見てみると、カフェイン摂取時の握力が摂取しない時よりも高い(疲労し易い)にも拘らず、摂取しない条件よりも常に高い力が維持できることが示された。カフェインの摂取は疲労感を軽減するのではないかと推察された。(3)(1)の結果にみられる握力の増大と、カフェイン摂取にともなう心拍数と動脈血圧の上昇との間には正の相関が示された。
1 0 0 0 OA 裸子植物グネツム綱から被子植物型負重力屈性の由来と進化を探る
裸子植物でありながら被子植物のような二次木部を持つグネツム科の高木について、傾斜樹幹における負重力屈性発現のメカニズムを調査した。傾斜樹幹では、上側で二次木部の肥大成長が促進されると同時に、特異的に大きな引張の成長応力が発生することがわかった。その微視的メカニズムは、原始的なタイプの引張あて材をつくるモクレン科の樹種に類似していることがわかった。このことから、グネモンノキの負重力屈性挙動は、他の裸子植物に見られるような圧縮あて材型ではなく、被子植物に見られるような引張あて材型であると結論した。さらに二次師部においても、傾斜の上側で著しい肥厚が見られ、そこには大きな引張応力の発生が認められた。
1 0 0 0 OA シミュレーションを用いた東南海・南海地震の発生順序について
- 著者
- 高山 博之 黒木 英州 前田 憲二
- 出版者
- 気象庁気象研究所
- 雑誌
- Papers in Meteorology and Geophysics (ISSN:0031126X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.127-134, 2007 (Released:2007-11-01)
- 参考文献数
- 15
すべり速度・状態依存摩擦構成則を平面および3次元の形状をしたプレート境界面に適用し,東南海および南海地震の発生順序に関するシミュレーションを行った。平面のプレート境界では,プレートの形状の影響がないので,東南海・南海地震のそれぞれのアスペリティの大きさおよび摩擦係数(a-b)の大きさの影響を調べた。アスペリティの大きさおよびa-bの絶対値が同じ場合(基本モデル)は,どちらかが先に起こる傾向は見られないことがわかった。アスペリティの大きさまたはa-bの絶対値が異なる場合は,いずれも小さい方が先に起きた。前者は応力の集中の早さの違いに起因し,後者は応力降下量の大きさの違いに起因する。プレート境界を3次元の形状にした場合についてもシミュレーションを行った。東南海と南海のアスペリティの大きさとa-bの大きさを同じにし,両アスペリティのa-bの絶対値を基本モデルと同じにした場合は東南海から先に起き,10%小さくすると南海から先に起こるようになった。これは東南海の東端からの応力の集中の早さと紀伊半島沖の安定すべりによる南海側での応力集中の早さの関係がa-bの値の大小で入れ替わるためと考えられる。
1 0 0 0 OA 持続的噛みしめ時の胸鎖乳突筋筋活動の変化 ―周波数分析を用いた検討―
- 著者
- 山澤 秀彦
- 出版者
- 口腔病学会
- 雑誌
- 口腔病学会雑誌 (ISSN:03009149)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.84-92, 1998-03-31 (Released:2010-10-08)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 3 3
The purpose of this study was to investigate the changes of the activity of the sternocleidomastoid (SCM) muscles during sustained voluntary clenching. Ten healthy male subjects without any occlusal functional problems were asked to clench as long as possible in the intercuspal position while keeping the electromyographic activity of the masseter muscle at the 50% maximum voluntary contraction. Frequency analysis was carried out by computer using a fast Fourier transform algorithm to obtain the power spectrum of the SCM muscle during the fatiguing process and the recovery process. The results were as follows:1. Sustained activities of the SCM muscles were observed during sustained voluntary clenching.2. The power spectra of the SCM muscles significantly shifted to a lower frequency as time elapsed.3. The power spectra of the SCM muscles obtained three minutes after relaxation recovered to those of the beginning of clenching.These findings indicated that muscle fatigue may be induced in the SCM muscle during sustained voluntary clenching and that electromyographic power spectral analysis can be used as a noninvasive, objective, and quantitative index of SCM muscle fatigue.
1 0 0 0 OA 窒素炭化と二酸化炭素賦活竹炭の表面特性および調湿能力の検討
- 著者
- 王 鋭 天野 佳正 町田 基
- 出版者
- 一般社団法人 廃棄物資源循環学会
- 雑誌
- 廃棄物資源循環学会研究発表会講演集 第22回廃棄物資源循環学会研究発表会
- 巻号頁・発行日
- pp.126, 2011 (Released:2011-11-07)
本研究では,竹を原料とした活性炭を調製し,水蒸気吸着に及ぼす炭化温度の影響とCO2賦活で得られた竹活性炭の物性,表面官能基量の関係について検討した。その結果,CO2賦活で得られた竹活性炭の表面積,細孔容積および表面官能基量は,竹の炭化温度によらずほぼ一定の値を示すことが明らかとなった。また,水蒸気の吸着は竹活性炭の表面積・細孔容積の序列と一致したことから,水蒸気吸着は活性炭の表面積・細孔容積にも大きく依存していることがわかった。
1 0 0 0 竹-氷複合系を用いた極低温電気絶縁構成の可能性
本研究の目的は、含水冷却固化させた竹繊維(竹-氷複合系)をガラス繊維強化プラスチック(GFRP)の代替材料として極低温超電導機器の電気絶縁システムに適用する可能性を検討することにある。従来から、超電導電力機器に必要とされる極低温領域の電気絶縁材料としてはもっぱらGFRPが使われてきた。しかし、GFRPは廃棄の際に環境に与える負荷が大きいことが問題視されている。これに対して、竹と氷で構成した竹-氷複合系は廃棄の際に環境に与える負荷は著しく小さい。竹材は、構造上水分を吸収するために、竹材に水分を含浸させた後、極低温冷媒中(液体窒素)に含浸し竹-氷複合絶縁系を形成させることを考えた。この複合系を試料として絶縁破壊特性を観測し、極低温領域における新しい複合材料の電気絶縁構成の可能性を評価した。本年度は、竹-氷複合絶縁系における交流絶縁破壊特性に及ぼす竹の異方性の影響を取り除くために竹をパルプにし、竹パルプ-氷複合系として実験を実施し、検討を行った。その結果、竹が持つ構造上の異方性を取り除くことができ、交流絶縁破壊特性に及ぼす異方性の影響も小さくすることができた。交流絶縁破壊特性においては、GFRPのものと同等程度の値を得ることができた。さらに竹をパルプ化することで形状を変化させることが可能となった。これらの結果より竹パルプ-氷複合系は、低環境負荷の極低温電気絶縁材料であることが実証され、今後、GFRPの代替材料として実機への応用の可能性が示された。
1 0 0 0 OA 破傷風患者血清治療ノ實驗一例(治癒) 破傷風
- 著者
- 吉澤 義夫
- 出版者
- 日本細菌学会
- 雑誌
- 細菌學雜誌 (ISSN:18836925)
- 巻号頁・発行日
- vol.1903, no.93, pp.513-519, 1903-08-25 (Released:2009-07-09)
1 0 0 0 OA 『法華経』における「加持」の概念(福田亮成先生古稀記念 密教理趣の宇宙)
- 著者
- 津田 眞一
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, pp.B15-B37, 2007-03-31 (Released:2017-08-31)
平成15年度は、平成14年度に明らかにした知見(緑茶に炎症性サイトカインの産生抑制作用がある事、TPA誘導耳介浮腫等の炎症モデルに対し抗炎症作用を示す事、それらの活性物質がカフェインである事)を元に、新たに発癌抑制作用を明らかにし、抗炎症作用および発癌抑制作用の機作の検討を行った。前年度の抗炎症実験において起炎剤として用いたTPAが発癌プロモーターとしても使用されている点に注目し、緑茶が、DMBAをイニシエーター、TPAをプロモーターとする多段階発癌も抑制出来る事を明らかにした。次に、炎症あるいは発癌におけるサイトカインの関与を明らかにするため、炎症あるいは発癌部位の皮膚をホモジェナイズし、ELISAにより局所性サイトカインを測定したところ、IL-1α、IL-1β、IL-6、IFN-γ、TNF-αの増加が認められ、しかも、それらは緑茶による抗炎症・発癌抑制時には抑制されていた。したがって、炎症・発癌過程に炎症性サイトカインの局所産生が関与し、緑茶は、それらの産生を抑制する事により抗炎症・発癌抑制作用を発揮している事が示唆された。次に、サイトカイン抑制の機作を検討した。緑茶およびカフェインは、LPSで誘導されるサイトカイン産生を蛋白およびmRNAレベルで抑制した。ヤクロファージをLPSで刺激すると、30〜60分にかけて1κBがリン酸化されたが、緑茶およびカフェインはこのリン酸化を抑制した。また、緑茶およびカフェィンは、p44/42MAPKのリン酸化を抑制した。JNK/SAPKのリン酸化は、緑茶により抑制されたが、カフェインでは抑制されなかった。したがって、緑茶およびカフェインは、1κBやp44/42MAPK系のリン酸化の抑制によりサイトカインの局所産生を抑制し、抗炎症・抗アレルギー作用や発癌抑制作用を発揮していることが推測された。
1 0 0 0 OA 贈正一位楠朝臣正成公御墓所の由来
- 著者
- 別格官幣社湊川神社 編
- 出版者
- 別格官幣社湊川神社
- 巻号頁・発行日
- 1934
1 0 0 0 OA いもの調理
- 著者
- 瓦家 千代子
- 出版者
- 社団法人 大阪生活衛生協会
- 雑誌
- 生活衛生 (ISSN:05824176)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.174-176, 1985-05-10 (Released:2010-03-11)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 東海道新幹線完成に寄せて
- 著者
- 野田 忠二郎
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.913, pp.1462-1463, 1964-10-01 (Released:2008-04-17)
1 0 0 0 OA 食事調査に用いられる青果物の目安量に関する検討
- 著者
- 野末 みほ 猿倉 薫子 由田 克士
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.1, pp.36-41, 2010 (Released:2010-09-01)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2
エネルギー及び栄養素摂取量を把握するために食事調査が用いられる。ほとんどの思い出し調査の方法では,食事の記録の際,目安量が用いられる。そのため,目安量から実際に摂取した重量を推定する必要がある。しかしながら,各書籍や栄養計算ソフトに収載されている食品の目安量は様々であり,特に野菜,果物,魚,肉などの生鮮食品の重量についての研究は少ない。従って,本研究では,青果物の規格の面から,階級やその重量等が地域によって,どの程度異なるのかを明らかにすることを目的とした。さらに,食事調査において,青果物を目安量から重量に換算する際の問題点や課題等について検討した。青果物により階級の数及び名称は複数にわたり,なすでは13の階級,いちごでは28の階級があった。さらに,各階級における重量等にも幅があり,いちごのMにおいては,下限の最小値が7g,最大値が74gであった。これらのことから,食事調査において,目安量によって食品が記録された場合に,対象者と調査員,さらに調査員の間で,その目安量に関して共通の認識を持っていることが確認できることが望ましいと考えられる。実際の青果物の摂取量を過大あるいは過小に評価してしまうことを避けるためには,目安量の設定,つまりどの目安をどの重量で採用するのかを十分に配慮する必要がある。(オンラインのみ掲載)
- 著者
- Junpei Nagasawa Kenichi Suzuki Sayori Hanashiro Masaru Yanagihashi Takehisa Hirayama Masaaki Hori Osamu Kano
- 出版者
- The University of Tokushima Faculty of Medicine
- 雑誌
- The Journal of Medical Investigation (ISSN:13431420)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.3.4, pp.411-414, 2023 (Released:2023-11-09)
- 参考文献数
- 19
Introduction:Branch atheromatous disease (BAD) is a type of cerebral infarction caused by stenosis or occlusion at the entrance of the penetrating branch due to the presence of plaque. Despite its clinical significance, it is not clear how these plaques are formed. Focal geometrical characteristics are expected to be as important as vascular risk factors in the development of atherosclerosis. This study aimed to analyze the association between middle cerebral artery (MCA) geometric features and the onset of BAD. Shear stress results from the blood flow exerting force on the inner wall of the vessels and places with low wall shear stress may be prone to atherosclerosis. At the curvature of blood vessels, the shear stress is weak on the inside of the curve and plaque is likely to form. When this is applied to the MCA M1 segment, downward type M1 is likely to form plaques on the superior side. Because the lenticulostriate artery usually branches off from the superior side of the MCA M1 segment, in downward type M1, a plaque is likely to be formed at the entrance of the penetrating branch, and for that reason, BAD is likely to onset. Methods:We retrospectively reviewed hospitalized stroke patients with BAD and investigated the morphology of their MCA using magnetic resonance imaging. The M1 segment was classified as straight or curved. Additionally, we compared the difference between the symptomatic and the asymptomatic side. Data regarding patients’ medical history were also collected. Results:A total of 56 patients with lenticulostriate artery infarctions and BAD were analyzed. On the symptomatic side, downward type M1 accounted for the largest proportion at 44%, whereas on the asymptomatic side, it was the lowest, at 16%. Conclusion:A downward type MCA may be associated with the onset of BAD and the morphological characteristics might affect the site of plaque formation. J. Med. Invest. 70 : 411-414, August, 2023
1 0 0 0 OA 生活習慣および体力との関係を考慮した幼児における適切な身体活動量の検討
- 著者
- 中野 貴博 春日 晃章 村瀬 智彦
- 出版者
- 日本発育発達学会
- 雑誌
- 発育発達研究 (ISSN:13408682)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, no.46, pp.46_49-46_58, 2010 (Released:2011-02-20)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1 1
[Purpose] We examined the appropriate physical fitness level related to lifestyle and motor ability for kindergarten children. [Method] The subjects were 152 kindergarten children. The measurement items were physical activity (7 days) which was measured by pedometer, a fitness test (9 items), and a lifestyle questionnaire. [Results] The weekday average walking steps were 11,482±4,065 steps in a day (Boys : 12,354±4,308, Girls : 10,742±3,693), and half of the daily steps were counted during kindergarten activities in a day. The kindergarten children who have good lifestyles walked 12,531−13,558 steps in a day. The motor ability of the kindergarten children who had taken more than 13,000 steps daily was significantly better than that of other children. However, we should pay attention to the difference of the average steps of each school year because the result of the analysis of covariance for school year was not significant. The motor ability of the kindergarten children who had taken more than 6,500 steps after kindergarten activity was also significantly better. [Discussion] The results suggested that more than 13,000 steps daily, and more than 6,500 steps taken after kindergarten activity, constitute an appropriate level of physical activity for kindergarten children.
1 0 0 0 OA 近代朝鮮医学史研究への日本宣教医療という視点の導入
日本宣教医療について考える場合には、朝鮮の農民たちが「総督府主導の植民地医学」/西洋医学から放逐され、西洋医学の経験を獲得しておらず、伝統医たちも存在しない中で生活をしていたという社会的背景を考慮しなければならない。そのうえで、(1)天理教と朝鮮総督府の関係は、「緊張と協力」の間にあった。(2)天理教の医療者は、非天理教の医師や看護婦と異なる医学・医療体系を身に付けていたのではなく、見捨てられた患者を懸命に看病・介護する「態度」の違いとして表現された。(3)天理教の医療伝道論と医学観には、中国大陸に漢方医学の普及を求めた日本漢方医学者に通じる点があった。
1 0 0 0 OA 〝ヒロシマの声”を聞くことをめぐって
- 著者
- 好井 裕明
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.3, pp.137-139, 2020-02-01 (Released:2022-04-07)