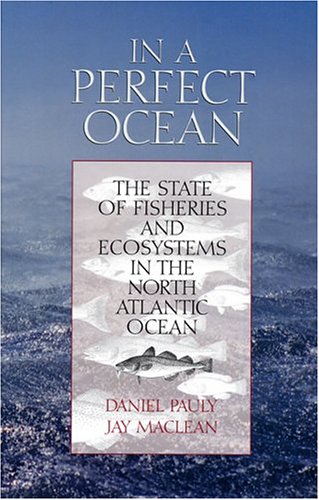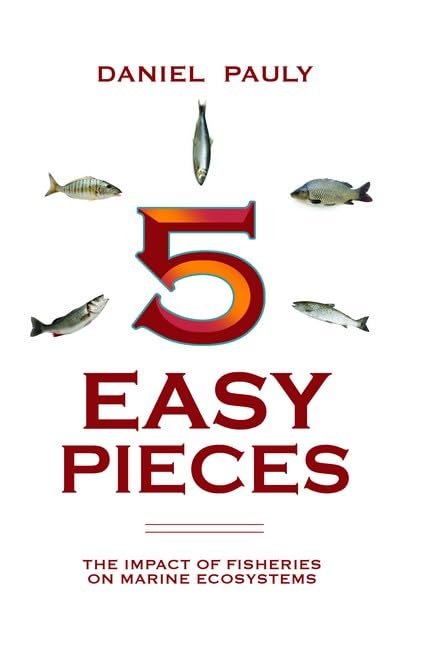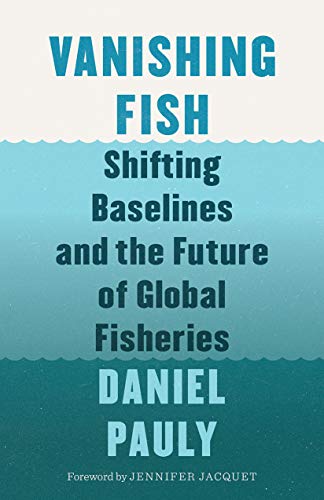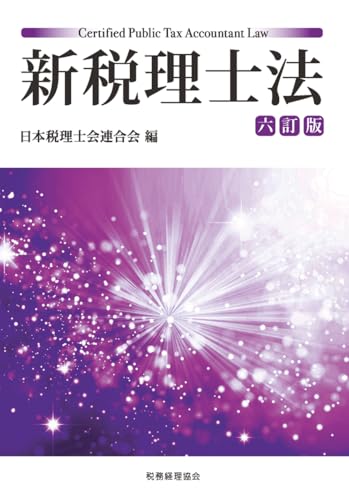- 著者
- Daniel Pauly and Jay Maclean
- 出版者
- Island Press
- 巻号頁・発行日
- 2003
- 著者
- Daniel Pauly
- 出版者
- Island Press
- 巻号頁・発行日
- 2010
- 著者
- Daniel Pauly foreword by Jennifer Jacquet
- 出版者
- David Suzuki Institute : Greystone Books
- 巻号頁・発行日
- 2019
1 0 0 0 OA さまざまな視点からみた「視点」
1 0 0 0 OA 自己物語の潜在性と可能性――「山月記」を読み直す――
- 著者
- 千田 洋幸
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 全国大学国語教育学会国語科教育研究:大会研究発表要旨集 134 (ISSN:24321753)
- 巻号頁・発行日
- pp.213-216, 2018-05-26 (Released:2021-12-13)
1 0 0 0 OA 微生物の発電
- 著者
- 高妻 篤史
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.5, pp.296-301, 2016-05-05 (Released:2016-07-12)
- 参考文献数
- 29
最近,クリーンエネルギーに対する関心の高まりから,微生物発電が注目を集めている.微生物を利用した発電装置は微生物燃料電池( Microbial Fuel Cell; MFC)と呼ばれ,そこでは微生物が燃料(主に有機物)から電子を取り出すための触媒として用いられる.微生物は様々な有機物を分解できる能力を持っているため,化学触媒では分解できない多種多様な化学物質から電気を作り出すことができる.このことは水素等の純粋化合物しか利用できない化学燃料電池と比べて, MFCが大きく有利な点である.また常温でも反応が可能であることや,有機物を餌にして自己増殖できることなども,微生物触媒の長所として挙げられる.こうした利点から MFCは廃棄物系バイオマスを利用した発電システム等への応用が期待されており,特に工業廃水処理プロセスに MFCを適用する技術に関しては,大型装置の開発が進むなど実用化に向けた動きが加速してきている. MFCでは,微生物が有機物を酸化分解し,その過程で生じた電子が微生物細胞内から電極(アノード電極)へと移動することによって電流が生じる.このプロセスには複数の微生物が関与する場合もあるが,純粋培養された状態でも発電が可能な微生物(発電微生物)も存在する.しかし生物の細胞膜は絶縁体であり,通常の生物は細胞の外へ電子を放出することはできない.ではいったい発電微生物はどのように細胞外の物質に電子を伝達するのだろうか? そのメカニズムは多くの微生物学者の興味を惹きつけ,その解明に向けた研究が世界中で盛んに行われてきた.その結果,発電微生物は細胞外に電子を放出するための導電経路(細胞外電子伝達経路)を備えており,この経路を介して電極に電子を直接,あるいは間接的に受け渡すことが明らかとなってきた.また電極の電位を制御すれば,この導電経路を介して逆に電極から微生物細胞内へと電子を注入できることも,最近の研究によって明らかとなった.注入された電子は細胞内の物質変換反応に使用されるため,電子注入によって微生物による有機物合成を促すシステムを構築することができる.このシステムは微生物電気合成系(Microbial Electrosynthesis System; MES)と呼ばれており,二酸化炭素や安価な低分子有機化合物から有用化合物を合成するプロセスの開発を目指して,現在基礎研究が進められている.このように,電極と微生物間の電子移動(細胞外電子伝達)を利用し,新たなバイオプロセス(“微生物電気化学プロセス ”)を創出しようとする試みが,近年活発化してきている.既存の学問分野の垣根をこえ,微生物学や化学・工学的知識の統合による技術発展を進めることが,実用化に向けた鍵となるだろう.
1 0 0 0 新税理士法
- 著者
- 日本税理士会連合会編
- 出版者
- 税務経理協会
- 巻号頁・発行日
- 2023
1 0 0 0 OA 娯楽コンテンツとしてのベクションの歴史研究
- 著者
- 青木 卓也 妹尾 武治 中村 信次 藤井 芳孝 石井 達郎 脇山 真治
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会
- 雑誌
- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.255-265, 2020-09-30 (Released:2020-09-30)
- 参考文献数
- 46
Visually induced illusory self-motion perception is named “Vection”. In this article, we investigated the history of vection. There have been a lot of contents and technology using and relating to vection, e.g. analogue contents, movies, animations, 3D computer graphics (3D CGs), Games, and VR contents. We introduced these things in chronological order. The readers will be able to understand the history of vection very briefly.
- 著者
- 今川 真志 阪田 真己子
- 出版者
- 一般社団法人 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- 日本デジタルゲーム学会 年次大会 予稿集 第12回 年次大会 (ISSN:27586480)
- 巻号頁・発行日
- pp.19-22, 2022 (Released:2023-03-20)
- 参考文献数
- 12
これまで自己主体感と選択肢に関する研究が行われてきたものの、従来の研究ではボタンを押すといった非常に短期間での行動について明らかにするのみであった。しかしゲームプレイのような日常の場面では、ある行動がより長期的な目標のための手段に過ぎないことも多く、この違いを無視して一般化するのは難しい。そこで本研究では長期的な目標に対する行動における選択肢の数を変化させることにより、短期的ではない目標設定がプレイヤーの自己主体感に与える影響について検討した。この結果、選択肢の数が自己主体感に影響するのは、選択する行動が自己目的的である場合であることが示唆された。
1 0 0 0 OA メタバースの本質は何か? 仮想空間の『遊び』か、それとも仮想空間に進出した『現実』社会か
- 著者
- 中尾 優奈
- 出版者
- 一般社団法人 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- 日本デジタルゲーム学会 年次大会 予稿集 第12回 年次大会 (ISSN:27586480)
- 巻号頁・発行日
- pp.70-73, 2022 (Released:2023-03-20)
- 参考文献数
- 18
本発表では、『メタバース』 が考察対象である。今後の発展が推察されるメタバースは、デジタルゲームの延長線にある仮想空間を用いた『遊び』が本質なのか、それとも仮想空間に進出した『現実社会』か、これらの対立する命題を比較検討する。具体的には、和田洋一・ザッカーバーグのメタバース論を対比させつつ、ディシプリンとしてはメディア論を援用する形で、メタバースの発展の指向性について仮説構築的な考察を行う。
1 0 0 0 OA ゼロ年代以前のゲーム雑誌分析
- 著者
- 武田 拓也 久野 桜希子
- 出版者
- 一般社団法人 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- 日本デジタルゲーム学会 年次大会 予稿集 第13回 年次大会 (ISSN:27586480)
- 巻号頁・発行日
- pp.102-106, 2023 (Released:2023-03-30)
- 参考文献数
- 15
本発表では、ゼロ年代以前のゲーム雑誌の分析を行う。前半では、ゲーム雑誌が誕生し始めた1980 年代に焦点を当てる。その際、読者同士あるいは読者と編集者とのコミュニティがどのようなかたちで形成されていたのかを明らかにする。後半では、ゲームが社会的な認知を得ると同時に、ゲーム雑誌の創刊も相次いだ1990 年代の様相に着目し、ゲームに対する社会一般の眼差しと、それに対する読者および編集者の応答を考察する。
1 0 0 0 OA 中国企業の株主構成と知財戦略 —特許データを用いた実証分析
- 著者
- 袁 媛
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.4, pp.406-420, 2021-12-31 (Released:2022-03-15)
- 参考文献数
- 18
The purpose of this study is to analyze the impact of shareholder structure on the innovation activities of the firms by using the patent database and industrial enterprises database of China. In particular, we focus on the role of state-owned shareholders. The main results are as follows.First, there is a tendency that the central state-owned firms and local state-owned companies produce new products. However, we only observed the tendency of patent application and registration for central state-owned firms.Second, regarding the effect privatization on innovation, we find, that firms that have been privatized to private firms (hereafter: PPF), reduces the patent application or registration, tend to produce new product. However, we don't find any significant effect on firms that have been privatized to foreign companies (hereafter: PFF).Third, our analysis shows that firms with high competitive pressures from foreign companies, export firms, debt less firms, firms with large market share, firms with large asset size, elder firms, have a tendency of application, registration and new products.The results of this study, suggest that in China, leading-edge innovation was driven by state-owned firms, particularly state-owned firms which have strong supports from government, while new products that respond to the market needs are almost developed by the private firms.
- 著者
- 髙橋 宏和
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.34-52, 2022-03-31 (Released:2022-04-18)
- 参考文献数
- 27
1 0 0 0 OA 「パテント・パラドックスの再検証」から見る特許研究
- 著者
- 蟹 雅代
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.53-57, 2022-03-31 (Released:2022-04-18)
- 参考文献数
- 8
- 著者
- 比留川 ありさ 西川 英彦 米満 良平
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.83-91, 2023-06-30 (Released:2023-06-30)
- 参考文献数
- 15
ユーザーからアイデアを集め,製品開発に活用するクラウドソーシングが注目されている。しかし,クラウドソーシングを活用する企業の多くが,アイデア募集に苦労している。たとえユーザーからアイデアを集められたとしても,そのアイデアを上手く活用できず失敗する企業や,継続できていない企業も多い。その困難克服の好例が格安スマホのmineoである。mineoはこれまでに約9,100件のアイデアをユーザーから集め,約1,100件ものアイデアを実現している。本稿では,まずmineoのコミュニティサイト「マイネ王」にて,ユーザーからアイデアを集める場として中心的に機能している「アイデアファーム」について紹介する。次に,ユーザーのアイデアをもとにサービスの創造やアップデートが行われていることを確認する。最後に,ユーザーのアイデアを数多く実現し,魅力的なサービスへと進化しているmineoの優れている点,すなわち1.アイデアの量の確保2.アイデアの質の向上3.役職者による全アイデアの検討と実現化の促進について述べる。
1 0 0 0 OA 自然感の影響 ― 既存研究の整理と今後の研究の方向性 ―
- 著者
- 渡邊 久晃
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.75-82, 2023-06-30 (Released:2023-06-30)
- 参考文献数
- 37
近年,消費者は食品や化粧品といったさまざまなカテゴリーで自然製品をますます好むようになっている。自然感(naturalness)は,「人間による介入や処理,添加物がないこと」を意味する概念であり,自然感の影響に関する研究は徐々に増えてきている。そこで本稿では,消費者行動研究分野とマーケティング研究分野に関連する海外ジャーナルの論文のレビューを行った。その結果,自然感が特定の信念や推論を通じて消費者の判断や感情的反応に影響を及ぼすこと,プロセス要因と感覚的要因が自然感知覚に影響を及ぼすことがわかった。最後に,今後の研究の方向性について議論した。本稿は,自然感概念及び自然感選好についての理解に役立つ知見を提供している。
- 著者
- 石田 真貴
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.66-74, 2023-06-30 (Released:2023-06-30)
- 参考文献数
- 34
マーケターは新製品に対する消費者選好を正確に予測できているのだろうか。新製品開発において消費者選好を正確に予測することは重要だが,先行研究では,マーケターによる予測は正確でないことが示されている。そこで本稿の目的は,消費者選好を予測する際に生じるフォールスコンセンサス効果(False Consensus Effect:以下FCE)に関する研究を整理し,マーケターによる消費者選好の予測の正確さに貢献していくことにある。FCEとは,製品に対する個人選好を消費者に投影させる認知バイアスのことである。FCEが生じたマーケターの予測は,実際の消費者選好と乖離し,非魅力的な製品の開発を続けるなどの望ましくない意思決定を下す。そのため本稿では,FCEが生じる要因である「消費者への共感」と「顧客志向」について確認した上で,FCEを回避する方法である「個人選好抑制」について詳述していく。しかし,FCEに関する研究には残された課題が多い。そのため最後に,個人選好抑制,予測対象である消費者の属性,消費者選好の測定の正確さ,マーケターの特徴の観点から今後の研究の方向性を示唆する。
- 著者
- 井関 紗代
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.42-52, 2023-06-30 (Released:2023-06-30)
- 参考文献数
- 61
近年のデジタル化による技術革新は,短命で,アクセスベースで,脱物質的なリキッド消費を促進している。このような消費環境の変化は,心理的所有感(psychological ownership)を減衰させたり,他の対象へと転移させたり,維持するための新たな機会を生み出したりしている。本研究では,心理的所有感の根底にある動機として,コントロール欲求に着目し,音楽配信サービスに対する心理的所有感の醸成にどのような影響を及ぼしているのかについて検証した。調査は,音楽配信サービスであるSpotifyまたはApple Musicを週に1回以上利用する人を対象に実施された。分析の結果,コントロール欲求がサービスへの心理的所有感やロイヤルティに及ぼす影響は,利用頻度によって異なるだけでなく,サービスの違い(Spotify/Apple Music)によっても異なるパターンが示された。これらのことから,コントロール欲求が心理的所有感に及ぼす影響は,他の要因(e.g.,利用頻度)によって調整されるため,コントロール欲求が高いと心理的所有感も醸成されやすいというほど単純ではないことが示唆される。
1 0 0 0 OA 人工物とともに暮らす社会
- 著者
- 斉藤 了文
- 出版者
- 科学・技術研究会
- 雑誌
- 科学・技術研究 (ISSN:21864942)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.3-16, 2023 (Released:2023-06-30)