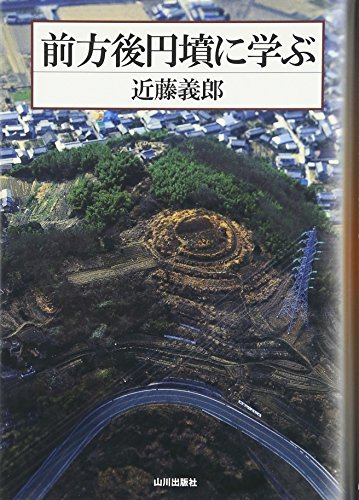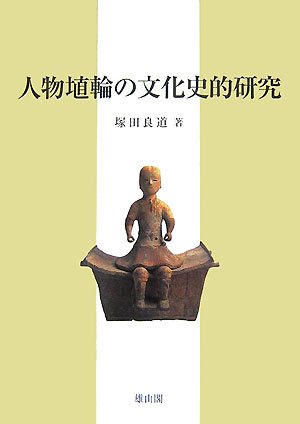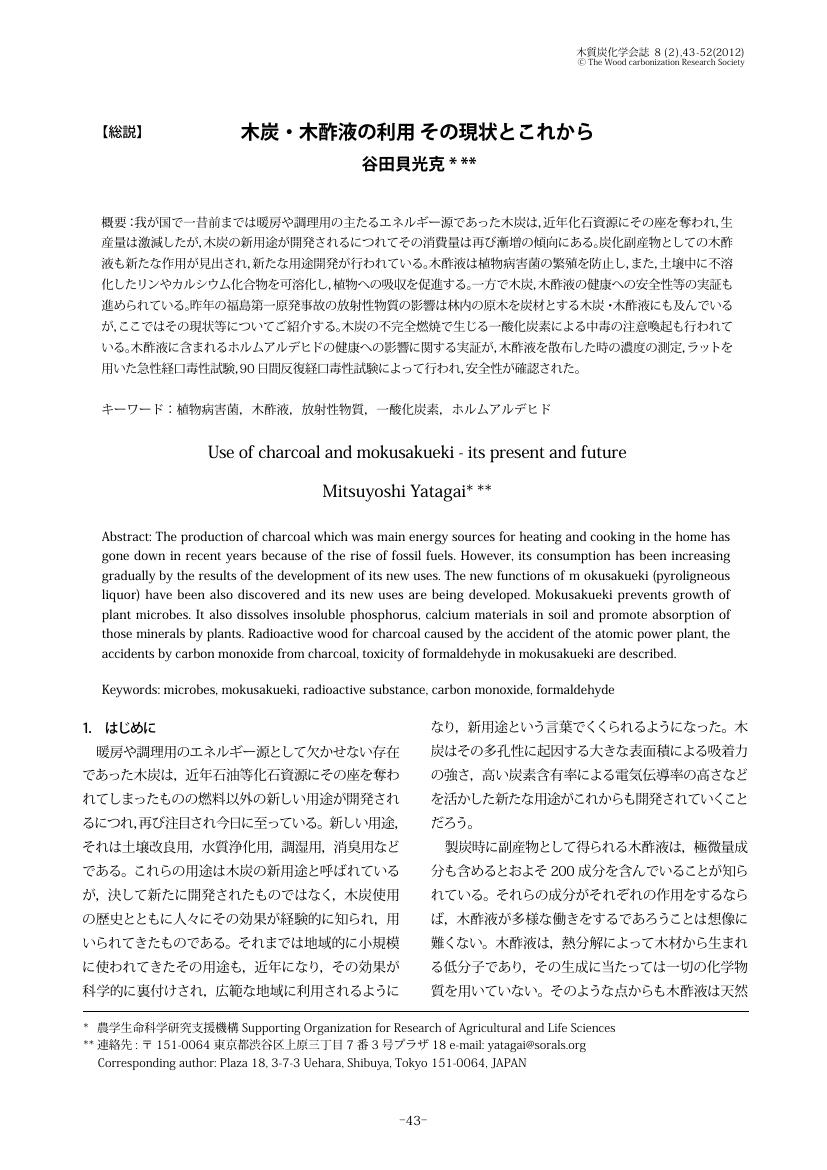- 著者
- CHIHARU UDA KIKUTA
- 出版者
- The English Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- ENGLISH LINGUISTICS (ISSN:09183701)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.357-370, 2015 (Released:2019-07-12)
- 参考文献数
- 17
1 0 0 0 OA 肥満者と瘠痩者の保持代謝の相違に就いて
- 著者
- 池田 駿
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.13-18, 1955-03-31 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 5
Up until to-day, it is generally believed that the metabolism of the corpulent person is essentially not different from that of the slender person. In order to elucidate as to whether a similar result is observed or not even when the variation in the metabolism due to the adaptation is taken into consideration, the author determined the gas metabolism and the various somatic functions at rest, and obtained the following results.(1) The basal metabolism and the metabolism at rest per body weight of the corpulent person demonstrated very much lower value compared with that of the slender person. However, no significant difference was noted in the value per body surface area.(2) Among the corpulent persons, especially those who recently became corpulent with relatively poor working ability, showed a low value, and those who recently became slender demonstrated a high value. Moreover, the values of the basal metabolism of the corpulent and slender persons who remained unchanged during these several years showed a reversed aspect in the difference compared with that stated in the above (1) . The high value in the metabolic rate demonstrated by the former is due to the higher cardiac function, espcially to the higher pulse pressure adapted to the prolonged continuous living conditions, and the lower value observed in the latter is considered to be due to the diminution of the cardiac function.(3) No qualitative differences were noted in the respiration quotient of the rest metabolism and its daily fluctuation between the groups of corpulent and slender persons examined.
1 0 0 0 OA ドライキャットフードへのL-シスチン添加による尿の酸性化
- 著者
- 大島 義之 和田 沙依子 田村 充宏 後藤 健 金子 政弘 舟場 正幸 入来 常徳 波多野 義一 阿部 又信
- 出版者
- 日本ペット栄養学会
- 雑誌
- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.2, pp.64-73, 2003-04-10 (Released:2012-09-24)
- 参考文献数
- 34
ネコにおけるシスチンの尿酸性化効果と有害作用の有無について検討した。健康な成ネコ6頭(平均3.3kg)を2頭ずつ3群に分け,1期8日間の3×3ラテン方格法により,L-シスチンを0,2.4,4.8%添加した3種類の実験食を各群に割り当てた。実験期間を通して実験食と飲水は不断給与し,各期最終5日間に増体量,摂食量,飲水量,尿量,糞量を測定した。また,毎朝新鮮尿を採取し,直ちにpHとストルバイト結晶数を測定した.残りの尿はMg,P,尿素態N,アンモニア態N,クレアチニン,遊離アミノ酸濃度の測定に用い,[Mg2+]×[NH4+]×[PO43-]によりストルバイト活性積を求めた。一方,各期最終日には頚静脈より採血し,ヘマトクリットと血漿中の総蛋白質,尿素態N,アンモニア態N,クレアチニン,および遊離アミノ酸濃度を測定した。尿および血漿のクレアチニン濃度を指標として糸球体濾過量も求めた。その結果,L - シスチンには等S量のDL-Metに匹敵する尿酸性化効果がある一方,DL-Metのような強い毒性はないことが明らかとなった。しかし体重の有意な減少なしに摂食量が減少したことから,インバランスは生じ得ることが示唆された。L-シスチンの適正投与水準はドライフード当たり2.4%以下と考えられたが,この問題に関しては今後さらに検討の余地がある。L-シスチンの投与がシスチン尿症または同尿石症を増加させるとの証拠はなかったものの,二塩基性アミノ酸- 特にシスチン, リジン,アルギニンーの尿中排泄に関するネコの特異性が示唆された。
- 著者
- 佐藤 洋希
- 出版者
- 九州教育学会
- 雑誌
- 九州教育学会研究紀要 (ISSN:02870622)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.113-120, 2019 (Released:2020-10-14)
- 著者
- 百村 伸一
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.78-83, 2007-01-15 (Released:2013-05-24)
- 参考文献数
- 4
日本人のための急性心不全治療ガイドラインとしては,日本循環器学会が2000年に発表した急性重症心不全治療ガイドラインがある.それから5年以上経過するなかで,新しい臨床成績を反映させるべく全面的な改訂作業が進められ,「急性心不全ガイドライン」がまとめられた.新たなガイドラインは,重症心不全に限定せず全ての急性心不全を対象に,各種診断・治療法を臨床成績のエビデンスに基づきクラス分類して,科学的根拠を明示した.最も大きな特徴は,治療戦略のなかに長期予後を考慮し,心臓および他の重要臓器の保護の概念を位置付けたことである.ナトリウム利尿ペプチドに関しては,ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(hANP:カルペリチド)の血管拡張作用以外の臓器保護作用,交感神経抑制作用などが評価され,より積極的な位置付けがなされている.本ガイドラインが臨床の場で貢献することを期待する.
1 0 0 0 琵琶湖における侵入種と在来種の生態的相互作用
本研究では、琵琶湖に侵入した生物としてヌマチチブ、ブルーギルをとりあげ、琵琶湖における生態について水中観察を行った。ヌマチチブは、湖底の石礫上に成育する糸状藻類を主要な餌として利用していた。糸状藻類は、琵琶湖沿岸部ではここ10数年ほどの間に急増したものであり、現在、ヌマチチブ以外はこれを餌資源として利用していなかった。このことから、餌資源の分割様式の点では、ヌマチチブは最近に生じた新たな餌資源を利用しており、琵琶湖の在来種と競合することなく、その生態的地位を確立したものと考えられた。またブルーギルでは、琵琶湖に生息するものの中に、体型や微生息場所が異なるものが混在しており、それぞれに摂食様式や繁殖様式も異なると予想されるため、さらに詳しく調査をすすめる必要性が生じた。一方、琵琶湖在来の魚類では、ほぼすべての種が沿岸部で産卵を行い、稚仔魚期も産卵場所付近で生活することがわかっている。そこで在来種のコイ・フナ類に焦点をあて、その産卵様式の詳細について調査を行った。その結果、コイ・フナ類では、繁殖をひかえた成魚は数日先の降雨を予想し、降雨による沿岸部への栄養塩の流入によって引き起こされる動物プランクトンの増大を見込んで産卵していることが推察された。また、そこでは外来種のブルーギルやオオクチバスの稚仔魚はほとんどみられなかった。このことは、在来種と外来種では、初期生活史における餌、空間資源の利用様式に違いがあることを示唆している。このように、ヌマチチブやブルーギルなどの侵入種と琵琶湖の在来種の間では、餌資源などの利用様式に違いが見られ、このことによって侵入種がすでに多様な群集を形成していたと言われてきた琵琶湖に定着できた要因の一つであると考えられる。
1 0 0 0 OA 小児の安全性に配慮したミニタブレット開発への取り組み
- 著者
- 寺田 浩人
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.8, pp.777, 2021 (Released:2021-08-01)
- 参考文献数
- 2
2000年に合意された医薬品規制調和国際会議のICH-E11ガイドラインでは,「小児への使用が想定される医薬品については,小児集団における使用経験の情報の集積を図ることが急務であり,成人適応の開発と並行して小児適応の開発を行うことが重要である.」と記述されている.しかしながら,現在流通している医薬品のうち小児に対する用法・用量および安全性が確立されている医薬品は限られている.このことは,小児製剤開発が臨床試験だけではなく,小児に対する添加剤の安全性にも特段の配慮を必要とすることが一因であり,これらを考慮した製剤設計を行うことが課題である.ミニタブレットは,小児製剤で重要な用量調整を錠数で管理でき,用量調整に天秤等が必要な顆粒剤と比較して利便性が高いと考えられる.また,その小ささから通常の錠剤と比較して服用性の面でも有用である.本稿では,Freerksらの安全性に配慮した小児用ミニタブレットの製剤設計に関する研究報告を紹介する.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) 「小児集団における医薬品の臨床試験に関するガイダンスについて」,PMDAホームページ.2) Freerks L. et al., Eur. J. Pharm. Biopharm., 156, 11-19(2020).
- 著者
- 群馬町教育委員会編集
- 出版者
- 群馬町教育委員会
- 巻号頁・発行日
- 2000
- 著者
- 豊田長敦 [著] . . 小野高潔 [著] . . 大田覃 [著] . 清水濱臣 [著] . . 松平樂翁 [著]
- 出版者
- 吉川弘文館
- 巻号頁・発行日
- 1927
1 0 0 0 人物埴輪の文化史的研究
1 0 0 0 鵜飼 : 甲斐の川漁と鵜飼をめぐる伝説 : シンボル展
1 0 0 0 IR 器財埴輪の編年と古墳祭祀
- 著者
- 高橋 克寿
- 出版者
- 史学研究会 (京都大学文学部内)
- 雑誌
- 史林 (ISSN:03869369)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.p259-294, 1988-03
個人情報保護のため削除部分あり形象埴輪研究のもっとも重要な意義は古墳祭祀の実態とその変遷を明らかにすることにある。本稿はその対象として古墳の墳頂に置かれる四種の代表的な器財埴輪を選び、その変化の中に古墳祭祀の変容を見ようとしたものである。基礎作業としてまず各器財埴輪にたいして型式分類を試み、靱形埴輪を二類四型式、盾形埴輪を二類二型式、甲冑形埴輪を三類四型式、蓋形埴輪を三類四型式にわけ、それぞれの型式変化を明らかにした。次に器財埴輪の各型式の古墳におけるセット関係と古墳の年代から器財埴輪の変遷を五期にわけて論じ、その消長を見た。その結果、器財埴輪は本来被葬者の眠る墳頂を厳重に隔絶し守護することを目的に鰭付円筒埴輪との強い関連のもとで四世紀後半に誕生したことが明らかになった。そして、製作技法の能率化、簡略化を進めながら発展した器財埴輪が五世紀後半から顕著に見せる衰退は、横穴式石室の導入などにかかわる新しい葬送観念の浸透によって引き起こされたことが考えられた。Haniwa figures are significant for illustrating the rites performed on tumuluses and for reflecting the concept of funerals of the Kofun 古墳 era. I have chosen four kinds of typical Haniwa figures called Kizai-Haniwa mainly of the Kinai 畿内 district and have tried to make a typological classification and a chronology for each one. Then I examined several instances of their assemblages on tumuluses and set up a five-stage chronology. Consequently, it was revealed that Kizai-Haniwa figures developed in the last half of the 4th century A. D. in order to defend the dead chieftain inside who was buried on top of the tumulus, with a special relation to Haniwa cylinders that had fins 鰭付円筒埴輪. In the 5th century Kizai-Haniwa figures prevailed over most of Japan, but their wane from the last half of the century was brought about by a new concept of funerals that came from the continent.
1 0 0 0 文化財調査報告書
- 出版者
- 前橋市教育委員会事務局社会教育課
- 巻号頁・発行日
- 1971
1 0 0 0 野見宿禰の埴輪創出伝承
- 著者
- 寺川 眞知夫
- 出版者
- 奈良県万葉文化振興財団万葉古代学研究所
- 雑誌
- 万葉古代学研究所年報
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.1-14, 2009-03
1 0 0 0 OA 小河・刈谷城主としての水野信近
- 著者
- 松島 周一
- 出版者
- 愛知教育大学歴史学会
- 雑誌
- 歴史研究 (ISSN:02879948)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.17-36, 2020-03-31
1 0 0 0 OA 自閉症児における視線回避と共同注意の障害及び心の理論の構築について
- 著者
- 橋本 由里 Yuri HASHIMOTO
- 雑誌
- 島根県立大学出雲キャンパス紀要 (ISSN:2187199X)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.59-69, 2016-12-22
自閉症の定義に変遷があるために明確とは言えないものの、自閉症と診断される児童・生徒数が増加傾向にあることは否定できない。自閉症に特有な症状の一つに視線回避がある。自閉症児では、定型発達児と比較して視線回避が頻繁に見られ、共同注意に障害が認められる。このため、自閉症児は他社とのコミュニケーションに支障をきたし、結果的に他者と社会的にかかわることが難しくなっている。本稿ではとくに心の理論に焦点をあて、自閉症に特徴的な視線回避と、共同注意の障害及びそれらの症状を改善するトレーニングについて概説する。
1 0 0 0 OA 木炭・木酢液の利用 その現状とこれから
- 著者
- 谷田貝 光克
- 出版者
- 木質炭化学会
- 雑誌
- 木質炭化学会誌 (ISSN:13493418)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.43-52, 2012 (Released:2019-01-10)
1 0 0 0 OA ドゥルーズにおける「記号」概念について―『シネマ 2』第2章の精読―
- 著者
- 築地 正明
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.102, pp.115-136, 2019-07-25 (Released:2019-11-19)
- 参考文献数
- 39
本稿では、ジル・ドゥルーズ著『シネマ 1』、『シネマ 2』における「記号(signe)」概念に焦点を当てた考察を行う。それは、この概念が『シネマ』全二巻における本質的な要素をなしており、ドゥルーズによる「記号」概念の理解と、『シネマ』全体の理論に対する包括的視点を得ることとは、分けて考えることができないと思われるからである。またそれに加えて、ドゥルーズの提起した「記号」の理論は、古典的な映画研究にとどまらず、広く映像理論領域においても、今なお普遍的な価値を有していると考えられる。すでにこれまでにも、『シネマ』の批判的な分析の試みは、多くの理論家によってなされてはいる(1)。しかしながら、特にこの「記号」という点に関しては、必ずしも包括的な論述はなされてこなかったように思われる(2)。それゆえ本稿では、ドゥルーズが、アメリカの論理学者 C.S. パースの記号論、およびフランスの哲学者アンリ・ベルクソンのイマージュ論から引き出し、発展させた自身の新たな記号論と、クリスチャン・メッツの提起した言語学を基礎とする記号学とを対決させている、『シネマ 2』第 2 章の精読を通じて、この概念の重要性とその独特の性質を明らかにすることを試みたい。