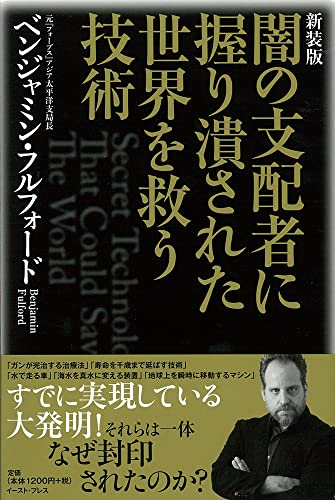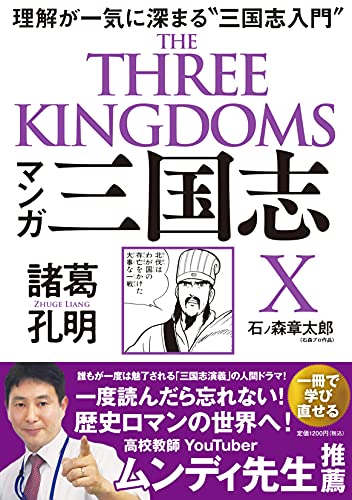1 0 0 0 OA FSW 技術と自動車への適用例
- 著者
- 大石 郁 藤井 英俊
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- まてりあ (ISSN:13402625)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.12, pp.603-607, 2014 (Released:2014-12-01)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 6 9
1 0 0 0 OA 航空機製造へのFSW(摩擦攪拌接合)適用の現状と問題点
- 著者
- 柿本 晴彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本塑性加工学会
- 雑誌
- ぷらすとす (ISSN:24338826)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.26, pp.94-98, 2020 (Released:2020-02-25)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA 病害防除における抵抗性誘導剤の可能性
- 著者
- 沢田 治子
- 出版者
- Pesticide Science Society of Japan
- 雑誌
- Journal of Pesticide Science (ISSN:1348589X)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.4, pp.326-329, 2009-11-25 (Released:2013-12-14)
- 被引用文献数
- 2 3
1 0 0 0 OA 21番目のアミノ酸を取り込むための分子機構
- 著者
- 尾瀬 農之 Rasubala Linda 吉澤 聡子 Fourmy Dominique 神田 大輔 前仲 勝実
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.102-105, 2006 (Released:2006-03-25)
- 参考文献数
- 13
1 0 0 0 OA クラストが形成された土壌の表層の性質
- 著者
- 山田 宣良
- 出版者
- 社団法人 農業農村工学会
- 雑誌
- 農業土木学会論文集 (ISSN:03872335)
- 巻号頁・発行日
- vol.1991, no.152, pp.9-13,a1, 1991-04-25 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 10
4種類の土壌を用いた土性別検討および4種類の土壌管理別にみた土地利用別検討をもとにして, クラストが形成された土壌の表層の性質を比較した。その結果, 次の3種類の形態が認められた。(1)沈澱クラスト:最表層とその下層との間の団粒率, 比表面積とK含有量に差がみられる。(2)衝潅クラスト:団粒率とK含有量に差がみられる。(3)化学クラスト:K含有量のみに差がみられる。また, 土壌侵食因子の中では, 分散率がクラストと高い相関を示した。したがって, 土壌の最表層とその下層の間の団粒率, 比表面積, K含有量に, 分散率を対比して, クラストの形態を知ることができることがわかった。
1 0 0 0 OA <研究ノート>台湾の国交樹立外交の軌跡
- 著者
- 三宅 康之 Yasuyuki Miyake
- 雑誌
- 国際学研究 = Journal of international studies (ISSN:21868360)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.97-108, 2021-03-30
1 0 0 0 OA 「加治木のくも合戦」の存続要因——担い手に注目して——
- 著者
- 岩月 健吾
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集 2021年度日本地理学会秋季学術大会
- 巻号頁・発行日
- pp.84, 2021 (Released:2021-09-27)
1.研究の背景および目的 かつて日本では,野外で採集したクモ同士を闘わせて勝敗を決める遊び(クモ相撲)が,沿岸の地域を中心に全国的に見られた(図1).クモ相撲は,第二次世界大戦後の経済成長に伴う社会・自然環境の変化を背景に多くの地域で消滅してしまった(川名・斎藤 1985).しかし,関東・近畿・四国・九州の一部地域では,クモ相撲が行事化し,組織的な運営のもとで現在も存続している. 本研究の目的は,現代におけるクモ相撲行事の存続要因を,行事の担い手(行事の運営者・参加者)に注目して明らかにすることである.民俗学における従来のクモ相撲研究では,遊びの分布やクモに関する方言,使用するクモの種類,遊びの形式に注目して,その地域差や類似性等が論じられてきた.しかし,行事化したクモ相撲を対象に,その存続の仕組みを明らかにする試みは少ない. 2.調査の対象および方法 本研究では,鹿児島県姶良市加治木町の年中行事「姶良市加治木町くも合戦大会」を事例として取り上げる(図2).地元で「加治木のくも合戦」の呼称で親しまれる本大会は,1996年に文化庁により,「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に選択された.本研究では,「姶良市加治木町くも合戦保存会」役員や姶良市役所加治木総合支所加治木地域振興課職員,大会参加者を対象に,聞き取り調査を実施した.調査は主に,2015年,2018年,2019年の大会開催日(6月第3日曜日)に実施した. 3.結果 2011年〜2019年の大会参加者は,105人〜153人で推移している.全体に占める姶良市内からの参加者の割合は,2014年の45.7 %を除くと,53.6 %〜64.5 %で推移しており,本大会が地元住民によって支えられていることがわかる.また,県外からの参加者も,大会を活気づけ,試合を迫力あるものにする重要な存在である. 本大会の参加者の特徴として,他の参加者と家族・親族の関係にある者が多いことが挙げられる.例えば,2019年の参加者のうち,他の参加者と家族・親族の関係にある者は全体の64.5 %を占めている.何年も続けて大会に参加する者も多く,2019年の参加者のうち,2018年の大会にも参加した者の割合は66.1 %であった.このうち69.5 %は家族・親族の関係にあり,家族・親族での参加が大会参加者数の維持に大きく貢献しているといえる.こうした集団は,交際・結婚を機に新たに誕生したり,人数を拡大したりする.また,分裂してライバル関係になることもある. クモの採集場所は他人には秘密にされるが,家族・親族内では共有され,共に採集・飼育を行うことで知識・技術が継承される.子どもも幼い頃からクモに触れ,一担い手へと成長していく.しかし,中学生になると忙しくなり,継続できなくなるという課題がある. 本発表では,大会参加者の他に,運営者についても言及する. 文献川名 興・斎藤慎一郎 1985.『クモの合戦—虫の民俗誌』未来社.
1 0 0 0 OA 破裂性腹部大動脈瘤の治療法と合併症対策
- 著者
- 伊東 啓行
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本血管外科学会
- 雑誌
- 日本血管外科学会雑誌 (ISSN:09186778)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.127-132, 2019-04-10 (Released:2019-04-09)
- 参考文献数
- 23
腹部大動脈瘤破裂(ruptured abdominal aortic aneurysm, RAAA)に対する救命手段は緊急手術のみであるが,今日その方法としては人工血管置換術(open surgical repair, OSR)に加えて,ステントグラフト内挿術(endovascular aneurysm repair, EVAR)も有力な選択肢となっている.RAAAの治療に当たる血管外科医はOSR, EVARのいずれにも精通しておく必要がある.ここではRAAA治療の現状に加えて,RAAA術後合併症として重要な腹部コンパートメント症候群について述べる.
1 0 0 0 OA カブトムシの体のつくりと節足動物の体節構造や進化についての理解を深める授業の開発
- 著者
- 山野井 貴浩 横内 健太
- 出版者
- 一般社団法人 日本理科教育学会
- 雑誌
- 理科教育学研究 (ISSN:13452614)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.485-495, 2023-03-31 (Released:2023-03-31)
- 参考文献数
- 32
カブトムシは人気のある昆虫であるが,児童,教員志望学生,小学校教員の多くはその体のつくりを正しく理解できていないことが報告されている。そこで,本研究は昆虫の体節構造の進化を扱うことで,カブトムシの体のつくりを理解させる授業を開発した。また,本授業の副次的な効果として,節足動物の体のつくりや進化についての理解も深められることを期待した。中学生対象の授業実践の結果,授業後にはカブトムシの体のつくりに関して適切なイラストを選択する生徒の割合が有意に増加した。また,節足動物の体のつくりの特徴に関して,授業を通して「1つの節から1対のあしが生えていること」や「(進化の過程で)体節が融合したものがいること」の理解が深まったことが示唆された。一方で,授業後には「頭・胸・腹に分かれた体」や「胸からあし」などの昆虫の特徴を,節足動物の特徴として記述する生徒が増加した。地球上の既知種の約半分を占める節足動物を題材とした進化や分類に関する教材の開発が今後も期待される。
- 著者
- 深澤 泰弘
- 出版者
- 公益財団法人 損害保険事業総合研究所
- 雑誌
- 損害保険研究 (ISSN:02876337)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.4, pp.249-265, 2012-02-25 (Released:2020-06-21)
- 参考文献数
- 25
1 0 0 0 実験考古学ワークショップ : 東北知のフォーラム2018
- 著者
- 東北大学大学院文学研究科考古学研究室企画編集
- 出版者
- 東北大学研究推進・支援機構知の創出センター
- 巻号頁・発行日
- 2019
1 0 0 0 シンポジウムHunting : 狩猟相解明のためのアプローチ
- 著者
- 堤隆編
- 出版者
- 八ケ岳旧石器研究グループ
- 巻号頁・発行日
- 2019
- 著者
- ベンジャミン・フルフォード著
- 出版者
- イースト・プレス
- 巻号頁・発行日
- 2013
1 0 0 0 メキシコ・ペルー神話と傳説
1 0 0 0 京都ラテンアメリカ研究所紀要
- 著者
- 京都外国語大学 [編]
- 出版者
- 京都外国語大学京都ラテンメリカ研究所
- 巻号頁・発行日
- 2001
1 0 0 0 京都外国語大学ラテンアメリカ研究所紀要
- 出版者
- 京都外国語大学ラテンアメリカ研究所
- 巻号頁・発行日
- 2016
1 0 0 0 京都大學文學部研究紀要
- 著者
- 京都大學文學部 [編]
- 出版者
- 京都大學文學部
- 巻号頁・発行日
- 1952
1 0 0 0 OA 群集生態学の最近の動向について : 平衡と非平衡群集
- 著者
- 武田 博清
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.41-53, 1986-04-30 (Released:2017-05-24)
The balance of nature has been a background concept in community ecology. In contrast to the concept, the variability of biological populations has been appreciated in mature, such as in outbreak and extinction of species. The two concepts have been transformed into density dependent and density independant regulation in population dynamics and then into equilibrium and non-equilibrium community theories. The competition-equilibrium community theory has been advanced in the empirical and theoretical studies of community and has explained the community organization by the niche theory. The non-equilibrium community theory has argued the importance of non-equilibrium conditions of populations in nature and the reconsideration of community organization from the individualistic or auto-ecological studies of populations constituting communities. The two theroies represent the opposite ends in the continuum of the community patterns in the nature. In the recent 20 years, community ecology has advanced in the diversity studies, competitive-equiliblium and non-equilibrium community theories and now is entering a new stage over these past community studies.
1 0 0 0 マンガ三国志X諸葛孔明 : 理解が一気に深まる"三国志入門"
- 著者
- 石津 智大 大黒 達也
- 出版者
- 関西大学
- 雑誌
- 学術変革領域研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2021-08-23
人間は、快不快を超え集団に資する行動に自分を動機づけられる利他性や共感性を備えている。負の感情価と美的快の混合された美学的体験には利他性を促進させる効果があり、近年人文学的議論だけでなく認知科学や経験美学においても注目されている。本研究では、このような美的体験の構成情動を明らかにし、人間らしい利他自己犠牲の意思決定へ与える影響について、行動特性と脳内機構を情動脳情報学の視座から解明する。