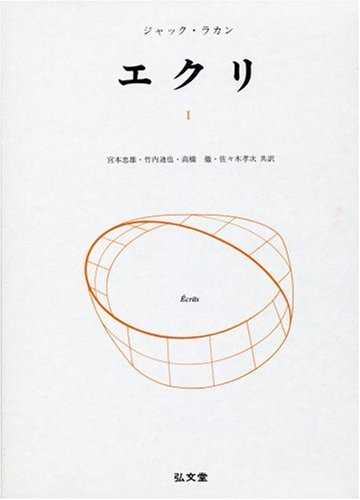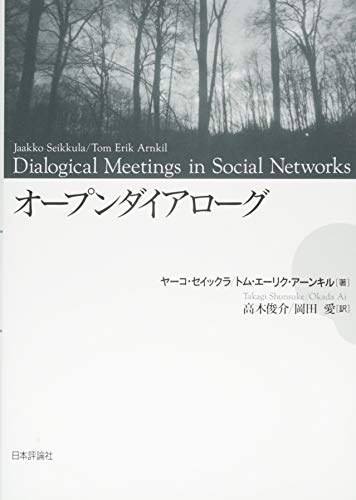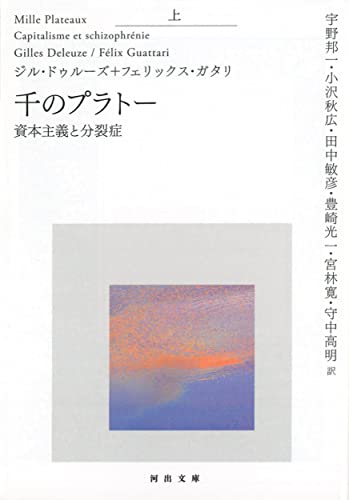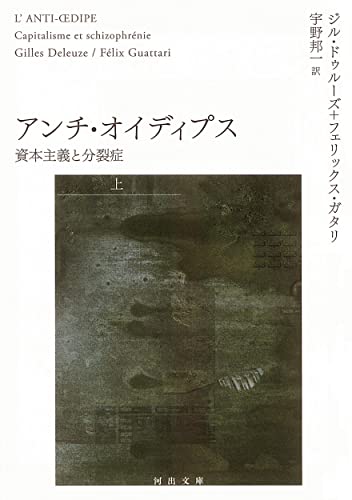1 0 0 0 エクリ
- 著者
- ジャック・ラカン [著] 宮本忠雄 [ほか] 共訳
- 出版者
- 弘文堂
- 巻号頁・発行日
- 1972
1 0 0 0 オープンダイアローグ
- 著者
- ヤーコ・セイックラ トム・エーリク・アーンキル著 高木俊介 岡田愛訳
- 出版者
- 日本評論社
- 巻号頁・発行日
- 2016
1 0 0 0 千のプラトー : 資本主義と分裂症
- 著者
- ジル・ドゥルーズ フェリックス・ガタリ著 宇野邦一 [ほか] 訳
- 出版者
- 河出書房新社
- 巻号頁・発行日
- 2010
1 0 0 0 アンチ・オイディプス : 資本主義と分裂症
- 著者
- ジル・ドゥルーズ フェリックス・ガタリ著 宇野邦一訳
- 出版者
- 河出書房新社
- 巻号頁・発行日
- 2006
1 0 0 0 天才論
- 著者
- チェザレ・ロンブロオゾオ著 辻潤訳
- 出版者
- 改造社
- 巻号頁・発行日
- 1930
1 0 0 0 OA 牛頭禪の思想
- 著者
- 柳田 聖山
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.16-23, 1967-12-25 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA 受動喫煙を防止するための効果的な呼吸用保護具のフィルタの検討
- 著者
- 保利 一 石田尾 徹 樋上 光雄 山本 忍
- 出版者
- 独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
- 雑誌
- 労働安全衛生研究 (ISSN:18826822)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.2, pp.97-107, 2021-09-30 (Released:2021-09-30)
- 参考文献数
- 13
清掃作業のため喫煙室等に入って働く作業者や喫煙可能な飲食店等で働く作業者の受動喫煙を防止する方法としては,作業環境管理上の対策が困難であることから,呼吸用保護具の活用が有効と考えられる.しかしながら,現在使用されている呼吸用保護具がたばこ煙に有効であるか否かは検討されていない.そこで,防じんマスク,防毒マスクの吸収缶および新たに開発した極性と非極性の性質を有する両親媒性吸着材のたばこ煙に対する捕集特性を調べた.その結果,粉じんについては,現在の区分RL2,DS2以上の防じんマスク用フィルタであれば,98%以上捕集できることが認められた.ガス状物質については,防じんマスクではほとんど捕集できないが,活性炭素繊維入り防じんマスクは若干ではあるが捕集することが認められた.一方,有機ガス用防毒マスク吸収缶は有機物質をかなり捕集できること,また活性炭とセピオライトを7:3で配合した両親媒性吸着材およびホルムアルデヒド用吸収缶では,アルデヒド類やアセトンをほぼ捕集できることが示された.また,活性炭入り防じんマスクは低沸点の揮発性有機化合物(VOC)はほとんど除去できなかったが,ベンゾ[a]ピレンやニコチンは98%以上捕集できることが示された.ただし,臭気については,防じんマスク用フィルタはほとんど効果がないこと,また,防毒マスク吸収缶でも50%程度以下しか除去することができないことがわかった.
1 0 0 0 OA ウィトゲンシュタインはメタ言語を認めずに使用していたのか?
- 著者
- 中村 直行
- 出版者
- 金沢大学大学院社会環境科学研究科
- 雑誌
- 社会環境研究 (ISSN:13424416)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.89-96, 2005-03-01
1 0 0 0 OA 画僧月僊の同時代評価についての文献的検討
- 著者
- 山口 泰弘 YAMAGUCHI Yasuhiro
- 出版者
- 三重大学教育学部
- 雑誌
- 三重大学教育学部研究紀要. 人文・社会科学 (ISSN:03899241)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.97-106, 2002-03-29
1 0 0 0 OA 馬祖禪の諸問題
- 著者
- 柳田 聖山
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.1, pp.33-41, 1968-12-25 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA 戦前期日本の買売春に関する社会史的研究
- 著者
- 羽田野 慶子
- 巻号頁・発行日
- 2009
課題番号:18710225
1 0 0 0 大田区の文化財
- 著者
- 東京都大田区教育委員会社会教育部社会教育課 編
- 出版者
- 大田区教育委員会
- 巻号頁・発行日
- vol.第26集 (地図でみる大田区 3), 1990
1 0 0 0 OA 金属の着火と燃焼の特性
- 著者
- 湯浅 三郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本燃焼学会
- 雑誌
- 日本燃焼学会誌 (ISSN:13471864)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.133, pp.152-163, 2003 (Released:2019-10-24)
- 参考文献数
- 57
- 被引用文献数
- 3
- 著者
- 北 明美
- 出版者
- 社会政策学会
- 雑誌
- 社会政策学会誌 (ISSN:24331384)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.161-175, 2008-03-31 (Released:2018-04-01)
In the 1960s, the Japanese government and bureaucracy sought to introduce a child benefit program funded by both employees' and employers' contributions, while rejecting an alternate plan to fund children's benefits from general revenues. The plan to introduce employees' contributions, which was blocked by strong opposition from labor, has now been redesigned as a plan to introduce "social insurance for dependent children." This development shows that the importance of non-means-tested and noncontributory cash benefits has been often ignored in discussions on social policy in Japan. Bunji KONDO, an influential researcher of social policy, classified such noncontributory cash benefits in a category close to public assistance and argued that a form of social insurance based on employees' contributions as well as those of employers that benefited workers most. Furthermore, he considered that even child benefits were similar to such forms of insurance, before World War II and in the postwar days up to the 1960's. I would like to point that KONDO's discussions are among the backdrops of the recent odd proposal to replace the current child benefit with "social insurance for dependent children" for which there is no precedent elsewhere in the world. On the other hand, the labor movement in the 1960s did not launch strong campaigns for child benefit programs based only on general revenues. It is not only because it seemed impossible then, but also because labor tended to support benefits based on employers' unilateral contributions. At that time, benefits based on such contributions were regarded as more advantageous for workers, as they channeled portions of profits into worker incomes. However, in other countries, it has been recognized that child benefit programs based on employer contributions have an effect only on horizontal income re-distribution, while child benefit programs funded only by general revenues affect both vertical and horizontal income re-distribution. It is also argued that the former tends to function more strongly to lower wages than the latter. I argue that the Japanese labor movement should reconsider its preference for child benefit programs based on employer contributions, recognizing their gender-biased character and vulnerability to cost-cutting pressures from employers and big business.
1 0 0 0 OA 聴皮質の情報処理(<小特集>動物実験から学ぶ聴覚システム)
- 著者
- 高橋 宏知
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.3, pp.119-124, 2011-03-01 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 27
1 0 0 0 OA 没入型仮想空間における奥行き知覚に関する研究
- 著者
- 小西 陽平 橋本 直己 中嶋 正之
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会技術報告 25.32 (ISSN:13426893)
- 巻号頁・発行日
- pp.21-26, 2001-04-27 (Released:2017-06-23)
本研究では, CAVEのようなユーザの視点移動に関する自由度の高い没入型ディスプレイを想定し, 観察者がスクリーンを斜めから見る際の奥行き知覚誤差について計測実験を行い, 没入型仮想空間における奥行き知覚特性の分析を行った.その結果, 奥行き知覚誤差には人間の視覚構造やその特性から決まる傾向が存在することを明らかにした.更に, その奥行き知覚特性の分析に基づき, 奥行き知覚誤差を補正する方法を検討した結果, 本研究で提案する補正方法を用いることで, 没入型仮想空間における奥行き知覚誤差を軽減することができた.また, 計測データの存在していない観察点における奥行き知覚誤差を推定することにより, 予め奥行き知覚誤差を補正した没入型仮想空間を構築することができた.
1 0 0 0 OA ポストコロナの教育格差研究:世界的課題の解明とオンラインでの調査・実験手法の革新
- 著者
- 赤林 英夫 敷島 千鶴 島田 夏美 竹ノ下 弘久 加藤 承彦 井深 陽子 稲葉 昭英 野崎 華世 川本 哲也 中村 亮介 直井 道生 佐野 晋平 田村 輝之 栗野 盛光
- 出版者
- 慶應義塾大学
- 雑誌
- 基盤研究(S)
- 巻号頁・発行日
- 2021-07-05
新型コロナパンデミックは、子供の教育格差研究に対し、取り組むべき課題と研究手法との双方に、変革の必要性を迫っている。社会のオンライン化に伴い、家庭環境が子供に与える影響が強まることが懸念されている。また、教育格差拡大を防ぐために、世界各国で、新たな政策的対応の必要性が議論されている。そこで、本研究では、全国の子供を対象とし、オンラインにより、ポストコロナの新たな課題に対応した調査や実験による研究手法を考案する。それらを通じ、コロナ禍が子供の学力や日常生活に及ぼした影響を厳密に分析し、国際比較も行うことで、コロナ後の研究と政策のあり方を提示する。
1 0 0 0 宇佐美勝夫氏之追憶録
- 著者
- 故宇佐美勝夫氏記念会 著
- 出版者
- 故宇佐美勝夫氏記念会
- 巻号頁・発行日
- 1943