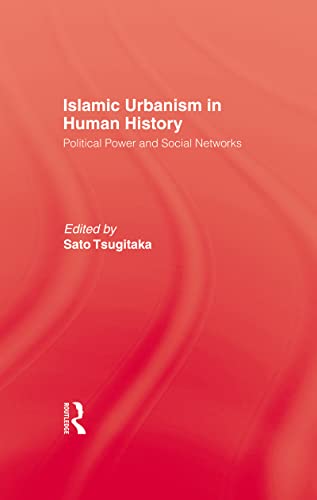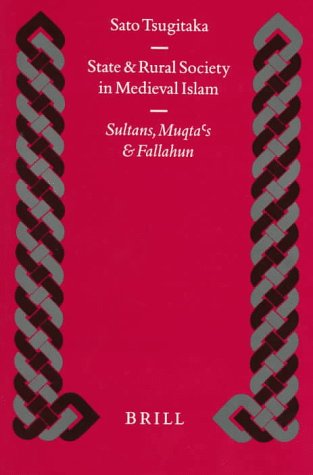1 0 0 0 OA 低次元量子構造作製技術とデバイス応用の現状と展望 —量子ドットを中心にして—
- 著者
- 荒川 泰彦 塚本 史郎
- 出版者
- 公益社団法人 応用物理学会
- 雑誌
- 応用物理 (ISSN:03698009)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.3, pp.293-306, 2005-03-10 (Released:2019-09-27)
- 参考文献数
- 122
- 被引用文献数
- 3
1982年に提案された量子ドットは,自己形成量子ドットを中心とする半導体ナノ技術により,レーザーや単電子素子など現実に動作するナノ素子の基本構造として発展してきている.本総合報告では,量子ドットを中心とした低次元半導体構造について,フォトニック素子への展開を念頭に置きながら,結晶成長・プロセス技術,光・電子物性,素子応用について論じる.まず,半導体ナノ構造の歴史的発展を振り返った後,自己形成量子ドットの展開について議論する.さらに,自己形成手法以外のナノ結晶成長・プロセス技術について概観した後,量子ドットの光・電子物性物理の進展状況を論じる.そして,さらに,量子ドットレーザーを中心にして,ナノフォトニック素子についてその展開を紹介するとともに,量子暗号通信に不可欠な単一光子発生素子について量子ドット応用の立場から述べる.
1 0 0 0 OA 道元とベーメの「自己」について
- 著者
- 笠井 貞
- 出版者
- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.713-716, 1971-03-31 (Released:2010-03-09)
1 0 0 0 OA 差別の規範理論――差別の悪の根拠に関する倫理学的研究
差別概念の哲学的な分析論の主要な議論を検討した。①被差別者に与える害や不利益に注目する帰結主義的な立場としての不利益説、②差別者の動機や悪意に注目する悪意説、③帰結にも意図にも還元できない「意味」があるという意味説を検討した。現在の議論では不利益説が主流である。不利益説は差別がもたらす害悪の大きさに関する直観にも適合しており一定の説得力がある。本研究では、しかしこの立場では十分に差別の悪質さを分析することはできないことを明らかにし、意味説に一定の利点があることを確認した。差別の悪質さを評価するための規範的な根拠の解明が今後の課題である。
1 0 0 0 OA 中枢セロトニンはグルコースに対する末梢インスリン分泌反応を修飾する
- 著者
- 黒瀬 陽平 若田 雄吾 坂下 幸 寺島 福秋
- 出版者
- 公益社団法人 日本畜産学会
- 雑誌
- 日本畜産学会報 (ISSN:1346907X)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.7, pp.653-658, 1998-07-25 (Released:2008-03-10)
- 参考文献数
- 16
セロトニンは,脳において神経伝達物質として存在する.中枢セロトニンは,内分泌系に影響することが示唆されている.本研究の目的は,中枢セロトニン神経の活性とグルコースに対する末梢インズリン分泌反応との関係を明らかにすることである.実験動物としてWistar系雄ラット(体重351~400g)を使用した.セロトニン合成阻害薬P-クロロフェニルアラニン(pCPA,1mg)を脳内のセロトニン合成を阻害する目的で側脳室へ投与した、グルコースに対する末梢インスリン分泌反応を,グルコースクランプ法によって,pCPA投与群および生理食塩水投与群において比較検討した、グルコース注入率(GIR)および血糖値は両者間で差がないにもかかわらず,血清インスリン濃度平均増加量(MSII)は,pCPA投与群の方が有意に低かった.グルコース注入に対するインスリン分泌の指標値(MPII/GIR)は,pCPA投与群の方が有意に低かった.本研究は,脳内のセロトニンの合成阻害による欠乏,すなわちセロトーン神経の不活化が,グルコースに対する末梢インスリン分泌反応を抑制することを明確に例証した.
- 著者
- edited by Sato Tsugitaka
- 出版者
- Distributed by Columbia University Press
- 巻号頁・発行日
- 1997
- 著者
- by Sato Tsugitaka
- 出版者
- E.J. Brill
- 巻号頁・発行日
- 1997
- 著者
- edited by Sato Tsugitaka
- 出版者
- RoutledgeCurzon
- 巻号頁・発行日
- 2004
1 0 0 0 アラブ中世社会史研究
1 0 0 0 OA 追悼 佐藤次高先生
- 著者
- 三浦 徹
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.6, pp.1154-1156, 2011-06-20 (Released:2017-12-01)
1 0 0 0 OA (書評)佐藤次高著「Sato Tsugitaka, State & Rural Society in Medieval Islam: Sultans, Muqta's & Fallahun」
- 著者
- 三浦 徹
- 出版者
- 法制史学会
- 雑誌
- 法制史研究 (ISSN:04412508)
- 巻号頁・発行日
- vol.1998, no.48, pp.269-274, 1999-03-30 (Released:2009-11-16)
1 0 0 0 OA 日本の霊長類学小史:野生ニホンザル研究を中心に
- 著者
- 杉山 幸丸
- 出版者
- 一般社団法人 日本霊長類学会
- 雑誌
- 霊長類研究 (ISSN:09124047)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.41-55, 2020 (Released:2020-12-23)
- 参考文献数
- 135
- 被引用文献数
- 1 1
Modern primatology began in 1952-3 through artificial feeding of Japanese macaques at Koshima and Takasakiyama. Artificial feeding allowed short-distance observation, individual recognition and long-term observation. These new methods applied to wild monkeys made possible new findings, such as life-time kinship bonds, social organization, cultural behaviors, etc., which changed anthropology, biology, psychology and also other social sciences.During the 1st stage of the studies led by K Imanishi and J Itani, researchers focused their efforts not on biology but on sociology. Itani declared that Japanese primate studies do not reflect natural science. On the other hand, some other researchers carried out ecological studies of monkeys and proceeded on to socioecology. Itani attributed the dominance relations among individuals to the social order or hierarchy, whereas other researchers did so to competition over resources to increase reproductive success.In 1956 and in 1962, respectively, the Japan Monkey Centre and the Kyoto University Primate Research Institute were established. JMC contributed as the first organization of primatology in Japan, and KUPRI added to a confluence of field and experimental primatology. DNA fingerprinting to analyze the relatedness of individuals accelerated the unification of field and laboratory studies.After 1970, agricultural damage caused by wild monkeys exploded due to deforestation and the presence of unguarded crops. Researchers had to work to prevent such monkey activity in the field. They were also forced to cull this endemic primate species. As a result, the field of primatology had to expand in cognitive science, physiology, brain science and genetics as well as conservation activity.
1 0 0 0 確率論における組合せ論・代数幾何学の応用とその周辺
数学の各分野において近年国際的発展のはなはだしい研究を見る組合せ論的な扱いを主として、我が数学教室においては、代表者白尾は、マルコフ過程の從来の解析的思考を組合せ論的な立場から見直すべく出来るだけ夛くの知識と概念を導入して来年度への研究の活力とした。分担者岩堀は、組合せ論properな未解決問題をプログラムし、計算実験をくりかえし、いくつかの部分的な成果および予想を得た。分担者本間,井上は或る種の非代数的曲面の変形の研究から新しい非代数的低次元複素夛様体を構成することを試みた。分担者小池は、昨年夏の日米合同セミナー"可換群と組合せ論"(バークレイ)において、Littlewood's公式に基き、(対称な有理関数のShier関数への展開公式)偶数次の対称群とワイル群の間の既約表現に関連する分解公式を得た。以上、いくつかの方面からの研究をひろく行ったが、いづれもコンピューターによる補助計算、実験計算等に夛くの時間をかけているので、結果を得られたものもあるが、未だその途上に研究をつづけているものが夛数あるのでこれらを来年度の課題としたい。
1 0 0 0 OA 光重合型感光性樹脂
- 著者
- 長谷川 正木
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.102-108, 1970-02-01 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1
最近,光化学反応に関する基礎面での活発な研究に伴い,それらを利用した数々の感光性樹脂が開発されている。光重合の一般的性質,種々の開始系についてカルボニル化合物を中心に述べ,さらに最近見出された結晶状態での一連の光重合反応を概説した。最後に光重合の応用例のいくつかについて述べた。光重合による硬化はかなり厚みのあるものまで行なえるので,レリーフ型の画像を形成させることも可能で,現在,印刷用凸版材料などとしての用途が注目されている。レリーフ型感光性樹脂の二三について,おもに組成,反応性の面
- 著者
- 金井塚 生世
- 出版者
- The Japanese Society for Medical Mycology
- 雑誌
- 日本医真菌学会雑誌 (ISSN:09164804)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.343-349, 1993-07-20 (Released:2010-11-18)
- 参考文献数
- 29
我々はCandida albicansのsecretory aspartate proteinase遺伝子の塩基配列中にpolymerase chain reaction (PCR) 法による増幅領域を設定し, 273bpの標的DNAがC. albicansで明らかに増幅されることを報告してきた. 今回はこの方法を用いて, 病理組織学的に内臓カンジダ症と診断された剖検材料20件のパラフィン包埋組織からDNAを抽出し, PCR法で診断可能か否かを検討した. その結果, 全例に273bpのDNA断片の増幅が観察され, サザンプロットハイブリダイゼーションでC. albicansのプローブDNAの結合が確認された. しかも, 対照としたカンジダ症でない内臓および脳のパラフィン包埋組織19件からは目的とするDNAの増幅は認められなかった. また, このPCR陽性のパラフィン包埋組織20件に抗カンジダ抗体を用いた免疫組織化学染色を行ったところ, 20件すべてに菌要素の多寡はあるものの陽性所見が認められ, 対照群ではすべて陰性であった. このように, PCR法を用いることにより, 内臓カンジダ症のパラフィン包埋組織からもC. albicansのDNAの検出が可能であることが明らかとなり, 本法はカンジダ症の新たな診断法となり得ることが示唆された.
1 0 0 0 久米島住民虐殺事件資料
1 0 0 0 OA 温度センサーによる脳機能調節
- 著者
- 柴崎 貢志
- 出版者
- 大学共同利用機関法人自然科学研究機構(共通施設)
- 雑誌
- 若手研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2008
これまで報告されてきたTRPV4の機能(皮膚における外界の温度受容体としての機能)とは全く異なり、海馬TRPV4は神経活動調節因子として機能している可能性が高いと考えられた。この可能性を検証するために、野生型とTRPV4欠損マウスの海馬より培養神経細胞を調整し、静止膜電位および発火特性を調べた。その結果、海馬神経細胞において、TRPV4は体温により活性化されており、その活性化を介して静止膜電位を脱分極させ、神経細胞が興奮しやすい土台環境を産み出していることが示唆された。さらに、個体レベルでのTRPV4の学習・記憶に果たす役割を調べ、TRPV4が脳内温度で恒常的に活性化されていることを証明した。
1 0 0 0 OA 自由飛行試験によるバドミントン用シャトルコックの非定常空力特性の解明
- 著者
- 板倉 嘉哉 赤井 貴洋 桑原 直弘 Itakura Yoshiya Akai Takahiro Kuwahara Naohiro
- 出版者
- 宇宙航空研究開発機構(JAXA)
- 雑誌
- 宇宙航空研究開発機構特別資料: 第48回流体力学講演会/第34回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム論文集 = JAXA Special Publication: Proceedings of the 48th Fluid Dynamics Conference / the 34th Aerospace Numerical Simulation Symposium (ISSN:1349113X)
- 巻号頁・発行日
- vol.JAXA-SP-16-007, pp.201-206, 2016-12-27
第48回流体力学講演会/第34回航空宇宙数値シミュレーション技術シンポジウム (2016年7月6日-8日. 金沢歌劇座), 金沢市, 石川