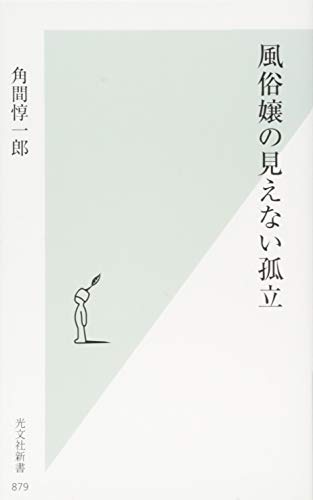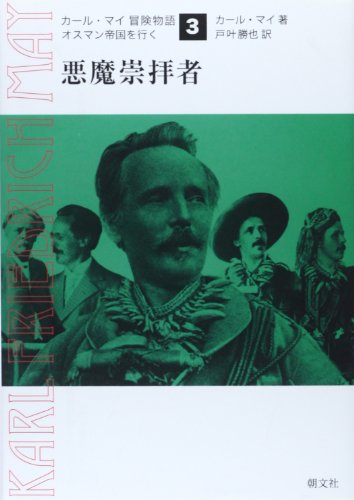1 0 0 0 OA プチスポット火山がもたらすケイ長質捕獲岩: 太平洋プレート最古部の海洋地殻物質断片
- 著者
- 三國 和音 平野 直人 秋澤 紀克 町田 嗣樹
- 雑誌
- 日本地質学会第129年学術大会
- 巻号頁・発行日
- 2022-08-08
1 0 0 0 OA 東京高等商業学校同窓会々員録
- 著者
- 児玉忠善 編
- 出版者
- 東京高等商業学校同窓会
- 巻号頁・発行日
- vol.明治44年11月改, 1911
- 著者
- 小笠原 宏 川方 裕則 石井 紘 中谷 正生 矢部 康男 飯尾 能久 南アフリカ金鉱山における半制御地震発生実験国際共同研究グループ
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震学会
- 雑誌
- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.Supplement, pp.563-573, 2009-07-31 (Released:2013-11-21)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 2 3
Experimental sites with potential earthquakes up to M ∼ 3 in coming few years are known beforehand from mining schedule at 2-3 km depths in South African gold mines, which allows us to deploy various borehole instruments including Ishii strainmeters, geophones, accelerometers and AE sensors. Deployment of these wide-dynamic-range and high-resolution observations in the past 15 years has led to many findings about the earthquake rupture and its preparation stage. High-sampling seismograms obtained at close proximity of M > 1 earthquakes have demonstrated similarities of these earthquakes to natural, greater earthquakes in many aspects, including stress drop, energy efficiency, and complexity of rupture propagation. Some of larger mine earthquakes are preceded by perceivable abnormal seismicity. However, no immediate precursors for earthquakes with M ∼ 2 were observed by our high-resolution strain and AE sensors installed within the dimension of mainshock rupture. In contrast, aseismic strain-step events that we had recently discovered were sometimes preceded by further slower forerunners. Ongoing projects bring in novel technologies such as field-scale AE monitoring and fast-response strainmeters, and novel targets including mines being flooded for closing operation.
1 0 0 0 OA 耐火集成材と鉄骨部材接合部の耐火性能
- 著者
- 抱 憲誓 佐々木 直幸 宮本 圭一 西村 光太
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.67, pp.1291-1296, 2021-10-20 (Released:2021-10-20)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
The Japanese government is promoting use of wood in recent years, because of the environmental provision of carbon dioxide fixation. The authors developed “FR wood”. “FR wood” is the only technique with simply use one tree species in Japan. When considering actual application, it is necessary to verify the fire-safety of joint parts in addition to the development of member. In particular, verification of the joint with the steel frame member is important. So, the specimens of the join part were constructed and fire resistance test was conducted. The resistance performance of steel members and wood members was confirmed.
1 0 0 0 風俗嬢の見えない孤立
- 著者
- 西川 正憲
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.53-58, 2012-06-30 (Released:2016-04-25)
- 参考文献数
- 29
23価肺炎球菌多糖体ワクチン(PPV23)接種は,65歳以上のCOPD患者および65歳未満で対標準1秒量が40%未満のCOPD患者の肺炎の発生を低下させ,介護施設居住者の肺炎球菌性肺炎の発症を64%減少させ,肺炎球菌性肺炎による死亡率を低下させる.PPV23は,3価不活化インフルエンザワクチン(IV)との併用により,PPV23やIVの単独投与と比較して,寝たきり高齢者の肺炎による入院を半減させ,高齢者の肺炎医療費を抑制し,COPD患者の感染性増悪を減らし,外来通院する慢性疾患を有する高齢者の肺炎による入院を減少させ,高齢者の医療費削減につながる.わが国でのPPV23の認知度は米国に比して低い.PPV23の普及には,接種費用の公費助成とともに,日常診療における適切な病診連携の構築による医療者の啓発と患者教育が大切である.私たちが「元気な高齢社会」を享受するためには,IVとともにPPV23接種も積極的に推奨すべきと考えられる.
1 0 0 0 OA 携帯端末向けWeb閲覧手法
- 著者
- 久野 友也 服部 隆志
- 雑誌
- 第66回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.1, pp.247-248, 2004-03-09
1 0 0 0 OA イギリスの階級について
- 著者
- 松岡 美香
- 出版者
- 大妻女子大学人間生活文化研究所
- 雑誌
- 人間生活文化研究 (ISSN:21871930)
- 巻号頁・発行日
- vol.2016, no.26, pp.129-131, 2016-01-01 (Released:2020-03-18)
- 参考文献数
- 1
イギリス文学の背景的特徴として,階級が挙げられる.現在のイギリスにおいて,階級という仕組みは表面上ではかなり隠ぺいされているが,実際には依然として,社会に何らかの影響を及ぼす力を持ち続けている.本研究では20世紀に焦点をあて,階級の変遷,階級を反映させた小説が一体どのようなものなのか,ということを考察していくことを目的とする.
1 0 0 0 車両と電気
- 著者
- 車両電気協会 [編]
- 出版者
- 車両電気協会
- 巻号頁・発行日
- vol.18(4), no.207, 1967-04
1 0 0 0 戦跡を語る : 附・十番指し実戦棋譜
- 著者
- 溝呂木光治, 清水文春 共著
- 出版者
- 将棋春秋社
- 巻号頁・発行日
- 1931
1 0 0 0 車両と電気
- 著者
- 車両電気協会 [編]
- 出版者
- 車両電気協会
- 巻号頁・発行日
- vol.17(10), no.201, 1966-10
1 0 0 0 車両と電気
- 著者
- 車両電気協会 [編]
- 出版者
- 車両電気協会
- 巻号頁・発行日
- vol.15(8), no.175, 1964-08
1 0 0 0 OA 劇症型心筋炎4例の臨床的特徴と治療的転帰について
- 著者
- 高橋 俊明 井根 省二 竹内 雅治 伏見 悦子 関口 展代 木村 啓二 林 雅人 斉藤 昌宏 高橋 さつき
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会雑誌 (ISSN:04682513)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.4, pp.749-754, 2003 (Released:2005-03-29)
- 参考文献数
- 15
1995年から2001年の6年間に4例の劇症型心筋炎 (男2例, 女2例, 年齢21~67歳) を経験した。診断は臨床症状, 心電図, 心エコー所見などから総合的に行い, 3例では病理学的に確定診断された。4例全例が発熱などの感冒症状で発症し, 1例は心肺停止で来院し, 蘇生できなかった。残り3例は初発から5~7日後にショック状態で入院し, 一時ペーシング, カテコラミン, ステロイドパルス療法, そのうち1例では経皮的心肺補助 (PCPS) を導入したが, 3例とも入院1~10日後死亡した。心電図では心室調律, 異常Q波, ST上昇, 低電位を呈した。血清酵素の著明な上昇, 代謝性アシドーシス, DICは予後不良の徴候と考えられた。劇症型心筋炎の救命のためには, まず本症を早期に的確に診断すること, そして積極的に補助循環を導入し, 急性期を乗り切ることに尽きる。
- 著者
- Tomohiro Kondo Hana Morizono
- 出版者
- The Japanese Society for Horticultural Science
- 雑誌
- The Horticulture Journal (ISSN:21890102)
- 巻号頁・発行日
- pp.QH-006, (Released:2022-08-20)
- 被引用文献数
- 3
To determine the effects of drought stress, especially light drought stress, on flower number in passion fruit, one-year-old passion fruit plants grown in 7.5 L plastic pots were subjected to different soil water content treatments, namely wetness, light drought, and heavy drought for two months. Average, maximum, and minimum soil water contents (v/v) were 44, 47, and 41% in the wetness treatment, 23, 40, and 11% in the light drought treatment and 11, 33, and 6% in the heavy drought treatment. Flower number decreased as the strength of drought stress increased, although the number of nodes and flower buds did not. Flowering periods were from June 27 to July 19 in the wetness treatment and June 26 to July 16 in the light drought treatment with three peaks around July 1, 6, and 13. In the heavy drought treatment, the flowering period was from July 11 to 18 with one peak. The flower bud number was not affected by drought stress. Light drought stress did not suppress vegetative growth, such as vine length, leaf number, leaf length, or photosynthetic rate, although heavy drought stress did. Stomatal conductance was suppressed by light drought only at 12:00PM and by heavy drought throughout the day. Leaf water potential was decreased by heavy drought at 3:00PM, but not by light drought. In the wetness and light drought treatments, visible wilting was not observed, and in the heavy drought treatment the plants wilted before irrigation, although they recovered about 15 min after irrigation. In conclusion, even light drought stress, which did not suppress vegetative growth, reduced the flower number in passion fruit. Drought stress suppressed flower bud development but not differentiation.
1 0 0 0 OA 最近の電磁気的適合性 (EMC) の動向
- 著者
- 梶川 嘉雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会
- 雑誌
- 日本舶用機関学会誌 (ISSN:03883051)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.9, pp.662-670, 1997-09-01 (Released:2010-05-31)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 教職課程におけるICT活用の指導 ―教員養成の現状や課題―
- 著者
- 村石 幸正
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.2, pp.67-70, 2022-07-15 (Released:2022-08-15)
- 参考文献数
- 9
1.はじめに中学校は2021年度から全面的に,高等学校は2022年度の入学生から年次進行で実施される新しい学習指導要領では,総則に「コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用する
1 0 0 0 OA 卵料理考
- 著者
- 松下 幸子
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.319-324, 1987-12-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 20
1 0 0 0 OA 摂食障害の精神療法 ―診立てのコツと一般外来での工夫―
- 著者
- 野間 俊一
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.3, pp.215-219, 2022 (Released:2022-05-01)
- 参考文献数
- 3
摂食障害の治療は容易ではないが,その精神病理を理解し適切に診立てることで,患者に応じた精神療法を行うことができる.摂食障害の症状の本質は「こだわり」であり,その背景には自己存在の不確かさに由来する「完璧主義」が認められる.症状が慢性化しやすい理由としては,摂食障害が「嗜癖」という側面をもっていることと,他者からの評価を過剰に意識する「自己過敏傾向」が存在することが挙げられる.診立てるためには,摂食障害のステージ,パーソナリティのタイプ,動機づけレベルの3つの軸から評価すべきである.すなわち,ステージは初期・持続期・慢性期,タイプは反応葛藤型・固執型・衝動型,動機づけレベルは回復の段階・怯えの段階・否認の段階と分けて病理の深さを評価する.外来診療では,簡易版認知行動療法を中心に据えながら,病理の深さに応じた治療的アプローチを行う.治療者が患者とともに回復のイメージを共有することが重要である.