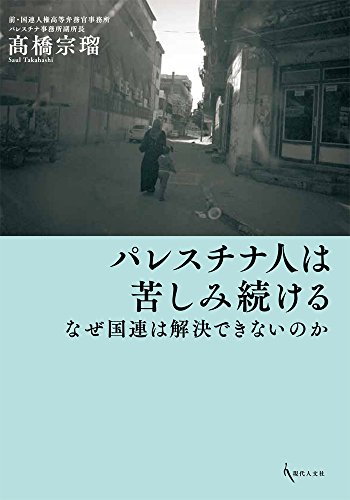1 0 0 0 パレスチナ人は苦しみ続ける : なぜ国連は解決できないのか
1 0 0 0 OA ツバメの巣に関する諸調査
- 著者
- 金井 郁夫
- 出版者
- Yamashina Institute for Ornitology
- 雑誌
- 山階鳥類研究所研究報告 (ISSN:00440183)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.31-41, 1964-06-30 (Released:2008-11-10)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
1960年から1963年までの4年間に調査した,70個のツバメの巣に関するデーターをまとめた結果を次に記す。1.造巣作業中,巣での滞在期間は平均34秒,泥の運搬間隔の平均は73秒で,1時間の回数は平均27回である。仕事は主に午前中行い,造巣日数は平均10日である。2.縦の変異は4.8~12.1cmで平均が7.9cm,標準偏差は1.05である。3.横の変異は7.5~14cmで平均が9.9cm,標準偏差は1.23である。4.縦横差の変異は0~6cmで平均が1.7cmである。5.縦横平均の変異7~13cmで平行が8.9cm,標準偏差は1.09である。6.深さの変異は1.5~5cmで平均が3.2cm,標準偏差は0.27である。7.外高の変異は2~32cmで平均が7.8cm,標準偏差は6.04である。8.巣上空間の変異は4~42cmで平均が10.8cm,標準偏差は2.78である。9.旧巣と新巣の測定差は,縦で0.3cm(3.8%)古巣,横で0.9cm(9.1%)古巣,縦横変異(差)で0.4cm(24%)新巣,縦横平均で1.4cm(16%)古巣,深さでは0.4cm(1.1%)古巣,外高で0.8cm(10%)古巣,巣上空間で2.5cm(23%)古巣の方が大きい。10.屋外と屋内の測定差は,縦で0.1cm(1.3%)外,横で0.4cm(4%)外,差で0.4cm(23.%)外,縦横平均で0.1cm(1.1%)内,深さで0,外高で1.6cm(2.1%)内,巣上空間で4.8cm(44%)外が大きい。11.各調査項目とも一般に旧巣が新巣より大きい。但し,縦横変異は新巣が大である。屋外と屋内を比べると,巣の上面積と巣立ちの空間は屋外の方が大きい。他はすべて屋内巣が大である。12.ツバメの巣は一般に横長である。縦と横は比例し,縦横平均に対し深さは変異の幅が狭い。営巣に必要な空間は6~74cmで平均19cmである。縦横平均と容積指数,深さと容積指数は比例している。
- 著者
- Nobuki Takamatsu Masayuki Imahashi Kyoko Kamimura Makoto Tsutsumi
- 出版者
- GEOCHEMICAL SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- GEOCHEMICAL JOURNAL (ISSN:00167002)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.143-151, 1986-06-20 (Released:2008-04-08)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 3 8
Lithium as well as major chemical constituents, and stable hydrogen and oxygen isotopic ratios in 30 saline spring waters (Cl>5, 000 mg/l) in Japan were determined to clarify the genesis of the waters. The relationship between log (Na/Li) and the temperature estimated by geothermometers revealed that the lithium content of saline spring waters are not usually controlled at the present-day temperatures of the hydrothermal systems. Taking into account the values of the deviation coefficient of lithium to seawater, CLi = (Li/Cl) sample/(Li/Cl) seawater, and the regions from which the spring waters were collected, the spring waters can be classified into the following four groups: Group 1, representing saline waters from coastal line (CLi = 1.2–22), Group 2 those from greentuff region (CLi = 17–110), Group 3 those from Osaka Basin (CLi = 160–220), and Group 4 those from the outer part of Median Tectonic Line (CLi = 250–440). The genetic features of the respective groups are discussed in detail.
1 0 0 0 OA 調剤業務における安全性評価の試み —調剤ミス率,鑑査見逃率及び過誤発生率の関係の解析—
- 著者
- 添田 真司 高柳 理早 渡邊 昌之 山田 安彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.137, no.5, pp.589-593, 2017 (Released:2017-05-01)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
In this study, we established a methodology to calculate the rate of overlooking a dispensing error (inspecting error rate) as a new index for the purpose of determining dispensing error and malpractice rates. Using data obtained from analyses of these error rates at our and two other hospitals, an inspecting error rate was calculated for each institution. Our results showed that inspecting errors occurred at a frequency 3-5 times greater as compared to dispensing errors at each of the examined hospitals. We concluded that construction of a higher quality safety management system would be enabled by incorporation of an inspecting error rate as a new index to evaluate medical safety in regard to dispensing of medicines and managing inspection accuracy.
1 0 0 0 大嘗祭の久米舞と中国禘祭の大武 : 神武伝説久米歌由来譚の背景
- 著者
- 廣畑 輔雄
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 民族學研究 (ISSN:00215023)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.32-49, 1986
1 0 0 0 後見制度支援信託の目的とその運用状況
- 著者
- 和波 宏典 松永 智史
- 出版者
- 民事法研究会
- 雑誌
- 実践成年後見 (ISSN:13470108)
- 巻号頁・発行日
- no.54, pp.60-68, 2015-01
1 0 0 0 OA 新生児の母親に対する乳児の睡眠形成についての簡便な親教育
- 著者
- 羽山 順子 足達 淑子 津田 彰
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.21-30, 2010 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 1
[研究背景]寝渋り、夜泣きのような乳幼児の睡眠問題は、母親の睡眠と健康に悪影響を及ぼす。児の睡眠問題は、就床時および夜間覚醒時の児に対する適切な対応を親に教育することで予防できるとの報告がある。先行研究において、筆者らは生後4ヵ月の乳児を持つ母親を対象に児の睡眠問題予防を目的とした教育介入を実施した。しかし教育の効果は限定的であり、4ヵ月より早い月齢である新生児の親に対する教育が、児の睡眠問題の予防にはより有用であると考えられた。 [目的]先行研究の結果を踏まえ、本研究は、新生児の母親に対して行った児の睡眠問題予防教育が、母親の養育行動と児の睡眠問題予防に及ぼす効果を、その後の4ヵ月児健康診査で比較して検討した。 [方法]対象は教育群46名と教育をしなかった比較群30名であった。教育では、乳幼児の睡眠問題予防のため望ましい養育行動について説明した小冊子を、地域の新生児訪問時に助産師が母親に配布した。評価した行動は1)児の睡眠に関連した親の養育行動(望ましい養育行動13項目、望ましくない養育行動3項目)、2)児の睡眠と睡眠問題、3)母親の睡眠と健康問題であった。 [結果]教育の結果、教育群の母親は、児の夜間覚醒時に「すぐには触らず様子をみる」という望ましい養育行動が比較群より高率に見られた(教育群:比較群=48.9%:23.3%,p<0.05)。さらに望ましい養育行動の合計数は比較群よりも多く(教育群:比較群=4.4:3.3,p<0.01)、望ましくない養育行動の合計数は少なかった(教育群:比較群=1.3:1.7,p<0.05)。また、教育群の母子は就床時刻が規則正しい者の割合が高く、母親は頭痛を感じる者の割合が低かった(教育群:比較群=2.3%:20.0%,p<0.05)。 [考察]以上の結果から、小冊子を用いて児の就床覚醒時刻を規則正しくするための養育行動を教育したことは、教育群の児における就床時刻の規則性促進に影響したと考えた。また、児の就床時刻が規則正しいことは教育群の母親における就床時刻の規則性を促し、母親の頭痛の減少につながった可能性があると考えた。 一方、児の睡眠問題では群間差が見られず、新生児の母親への教育介入が、4ヵ月児の母親への教育よりも児の睡眠問題の予防に有用とした本研究の仮説は支持されなかった。この理由として、①予防効果の検証時期が生後4ヶ月では早過ぎた可能性、②今回用いたような簡素な介入の効果検証にはサンプル数(76名)が小さ過ぎた可能性、③本研究における教育法が、必ずしも児の睡眠に問題意識を有してはいない母親には不十分であった可能性が考えられた。従って、新生児の母親に対しては、本研究の教育方法では不十分で、情報の提供の仕方などに一段の工夫の余地があると考えた。 他地域も含めたより多数の対象者における比較試験を行うこと、睡眠日誌などで睡眠指標の精度を高める必要がある。 [結論]4ヵ月より早い月齢での親教育が児の睡眠問題の予防にはより有用であるとの仮説は支持されなかった。しかし、本研究における教育介入の結果、限定的ではあるが児の睡眠に関連する養育行動および母子の睡眠習慣に効果が認められた。また、母子の睡眠習慣の改善は、母親の健康問題の改善に貢献する可能性があることが示された。
1 0 0 0 IR イリヤ・エレンブルグの写真集 『私のパリ』におけるベルヴィルの表象について(1)
- 著者
- 椎原 伸博 シイハラ ノブヒロ Nobuhiro Shiihara
- 雑誌
- 実践女子大学文学部紀要
- 巻号頁・発行日
- no.54, pp.11-22, 2012-03-12
- 著者
- 竹熊カツマタ 麻子 ダーモディー ゴーデイナ
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 看護管理 (ISSN:09171355)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.12, pp.1084-1092, 2015-12
- 著者
- 吉川 千恵子 野口 美和子 大湾 明美
- 出版者
- 沖縄県立看護大学
- 雑誌
- 沖縄県立看護大学紀要 (ISSN:13455133)
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.137-144, 2016-03
- 著者
- 西川 節 金 安明 正村 清弥 井上 剛 中西 愛彦 生野 弘道
- 出版者
- 日本脊髄外科学会
- 雑誌
- 脊髄外科 (ISSN:09146024)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.2, pp.221-226, 2012 (Released:2017-05-11)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1 1
Object : To study long-term outcomes of anterior decompression and fusion (ADF) and expansive laminoplasty (ELP). Materials and Methods : Our study included 120 patients who underwent iliac bone grafting via the modified trans-unco-discal approach (TUD) or ELP with spinous process or ceramic spacers over 5 years ; the neurological symptoms and Japanese Orthopedics Association (JOA) scores of these patients were reviewed. Results : Neurological symptoms and JOA scores improved in 111 out of the 120 patients (93%), and worsened in 9 patients (8%). There was no significant difference in the rate of improvement of neurological symptoms, and JOA scores in all groups. There was no significant difference in the improvement rates of neurological symptoms and JOA scores between all groups. Conclusions : ADF and ELP showed comparable rates of improvement in neurological symptoms and JOA scores. It is important to choose the appropriate methods according to the pathophysiological conditions. ADF should be performed only for the appropriate lesions, since the problems pertinent to the adjacent lesions may ensue.
1 0 0 0 IR 書評と紹介 呉学殊著『労使関係のフロンティア : 労働組合の羅針盤』
- 著者
- 熊沢 誠
- 出版者
- 法政大学大原社会問題研究所
- 雑誌
- 大原社会問題研究所雑誌 (ISSN:09129421)
- 巻号頁・発行日
- no.644, pp.69-73, 2012-06
- 著者
- 道家 真平
- 出版者
- 国際基督教大学
- 雑誌
- アジア文化研究 (ISSN:04542150)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.165-172, 2015
1 0 0 0 IR 書評 鍾以江『日本における近代神道の起源 : 征服された出雲の神』
- 著者
- 井上 智勝
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 日本研究 (ISSN:09150900)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, pp.269-272, 2018-11
1 0 0 0 IR 司書合格体験記
- 著者
- 安田 さくら Sakura Yasuda
- 出版者
- 同志社大学図書館司書課程
- 雑誌
- 同志社大学図書館学年報 = Doshisha Library Science Annual (ISSN:09168850)
- 巻号頁・発行日
- no.46, pp.65-68, 2021-03-31
1 0 0 0 OA 成層圏突然昇温の力学をどう理解すればよいか?
- 著者
- Michael E. McIntyre
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.1, pp.37-65, 1982 (Released:2007-10-19)
- 参考文献数
- 101
- 被引用文献数
- 208 252
成層圏突然昇温に関する Matsuno の朱駆的な数値実験が成功して以来,この荘大な自然現象が力学的な原因に由来するものであることは疑いをはさむ余地のないところである。しかし,その理論的なモデル化や衛星観測に基づく諸研究は,昇温現象の詳細にわたる理解や適切な予測に関してある程度の見通しが得られた段階に到ったばかりである。本論文では,この現象に関する最近の研究の進展ぶりを自由に論じ,あわせて,数値モデル化に際して対流圏の運動を先駆的に与えることによって生ずる偽の共鳴を避ける方法など,将来の研究のあり方についても示唆を与える。
1 0 0 0 IR ILL文献複写サービスの無料化がもたらしたもの
- 著者
- 土田 大輔
- 出版者
- 明治大学図書館
- 雑誌
- 図書の譜:明治大学図書館紀要 (ISSN:1342808X)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.83-92, 2021-03-31
1 0 0 0 IR コロナ禍における図書館業務委託の運営事例について
- 著者
- 大久 幸世
- 出版者
- 明治大学図書館
- 雑誌
- 図書の譜:明治大学図書館紀要 (ISSN:1342808X)
- 巻号頁・発行日
- no.25, pp.35-40, 2021-03-31
- 著者
- 杉本 栄佑 幸塚 善作
- 出版者
- 一般社団法人 資源・素材学会
- 雑誌
- 日本鑛業會誌 (ISSN:03694194)
- 巻号頁・発行日
- vol.104, no.1200, pp.89-95, 1988
- 被引用文献数
- 2
The present study was done for the purpose of finding any available solid reference electrode for SO<SUB>2</SUB>sensor employingbeta alumina solid electrolyte. In this paper, we tried a few experiments for this sensor using two solid reference electrode, (β+β')-alumina and (α+β)-alumina.<BR>The cells used were as follows: Pt, (β+β')-alumina in air/β'-alumina/Na<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>/SO<SUB>2</SUB>+O<SUB>2</SUB>+SO<SUB>3</SUB>, Pt (1) Pt, (α+β)-alumina in air/β-alumina/Na<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>/SO<SUB>2</SUB>+O<SUB>2</SUB>+SO<SUB>3</SUB>, Pt (1)(11) From the present experiments, the following conclusions were obtained.<BR>1) The constant sodium activities in these solid reference electrodes were maintained for a long duration of the experiment.<BR>2) For both cells, good straight lines were obtained between e.m.f.'s and log Pso2 within the temperature ranges from 933 to 1230 K in the cell (1) and from 932 to 1278 K in the cell (11). Especially, in the (β+β')-alumina solid reference electrode, it was shown that the cell using this electrode could be employed to determine concentrations up to a few ppm of SO<SUB>2</SUB> gases at temperatures of 932 to about 1100 K. Consequently, this (β+β')-alumina mixture is recommended for the solid reference electrode ofSO<SUB>2</SUB> sensor employingβ'-alumina solid electrolyte.<BR>3) From e.m.f.'s of these cells, the activities of Na<SUB>2</SUB>O in β-Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>+β'-Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>and α-Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>+β-Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>coexistences were respectively calculated by considering thermochemical data and compared with the others.
1 0 0 0 OA 国士舘と松陰
- 著者
- 熊本 好宏
- 出版者
- 国士舘大学文学部人文学会
- 雑誌
- 国士舘人文学 = Kokushikan journal of the humanities (ISSN:21876525)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.167-176, 2017-03-15
2015年11月21日 (土) 13:00~ (於:34号館B 301教室)