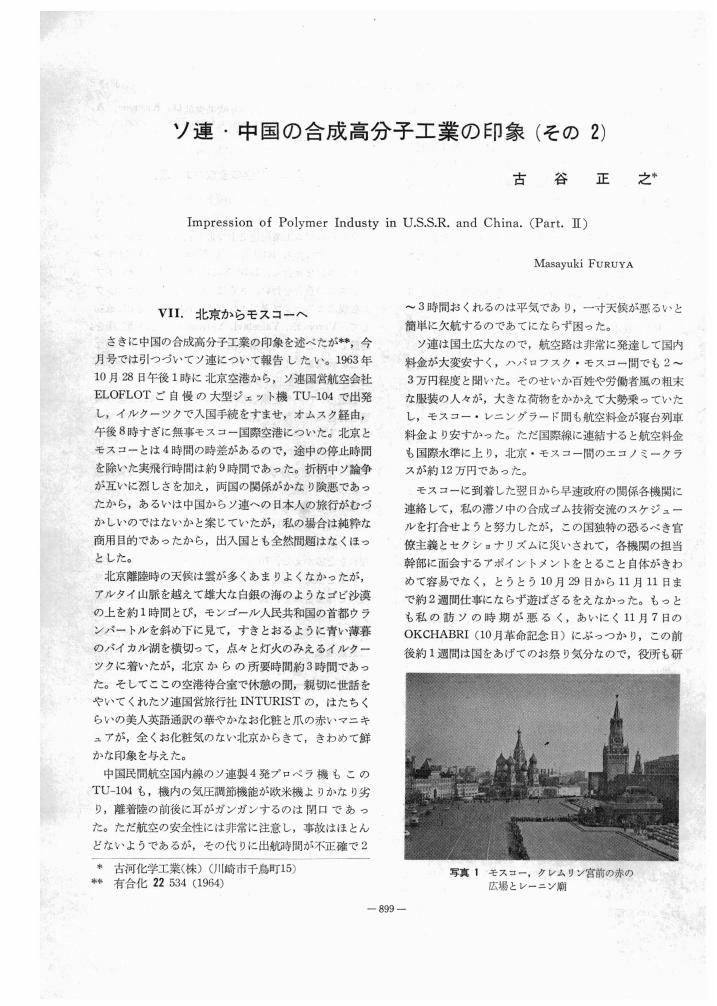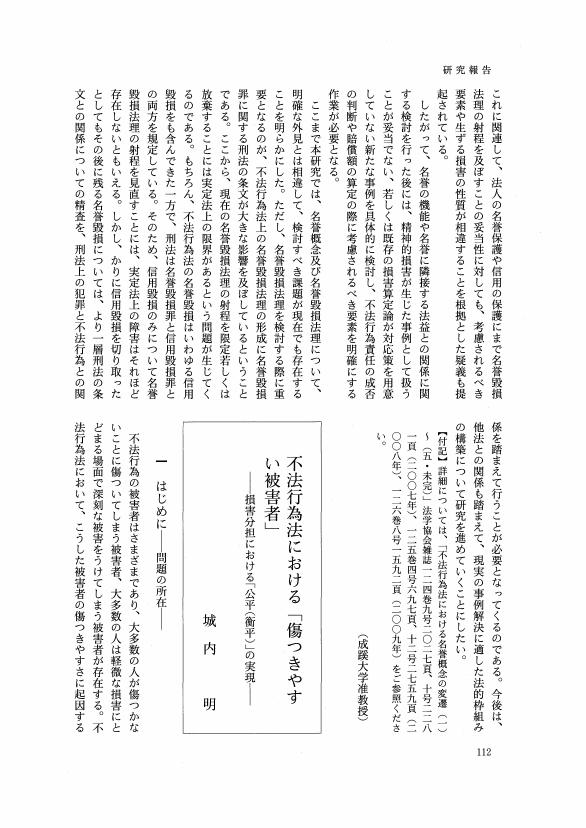1 0 0 0 OA 変動する世界と適応する私たちのために
- 著者
- 高橋 康介
- 出版者
- 中京大学心理学研究科・心理学部
- 雑誌
- 中京大学心理学研究科・心理学部紀要 = Chukyo University Bulletin of Psychology (ISSN:13488929)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.23, 2021-03-15
1 0 0 0 OA ダイバーシティについて考える
- 著者
- 岡本 ゆかり
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経パソコン = Nikkei personal computing (ISSN:02879506)
- 巻号頁・発行日
- no.775, pp.38-49, 2017-08-14
デジカメやスマホで撮りためた数多くの写真も、「Googleフォト」なら容量無制限でクラウドに保存でき、撮影日や人物などで自動的に整理できる。手軽に使いこなすポイントを紹介しよう。(岡本 ゆかり=ライター) 長年撮りためた写真や動画が、パソコンのスト…
- 著者
- 斎藤 幾郎
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経パソコン = Nikkei personal computing (ISSN:02879506)
- 巻号頁・発行日
- no.786, pp.58-61, 2018-01-22
パソコンからGoogleフォトに写真をアップロードするには、WebブラウザーでGoogleフォトにアクセスして手動でアップロードする方法と、専用アプリを使って自動的にバックアップする方法の2種類がある。どちらか一方を選ぶのではなく、併用も可能だ。まず、手動でアップロードする方法を説明しよう。WebブラウザーでGoogleフォトのWebサイトにアクセスし、Googleアカウントでログインすると、メイン画面が表示される。
- 著者
- 斎藤 幾郎
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経パソコン = Nikkei personal computing (ISSN:02879506)
- 巻号頁・発行日
- no.805, pp.54-57, 2018-11-12
今回は、クラウドサービスに保存した写真を、身の回りの人に公開する手順を解説する。「OneDrive」や「Googleフォト」に保存した写真を友人や知人と共有するには、公開したい写真を「アルバム」にまとめて、アルバムの保存先を記したリンク(URL)を相手に教えればよい。受け取った相手が、該当のURLをWebブラウザーで開くとアルバムが表示される仕組みだ。
1 0 0 0 OA 水族館におけるアクティヴィティを促すメディアシステム ~のとじまアクアリウムラリー~
- 著者
- 山内 暢人 出原 立子
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第64回春季研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.48, 2017 (Released:2017-06-29)
のとじま臨海公園水族館の各施設を巡る楽しさを向上し、来館者が能登の海洋生物についてさらに学ぶ機会を提供する目的として、「のとじまアクアリウムラリー」を展開し実証実験を行った。本ラリーシステムは、モバイル端末と3DCGを映す擬似ホログラフィを用いた仮想水槽をデータ通信で繋いだ点が特徴であり、水族館内を巡りながら能登の海洋生物を自分のスマートフォンに集め、さらに館内の大型水槽に向けてリリースする、キャッチ&リリースラリーである。チェックポイント内に手をかざすことによって、海洋生物をアプリケーション内の水槽に捕まえることができ、能登近海の海洋生物への興味に繋げるようにした。さらに、図鑑の説明文などを通すことで、学習向上に繋げた。捕まえた海洋生物は、ラストポイントにてフリックすることによって、壁面にその海洋生物を投影することができ、リリースシステムを楽しむことができる。そして、映像コンテンツを制作することで、切り替え映像用として、壁面に溜まった海洋生物をクリアおよび最後の演出とした。
1 0 0 0 OA 料理レシピ検索を支援するための3D空間表現を用いた検索結果の可視化システム
- 著者
- 川端 彬子 金 尚泰
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- デザイン学研究 (ISSN:09108173)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.2_43-2_48, 2016-07-31 (Released:2016-11-15)
- 参考文献数
- 13
従来の料理レシピ検索では、検索結果がリスト形式で表示されることが多い。しかし、「冷蔵庫の中にある食材を使った料理」という、漠然とした検索欲求下においては、ユーザーは適切なクエリ作成を行うことが難しいため、検索結果の絞り込みが困難である、と言われている。また、料理レシピ検索におけるユーザーのコンテクストは多様で、絞り込みきれていない膨大な結果の上位数件で満足する可能性は低い。そこで、料理レシピデータの持つ複数レシピ属性値をユーザーが比較できる数値とし、検索結果を「ざっと」見て、「一目で」複数レシピ属性を比較できる料理レシピ検索UIの開発を行った。各料理レシピをオブジェクトとして表現して、3次元空間に配置し、マウスで操作できるようにすることで、料理レシピ検索結果の俯瞰視を可能にし、新たな料理レシピの検索体験を生み出した。
1 0 0 0 OA Space of Resistance and Place of Local Knowledge in Karen Ecological Movement of Northern Thailand:
- 著者
- Prasert Trakansuphakorn
- 出版者
- Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University
- 雑誌
- 東南アジア研究 (ISSN:05638682)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.586-614, 2008-03-31 (Released:2017-10-31)
This paper is based on an insiders' view of the ecological movement in Northern Thailand as carried out by Sgaw Karen (Pgaz K'Nyau) people whose knowledge was accumulated in the form of cultural capital including oral traditions such as legends, storytelling, hta (traditional songs or poems), and rituals. Through the movement, in which each of these repositories of knowledge were put into practice, the Pgaz K'Nyau image as conservationists was shaped and reinforced. Leaders of the Pgaz K'Nyau movement used their ecological knowledge, which was reinterpreted to represent Pgaz K'Nyau as children of the forest. Such images were the result of converting knowledge into symbolic power to create a space of resistance, which served as an instrument to contest the hegemonic discourse imposed by the state forestry agencies. A shift in Pgaz K'Nyau identity occurred through the process of inserting their relatively little-known cultural image into the political context of rights framed by the newly promulgated (1997) Constitution.1) This paper focuses on the use of hta in the eco-political conflict in the Mae Lan Kham river basin, Sameong District, Chiang Mai Province.
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経パソコン = Nikkei personal computing (ISSN:02879506)
- 巻号頁・発行日
- no.753, pp.26-29, 2016-09-12
Googleフォト デジタルカメラやスマートフォンの普及で、パソコンに保存している写真の画像ファイルは増え続けている。一つひとつの容量が大きく、検索もしづらいこれらのファイルの整理にお悩みなら、お薦めしたいのが「Googleフォト」だ。 解像度の制限付きと…
1 0 0 0 OA ソ連・中国の合成高分子工業の印象(その2)
- 著者
- 古谷 正之
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.11, pp.899-916, 1964-11-01 (Released:2010-06-28)
1 0 0 0 OA 不法行為法における「傷つきやすい被害者」 損害分担における「公平(衡平)」の実現
- 著者
- 城内 明
- 出版者
- 日本私法学会
- 雑誌
- 私法 (ISSN:03873315)
- 巻号頁・発行日
- vol.2010, no.72, pp.112-119, 2010-04-30 (Released:2014-04-01)
- 参考文献数
- 8
- 著者
- 藤原 達矢
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経パソコン = Nikkei personal computing (ISSN:02879506)
- 巻号頁・発行日
- no.744, pp.64-67, 2016-04-25
オンラインストレージ上に保管して、複数のデバイスやメンバーと共有/代表的なオンラインストレージサービス/オンラインストレージのアカウントを登録/写真をオンラインストレージにアップロード/スマホからオンラインストレージにアクセス/写真を自動アップロード/手動アップロードも可能/Googleフォトの写真を他人と共有/スマホでも共有できる
1 0 0 0 OA 数種動物における遠心加速度負荷中の心拍数変化
- 著者
- 岩根 正昭 藤原 弘
- 出版者
- Japanese Society of Agricultural, Biological and Environmental Engineers and Scientists
- 雑誌
- 生物環境調節 (ISSN:05824087)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.19-28, 1968-08-31 (Released:2010-06-22)
- 参考文献数
- 6
健康成熟のラット100匹, ウサギ15羽, モルモット16匹, ハムスター18匹については, +15Gzおよびtransverse15G (Gx) の負荷を10分間ほどこし, ハムスターには-10Gz10分間, イヌには+10Gz10分間, およびラット, ウサギ, モルモットにはそれぞれ-5Gz10分間負荷したときの心拍数変化を検討した.結果はつぎのとおりである.1) イヌに+10Gz10分間負荷した際の心拍数の変化: G増加にともない7G付近までは心拍数の増加傾向があるが, 以後10Gまでは減少を来たし, 10G滞留中は, さらに減少を来たし, 一過性の増加, その後減少が5分時までみられるが, 以後ゆるやかに減少, 徐脈となって死亡する.2) ラット生存群における+15Gzにおける心拍数変化: 生存群においては, Gの増加にともなって変化することなく, 心拍数は滞留負荷時にやや減少するが著しい徐脈とはならない.3) ラット♂死亡群における+15Gzにおける心拍数変化: Gの増加にともないゆるやかに心拍数は増加し, 滞留負荷開始後は, すみやかに徐脈となって死亡する.4) ハムスターに+15Gzを負荷した際の心拍数の変化: G増加にともない, わずかに心拍数の増加が続くが滞留負荷後は急速に減少を示す.8分時以後一時回復様: 相を示し, ある程度の増加を来たし死亡しない.5) モルモットに+15Gzを負荷した際の心拍数変化: G増加にともない多少心拍数の増加が見られるが15Gまでは元値と変わらず, 滞留負荷に至って著しく減少後, 死亡する.6) ウサギに+15Gzを負荷した際の心拍数変化: G増加にともない, 6G付近まで心拍数の増加を来たし, 以後ゆるやかに減少が続き, 滞留負荷中も漸次徐脈になり死亡する.7) ラット, ウサギ, モルモットに-5Gz, ハムスター, ラットに-10Gzを負荷した際の心拍数変化: -G負荷の場合はG増加にともなってはじめから心拍数の減少が著しく, 滞留負荷中一時動揺するが, 徐脈になって死亡する.8) ラット, ハムスター, モルモットおよびウサギにtransverse15G (Gx) を負荷t, た際の心拍数の変化: Gの増加にともない多少心拍数の増加が起こるが, 滞留負荷中はラット, ハムスターにおいて徐脈にはならない.モルモットの場合は滞留負荷中に急速の徐脈となって死亡する.ウサギの場合は滞留中に一時増加をともない, その後徐脈に移行する.
1 0 0 0 特集 今から学ぶ 今から始める お役立ちAI大集合
- 著者
- 岩元 直久
- 出版者
- 日経BP
- 雑誌
- 日経パソコン = Nikkei personal computing (ISSN:02879506)
- 巻号頁・発行日
- no.859, pp.30-41, 2021-02-08
スマホからAIの機能を体感できるアプリも多い。特集の冒頭で紹介したように、Googleフォトの検索機能や、メルカリのAI出品のように、AIが関与していることを意識せずに使っているアプリやサービスも少なくない。 ここでは、スマホアプリから2つのAI活用例を紹介…
1 0 0 0 OA 消費者空間選択の一考察—制約を導入した店舗選択の分析—
- 著者
- 神谷 浩夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.6, pp.413-426, 1984-06-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 52
Consumer behavior research stimulated by the development of cognitive behavioral approach has accumulated many empirical studies, having close relation to such established fields as spatial interaction studies and the central place theory. Recent trends in this field suggest that spatial behavior is influenced by spatial and temporal constraints and that preference structure behind the behavior is not intrinsic to individuals. In the light of this argument, the focus of the study is placed on the constraints-oriented spatial choice process. The purpose of the paper is to propose a store choice model which includes the concept of constraints and to test its validity. First, through the descriptive analysis in Section III, consumers' patronage patterns for various facilities (including grocery store, pharmacy, post office and bank) are examined. The data are gathered through the self-reporting about these facilities by housewives living in Nagoya City. In Section IV the proposed model is operationalised and applied to the grocery store choice. In this model, the choice process is divided into two components. One expresses the process of constructing individual's choice set. The other indicates the process of choosing the best alternative among the choice set. And the standard ellipse is used as the choice set to delineate the activity space where consumers usually keep contact. The form of the choice function is multiplicative. When we introduce the activity space ellipse, we could explain the observed behavior better than without employing the ellipse. At the next step, we subdivid the population into subgroups according to their socio-economic status. This subdivision is repeated in terms of the ownership of private vehicle and the housewife's working status. After the population is divided, the activity ellipses are changed respectively and then applied to the grocery choice model. This time the explanable results were not obtained. The defficiency of the activity ellipse may be due to the discrepancy between the actual travel mode used and the household's ownership reported, and also due to the shape of ellipse.
1 0 0 0 OA 加工用原料野菜の除菌技術
- 著者
- 宮尾 茂雄
- 出版者
- Japan Association of Food Preservation Scientists
- 雑誌
- 日本食品保蔵科学会誌 (ISSN:13441213)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.4, pp.267-280, 1998-07-30 (Released:2011-05-20)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 22 フィルムスキャナによるRMS粒状度測定について : オルソシステム
- 著者
- 細渕,安弘
- 出版者
- 日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術学会総会学術大会一般研究発表後抄録
- 巻号頁・発行日
- no.56, 2000-08-31
1 0 0 0 OA 西洋松茸の春夏秋冬栽培法
- 出版者
- 醍醐農園
- 巻号頁・発行日
- 1925
1 0 0 0 E・カッシーレル「國家の神話」
- 著者
- 五十嵐 豐作
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 日本政治學會年報政治學 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.99-107, 1951
1 0 0 0 政治思想史
- 著者
- 五十嵐 豐作
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 日本政治學會年報政治學 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.240-246, 1950