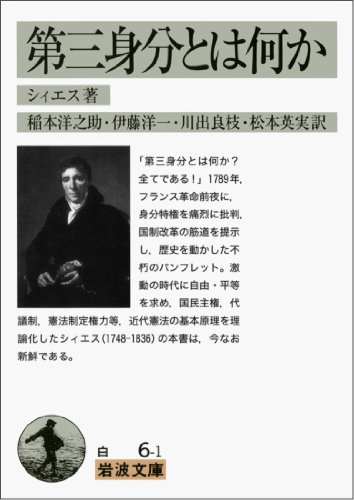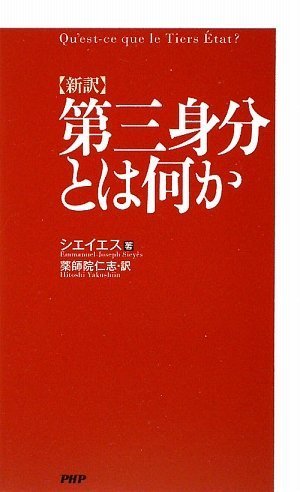1 0 0 0 近代國家と社會的自由 : デモクラシーの問題史として
- 著者
- 小浜 耕己
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経systems (ISSN:18811620)
- 巻号頁・発行日
- no.285, pp.68-71, 2017-01
今も、手嶋実業さんを含めて、三つのプロジェクトを切り回している。後輩が活躍してくれるのは嬉しいけれど、涼子としては、一抹の寂しさと、追い越されて行くような不安も感じざるを得ない。 それはともかく、さっきの応対は? かけもちPMの負荷は高い。
1 0 0 0 OA L-ASCORBIC ACID DEGRADATION BY BACTERIA
- 著者
- SHINTARO KAMIYA
- 出版者
- THE VITAMIN SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- THE JOURNAL OF VITAMINOLOGY (ISSN:00225398)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.14-18, 1961 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1 1
1. From the fact that dehydroascorbic acid metabolism of ascorbic acidadapted bacterium was markedly accerelated by adding a small amount of glucose or ascorbic acid, a reductive process is assumed to be involved in the metabolism of dehydroascorbic acid.2. D-Arabinosone was hardly metabolized by unadapted cells, whereas it was slowly metabolized by adapted cells and it was markedly accerelated by adding a small amount of ascorbic acid. It suggests that D-arabinosone is reduced to D-ribose as follows.Ascorbic acid→dehydroascorbic acid -CO2→diketo-L-gulonic acid→L-xylosone→D-arabinosone +2H→D-ribose
- 著者
- 田中 信介 渡辺 言夫 宮沢 博 芦原 義守
- 出版者
- 一般社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.7, pp.582-587, 1982
妊婦145名についての風疹抗体測定を, 近年開発されキット化されたRUBEHSA<SUP>®</SUP>を用いて行い, HIと比較した. また, 青年女子25名に風疹ワクチンを接種し, そのうち18名について抗体価を測定, その副反応も検討した.<BR>結果は, RUBELISA value 0.14以下を抗体陰性とすると, 抗体保有率は74.1%であった. HIでは23名が8倍未満で, 抗体保有率は84.7%であった. これら2方法の一致率は88.0%であり, 相関係数は0.85であった. 1977年秋の風疹ワクチン接種開始時すでに16歳以上であった予防接種対象外の者が現在妊娠可能年齢層となっており, いまだに妊婦の風疹感染の可能性が残されていると考えられた.<BR>青年女子のワクチン接種では8名32%に副反応を認め, すべてが関節症状を呈し, 関節痛6, 関節腫脹と痛み2であった. 抗体価は測定全例で上昇し, 平均HI価は25.1であった。年齢の高い女子の場合には, 副反応としての関節症状が重要であることが注目された.
- 著者
- 中村博文
- 出版者
- 独立行政法人 国立高等専門学校機構 都城工業高等専門学校
- 雑誌
- 都城工業高等専門学校研究報告 (ISSN:24321036)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.69-80, 2018 (Released:2018-03-30)
あらまし 本論文は、記録や通信におけるデータの修復が、実際には計算でなされていることについて、 小学校で習う剰余計算の学習のみを前提として、10~15 分でデモンストレーションする例の報告である。 具体的には、数枚のトランプの並びの中で1 枚分の取り替えがあっても、取り替え前を知らない他者が 計算で数を復元できる例を参加者皆で確認し、更に、なぜ復元できるかの理由を参加者皆が納得できるこ とを目指したデモンストレーションである。 本校の毎年の科学イベントとなっている「おもしろ科学フェスティバル」において実施し、剰余計算を 学習済みの小学生から大人までの殆どが内容を理解し納得できている。 記録や通信においてデータの一部が違ってしまう、即ち誤りが生じる、ということは、頻度は低いが日 常的に起こっている。誤り訂正も現代の情報社会を裏方で支えている技術の一つであるが、例えばQR コ ードの一部をわざと隠したり汚したりして難なく読めるという実験をするというようなことでもなけれ ば、データの修復をする誤り訂正技術の存在は意識することさえも難しい。本論文のデモンストレーショ ンは、誤り訂正符号のひとつであるリード・ソロモン符号のアイデアを、トランプの数が13 種類であり 素数であることを利用した具体化と変形により、トランプ数枚の内の1 枚分の誤り訂正の場合において小 学4 年生以上が納得できる内容になっている。決して単純ではないリード・ソロモン符号ではあるが、そ のアイデアを、より知る人の多い、少ない数学的要素に落とし込む挑戦でもある。 キーワード [出前授業,科学イベント,小学生,誤り訂正,リード・ソロモン符号]
1 0 0 0 OA 日本における知覚・行動地理学の回顧と展望
- 著者
- 若林 芳樹
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.266-281, 2009 (Released:2018-01-10)
- 参考文献数
- 95
- 被引用文献数
- 2
The annual review of human geographical studies in Japan published in the Japanese Journal of Human Geography (Jimbun Chiri) has included a section on perceptual and behavioral geography since 1982. Nevertheless, the editorial board of the journal decided to remove this section in 2008. There is no doubt that this decision was made because of the need to re-examine the classification of the sections in this article, and was affected by the recent reorganization of this discipline. However, it is too early to say that perceptual and behavioral geography has lost its productivity and attraction. The aim of this paper is to review the advancements in perceptual and behavioral geography in retrospect and to evaluate the prospects for research in this field in Japan in comparison with the trends in English-speaking countries.To elucidate the place of perceptual and behavioral geography in Japanese geography and the changes over the years, the author analyzed the literature in Bibliographies on Japanese Geographical Research, the fields of interest of Japanese geographers, and the change in the tone of the articles published in the annual review of the above journal. The analysis revealed that perceptual and behavioral geography in Japan has not lost its productivity and still attracts the attention of more than a few young geographers; however, the number of researchers specializing in this field remains few. As the studies in this field tend to overlap with other branches of geography, and since the polarization between perceptual and behavioral studies has not yet been reconciled, the unity of this field of research has become lost. As a result, this field is marginalized in human geography.While this trend in perceptual and behavioral geography observed in Japan is similar to that observed in UK, perceptual and behavioral geography in the USA enjoys a more optimistic outlook, since the specialty group of EPBG, which has made close connections with GIS and cartography, remains active there. After 2000, new trends in perceptual and behavioral geography have been observed in Japan. A notable one is the interdisciplinary collaboration with related fields (e. g., psychology and information science). In addition, there has been an increase in the number of studies focusing on special segments of the population, such as the disabled, foreigners, children, the elderly, and women; these studies are more concerned with specificity rather than generality, since they take into consideration the geographic context of environmental perception and spatial behavior. These studies aim at solving actual problems and are applicable to public policy and urban planning. Recently, studies on spatial cognition have also contributed significantly to GIS and cartography.
1 0 0 0 OA 認知地図を用いた都市構造に関する意識分析
- 著者
- 長瀬 恵一郎 松本 昌二
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.493-498, 1992-10-25 (Released:2019-12-01)
- 参考文献数
- 4
IN ORDER TO GRASP THE ATTITUDE OF INHABITANTS TOWARD THE URBAN STRUCTURE OF A LOCAL CITY,THE IMAGE MAPS WERE COLLECTED BY QUESTIONNAIRE. THE ANALYSIS OF THE OBTAINED IMAGE MAPS REVEALED THAT THE RIVER CHANGED THE COGNITIVE DISTANCE OF INHABITANTS AND THE RAILWAY DID THE COGNITIVE DIRECTION. IT WAS CONFIRMED THAT THE IMAGE MAP METHOD COULD ANALYZE THE COGNITIVE STRUCTURE OF URBAN SPACE SUCH AS A DIVIDING EFFECT.
1 0 0 0 OA 中国残留婦人国賠訴訟における立法不作為違憲論
- 著者
- 内藤 光博
- 出版者
- 専修大学法学会
- 雑誌
- 専修法学論集 (ISSN:03865800)
- 巻号頁・発行日
- vol.99, pp.57-102, 2007-03-15
1 0 0 0 第三階級とは何か : 他2篇
1 0 0 0 第三身分とは何か : 新訳
1 0 0 0 第三身分とは何か
- 著者
- シィエス著 稲本洋之助 [ほか] 訳
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 2011
1 0 0 0 新たに発見された高野山天野社伝来の舞楽装束について
- 著者
- 河上 繁樹
- 出版者
- 東京国立博物館
- 雑誌
- 東京国立博物館研究誌 (ISSN:00274003)
- 巻号頁・発行日
- no.479, pp.p18-28, 1991-02
1 0 0 0 IR 楽曲に対応した英語カードを用いたグループ対戦ゲームの授業活用とその効果に関する一検討
- 著者
- 藤代 昇丈
- 出版者
- 中国学園大学/中国短期大学
- 雑誌
- 中国学園紀要 (ISSN:13479350)
- 巻号頁・発行日
- no.16, pp.247-257, 2017-06
大学において,教養共通科目として学ぶ講座「英語Ⅱ」において,外国語学習のための動機づけを高め,インプット強化を図るタスクとして,日本人アーティスト・西野カナの日本語の楽曲とその歌詞に対応した英語カードを用いたグループ対戦ゲームを実施し,学生の情意面に及ぼす影響を調べた。事後の自由記述アンケートの回答内容を計量テキスト分析用ソフトウェア「KH Coder」により分析した結果,回答内容は「活動の親しみやすさ」「歌詞の英語表現」「絵による視覚補助」「活動の難しさ」「やる気の醸成」「楽曲を用いたグループワーク」「表現使用への意欲」「英語学習の楽しさ」の8つのクラスターに分類され,回答の97.1%に「英語学習の楽しさ」に関連する語が出現し,中心クラスターである「英語学習の楽しさ」は「活動の難しさ」と「楽曲を用いたグループワーク」と結びつきがあり,「表現使用への意欲」と強く関連していることが分かった。
1 0 0 0 OA メンタルマップ研究の成果とその意義
- 著者
- 中村 豊
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.6, pp.507-523, 1979-12-28 (Released:2009-04-28)
- 参考文献数
- 66
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 OA 名古屋市の地理的空間とメンタルマップ
- 著者
- 中村 豊
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.1-21, 1978-01-01 (Released:2008-12-24)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 7 3
近年,わが国でも,メンタルマップに対する関心が寄せられているにもかかわらず,実証的な研究はほとんどなされてこなかった.そこで,筆者はわが国における都市域のメンタルマップの名古屋市における事例研究を行なった.都市域のメンタルマップについては,リンチLynchのエレメント抽出以後も,地理学においてはほとんどなされなかったが,1960年代後半にアダムスAdamsがくさび形のメンタルマップの仮説を示すことにより,1つの議論の材料が与えられた。しかし,アダムスの仮説は実際のメンタルマップを説明するには不十分であったので,それは再検討をせまられた.再検討の方向は,1つにはアダムスの仮説を,分析方法を洗練させることによって修正するものであり,もう1つはメンタルマップの操作的な概念の変更であった.本研究では,筆者はこの2つの方向に従って実証的に両者を比較検討した.その結果,アダムスの仮説は概念化が不十分であり,メンタルマップの概念化は行動的アプローチを基礎に行なわれる方がよいことが理解された.そして,その行動的アプローチによって,都市域のメンタルマップはより一貫した説明が可能になることが理解された.
1 0 0 0 OA 熟練者・未熟練者におけるインステップキック動作解析
- 著者
- 中村 康雄 齊藤 稔 林 豊彦 江原 義弘
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム (ISSN:13487116)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.53-64, 2010 (Released:2017-02-15)
- 参考文献数
- 12
サッカーは, キック動作を基本とした主に足でボールをコントロールするスポーツである. ボールを自在に操る蹴り脚は, 熟練者であるほど巧みな動きをする. そのため, 多くの先行研究では, 足のみを対象としてキック動作の定量的な測定・解析が行われてきた. しかし, キック動作は全身運動である. キック動作をさらに理解するためには, 足だけでなく, 蹴り脚の動作の要となる腰部の運動についても同時に測定し, 定量的に評価する必要がある. 本研究は, インステップキック動作を対象とし運動学・動力学解析することと, 熟練者と未熟練者の腰部の運動の違いを定量的に評価することを目的とした. キック動作はモーションキャプチャ・システムを用いて測定した. 熟練者と未熟練者の運動を評価した結果から, 腰部は, 上体の急激な屈曲運動の補助, 下肢へのエネルギー伝達, 姿勢の安定の3つの役割があると考えられた.
1 0 0 0 OA 働くこととリカバリーに関する予備的調査 ―量と質の両側面からの検討―
- 著者
- 大川 浩子 遠藤 芳浩 塩澤 まどか 船本 修平 本多 俊紀
- 出版者
- 北海道文教大学
- 雑誌
- 北海道文教大学研究紀要 = Bulletin of Hokkaido Bunkyo University (ISSN:13493841)
- 巻号頁・発行日
- no.45, pp.23-35, 2021-03-15
近年,パーソナル・リカバリーの中の客観的リカバリーの一つに就労が考えられている.しかし,先行研究において,就労とリカバリーの関係は量的手法と質的手法による結果が異なっている.今回,我々は,就労とリカバリーの関係を量と質の両側面から検討するために,就労している障害当事者に対し,自己記入式のアンケート調査とインタビュー調査を行い,検討した.まず,量的な検討としてUWES-J 短縮版とSISR-B を用いたが,両者の相関は認められなかった.また,質的な検討としてインタビュー内容をUWES-J 短縮版とリカバリーの段階(SISR-A)を外部変数としてテキストマイニングを行った.その結果,ワーク・エンゲイジメントのレベルとリカバリーの段階ごとの文章の内容はポジティブ,ネガティブの割合が異なって現れることが示されたが,就労とリカバリーの関係を直接検討までに至らなかった.今後,就労とリカバリーの関係を検討するうえで,①就労のとらえ方,②リカバリーの定義ととらえ方,③研究協力者の協力した時期の3 点が課題になることが考えられた.