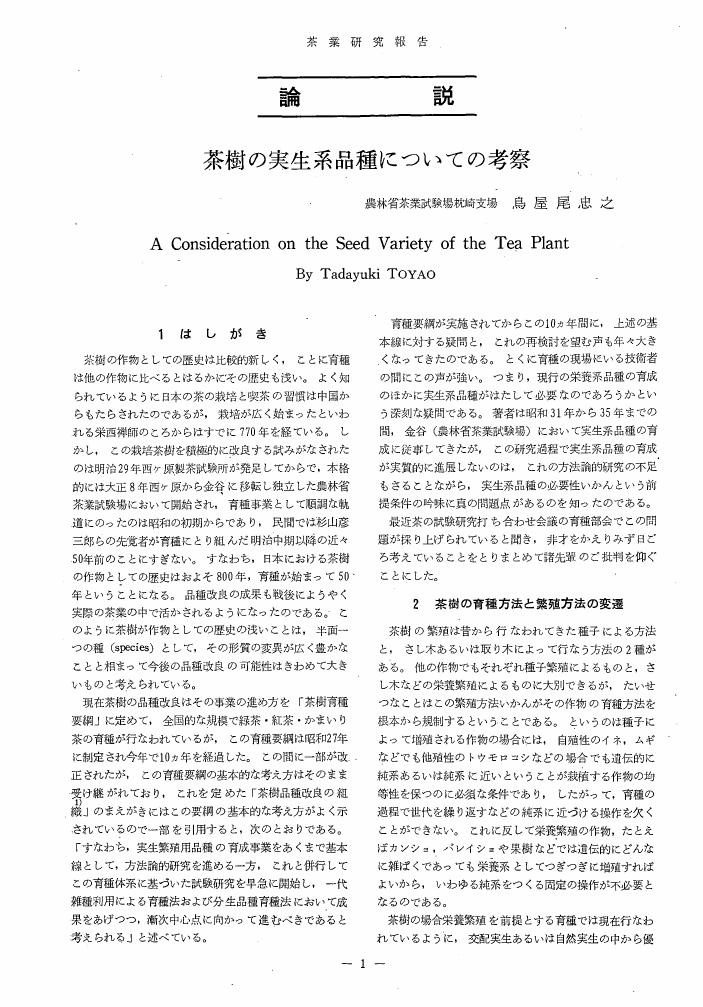1 0 0 0 秋播なたね「アリアナ」の品種特性と「キザキノナタネ」の栽培法
- 著者
- 村上 紀夫 沢口 敦史 梶山 努
- 出版者
- 北海道立農業試験場
- 雑誌
- 北海道立農業試験場集報 (ISSN:04410807)
- 巻号頁・発行日
- no.74, pp.63-68, 1998-03
- 著者
- 高槻 成紀 岩田 翠 平泉 秀樹 平吹 喜彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.155-165, 2018 (Released:2018-07-23)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 5
これまで知られていなかった東北地方海岸のタヌキの食性を宮城県仙台市宮城区岡田南蒲生と岩沼市蒲崎寺島のタヌキを例に初めて明らかにした。このタヌキは2011 年3 月の東北地方太平洋沖地震・津波後に回復した個体群である。南蒲生では防潮堤建造、盛土などの復興工事がおこなわれ、生息環境が二重に改変されたが、寺島では工事は小規模であった。両集団とも海岸にすむタヌキであるが、魚類、貝類、カニ、海藻などの海の生物には依存的ではなかった。ただしテリハノイバラ、ドクウツギなど海岸に多く、津波後も生き延びた低木類の果実や、被災後3 年ほどの期間に侵入したヨウシュヤマゴボウなどの果実をよく利用した。復興工事によって大きく環境改変を受けた南蒲生において人工物の利用度が高く、自然の動植物の利用が少なかったことは、環境劣化の可能性を示唆する。また夏には昆虫、秋には果実・種子、冬には哺乳類が増加するなどの点は、これまでほかの場所で調べられたタヌキの食性と共通であることもわかった。本研究は津波後の保全、復旧事業において、動物を軸に健全な食物網や海岸エコトーンを再生させる配慮が必要であることを示唆した。
1 0 0 0 OA やり取りを前提とした文章の産出に関する研究の展望 : 教育への応用を目的として
- 著者
- 菊池 理紗
- 出版者
- 法政大学大学院
- 雑誌
- 大学院紀要 = Bulletin of graduate studies (ISSN:03872610)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, pp.7-12, 2021-03-31
本論文は,より好ましい文章を書くための教育や支援への応用を目的として,やり取りを前提とした文章に焦点を当てて,これまでの文章産出研究について検討した。その結果,やり取りを前提とした文章においては,書き手も読み手も文章の内容よりも表現に相対的に重きを置くことと,読み手との関係性や関係継続の予期が文章に影響することが明らかになった。また,これらの知見をふまえ,山川・藤木(2015)の文章産出プロセスモデルに,外的表象を媒介しない循環と読み手の反応に対する推測という2点を追加して,修正した文章産出プロセスモデルを提案した。このモデルに基づくと,やり取りを前提としたより好ましい文章を書けるようになるための教育の方法として,外的表象を媒介しない循環,すなわち,事前にメモを作成せずに行える支援が考えられる。本論文では,そのような支援の一例として,書き手が文章産出を行う際の方向性を示すことを提案した。今後は,方向性として提示すべき情報の詳細や情報の提示の方法についてさらなる検討が望まれる。
1 0 0 0 パラジウム触媒を用いた脱ニトロ型カップリング反応の開発
- 著者
- 淺原 光太郎 柏原 美勇斗 武藤 慶 中尾 佳亮 山口 潤一郎
- 出版者
- 公益社団法人 有機合成化学協会
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.1, pp.11-21, 2021-01-01 (Released:2021-01-09)
- 参考文献数
- 108
- 被引用文献数
- 1
Transition metal-catalyzed cross-coupling between aryl halides and nucleophiles is one of the most reliable C-C and C-heteroatom bond forming reactions. However, preparation of haloarenes usually requires multi-step operation, making the whole cross-coupling process inefficient. Nitroarenes, synthesized by a single-step nitration of arenes, can be attractive alternatives as electrophiles in cross-coupling methodology, but inherent inertness of C(sp2)-NO2 bonds toward metal catalysts has been a bottleneck of general denitrative transformations. Recently, we have overcome this obstacle and achieved direct activation of Ar-NO2 bonds by using Pd/BrettPhos catalysis. Herein, we describe the development of denitrative couplings by Pd/BrettPhos catalyst and its unique suitability from a mechanistic point of view. Deep understanding of reaction mechanism also enabled us to design more active Pd/NHC system.
1 0 0 0 OA 唐詩選画本
- 著者
- 芙蓉先生 画
- 出版者
- 小林新兵衛[ほか2名]
- 巻号頁・発行日
- vol.[2編巻1-5], 1790
- 著者
- 牧 裕夫
- 出版者
- 作新学院大学
- 雑誌
- 作大論集 (ISSN:21857415)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.137-149, 2017-03
<要約> 計画と実践的行為の関係について人工知能の研究者であるL.C.Suchmanは「計画を実践する行為はその都度的な即興的行為による」と指摘した。支援過程がこの即興的行為によるとすれば、職業リハビリテーション支援者が実践的行為の中で体験する「逐次的な相互作用」を余剰的な効果として位置づけることはできない。前研究で、牧は2つの事例からその「逐次的な相互作用」に基づき「学習の身体化」「ギブ・アンド・テイク関係」「希望の共有」等の制御要因を指摘した。本論では、これらの理論的背景として状況論アプローチの諸論が職業リハビリテーション支援をどのように拡張しえるのか、その方向性を示す。J.Gibsonのアフォーダンス理論から、実際に利用者を支援する実践的行為では「逐次的な相互作用」によるとし、学習を拡大するために、試行錯誤行為による過程が必要条件であることを指摘する。そこで、計画場面と実践場面では別な構造を有するシステムとして「既存(制度)システム」「個別(計画)システム」「現場(状況)システム」の3つのシステムを提示する。特に「現場(状況)システム」で試行錯誤による相互作用を拡張しえる理論的枠組みとして状況論アプローチであるJ.laveの「正統的周辺参加」、L.Vygotskyの「発達の最近接領域」と職業リハビリテーション支援の関連について検討した。
1 0 0 0 OA 歩行時間,睡眠時間,生きがいと高齢者の生命予後の関連に関するコホート研究
- 著者
- 関 奈緒
- 出版者
- The Japanese Society for Hygiene
- 雑誌
- 日本衛生学雑誌 (ISSN:00215082)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.535-540, 2001-07-15 (Released:2009-02-17)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 24 29
The purpose of this study was to determine lifestyle factors in the elderly that affected longevity, using a population-based prospective study. The participants were 440 men and 625 women aged 60 to 74 living in a rural Japanese community. The baseline data such as age, sex, present illness, walking hours per day, sleeping hours per day, alcohol consumption, a history of smoking, and “ikigai” (meaningfulness of life) were collected in July 1990. During 90 months of follow-up from July 1990 to December 31 1997, there were 123 deaths. By Cox's multivariate hazard model adjusted age, sex, and medical histories, walking≥1 hour/day (HR=0.63, 95% CI 0.44-0.91) and an “ikigai” (HR=0.66, 95% CI 0.44-0.99) lowered the risk for all-cause mortality independently. In regard to hours of sleep, the cumulative survival curve showed that 7 hours/day was the border and sleeping≥7 hours/day lowered the risk (HR=0.49 95% CI 0.33-0.74). Based on the findings in this study, walking≥1 hour/day, sleeping≥7 hours/day, and “ikigai” are important factors for longevity in the elderly.
- 著者
- Izumi Oh-e Kuniyuki Saitoh Toshiro Kuroda
- 出版者
- CROP SCIENCE SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- Plant Production Science (ISSN:1343943X)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.4, pp.412-422, 2007 (Released:2007-10-19)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 124
The effect of high temperatures on growth, yield and dry-matter production of rice growing in the paddy field was examined during the whole growth period in a temperature gradient chamber (TGC) from 2002 to 2006. Experimental plots, TG1 (control), TG2, TG3 and TG4, were arranged along the temperature gradient (from low to high temperature) in TGC. The mean and maximum air-temperatures in TG4 were 2.0-3.6°C and 4.0-7.0°C higher, respectively, than those in TG1. The plant height was taller and the maximum tillering stage was earlier in TG2, TG3 and TG4 than in TG1. Plant dry weight at maturity in TG2 and TG3 was 12.8-16.4% heavier than that in TG1. In TG4, the increase in the panicle dry weight during the ripening period was smallest and plant dry weight at maturity was 11-16% heavier than that in TG1. The increase in plant dry-matter during the ripening period was smallest in TG4. The decrease in the dry weight of stem and leaf during the ripening period, which represents the amount of assimilate translocation to the panicle, was also larger in TG2-4 than in TG1. The increase in the dry weight of stem in TG2-4 at maturity was also larger than that in TG1. The photosynthetic rate in TG2-4 was up to 35.6% lower than that in TG1 because of the acceleration of leaf senescence. Brown rice yield in TG4 was 6.6-39.1% lower than that in TG1. This yield decline was due to the decrease in the percentage of ripened grains and increase in the percentage of sterile spikelets. The relation between brown rice yield and mean air-temperature during 20 days after heading showed that the brown rice yield declined when mean air-temperature exceeded 28°C.
- 著者
- 宮本 聖二 アリアナ・ ドゥフゼル
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.2, pp.115-119, 2018
<p>太平洋戦争の直前から戦後にかけて映画館で上映されていたニュース映画、「日本ニュース」。1940年6月に上映が始まり、戦争が終結した1945年夏までは、戦争遂行と国家総動員のためのプロパガンダを目的に制作された国策映画である。軍官当局の検閲を受け、あるいはその指導のもとで制作されていた。現在、デジタルアーカイブ「NHK戦争証言アーカイブス」でこの間の現存するすべての「日本ニュース」を観ることができる[1]。</p><p>当時、人々が接していたメディアは、ほかにラジオや新聞、雑誌などもあり、ニュース映画はその一部でしかない。しかし、唯一の動画であり、映像の持つ独自の訴求力で人々の意識に強く働きかけたはずである。ここでは、1940年6月から太平洋戦争開戦までの18ヶ月間(毎週火曜日公開、第1号から79号まで)に「日本ニュース」が何をどのように伝えたのかを見つめ、人々が新たな戦争を受け入れるにあたってどのような役割を果たしたのかを考察する。</p>
1 0 0 0 OA 伝承物語の読み聞かせの意義
- 著者
- 篠原 京子
- 出版者
- 常葉大学保育学部
- 雑誌
- 常葉大学保育学部紀要 = Bulletin of Faculty of Education and Care of Early Childhood Tokoha University (ISSN:21883645)
- 巻号頁・発行日
- no.4, pp.99-109, 2017-03-31
- 著者
- 清野 克行
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経コミュニケーション (ISSN:09107215)
- 巻号頁・発行日
- no.475, pp.124-129, 2006-12-01
Ajax(エイジャックス)は,JavaScriptやXMLなどの技術を組み合わせ,Webブラウザとサーバー間を非同期で通信する仕組み。Webブラウザの操作性を高められ,業務効率を向上できるなどのメリットがある。Web上のさまざまな資源を取り込んだリッチなコンテンツの提供も可能になる。清野 克行HOWS(ハウズ) 企画開発部長せいの・かつゆき1973年慶應義塾大学工学部電気科卒。
- 著者
- 佐川 馨 Sagawa Kaoru
- 出版者
- 秋田大学教育文化学部
- 雑誌
- 秋田大学教育文化学部研究紀要 教育科学 (ISSN:13485288)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, pp.63-71, 2011-03-01
This paper takes up the two songs of the Prefecture-"Song of the People of Akita Prefecture" and "Song of the People of the Prefecture"一and aims, in its first part, to deal with the history leading up to the establishment of the 80-year-old "Song of the People of Akita Prefecture" in the back drop of the first half of the Showa Era(1926-1989), in an effort to clarify the relationship between the establishment of the prefectural songs and the development of education in the local area. The following is a summary of the results of this research.1. Between the time that words for the prefectural songs were elicited from the public for entry into competition and the time that decisions on the selection and establishment of the songs were made, there was only a short span of time, which was a rare case as a project by a municipality.2. Tokyo Music School, which was entrusted with the composition of the music for the songs, spent only 9 days from the receipt of the request to the selection and revision of words, to the composition of music and to the dispatch of its products.3. The words selected for the songs shared common features in that they all incorporated the nature, the industry and the history, along with the various achievements by forerunners in the area-which has traces of influence from "songs of geography and history."4. The governor of the prefecture at the time of the establishment of the prefectural songs was Hiroki Hiekata, whose previous job was the head of the Department of Internal Affairs at Kanagawa Prefectural Government and from this fact it is very likely that he arranged the establishment of the prefectural songs for Akita modeling after his pilot project of establishing a prefectural song for Kanagawa Prefecture.5. The local education in Akita Prefecture in the early years of the Showa Era owes a great deal to Michitoshi Odauchi, a native of Akita City, to say nothing of the prefecture's pioneer efforts of various kinds and thus, the "Song of the People of Akita Prefecture" was born out of the prefecture's policies toward education and enlightenment of its people as well as the successful development of education in the local community.
1 0 0 0 OA カロテノイドとヒト
- 著者
- 高市 真一
- 出版者
- 日本医科大学医学会
- 雑誌
- 日本医科大学医学会雑誌 (ISSN:13498975)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.4, pp.264-267, 2012 (Released:2012-12-28)
- 参考文献数
- 21
Phototrophic organisms including land plants, algae, and photosynthetic bacteria can synthesize carotenoids for photosynthesis. A part of bacteria and fungi also synthesize carotenoids. On the other hand, animals cannot synthesize carotenoids, and they ingest carotenoids from foods. Most animals can modify the carotenoids, such as oxidation and reduction. Humans contain usually six kinds of carotenoids: β-carotene, α-carotene, lycopene, β-cryptoxanthin, zeaxanthin, and lutein. Furthermore in this paper, functions of carotenoids in animals especially humans are briefly summarized: Carotenoids are essential for organisms living under oxygen to prevent active oxygen. β-Carotene is cleaved into retinal by β-carotene-15,15'-monooxygenase. Retinal is used as photoreceptor in eye. Lutein and zeaxanthin are accumulated in macula of eye for prevent blue light. From epidemiology, carotenoids in vegetables have anticancer activities. Lycopene might prevent prostatic cancer. Some carotenoids have also functions, such as antioxidant, anticancer, and anti-obesity.
1 0 0 0 OA 高校生の将来喫煙のリスクからみた特徴の分析 喫煙防止教育の検討に向けて
- 著者
- 大塚 敏子 荒木田 美香子 三上 洋
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.5, pp.366-380, 2010 (Released:2014-06-12)
- 参考文献数
- 56
目的 本研究は,学校教育における効果的な喫煙防止教育を検討するため,高校生を対象に現在の喫煙行動と将来の喫煙意思から将来喫煙者となるリスクを 3 群に分け,喫煙に対する認識,主観的規範,禁煙勧奨意欲など喫煙に関連する要因の特徴の違いを分析することを目的とした。方法 調査は便宜的に抽出された近畿 3 府県の 4 高等学校 1 年生747人(男子311人,女子436人)を対象とした。質問項目は,性別,喫煙行動,将来の喫煙意思,喫煙の勧めを断る自信,喫煙に関する知識,喫煙に対する認識,主観的規範意識,自尊感情,周囲の喫煙状況および禁煙勧奨意欲である。喫煙行動のリスク状況を把握するため現在および過去の喫煙行動と将来の喫煙意思により対象者を 3 群に分類し,各項目の得点の群間による差の検定を χ2 検定,一元配置分散分析および多重比較を用いて行った。結果 各質問項目の平均値は,ほとんどの項目でリスクが高い群ほど,喫煙を断る自信がない,喫煙に対する美化や効用を信じる気持ちが強い,主観的規範意識が低い,周囲に禁煙をすすめる意欲が低いというように好ましくない状況を示した。また,自尊感情以外のすべての項目で女子に比べて男子の方が好ましくないという傾向だった。さらに自尊感情以外の項目で低リスク群と高リスク群,低リスク群と中リスク群の間に有意な差がみられた一方,喫煙に関する知識と禁煙勧奨意欲の項目で中リスク群と高リスク群間に有意な差がなかった。結論 喫煙行動の中リスク群は非喫煙者ではあるが,喫煙に関する知識や禁煙勧奨意欲などの項目で,既に喫煙を開始している高リスク群に近い傾向を持っていることが示唆された。高等学校で行われる集団的な喫煙防止教育ではこれら全体の 2 割を占める中リスク群の特徴を考慮した教育内容が必要であると考えられる。
1 0 0 0 低電圧駆動(逆ねじれTN)液晶における安定性
- 著者
- 西立野 将史 高頭 孝毅 穐本 光弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本液晶学会
- 雑誌
- 日本液晶学会討論会講演予稿集 (ISSN:18803490)
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp.153, 2009
本研究室において、液晶材料の螺旋ピッチの方向が従来のTN液晶に対して逆であるリバースツイステッドネマティック(RTN)方式の液晶を開発した。RTN液晶は電圧無印加状態ではスプレイツイスト構造に変化していくが、液晶材料の違いによりある程度安定に存在する事を確認した。RTN液晶の安定性を定量的に測定し、各パラメータと安定性の相関関係を検討した。液晶材料のK<SUB>22</SUB>が大きくK<SUB>33</SUB>が小さいほどRT構造を安定に保持できていた。
1 0 0 0 IR 文教大学越谷図書館における学外開放
- 著者
- 藤倉 恵一
- 出版者
- 大学図書館研究編集委員会
- 雑誌
- 大学図書館研究 (ISSN:03860507)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, pp.21-31, 2006
<p>文教大学越谷図書館は1981年10月の新図書館開館を機に,学外者に図書館を開放している。当時は画期的・先進的なことであったが,20年以上が経過して大学図書館の学外開放が一般的になったいま,あらためてサービス展開の経緯と現状,意義と課題についてまとめる。また,同図書館内で運営されている小学校中学年以下の子どもを対象にした児童文庫「あいのみ文庫」も開設以来盛況を保っているが,これについてもあわせて紹介する。</p>
1 0 0 0 OA 茶樹の実生系品種についての考察
- 著者
- 鳥屋 尾忠之
- 出版者
- Japanese Society of Tea Science and Technology
- 雑誌
- 茶業研究報告 (ISSN:03666190)
- 巻号頁・発行日
- vol.1964, no.21, pp.1-6, 1964-01-25 (Released:2009-12-03)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 長谷部 浩史 竹内 清文 高津 晴義
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- テレビジョン学会技術報告 (ISSN:03864227)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.62, pp.25-30, 1994
室温においてネマチック相を示すUVキュアラブル液晶を配向させた状態で、紫外線を照射することにより光重合させて光学異方性高分子を作製した。得られた光学異方性高分子は液晶骨格の配向を維持しており、しかも耐熱性にもすぐれていることがわかった。また、液晶の配向技術を適用することにより、内部にスーパーツイステットネマチック構造、ハイブリッド構造、ホメオトロピック構造を有する光学異方性高分子や場所ごとにリタデーションを制御した光学異方性高分子を作製することができた。これらの光学異方性高分子は、液晶表示素子の光学補償や視角依存性の改善に有用であると考えられる。