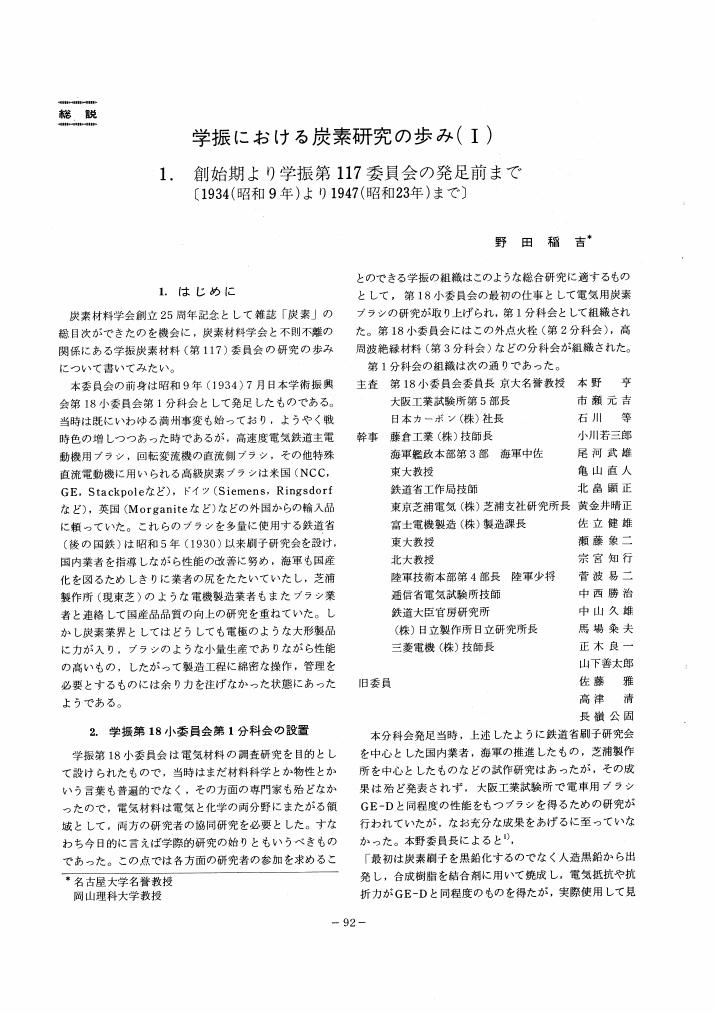1 0 0 0 IR 平成24年南空知豪雪による農業雪害とリスク評価
- 著者
- 井上 聡 廣田 知良 濱嵜 孝弘 根本 学
- 出版者
- 北海道農業研究センター
- 雑誌
- 北海道農業研究センター研究報告 = Research bulletin of the National Agricultural Research Center for Hokkaido Region (ISSN:13478117)
- 巻号頁・発行日
- no.203, pp.15-21, 2014-10
2011年から2012年にかけて豪雪が発生し,積雪調査の結果,南空知地方に集中したことが明らかになった。岩見沢での最深積雪(208cm)や長期積雪期間(163日)は,気象庁統計史上最大であった。重回帰分析の結果,冬型と低温が要因として説明できた。農業雪害として,積雪深がハウス骨組みの肩を超え,沈降力により倒壊被害が多数生じた。今回の積雪深の再現期間は73年になり,肩(145cm)を超える再現期間は4年であった。長期積雪期間の再現期間は83年になり,9月多雨の影響もあり,秋まき小麦の雪腐病被害が甚大となった。消雪日は4月25日と最も遅くなった(再現期間42年)が,生育遅れはその後回復した。
1 0 0 0 OA Narandasmrtiにおける司法総則
- 著者
- 佐々木 雄太
- 出版者
- 印度学宗教学会
- 雑誌
- 論集 = RONSHU (ISSN:09162658)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, 2018-12-31
1 0 0 0 OA 心理統計教育のためのテスト項目データベースの構築と運用
1 0 0 0 OA マレーシアにおける大学生の食生活・飲料摂取の現状 ─アンケート調査の結果から─
- 著者
- 戸張 千夏 高増 雅子
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.79, no.2, pp.76-89, 2021-04-01 (Released:2021-05-15)
- 参考文献数
- 28
【目的】本研究では,マレーシアにおける大学生の食生活や飲料摂取状況の現状を把握し,その特徴について明らかにすることを目的とした。【方法】マレー半島のトレンガヌ州にあるマラ工科大学ドゥングン校,スランゴール州にあるマラ工科大学プンチャックアラム校の学生632名を対象とし,2019年3月~4月に食生活調査及び飲料摂取調査を実施した。食生活調査について,アンケート回答をスコア化し,群間の差(男女間,大学間)にはMann-Whitney のU検定を用いた。飲料摂取調査については,項目ごとに結果を集計し,χ2検定を行った。【結果】食生活調査では,対象者全体で,運動と健康との関わりや食生活の大切さについては理解しているが,砂糖摂取量に関する知識は乏しいことが分かった。砂糖摂取に関するセルフ・エフィカシーが低い傾向がみられた。また,朝食の欠食が昼食や夕食よりも多かった。女性は,砂糖摂取についての意識や栄養教育ワークショップへの関心も高く,男性は,運動について興味を持ち積極的に行っている傾向がみられた。飲料摂取調査では対象者全体で,水の摂取頻度が高かった。また,紅茶(コンデンスミルク入り,砂糖入り),麦芽飲料などのsugar-sweetened beverage(SSB)の摂取頻度が高い一方で,砂糖なしの紅茶やコーヒーの摂取頻度が低かった。女性は,男性より砂糖なしの飲料の摂取頻度が低かった。【結論】対象大学生における砂糖摂取量及びSSBの摂取頻度に係る課題が明らかになった。
1 0 0 0 OA <論説>「静岡本名裁判」と在日韓国朝鮮人社会
- 著者
- 柳 赫秀
- 出版者
- 横浜法学会
- 雑誌
- 横浜法学 (ISSN:21881766)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2-3, pp.1-27, 2016-03-25
- 著者
- 小国 七慧
- 出版者
- 国学院大学大学院
- 雑誌
- 国学院大学大学院紀要. 文学研究科 = Journal of the Graduate School, Kokugakuin University (ISSN:03889629)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.99-118, 2019
- 著者
- 小国 七慧
- 出版者
- 國學院大學博物館学研究室
- 雑誌
- 國學院大學博物館學紀要 = Bulletin of museology, Kokugakuin University (ISSN:02865831)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.37-52, 2020
- 著者
- 小国 七慧
- 出版者
- 國學院大學博物館学研究室
- 雑誌
- 國學院大學博物館學紀要 = Bulletin of museology, Kokugakuin University (ISSN:02865831)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, pp.59-70, 2019
1 0 0 0 IR 全国文学館協議会設置後の文学館研究における文学館機能論の問題点について
- 著者
- 小国 七慧
- 出版者
- 國學院大學大学院
- 雑誌
- 國學院大學大学院紀要 : 文学研究科 (ISSN:03889629)
- 巻号頁・発行日
- no.51, pp.99-118, 2020-02
1 0 0 0 OA ISO14001における審査機関と有効性審査
- 著者
- 美濃 英雄 丸谷 一耕 中村 修
- 出版者
- 長崎大学 環境科学部
- 雑誌
- 長崎大学総合環境研究 = Journal of Environmental Studies (ISSN:13446258)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.15-20, 2010-10
The Certification Board is functioning for diffusion of ISO14001 that is a part of the environmental management system. Recently, the Certification Board is shifting from the conventional conformity audit to the effectiveness audit. Therefore, the definition of the effectiveness audit and the reality were investigated.
- 著者
- 安木 真世 黒田 真未 井 千尋
- 出版者
- 一般社団法人 室内環境学会
- 雑誌
- 室内環境 (ISSN:18820395)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.13-18, 2021 (Released:2021-04-01)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 2
世界的流行が続く新型コロナウイルス感染症の原因ウイルスSARS-CoV-2の不活化技術として, アルコールや界面活性剤に加え, オゾン水の有効性が報告された。有機物の存在はオゾンの分解を速めて有効オゾン濃度の減衰を招くことが知られており, ウイルスが存在し得る様々な環境を想定してオゾン水の有効性を評価すること, 更には様々な環境に応じてオゾン水の使用条件を設定することが重要な課題である。本研究ではこれら課題のための基盤実験として, 有機物の影響を抑えた(ウイルス培養液の溶媒をリン酸緩衝液に置換した)条件におけるSARS-CoV-2に対するオゾン水の不活化効果を評価した。その結果, (1)タンパク質濃度3.3 μg/mlのウイルス溶液では, 0.1 mg/l濃度のオゾン水の30秒間曝露で生残ウイルス量が1000分の1に, (2)タンパク質濃度33 μg/mlのウイルス溶液では, 0.5 mg/l濃度のオゾン水の3分間曝露で生残ウイルス量が10分の1に減少し, 低濃度のオゾン水がSARS-CoV-2を有意に不活化することが明らかとなった。
1 0 0 0 OA 患者給食の法制上の限界
- 著者
- 冨樫 仁美
- 出版者
- 日本外科代謝栄養学会
- 雑誌
- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.70-73, 2021-04-15 (Released:2021-05-15)
- 参考文献数
- 4
外科治療の進歩とともに栄養療法も進歩し, 手術の成功率の向上や術後合併症の減少を可能にしてきた. 栄養療法の基本は腸を使うことであり, 栄養補給法の第一選択は経口栄養法となる. しかし, 経口栄養法である患者給食を提供するにあたっては食材費, 目標栄養量, 衛生管理などの観点から規制があり, 患者のニーズに合わせた食事提供には限界を感じることもある. 入院患者にとって, 食事は唯一の楽しみであり, ‘食べる’という当たり前だと思っていた行為ができないときに,楽しみは苦痛になりかねない. さまざまな規制はあるものの経口栄養の基本である患者給食は, 患者が食べる喜びを得られる形で提供されるべきである. われわれ管理栄養士がなお一層の努力をするとともに, この現状を他職種の医療関係者にもご理解いただくことが, より良い患者給食の提供につながると信じている.
1 0 0 0 OA 周術期栄養管理のツールとしての患者給食と栄養状態
- 著者
- 前田 恵理 鍋谷 圭宏 河津 絢子 金塚 浩子 實方 由美 高橋 直樹 若松 貞子
- 出版者
- 日本外科代謝栄養学会
- 雑誌
- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.62-69, 2021-04-15 (Released:2021-05-15)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
外科とくに消化器外科周術期栄養管理の重要性は論を待たないが, その一環として給食の意義が論じられることは少ない. わが国ではかつて, 流動食から全粥までの段階食で外科医ごとに異なる術後管理が一般的であった. その後, 施設・術式ごとのクリニカルパスが普及し, 主に段階食で画一化された術後管理が行われるようになった. 最近は, 術後早期回復プログラムに則り術後早期経口摂取再開と早期退院を目指すクリニカルパス管理が増えているが, 実際の給食摂取状況や栄養状態などアウトカムの評価は少ない. 一方で, 患者の希望も考慮した術後食の個別化管理で, 栄養摂取増加や体重減少抑制などの有効性が報告されている. 今後は, 食事再開日, 段階食の必要性, 食形態, 提供量を患者ごとに考慮したアウトカム指向の個別化給食管理を念頭におき, 「栄養源として食べてもらえる」給食の考案と環境整備が望まれる. 適切な患者給食からの栄養摂取は患者の満足感や回復意欲の励起にも繋がると思われるが, 一方で栄養源としての限界も理解する必要があり, 癌患者の予後に影響するような栄養状態の低下を招かないように適時適切な経腸栄養・静脈栄養の併用を忘れてはならない.
1 0 0 0 OA 外科患者の栄養管理における給食の意義 ―本邦と世界の潮流―
- 著者
- 丸山 道生
- 出版者
- 日本外科代謝栄養学会
- 雑誌
- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.57-61, 2021-04-15 (Released:2021-05-15)
- 参考文献数
- 11
世界各国には, それぞれの国や地域の食文化を反映した独自の病院給食と術後食のシステムがある. 最近まで術後食に関して「手術後, 消化管運動が回復してから, 流動食から開始し, 段階的に普通食にステップアップしていく」というのが世界共通の考え方であった. 近年, 手術の安全性が増し, 低侵襲化されたことで, 従来の術後食を見直す動きが広がっている. 特に, 術後回復強化策ERASが種々の手術に普及することで, 術後早期の経口栄養と段階食の見直しが行われている. 今後, 術後栄養管理は経口栄養が主流となっていくと推測され, 術後食がさらに重要視されると考えられる. 術後給食の科学的, 臨床的検討と改善が望まれる.
1 0 0 0 OA 外科治療におけるミールラウンドの意義
- 著者
- 杉山 みち子 松本 奈々 高田 健人 深柄 和彦
- 出版者
- 日本外科代謝栄養学会
- 雑誌
- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.74-77, 2021-04-15 (Released:2021-05-15)
- 参考文献数
- 18
1 0 0 0 OA 患者給食の今後
- 著者
- 伊地知 秀明
- 出版者
- 日本外科代謝栄養学会
- 雑誌
- 外科と代謝・栄養 (ISSN:03895564)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.84-88, 2021-04-15 (Released:2021-05-15)
- 参考文献数
- 4
患者給食は, 入院診療の一部であり, その喫食により栄養状態を保つことが治療効果に影響するため, 喫食率を上げることの重要性を患者も医療者側も意識することが重要である. すなわち, 病院食は単なる楽しみではないのであるが, しかし, 患者に病院食を楽しんで食べてもらえれば喫食率が上がり, それは治療効果に繋がることが期待される. 現行の病院食には衛生基準に加え, 栄養素バランスの基準の遵守が求められているが, それは健康人を対象とした基準であり, 患者に対しては喫食率が上がるようにフレキシブルな対応も考慮されるのではないか. 病院給食は多職種のチーム医療であり, 献立検討・喫食率向上・患者満足度向上へ向けて全院で取り組んでいくことが重要と思われる. また入院時食事療養費の引き上げも病院給食の安定した運営のためには必要と考える.
1 0 0 0 OA 楕円接触のヘルツ応力の計算について
- 著者
- 田中 直行
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会論文集 C編 (ISSN:03875024)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.638, pp.4213-4215, 1999-10-25 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1 1
In the new method of calculating elliptical Hertz contact pressure described here, an elliptic integral is not necessary. Even the simplest numerical integration yields a Hertz contact pressure within 0.005% of the theoretical spherical contact pressure. Dimensionless parameters calculated using this method agreed well with the values given in the references. Elliptical Hertz contact pressure can thus now be calculated using a spreadsheet program for personal computers.
1 0 0 0 OA 水素ガスの放射線防護効果
- 著者
- 古谷 真衣子 小野 哲也 小村 潤一郎 上原 芳彦 地元 佑輔 仲田 栄子 高井 良尋 大澤 郁朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本放射線影響学会
- 雑誌
- 日本放射線影響学会大会講演要旨集 日本放射線影響学会第53回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.310, 2010 (Released:2010-12-01)
放射線はさまざまなラジカルを生成させるが、その中でも細胞障害の主な原因となるのは水の分解に伴うOHラジカルであることが知られ、しかもそれはSH剤によって捕獲されることが分かっている。他方、最近細胞内で生じるさまざまな活性酸素のうちOHラジカルだけが水素分子によって特異的に除去されることが示されている(Nature Med 13 (6) 688-694 (2007))。そこで我々はこの水素分子が放射線障害を軽減化する活性がないかどうかについて検討してみた。 [材料と方法] 8週齢のC57BL/6J、雌マウスを用いて2%の水素ガスを1時間吸わせた後同じ水素ガス存在下で8Gy及び12GyのX線全身照射を行い生存日数を調べた。X線は0.72Gy/minの線量率。また水素ガスに1時間曝露後普通の空気吸引にもどし、1時間あるいは6時間経た後で放射線を照射し、生存率を調べた。 [結果と考察] 水素ガス投与によって8Gy照射後の平均生存日数は10日から17日へと有意に増加し(p=0.0010)、12Gy照射でも増加傾向がみられた。これらは骨髄幹細胞や腸のクリプト幹細胞に対し水素ガスが防護効果を持つことを示している。さらに水素ガス吸引の効果は吸引を止めた後1時間及び6時間後では明白に減弱していることも分かった。 これらの結果は水素ガスが新しい放射線防護剤として有用であることを示唆すると同時に、水素分子がOHラジカルと反応し得ることも示唆するものである。 現在、水素ガスの効果が細胞レベル、DNAレベルでも観察されるものかどうかについて検討している。