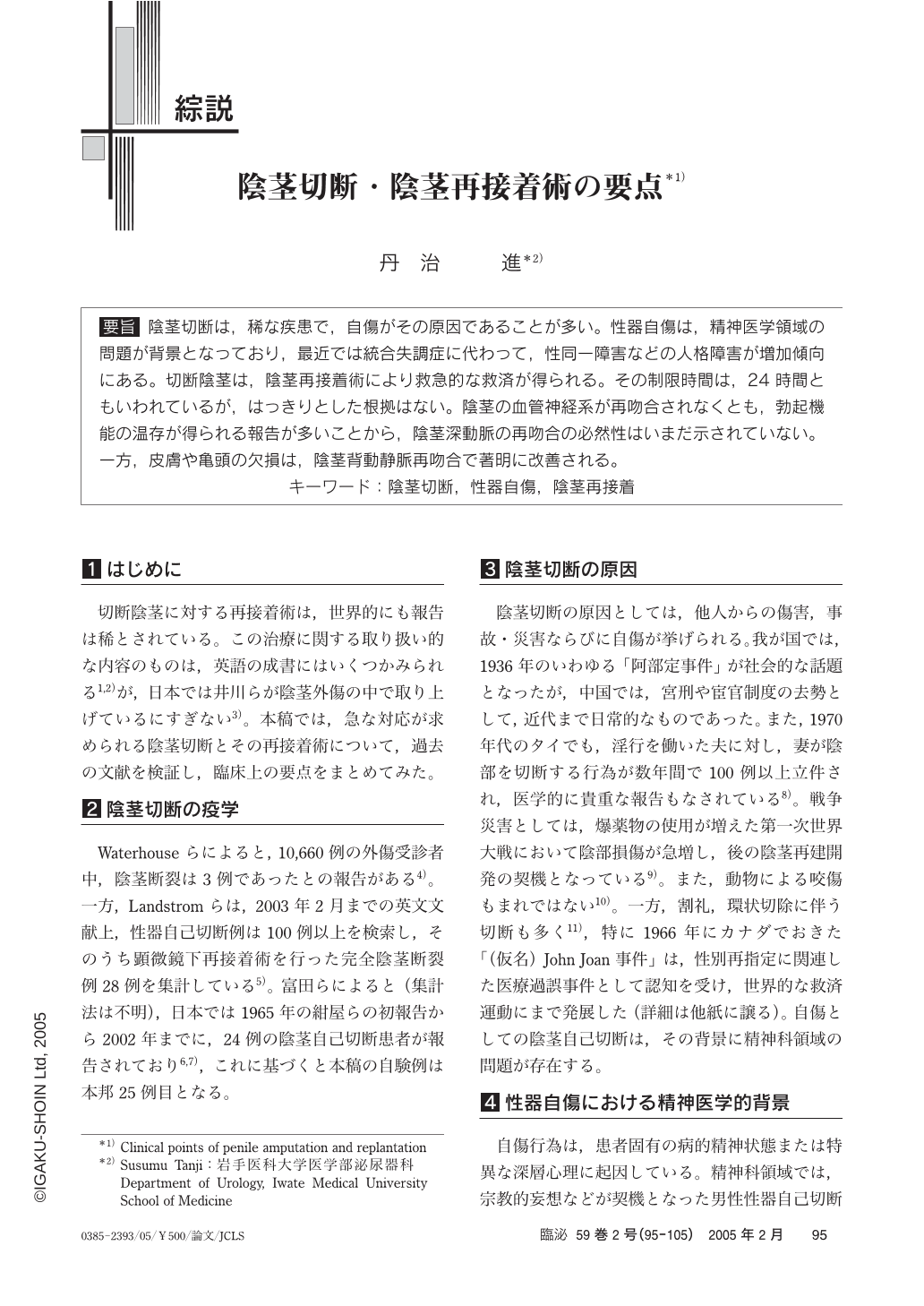1 0 0 0 OA 地域在住高齢者の胸椎アライメントおよび胸椎の可動域と胸郭可動性の関係
- 著者
- 坂本 梨花 羽﨑 完
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.40 Suppl. No.2 (第48回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.48100785, 2013 (Released:2013-06-20)
【はじめに、目的】呼吸は,胸郭の運動によって可能となり,胸郭の運動は肋骨の運動によって可能となる。肋骨は,肋椎関節で脊柱と連結されている。したがって,呼吸には脊柱の運動も関係していると考えられる。実際,脊柱を屈曲させると肋間隙が狭小し,脊柱を伸展させると肋間隙が拡大することが知られている。一方,加齢により身体機能は低下するが,脊柱では可動域制限が起こる。また一般に高齢者では呼吸機能が低下している。我々はこれまで,高齢者の最大呼気・最大吸気時の胸椎の変位量と呼吸筋力の関係を検討し,高齢者は,呼吸筋力,特に呼気筋力の低下の代償として胸椎を過剰に屈曲させることを明らかにしてきた。本研究の目的は,高齢者の安静時の胸椎アライメントおよび胸椎の可動域と胸郭可動性の関係を検討することである。【方法】高齢女性19 名,平均年齢80.1 ± 5.9 歳を対象とした。平均身長は150.4 ± 4.0cm ,平均体重は49.4 ± 8.5kgであった。また,対象者は独歩可能な高齢者であり,脊柱に痛みがなく,呼吸器に疾患を持たないものとした。胸椎アライメントの測定は,体表面上より脊椎の各椎体間の角度を測定できるスパイナルマウスを使用して行った。被験者に背もたれの無い椅子に楽な姿勢で座らせ,安静時・最大屈曲時・最大伸展時の脊柱アライメントを測定した。胸郭の可動性の測定は,メジャーを使用して行った。被験者に背もたれの無い椅子に楽な姿勢で座らせ,安静時・最大呼気時・最大吸気時の腋窩部胸郭周径(以下,上部),剣状突起部胸郭周径(以下,下部)を測定した。解析は,胸椎の可動域では,胸椎屈曲可動域(最大屈曲−安静時),最大伸展可動域(最大伸展時−安静時)を算出した。胸郭可動性については,最大呼気時から最大吸気時までの変位量(以下,最大胸郭可動性)・安静時から最大呼気時までの変位量(以下,最大呼気時の胸郭可動性)・安静時から最大吸気時までの変位量(以下,最大吸気時の胸郭可動性)を算出した。そして,安静時の胸椎アライメントおよび胸椎の可動域と胸郭可動性の相関係数をスピアマンの順位相関にて求め検討した。【倫理的配慮、説明と同意】各被験者には本実験を行う前に本研究の趣旨を文章ならびに口頭で十分に説明した上で,研究参加の同意を得た。【結果】胸椎屈曲可動域は平均17.56 ± 10.55°,胸椎伸展可動域は平均10.68 ± 7.26°であった。上部の最大呼気時の胸郭可動性は平均-0.158 ± 0.46cm,最大吸気時の胸郭可動性は平均1.579 ± 0.67 cmであった。下部の最大呼気時の胸郭可動性は平均-0.395 ± 0.55 cm,最大吸気時の胸郭可動性は平均1.342 ± 0.78 cmであった。安静時の胸椎アライメントと上部の最大胸郭可動性では-0.595(p>0.01)の有意な負の相関が認められた。安静時の胸椎アライメントと下部の最大胸郭可動性では-0.326 で有意な相関は認められなかった。胸椎の最大屈曲可動域と上部の最大胸郭可動性では0.1181,下部の最大胸郭可動性とでは-0.079 で相関は認められなかった。胸椎の最大伸展可動域と上部の最大胸郭可動性では0.105,下部の最大胸郭可動性とでは-0.113 で有意な相関は認められなかった。【考察】胸郭可動性から,高齢者では最大呼気時に上部および下部胸郭共にほとんど動かしていないことがわかった。つまり高齢者では,呼気時に十分に肋骨を下制できていないと言える。胸椎の安静時アライメントと上部の最大胸郭可動性で有意な負の相関関係が認められた。(p<0.01)これは,胸椎が安静時に後弯しているほど,上部の胸郭の動きが制限されることを示している。胸椎が屈曲位になると肋骨は上下方から集束が起こり肋間隙は狭小化する。その肋骨が狭小化された状態で肋骨を挙上しようとしても,肋骨が動ける範囲は小さくなるためこのような結果となったと考えた。一方,下部の最大胸郭可動性では相関が見られなかったのは,下部肋骨は浮肋であることや,上部肋骨では2 つの椎体と関節をなすが下部では単独の椎体と関節をなし,下部の肋椎関節は平面で横の位置で高さを変えるので胸椎後弯の影響を受けにくいのではないかと考える。胸椎の可動域と胸郭の変位量ではいずれも相関が認められなかった。このことから,安静時の胸椎弯曲状態が胸郭の動きに関係していることがわかった。【理学療法学研究としての意義】今回明らかになった高齢者の安静時の胸椎アライメントおよび可動域と胸郭可動性の関係は,高齢者に対する胸郭可動域改善のためには胸郭だけにアプローチするのではなく胸椎に対してもアプローチすることが重要であることがわかった。
1 0 0 0 OA 重量衝撃源の変化による床衝撃音レベルの互換性に関する検討
- 著者
- 鹿倉 潤二 井上 勝夫 天川 恭一 大川 周一郎 大川 平一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.53, pp.171-176, 2017 (Released:2017-02-20)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 2
The car tire and the rubber ball are standard impact sources to measuring floor impact sound. Both impact sources have same impact time, but different frequency characteristics. Purpose of this paper is to examine the correlation of two impact sources by comparing with frequencies in each floor impact sounds, and clarify the compatibility of two impact sources. We found that both floor impact sounds are correlated with octave frequency of 63Hz and under, uncorrelated with 125Hz and over. Therefore, we can make equivalent evaluation of heavy weight floor impact sound at 63Hz band.
1 0 0 0 OA アパレルセレクトショップにおける店員顧客間の同調傾向の研究
- 著者
- 辰巳 槙
- 巻号頁・発行日
- 2012-03
Supervisor:永井由佳里
1 0 0 0 OA 治療を受けながら生活する血液がん患者の情報ニーズ
- 著者
- 久保 江里 大川 百合子
- 出版者
- 宮崎大学医学部看護学科
- 雑誌
- 南九州看護研究誌 = The South Kyusyu Journal of Nursing (ISSN:21898995)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.27-35, 2020-03
本研究の目的は、治療を継続する血液がん患者が入院中から退院後の生活の中でセルフケア能力を発揮するための情報ニーズを明らかにすることであった。血液がんに対する2 クール以上の化学療法を終了し、一時退院し自宅での生活経験のある患者10 名を対象に半構造化面接を行った。面接で得られたデータを内容分析した結果、患者は治療過程において病気とともに「生きる」ニーズをもち、『「生きる」を実感したい』『「生きる」ための方略を探求する』の2つに分類された。 治療を継続しながら生活する血液がんの患者は、これらのニーズに対応するために【どうにかして食べるための情報】【可能な限り体を動かすための情報】【ピアサポートについての情報】【自分の治療についてのタイムリーな情報】【病気と付き合いながらの生活に関する情報】【自分のデータを理解するための情報】【自分の状況を見極めた服薬についての情報】【病気・治療そのものについての情報】を求めていることが明らかになった。
1 0 0 0 OA がん医療における患者-医師間のコミュニケーションに関する研究 :博士(人間科学)学位論文
- 著者
- 藤森 麻衣子
- 出版者
- Waseda University
- 巻号頁・発行日
- 2005-01
制度:新 ; 文部省報告番号:甲1975号 ; 学位の種類:博士(人間科学) ; 授与年月日:2005/1/26 ; 早大学位記番号:新3902
1 0 0 0 OA 腱板断裂に対する鏡視下腱板修復術の治療成績
- 著者
- 廣瀬 聰明 野中 伸介 上野 栄和 木村 重治 吉本 正太 道家 孝幸 杉 憲 岡村 健司
- 出版者
- 日本肩関節学会
- 雑誌
- 肩関節 (ISSN:09104461)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.3, pp.883-887, 2011 (Released:2011-12-21)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 4
We performed arthroscopic rotator cuff repair (ARCR) for all rotator cuff tears. The purpose of this study was to evaluate the clinical results of ARCR using double-row technique. We retrospectively studied 64 patients (65 shoulders) who had received ARCR using double-row technique and who were followed up for more than 2 years. The patients were 30 males and 35 females. The mean age at operation was 65 years old (range, 44-86). The mean postoperative follow-up period was 25 months (range, 24-36). The clinical results were assessed using JOA scores and MRI by Sugaya's classification. Tear size was small tear in 9 shoulders, medium in 36, large in 12, and massive in 8. The mean JOA total score was significantly improved from 66 points preoperatively to 96 points postoperatively. Postoperative MRIs showed 20% re-torn cuff in all cases, especially, 40% in large and massive tears. In 45 shoulders which had MRI taken regularly, re-tear by MRI was revealed within 3weeks: none, at 3 months: 4 shoulders, at 6 months: 1shoulder, at 1 year: 4 shoulders, and 2 years: none. In this study, the clinical results of ARCR using double-row technique was mostly satisfactory. But JOA score in no tear group (97points) was better than re-tear group (92points). So we have to consider the methods to prevent re-tear after ARCR.
1 0 0 0 OA 化学組成から見た層状チャートの堆積環境について : 堆積
- 著者
- 松本 良 飯島 東
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 第88年学術大会(1981東京) (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.249, 1981-04-01 (Released:2017-10-06)
1 0 0 0 付加体層状チャート-化学組成からのアプローチ-
- 著者
- 堀 利栄 藤木 徹 樋口 靖
- 出版者
- 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学論集 (ISSN:03858545)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.43-59, 2000-01-21
- 参考文献数
- 74
- 被引用文献数
- 3
付加体中に頻繁に含有される層状チャートの化学組成や同位体比は, チャートが堆積した場の環境や続成過程, また過去の大陸表面の化学組成や付加後のテクトニックなイベントを反映している.本論では層状チャートの化学組成や同位体比の解析例を示し, その問題点や将来性について議論した.REEやいくつかの主成分元素組成は, 層状チャートの珪質部と泥質部が濃度の差こそあれ同起源物質を含有していることを示しており, 珪質部は泥質部がSiO_2で希釈された部分とみなされる.さらに珪質部は, Sr同位体比による解析の結果, より初生的な情報を保持し易いことが示唆された.特に堆積場の酸化・還元状態は, 珪質部における一部の元素組成やS同位体比を用いることで解析可能であり, その一例としてFe^<2+>, Fe^<3+>の量比, AlやTi濃度で規格したMn, U, V比やS含有量をあげた.このような付加体堆積岩の環境解析において欠けてならない点は, 地球科学的な制約条件との整合性であり, 地球化学だけでなく他分野との総合的な議論が必要である.
1 0 0 0 OA 犬山市のまちづくりの研究(一) : 歴史的・文化的遺産を活かしたまちづくり
- 著者
- 鈴木 常夫
- 出版者
- 愛知淑徳大学現代社会学部
- 雑誌
- 愛知淑徳大学論集. 現代社会学部・現代社会研究科篇 (ISSN:18811922)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.123-135, 2007-03-03
1 0 0 0 OA 日本の母親のあいまいな養育態度と4歳の子どもの他者理解 : 日米比較からの検討
- 著者
- 風間 みどり 平林 秀美 唐澤 真弓 Twila Tardif Sheryl Olson
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.126-138, 2013-06-20 (Released:2017-07-28)
本研究では,日本の母親のあいまいな養育態度と4歳の子どもの他者理解との関連について,日米比較から検討した。あいまいな養育態度とは,親が子どもに対して一時的に言語による指示を控えたり,親の意図が子どもに明確には伝わりにくいと考えられる態度である。日本の幼児とその母親105組,米国の幼児とその母親58組を対象に,幼児には心の理論,他者感情理解,実行機能抑制制御,言語課題の実験を実施,母親には養育態度についてSOMAを用い質問紙調査を実施した。日本の母親はアメリカの母親に比べて,あいまいな養育態度の頻度が高いことが示された。子どもの月齢と言語能力,母親の学歴,SOMAの他の4変数を統制して偏相関を算出すると,日本では,母親のあいまいな養育態度と,子どもの心の理論及び他者感情理解の成績との間には負の相関,励ます養育態度と,子どもの心の理論の成績との間には正の相関が見られた。一方アメリカでは,母親の養育態度と子どもの他者理解との間に関連が見られなかった。子どもの実行機能抑制制御については,日米とも,母親の5つの養育態度との間に関連が見出されなかった。これらの結果から,日本の母親が,子どもが理解できる視点や言葉による明確な働きかけが少ないあいまいな養育態度をとることは,4歳の子どもの他者理解の発達を促進し難い可能性があると示唆された。
- 著者
- 佐中 孜
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3, pp.109-114, 2011 (Released:2011-07-12)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1 1
CKD(Chronic Kidney Disease;慢性腎臓病)治療には(1)CKDの原因となる腎臓病(原疾患)治療,(2)食事療法,(3)アンジオテンシンII受容体拮抗薬,(アンジオテンシン変換酵素阻害薬,(4)経口吸着薬,(5)合併症治療(虚血性心疾患,高血圧,脂質代謝異常症(高脂血症),貧血など)による集学的治療など5つの基本戦略がある. これらのうち,食事療法のもつ意義は次のようにまとめられる。 1 生活習慣が関与している場合は,これを是正することにより原疾患の治療につながる。 2 たんぱく質の過剰摂取はたんぱく尿の悪化を招くので,その是正が必要である。 3 食塩の過剰摂取は高血圧,動脈硬化,更には糸球体細動脈硬化の原因になるので,食塩の過剰摂取の是正は不可欠となる。 4 糸球体に続く尿細管で起きている有機酸の過剰負荷をとることはCKDの進展抑制をもたらす。 5 アンモニア,リンの体内蓄積を抑制するための食事療法は有用と期待される。 6 CKDにおける鉄欠乏性貧血,ビタミンB12,葉酸欠乏による貧血を治療することにより,進展を阻止することが期待される。 7 高尿酸血症を伴うCKDにはプリン体の摂取の適正化が必要である。 8 脂質代謝異常症(高脂血症)も悪化要因になるので,食事療法は不可欠となる。
1 0 0 0 IR 言霊の在り処 : 言霊と和歌との関係性をめぐって
- 著者
- 樋口 達郎 Higuchi Tatsuro
- 出版者
- 求真会
- 雑誌
- 求真 (ISSN:18837123)
- 巻号頁・発行日
- no.22, pp.1-10, 2016
フェミニズムを「現代市民社会論」の一環としてとらえ直すことを通じて、女性や家族をめぐる様々な問題を検討し、同時にポスト近代における新たな政治のあり方について研究を進めた。具体的には、以下の三つの観点から共同研究およびそれらの統合を行った。<1 基礎的研究>昨年度に続き、法学・政治学・現代正義論・政治思想史・法思想史・文学の各分野において,女性がどのように位置づけられてきたかを検討した。そこでは、多くの分野において女性をめぐる様々な問題が充分に検討されずに、理論的にも死角となってきていたことが明らかになった。この死角を埋めるべく、市民論・権利論などの視角から、女性や家族をめぐる問題を法や政治に取り込むためことを目指して研究を進めた。その過程で、女性や家族をめぐる諸問題は、それ自体として検討することは言うまでもなく、国際化と多文化主義の流れのなかで他のマイノリティーがかかえる問題とも関連させた上で、理論化すべきであることが強く意識されるに至った。<2 応用的研究>女性の政治参加のあり方・社会保障制度における女性の位置・差別と女性の問題・韓国の婚姻制度における諸問題・多文化主義と国家の中立性などの観点から、具体的な問題をとりあげ、既存の制度がかかえる問題点を明らかにするとともに、現代により相応しい制度のあり方の設計をも射程に入れた研究を行った。その過程で、個別の制度の検討・評価だけではなく、国際比較や比較法的研究や、例えば社会保障制度と民事的な扶養責任の関係などこれまで別の領域と見なされてきた問題・制度の間での比較・検討など、より多角的な研究が必要であることが痛感された。<3 研究の統合>今年度は,助成額が少額であったため、札幌・東京・名古屋を相互に訪問するなどの研究交流や、研究代表者・研究分担者が一堂に会しての研究会等は行えなかった。従って、情報の交換・各自の研究の統合は専らインターネット等を介してのものとなった。
1 0 0 0 陰茎切断・陰茎再接着術の要点
1 0 0 0 在日外国人の保健医療
- 著者
- 李 節子
- 出版者
- 日本国際保健医療学会
- 雑誌
- 国際保健医療 (ISSN:09176543)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.7-12, 2004
- 被引用文献数
- 1
在日外国人の健康問題, 保健医療課題を明らかにすることを目的して, 外国人人口統計・人口動態統計を分析した。以下のことが明らかとなった。<br>・1980年代後半から在日外国人人口, 国際婚姻が急増し, 日本における多民族化が進んでいた。<br>・日系ブラジル人人口は, 20歳代から30歳代の生産年齢人口に集中し, 日本で出生した15歳未満の子どもの人口が年々増加, 定住化傾向がみられた。また, 全死亡数に占める「傷病及び死亡の外因」が高くなっていた。<br>・在日韓国・朝鮮人は高齢化, 少子化が進み, 65歳以上の総外国人登録者人口の8割を占めていた。<br>・「韓国・朝鮮」の三大死因は悪性新生物(がん), 心疾患, 脳血管疾患死因であり, 日本人の死亡動向と類似していた。<br>・在日外国人の健康課題は大きく3つ分類される。在日韓国・朝鮮人については老人保健, 近年, 移住した外国人については母子保健と労働衛生, そしてすべての外国人に対しては, 移住, 異文化, マイノリティであることに起因した精神保健の問題である。
1 0 0 0 OA 小型ホバークラフトの現状と各種応用について
- 著者
- 守分 巧
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.586, pp.255-256, 2002-11-05 (Released:2019-04-12)
1 0 0 0 IR 石井寛治著『資本主義日本の歴史構造』を読む
- 著者
- 三和 良一
- 出版者
- 東京大学大学院経済学研究科
- 雑誌
- 經濟學論集 (ISSN:00229768)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.2, pp.65-77, 2017-01-01
日本経済史研究を先導してこられた石井寛治氏の『資本主義日本の歴史構造』は,研究史で十分掘り下げられていない論点を選んだ分析の深さ,方法的に試みられる「数量分析重視の最近の経済史的アプローチでもなければ伝統的な社会経済史的アプローチでもなく,新たな政治経済史的アプローチ」の鋭さ,歴史法則論・国家論の展開の大胆さ,そして,社会科学,歴史学の研究者が真正面から対峙すべき現代の課題の所在提示の鮮明さを特徴とした力作である.石井氏の問題提起について,評者の評価と見解を述べたい.論壇/Communication